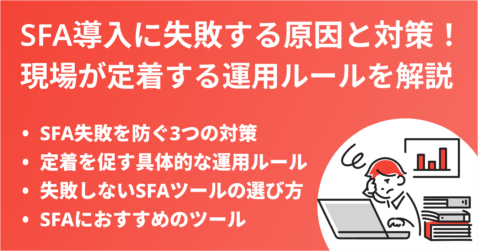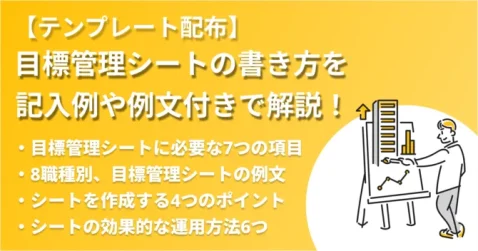会社の利益を上げるには、個人やチームの営業目標設定が欠かせません。目標の立て方を誤ると、利益が伸びないだけでなく、モチベーション低下や離職率の上昇を招く恐れがあります。
本記事では、弊社の支援実績や営業部門から得た知見をもとに、営業目標の立て方や達成のポイントを具体例とともに解説します。営業目標に関する悩みを解消できる内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
≫無料で「目標マネジメントパーフェクトガイド」をダウンロードする
▼ この記事の内容
- KGIとKPIの定義: KGIは売上や契約件数など最終的な定量目標で、KPIは新規リードの獲得件数や受注率などKGI達成のための中間目標(重要業績評価指標)です。
- KGIの決め方: 自社目線(欲しい売上)と市場目線(市場規模やシェア)の両方を意識し、実現可能な具体的数値を設定します。KSF(重要成功要因)を決めた上で、そこからKPIへと落とし込みましょう。
- KPIの設定の仕方: KGIから逆算して、KPIツリー(ロジックツリー)で階層構造を持たせながら細分化します。この際、特定のKPIに負荷が大きくかからないようにバランスを考慮することが重要です。
- 目標達成のためのポイント: SMARTの法則に基づき個人目標を設定し、目標を日々のタスクに落とし込むこと、定期的な進捗管理で注力すべき部分を軌道修正すること、評価制度と報酬を連動させ納得感を生み出すことです。
目次
営業で目標で設定をする重要性
適切な目標設定は、売上向上だけでなく、従業員のモチベーション向上にもつながります。
人間はちょうどいいストレス負荷が与えられている時が、一番スキルが上がります。
そのため、ギリギリ達成できるかできないかくらいの難易度の目標を設定する事でメンバーの成長を、促す事ができます。また、営業で成果を出せる個人やチームを分析した際に、「目標設定」のやり方に圧倒的に差が出ます。
目標設定は会社で体系的なやり方を持っておけば新しく入った方に、伝授する事ができるので力をいれる部分としてもとてもおすすめです。
>>【マネージャーの負荷削減と組織の生産性向上を実現】3分でわかる「コチーム」がわかる資料3点セットを無料でダウンロードする
営業のKGI
KGIとは「Key Goal Indicator」の頭文字を取ったもので、重要目標達成指標とも呼ばれます。KGIはプロジェクトの最終的な目標を定量的に示した指標のことです。
最終目標を数値化しないと、目標を達成できたのか判断することが難しくなってしまうので、数値を用いて具体的に設定するようにしましょう。営業のKGIは、売上(金額や契約件数)、シェア率が設定されることが多いです。
参考までに営業でKGIになり得る例を記載します。
- 売上
- 契約件数
- シェア
- 新規に獲得した顧客数
- 既存顧客のLTV
営業のKPI
企業にとってKGIは最終目標で、KPIはKGIを実現するための中間目標の役割を果たします。
KPIは「Key Performance Indicator」の頭文字を取ったもので、重要業績評価指標とも呼ばれます。KPIを設定すると定期的に活動を振り返りやすくなるので、PDCAサイクルを回しながら業務を改善することができます。
営業戦略のKPIは、営業活動の過程を評価するために設けられる中間目標の事なので、新規リードの獲得件数や受注率などが設定されることが多いです。
参考までに営業でKPIになり得る例を記載します。
- 新規リードの獲得件数
- 平均客単価
- 営業訪問回数
- 商談獲得件数
- 受注率
- コールの際の担当者接続数
- コール数
- コールから担当者に接続する率
【その目標管理、実は成果が出ないやり方かも?】
国内の多くのマネージャーは目標設定・目標管理のやり方を教えられずに、いきなり目標管理を任されています。
そんなマネージャーの中に、成果が出ない目標管理で苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。そんな国内に満映している「間違いだらけの目標管理」について解説した資料を公開中です!
>>「間違いだらけの目標管理」はコチラから無料ダウンロード!
KSFとは?
KGIやKPIの文脈の中で、KSFという言葉を使うことがあります。KSFとは「Key Success Factor」の略で、頭文字を取って、KSFと呼ばれています。
KSFとは企業や組織の経営戦略実現のためには、どのような要因が必要であるかを定めたもので、重要成功要因と訳されます。KPIは明確な数字を決めますが、数字を決める前の「営業機会の創出」「サイト流入数増加」のようなアクションがKSFとなります。
例えば、「600万の売り上げを作る」というKGIを設定した時、やるべきアクションとして「営業機会の創出」や「サイトから資料をダウンロードする人を増やす」というものが挙げられます。このアクションがKSFです。このアクションを決めた後に、「営業機会を増加するために50商談しよう」と明確な数字がついているKPIが設定されます。
KGIとKPIだけを決める企業が多いですが、実際にはKSFを決める作業が入っていることも忘れないようにしましょう。
KGIの決め方
「営業利益最大化」「できる限り多く新規顧客を見つけること」といったような定量で測れないKGIを設定してしまうと、進捗の確認や振り返りができないので目標設定をする意味がなくなってしまいます。
そのため、具体的な数値で目標を設定する必要があります。
例で言うと、「売上を昨年より120%向上させる」「年間の契約件数100件」「新規顧客開拓50件」などになります。
KGIには決め方が2種類あるので解説します。
自社目線での決め方
KGIの決め方一つ目は、「自社目線で決める」方法です。
「自社目線で決める」方法は、ほしい売上を経営者や事業責任者が決めてしまう方法です。スタートアップだと投資を受ける際に、予め成長曲線を描いているので、それに沿って月間や年間の目標を決めている場合もあります。
しかし、自社でKGIを設定する場合、自社の現状のリソースでは不可能だったり、市場規模的に不可能だったりするために実現不可能な数値が設定されてしまうことが多々あります。目標を未達すると、従業員のモチベーションが低下してしまう恐れがあるので、注意が必要です。
このため、次に紹介する「市場目線で決め方」も取り入れてバランスを見る必要があります。
市場目線での決め方
「市場目線で決める」というのは、自社の製品・サービスを購入してくれそうな企業や個人がターゲット市場において、どのくらいあるのかを調査し、そこから売上目標を決めていく決め方になります。
特定業種・業界を狙った商材・サービスであれば、市場目線で決めないと、無謀な目標値になってしまう事が多々あります。
例えば「従業員500名以上の人材紹介会社」を対象に、「人材紹介の際に使える管理ツールを売る」ことを考える場合、そもそも「従業員500名以上の人材紹介会社」がどのくらいあるのか?を調査して、そこから何%のシェアを取れるかを計算して目標を設定しなければなりません。
このため、自社目線での決め方と市場目線で決めていく決め方のどちらもを意識しないといけません。
【目標設定・目標管理の全解説!】
●効果的な目標設定のやり方
●マネージャーの負担にならない目標管理のやり方
●効果が出る目標管理の実践方法
●米国最先端の目標管理
など目標設定・目標管理について徹底解説した無料資料
>>「170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド」はコチラから無料ダウンロード!!
KPIの設定の仕方
営業目標のKGIを決めたら、次はKPIを決めましょう。
KPIはKGIを達成するための中間指標です。KPIを追えばKGIに到達できるよう、適切に設定する必要があります。
KPIを作る際は、KPIツリー(ロジックツリー)を作りながら、階層構造を持たせながらKGIをTOPにして、KPI、サブKPI、サブサブKPIというように設定していくと良いでしょう。
KPIの設定の例

KGIが「月の売り上げ600万」の場合、上記のようなKPIツリーになります。この図から、より注力するべきKPIを設定して、場合によっては評価と絡める事でメンバーのアクションを誘導します。
- KGI:月の売り上げ600万
- KPI:月の受注数10社(一社当たり平均単価60万)
- サブKPI①:受注率20%(商談から受注する可能性が20%)
- サブKPI②:月50社との商談
- KPI:月の受注数10社(一社当たり平均単価60万)
KPIツリーとロジックツリーについて、詳しくはこちらの記事もあわせてご覧ください。
KPIの決め方
営業戦略のKPIツリー(ロジックツリー)が完成したら、各KPIの目標値を決めましょう。
各KPIの目標値は、その目標値をすべて達成したらKGIも達成できている状態になる目標値(目安)にしなければなりません。
そのため、目標値の設定でエラーが出にくいKPIの決め方のおすすめの方法を二つご紹介します。
KGIから逆算して決める
1つ目の決め方は、KGIから逆算して決めていく方法です。
最終目標値であるKGIが決まっているため、そこから逆算して、必要なKPIを埋めていくイメージです。
例えば、KGIを売上600万円とします。このKGIから逆算してKPIを決めていくことになるため、まずは客単価を決めます。仮に客単価を60万と設定したとしたら、新規で獲得する顧客数は10社になります。
売上=客単価×顧客数なので、合計で600万円になります。
ここから、顧客数10社をすべて新規から取りに行くのか、それともアップセル狙いで新規を5社、既存を5社と設定していくのかという事を決めていきます。決めるときのコツとしては、一部のKPIに負荷が大きくかからないようにバランスを考慮する事が重要です。
あるKPIの負荷が大き過ぎると、そのKPIにばかり目がいってしまったりそのKPIが達成できなかった時に大幅にKGIが未達する可能性があるからです。
ただ、あるKPIの改善や向上施策に対して、自社のリソースが多くある場合はあえてそのKPIに期待を込めて大きな目標値を設定する事も可能です。
【OKRについて徹底解説!】
会社の目標でOKRを導入したいけど、どのように導入・運用すれば良いかわからない。そもそもOKRって何なのか?などのお悩みをマルッと解決いたします!
OKRの導入から運用まで成功までの道のりを完全解説した資料!
>>『売上を劇的に高める米国最先端の戦略実行手法「OKRパーフェクトガイド」』はコチラから無料でご覧いただけます!
KPIの目標値を社内調査して決める
2つ目の決め方は、KPIの目標値を社内調査して決める方法です。
社内調査とは、過去の自社データを調査する方法です。
例えば、メール送付で商談を打診した経験があるなら、その時の反応率などを過去の担当者に確認し、KPIとしてどのくらいの数値が現実的なのかを把握する方法です。
KPIツリー(ロジックツリー)を細分化していくと、だんだん現場に近いKPIになっていき、営業で言うと「何件架電するのか?」「何件メールをするのか?」といったようなKPIが出てきます。
その際、仮にメールの返信率が1%であれば、1件の商談を獲得するために、100件のメールを送付しないといけませんが、メールの返信率は送る企業や会社の知名度、業界によって大きく変動があるため、返信率1%に設定したが、実際は0.1%だったなんて事があってはいけません。そのため、過去のデータを調べてKPIを設定する必要があります。
また、デスクリサーチも有効です。デスクリサーチとは、既存の文献や資料、WEBサイトから必要な情報をリサーチすることです。
ネット上には多くのデータが公開されており、目標値の参考にできる情報を見つけられる可能性があります。営業であれば、営業支援の会社のHPやブログ、営業支援の会社の社長クラスのTwitter等に情報が書いてある可能性があります。
今回紹介した2つの決め方をベースに、KPIツリー(ロジックツリー)の各KPIの目標を決定するとよいでしょう。
注意点として、どうしても明確な数字がわからない場合は、どこかで折り合いをつける事も重要です。
実際に毎月、KGIやKPIを作成しながら調整していく事で最終的には良い目標を立てる事ができるようになります。
個人目標設定はSMARTの法則がおすすめ
会社全体のKGIやKPIは上司が決めますが、一個人のKGIやKPIは従メンバー本人に決めてもらう事もあります。その際に、従業員に伝えておくと良いフレームワークとして、SMARTの法則があります。
SMARTの法則は5つからなるフレームワークです。
- S:Specific(具体的)
- M:Measurable(測定可能)
- A:Achievable(達成可能)
- R:Related(上位目標との関連)
- T:Time-bound(期限)
S:Specific(具体的)
メンバーが目標を設定する際「一生懸命取り組む」「頑張る」といった抽象的な表現になりがちです。しかし抽象的な目標では、振り返りの際に成果の良否を判断できません。
そのため、具体的な目標を設定するように意識させないといけません。
参考までに、具体的な目標の例を下記に記載します。
「先輩に比べて商材理解が甘いので、会社にある商材に関わる資料を読み、自社商材の理解を深める」
「先月よりも訪問する企業を増やすことで、売上の向上をねらう」
M:Measurable(測定可能)
メンバーに目標設定をしてもらった後、測定によって進捗や実績を可視化できるようにしておかないと、途中や最後にフォローや振り返りができなくなります。
そのため、目標は測定可能なものにする必要があります。
例えば、Specific(具体的)で出した「先月よりも訪問する企業を増やすことで、売上げ向上をねらう」という目標であれば「先月よりも訪問する企業を1.2倍に増やす事で、売上げ向上をねらう」のように変更すると測定可能になります。
ただ、全ての目標を測定可能にする必要はなく、数値化可能なものは数値化させて測定可能にするくらいの意識が良いでしょう。
例えば、メンバーが「お客様からの信頼を向上させるために、ヒアリングを多めに商談を行う」と目標を設定した際に、定量で測れるようにしようとすると、「商談の動画の中でヒアリングを行った回数を数えて報告する」といった事ができますが、それだと工数がかかり過ぎてしまうので目標達成から遠ざかってしまいます。
A:Achievable(達成可能)
目標を立てる際に、よくあるミスとして達成不可能な目標を立ててしまう事があります。
例えば「1ヶ月で売上を2倍にする」といった大きすぎる目標も、根拠があれば問題ありません。しかし理由なく設定すると未達に終わり、翌月以降のモチベーション低下を招く恐れがあります。
また個人の目標未達がチームや他部署に迷惑をかける可能性があるので、達成可能な範囲内で、目標を設定するようにしましょう。
R:Related(上位目標との関連)
たまに、メンバーに目標設定をさせた際に会社や部門などの目標からそれてしまう事があります。そのため、メンバーの目標が会社、部門、チームの目標に一致しているかを確認するようにしましょう。
上位目標から逸れる内容としては、会社や部門では「今月の売上が後々に大事になってくるから今月の売上向上に注力したい」と思っているのに、メンバーが「資料がまだまだなので、資料をブラッシュアップする事に注力して、来月以降の売り上げアップに貢献する」といったような目標を立ててしまうと会社や部門としては困ってしまいます。
そのため、会社の目標、部門の目標やチームの目標にメンバーの目標を丁寧に伝え、そことブレないように確認してあげましょう。
T:Timebound(期限)
期限を設けなければ、目標としては機能しません。
メンバーに目標提出を求めた際に、期限の記載が無いことは少ないと思いますが、「3ヶ月での目標を決めて欲しいのに1ヶ月分の目標を設定してくる」のようなエラーはよく発生するので、いつまでの目標設定なのか、目線を合わせるようにしましょう。
また、KGIは月の目標であっても、途中のプランがわかるように一週間ごとの目標を設定させる事もおすすめです。営業の場合、月の初めにアポを取って月の後半で受注する事も多いので、単純に目標の売り上げを4分割するのではなく、「一週間目はアポ⚪︎件で売り上げは⚪︎円」といったように細かくイメージしてもらう事が重要です。
営業目標の具体例
新規開拓の営業部で「月600万円の売上」を目指す場合を例に解説します。
まず、600万円という目標だけではKPIを設定しにくいため「必要契約社数」に変換します。商材の平均単価を「売上÷契約社数」で算出し、仮に平均60万円なら、600万÷60万=10社が必要です。
次に、営業活動を電話に限定して計算します。商談獲得率5%、受注率20%とすると、10社契約には50件の商談が必要です。そのために1000件の架電(50商談÷0.05÷0.2)が必要となります。営業日を20日とすると1日50件の架電が必要です。
また、勤務時間8時間のうち商談2時間・会議1時間を除くと架電に使えるのは5時間。つまり、1時間あたり10件の架電を行う必要があります。
最初は上記のような細かい設定を最初は上司が行い、部下には行動させるだけでも良いですが、時間が経つにつれて部下自身にやらせるようにすることで、部下の思考力を向上させる事ができます。
営業目標を達成するためのポイント4選
ここまでは目標設定について解説してきましたが、実際にはその目標を達成する方が重要です。そこで、立てた営業目標を達成するためのポイントを4つ解説します。
▼ 部下に営業目標を達成させるためのスキル育成方法はこちら ▼
タスクに目標を落と仕込むようにする
営業目標を立てた後は、達成するために日々のタスクへと落とし込んでいく事が重要です。
内容が計画的であれば、何をしなければいけないのかが明確になっていきます。
例えば成約率を10%アップさせたいなら「ヒアリングを徹底して提案力を上げる」「ヒアリングシートを作成して質を高める」といったタスクができます。架電数を20%アップさせたいのであれば、「架電以外の時間で減らせる時間を探す」「架電の前と後のメモを残す時間を20%削減する方法を模索する」といったタスクができます。
やるべきタスクを書き出して、実行に移してPDCAサイクルを回す事が、成功への近道です。
進捗管理
目標達成に向けた進捗状況を管理する事で、途中までは目標が未達しそうでもサポートして達成に持っていく事ができます。
例えば、月の初めに「アポ数を1.2倍にする事で、売り上げを1.2倍にする」という目標を立てたものの中締め(半月)の時点で、「アポ数は上がったが、その分受注率が下がってしまい、目標の売り上げに達せそうにない」ということは多々あります。その際は、アポ数を1.4倍を目指すのか? それとも受注率を元に戻すのか? と注力すべき部分を見直す事で、目標達成できる確率を向上させる事ができます。
また、進捗管理をしていないと上司に相談しても上司側でアドバイスできる事が少ないですが、進捗管理をしておけば、上司に「今こういう状態なんんですけど、どうしたら良いでしょうか?」と聞くことで、上司もアドバイスをしやすくなります。
目標設定への納得感
目標達成には、目標設定への納得感が重要です。
営業組織でよくある目標への不満としては「目標が高過ぎて、達成できるイメージがわかずやる気が出ない」「目標設定が会社の貢献になっていない気がする」などになります。
「目標が高過ぎて、達成できるイメージがわかずやる気が出ない」に対しては、そもそもSMARTの法則でご紹介したAchievable(達成可能)の通り、達成可能な目標にする事が重要です。また、いつもより目標が高い場合は、「今月は広告を多めに打つからその分、商談数が増えるから目標を高めに設定した」など目標を高く設定した理由を説明する事も必要です。
「目標設定が会社の貢献になっていない気がする」という事が起きる組織では、KPIが評価に紐づいている場合が多いです。商材単価が高い会社では月の目標受注数が1、2件になる事があります。その場合、先月と先々月は0件だったが今月は4件受注した、といったようにばらつきが出る事が多いです。
そのため、KPIである商談数などを評価に組み込む事があります。その場合は、評価をする際に単月ではなく半年や一年での合計で評価をするという説明や、なぜKPIを評価項目に入れているのか、という背景を説明する事で、目標設定への納得感を生み出す事ができます。
目標達成後の評価について話しておく
チームでの目標を追う場合、どうしても目標を過達する人と大幅に未達する人が出てしまう事があります。
しかし、目標を過達した人と大幅に未達した人の評価にあまり差がない場合、メンバーのモチベーションが下がってしまいます。また、目標の2倍を達成した人が、目標の1.1倍達成した人評価が同じであれば、メンバーは目標を大幅に達成しようという意思が薄れてしまいます。
そのため、大前提として、目標を大幅に達成した人によりメリットがある評価制度にする事をおすすめします。また、目標設定を行った際に、メンバーともしその目標を達成したらどのような評価や報酬が得れるのか?ということを目線合わせをしておくと良いでしょう。
「現場の評価制度のまま売上を上げたい」「売上と納得度を上げる評価制度を作りたい」とお考えの方必見!
今ある人事評価を変えずに、少し足すだけで驚くほど売上と納得度が高まる「加点評価・インセンティブ型」人事評価の作り方について解説した資料!
>>売上・納得度を劇的に高める「加点評価・インセンティブ型」人事評価制度の作り方マニュアルはこちらから無料ダウンロード!
※一般的なインセンティブ制度とは異なるため「あ〜インセンティブね」と思わず、ぜひ一読いただけますと幸いです!(本や他社ではあまり語られていない部分がたくさんあります!)
目標達成には1on1がおすすめ
営業部の目標達成方法として、1on1ミーティングをおすすめしています。
1on1は離職改善などの守りの施策として認知されていますが、海外だと攻めの施策として使われる事も多いです。
1on1がおすすめの理由
目標達成のための施策として、1on1の活用がおすすめの理由としては、メンバーが抱えている課題を上司が直接アドバイスできることにあります。定例のMTGだけだとどうしても相談できない人がいるのと、全社研修だと一人ひとりに合った改善活動ができないので、そこの穴を埋める施策として有効です。
1on1の運用方法
目標について擦り合わせる
まずは1on1の最初に目標をすり合わせます。
「売り上げの目標達成」だけでなくミニマム100%達成で、マックスの目標は120%達成といったように二つ立てておくと、調子が良い場合はそのままマックスの目標を目指してもらい、調子が悪い際は、ミニマムの目標を目指してもらうといったように臨機応変な対応ができるのでおすすめです。
また、個人の売り上げだけでなく新しいメンバーのオンボーディングや他の部門との連携など他の目標がある場合もあるので、そういった点も擦り合わせるようにしましょう。
現在の状況を教えてもらう
次に現在の進捗状況をメンバーに教えてもらいましょう。
KGIやKPIをエクセルなどで管理している場合は、それを見れば現在の状況はわかりますが今注力している事や、失敗してしまった事などは聞いてみないとなかなかわからないです。
また、営業は月初にアポ獲得をして、月末に受注ということも多いので、中締め時に売り上げが40%だとしても、メンバーとしては、アポは目標の70%上がっているので順調という事もあります。
そのため、定量でわかる物と定性でないと分からないものを聞き、進捗を把握するようにしましょう。
課題と改善点を考えてもらう
次に、目標に対して現在、抱えている課題や、改善しようとしている事を聞きましょう。営業部で例を出します。
現在20日中の10日が過ぎているが、売り上げは目標の30%である。原因としては、電話でのアポが少ないことにある。そのため、電話のアポが得意な方に話を聞きに行き、テクニックがわかったので現在チャレンジしている。
まずはこのように状況とチャレンジしている事を最後まで聞くようにしましょう。聞く前に頭ごなしにアドバイスをしてしまうと、メンバーからの信頼がなくなったり、メンバーの思考力が育たない恐れがあります。
最後まで話を聞いたら、まずは抽象度の高い事を具体的にしていきましょう。今回であれば、「いいね!ちなみに具体的にどんなテクニックにチャレンジしているの?」といった質問になるでしょう。
アドバイス
状況とチャレンジしている事を最後まで聞いたらアドバイスを行うようにしましょう。
おすすめは全てティーチングで教えるのではなく、メンバーが考える事ができそうな部分はコーチングで自分で考えさせるようにする事です。そうする事で、最終的にはメンバー自身で考える事ができるようになります。
先ほどの例であれば、「アポのテクニック以外で伸ばせるところってある?テクニックって取得するのに時間がかかる可能性があるから」と他にもできる事がないかを確認します。そこでメンバーから「現在1日50架電していますがここって、伸ばせるコツとかありますか?」という質問があれば、メンバーの架電の様子をみてあげて、無駄な作業がないかを確認したり、架電のメモを自由記述ではなくフォーマットを作るようにするなどのアドバイスを行うと良いでしょう。
今の目標を達成した時の評価を擦り合わせる
目標に対して現在の達成状況や抱えている課題や、チャレンジしている事を聞いて話し合った後は、今の目標を達成した時の評価を擦り合わせる事をおすすめします。
人間は「報酬を手に入れる事ができそう」という実感があるとモチベーションを維持する事ができます。目標が未達の場合は、「このままだとまずいよ!」というだけでも良いですが、目標を達成しそうな方により高い目標を持たせる事がチームや部門視点ではとても重要です。メンバーの中には、目標100%達成でも120%達成でも評価が同じであれば、100%達成でもいいかなと思う方もいます。
そのため、「今の進捗だと目標120%以上達成できる可能性あるから、ぜひ目指してほしい。達成できた場合、うちの人事評価制度的に〇〇になると思う」と伝えると良いでしょう。
パフォーマンスマネジメントの事例
実は海外では、1on1でメンバーの抱えている課題を解決して目標達成を目指し、その結果や1on1メモに書いてあるチャレンジした事をもとに評価をするやり方を行っている会社はかなり多いです。
目標達成力が上がるだけでなく、評価への納得度合いが上がるので離職改善にも効きます。また、一見、マネージャーに負担が大きくかかるようにも感じますが、1on1でメモを残す事で、評価の時期にそのメモを見て評価を行う事で、評価に関わる作業を大幅に削減する事ができます。このやり方をパフォーマンスマネジメントを呼び、米国のTOP500企業の約20%が採用しています。
▼ パフォーマンスマネジメントについて詳しく知りたい方はこちら ▼
Adobe
パフォーマンスマネジメントが効果を発揮した例としてAdobe社会の事例を紹介します。
元々の状態
Adobe社では、マネージャーが1人のメンバーについて年次評価を決定するのに8時間かかっており、
当時アドビには約2,000人のマネージャーがいたので、会社全体では8万時間かかっている現場でした。
また、評価に不満を持ち退職する人や、目標達成できない人がいる状況がありました。
行った事
- 高頻度で目標達成のための話し合いと、現状の評価を振り返る1on1を行った
- 1on1トレーニングを、マネージャー向けとメンバー向けのそれぞれで10回ほど行った
- 1on1の中で従業員からマネージャーに向けてフィードバックすることもできるようにした
結果
- 退職の急激な減少(72%削減)
- 1人あたり平均10%の売上向上
- 年間8万時間の評価工数の削減
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 営業目標を立てる際、「KSF(重要成功要因)」はどのような役割を果たしますか?
A: KGIやKPIを達成するためにどのような要因が必要かを定めます。「営業機会の創出」といったアクションを明確にした後、KPIとして具体的な数字を付けるための土台となります。
Q2. KGIを「市場目線」で決めることの重要性は何ですか?
A: 自社のリソースや市場規模を無視した無謀な目標値が設定されてしまうのを防ぎます。実現可能な目標値を設定し、従業員のモチベーション低下を招かないために重要です。
Q3. 営業目標を達成するために、KPIを「KGIから逆算して決める」コツは何ですか?
A: 客単価や顧客数などを決め、一部のKPIに負荷が大きくかからないようにバランスを考慮することです。あるKPIが未達だった際のリスクを分散できます。
Q4. 営業メンバーの個人目標設定に「SMARTの法則」が推奨されるのはなぜですか?
A: 目標が具体的で測定可能、達成可能など5つの要素を満たすことで、振り返りが容易になり進捗管理がしやすくなるためです。達成への意欲を保てます。
Q5. 営業目標の達成と評価への納得感を高めるために、「1on1ミーティング」をどう活用すべきですか?
A: ミニマム目標とマックス目標を擦り合わせ、進捗状況や課題を定期的に聞き出します。達成状況に応じた評価を擦り合わせることで、評価への納得感が上がります。
まとめ
営業において、目標設定を行う事は最重要と言っても過言ではありません。
営業目標の立て方を失敗してしまうと、会社の利益が上がらないだけでなく、メンバーのモチベーションの低下やそれによる離職率が向上してしまう可能性があります。
慣れてくるとそこまで時間をかけずとも良い目標設定ができるようになるので、最初は時間をかけてでもしっかりと目標設定の基本を徹底するようにしましょう。
参考:トップ営業になるには?1年で成果を出すためのスキルとマインドセット|Roro Media
売上が上がる目標管理なら「コチーム」!

- 1on1をしながら、目標の進捗を入力できる!
- 目標の結果を人事評価に反映!
- 目標の進捗・結果を全て見える化!
- 1on1の記録を人事評価時に活用できる!
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。