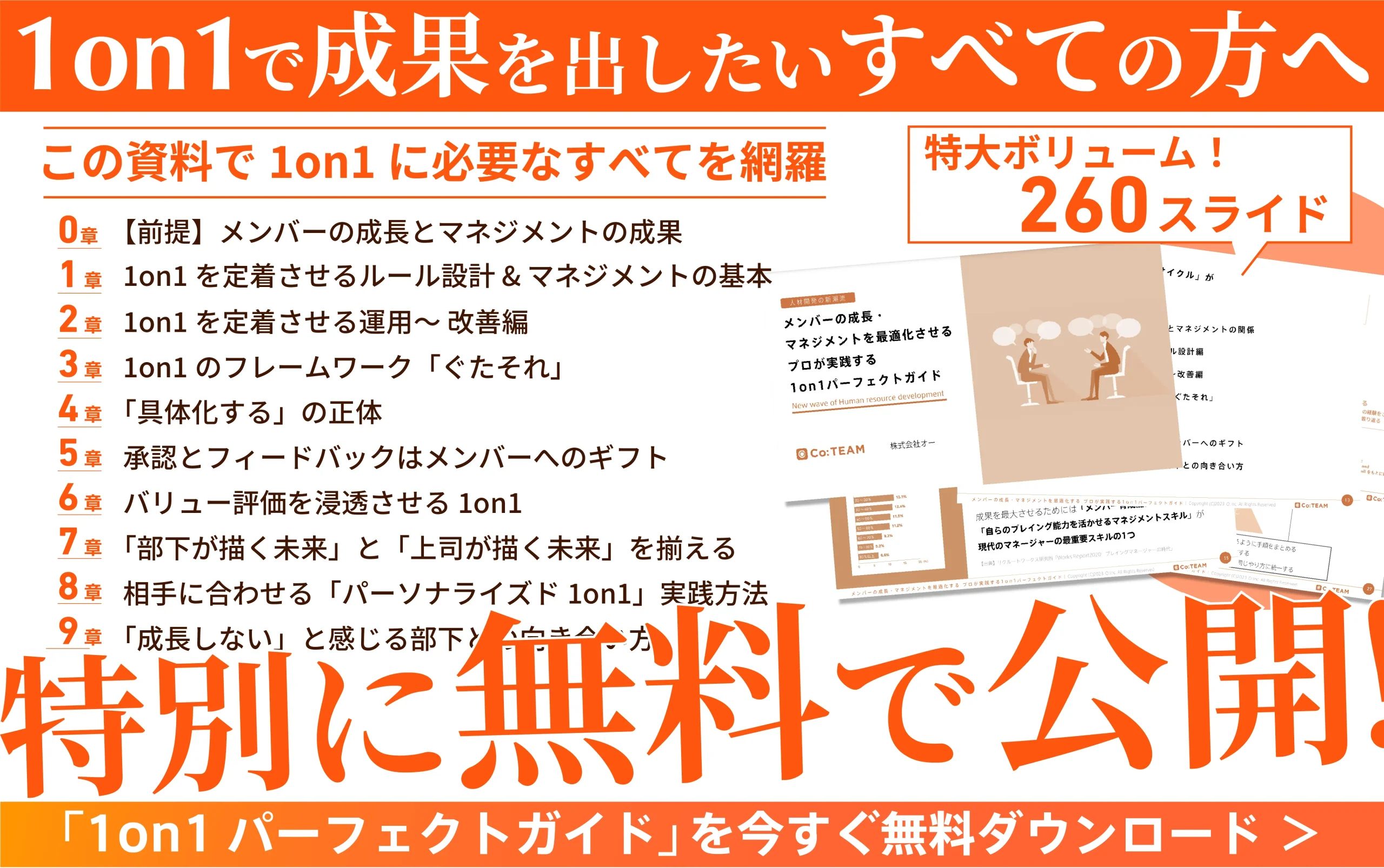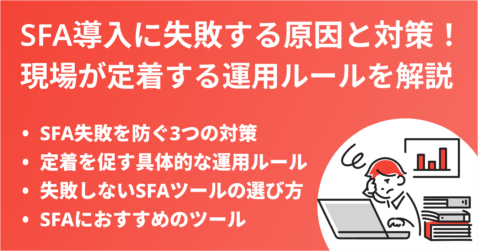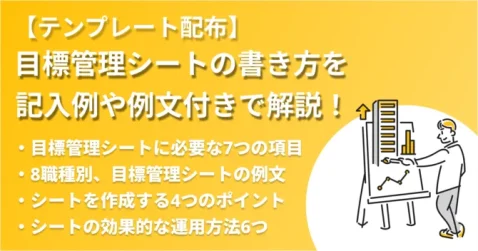SMARTの法則という言葉を聞いた事はあるもののうまく活用できないという方は少なくないと思います。そこで今回は、SMARTの法則を使った目標設定の方法を具体例付きで解説していきます。

≫無料で「目標マネジメントパーフェクトガイド」をダウンロードする
▼ この記事の内容
- SMARTの法則の定義と要素: 目標を達成させるためのフレームワークで、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Related(上位目標との関連)、Time-bound(期限)の5要素から構成され、誰でも効果的な目標設定ができるようになります。
- SMARTの法則を活用するメリット: モチベーションが向上し、メンバーがPDCAサイクルを正しく回すことで思考力が育ち成長につながります。また、目標が明確で数値化されるため、メンバーが納得のいく評価を運用しやすくなります。
- 関連する発展形と注意点: 発展形としてSMARTER(評価・承認)やSMARTTA(追跡可能・合意)などがあり、実行可能性を高めます。ただし、目標設定は経験学習サイクルを意識し、全ての要素を満たす必要がない場合もある点に注意が必要です。
目次
SMARTの法則とは?
SMARTの法則とは、目標を作る際に使うフレームワークとの事です。
SMARTとは、下記の英語のそれぞれの頭文字を取った言葉で、これら5つの要素が、目標を達成させて成功をするためのの5つの要因と考えられています。
- S:Specific(具体的)
- M:Measurable(測定可能)
- A:Achievable(達成可能)
- R:Related(上位目標との関連)
- T:Time-bound(期限)
目標設定で注目される理由
SMARTの法則が注目されている理由としては、誰でも使える点にあります。
上司の方が目標設定を行う場合は、あまりミスは少ないですが、部下に目標設定を行わせる場合や新人マネージャーに目標設定をさせる際はSMARTの法則を意識しないと、ゴールが不明瞭な目標ができてしまいます。
>>【助成金活用で最大75%補助】満足度98.2%のマネジメント研修がわかる資料3点セットをダウンロードする
SMARTの法則の5要素
S:Specific(具体的)
目標設定で「一生懸命取り組む」「頑張る」「粘り強く取り組む」といった抽象的な表現を使うと、振り返りの際に成果の良否が判断できず、非効率になります。そのため、常に具体的な目標を設定することが重要です。
Specific(具体的)を取り入れた例は下記のようになります。
- 「得意先のニーズを汲み取った企画立案を行い、効果的なプレゼンテーションをする」
- 「先月よりも訪問する企業を増やす事で、売り上げの向上をねらう」
このような目標であれば、次月には「プレゼンは改善したから次はツールの習得に注力しよう」「訪問数を増やしても成果が伸びなかったので、次は資料を作り込もう」といった形で、新たな挑戦や改善につなげられます。
M:Measurable(測定可能)
目標を設定する際、測定によって進捗や実績を可視化できる物にする必要があります。
Specific(具体的)で出した「先月よりも訪問する企業を増やす事で、売り上げの向上をねらう」という目標であれば「先月よりも訪問する企業を1.2倍に増やす事で、売り上げの向上をねらう」のように変更すると測定可能になります。
また、定性的な目標を設定した場合でも、評価の際は定量で測ると言う方法も存在します。
Specific(具体的)で出した「得意先のニーズを汲み取った企画立案を行い、効果的なプレゼンテーションをする」という目標では、効果の判断が主観的になりがちです。そこで「得意先アンケートで5段階中4以上を獲得する」「プレゼンで月30万円のアップセルを達成する」といった数値で測れる目標にすると、客観的に評価できます。
A:Achievable(達成可能)
目標を立てる際に、よくあるミスとして達成不可能な目標を立ててしまう事が挙げられます。
例えば「1ヶ月で売上を2倍にする」という目標も、取引先が増える見込みなど理由があれば問題ありません。 しかし根拠なく大きすぎる目標を立てると、かえってメンバーのやる気を削いでしまいます。
また、目標を大幅に未達すると「なにが課題だったのか?」が見えづらくなってしまうので、メンバーの成長や能力強化に繋がりません。
そのため、達成できる目標を設定するようにしましょう。
【その目標管理、実は成果が出ないやり方かも?】
国内の多くのマネージャーは目標設定・目標管理のやり方を教えられずに、いきなり目標管理を任されています。
そんなマネージャーの中に、成果が出ない目標管理で苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。そんな国内に満映している「間違いだらけの目標管理」について解説した資料を公開中です!
>>「間違いだらけの目標管理」はコチラから無料ダウンロード!
R:Related(上位目標との関連)
会社の目標と部門の目標が一致しているか、部門の目標やチームの目標に自分の目標が一致しているか、を確認しましょう。営業部などの目標と行動がわかりやすい部署であれば、あまり上位目標との関連がなくなる事がありませんが部署によっては会社の目標と部署の目標がずれてしまう事があります。
例えば「売上を1.2倍にしたい」と考える会社の人事部門が、営業職ではなく他職種ばかり採用していたらどうでしょうか。もちろん、マーケ人材を採用して集客を強化したり、営業が事務作業を抱えているため事務担当を採用したりするなど、売上向上につながる理由があれば問題ありません。
しかし理由を示さずに採用を進めると「人事は採用人数だけを追っている」と他部門から誤解される恐れがあります。そのため「事務員採用は営業の業務効率化を図り、売上1.2倍の達成につながる」といった関連性を明確に伝えることが重要です。
T:Time-bound(期限)
目標に期限を設けなければ、行動計画を決定する事ができません。そのため、目標に応じて明確な期限を設けるようにしましょう。
年間や半年の目標を設定し、そこから逆算して四半期や月間の目標、そしてできる事なら一週間や1日の目標も作っておく事がおすすめです。細かいアクションや期限が決まっていると、早めに改善すべき事をチェックできるからです。
また、月末や期末の期限を決める際は、「5/30」という期日ではなく、「5/30 17:59まで」と言ったように時間まで決める事をおすすめします。
理由としては、営業職では契約完了を目標とする場合がありますが、例えば顧客が5月30日22時に契約書へサインしたのに、バックオフィス側が「17時59分までの契約」で集計してしまうと、数値にズレが生じることがあります。
SMARTの法則を使った具体例
このセクションでは、SMARTの法則を使った具体例を3つご紹介します。会社に合わせて応用してお使いください。
経営部
経営の仕事内容はたくさんあるため、さまざまな目標を設定する必要があります。例としては、コストカット、採用、売り上げ、認知度拡大などです。
ここでは、売上に関する目標を例として、紹介するので参考にしてください。
| SMARTを用いてない目標(NG例) | 売上を2023年度より伸ばし、利益率を上げる。 |
| Specific(具体的な) | 目標が具体的でないので、「売上」、「利益率」という指標を軸に目標を立てることで具体的な目標にする。 |
| Measurable(測定可能な) | 「売上」、「利益率」の数字が決まっていなかったので、数字を設定する。2021年度より10%の売上を伸ばす。利益率を15%にする。 |
| Achievable(実現可能な) | 2024年度は2023年度より7%売上を伸ばせたことと、営業マンを雇ったことによる戦力増加で実現できると予想。前年度よりも投資額を抑える計画があるため、利益率15%は目指せるという見解。 |
| Relevant(関連した) | 会社の目的を果たすために、会社の売り上げや利益率を向上させる事は直接関与するため、上位目標に関連していると言える。 |
| Time-bound(期限を定めた) | 期限を2024年度末までに設定する。 |
| SMARTを用いて設定した明確な目標 | 2024年は2023年度より売上を10%増加し、利益率を15%にする。 |
営業部
営業部は数値を扱う業務が多いため、具体的な目標を設定しやすい職種になります。目標を適切に決めておくことで営業マンのパフォーマンスが大きく変化するので、しっかり目標設定を行うようにしましょう。
こちらもSMARTの法則を用いた事例を紹介します。
| SMARTを用いてない目標(NG例) | 顧客を増やす。 |
| Specific(具体的な) | 顧客には新規顧客と既存顧客がいるので、どちらにどれくらい注力するのか決める。今回は、新規の顧客に注力する。 |
| Measurable(測定可能な) | 300人の新規顧客獲得を目指す。 |
| Achievable(実現可能な) | 2023年度が250人で、年々受注率が向上しているので、達成可能と判断。 |
| Relevant(関連した) | 営業部は売り上げを上げるのが目標になるので、新規顧客獲得は上位目標と密接である。 |
| Time-bound(期限を定めた) | 2024年度末までに達成する。 |
| SMARTを用いて設定した明確な目標 | 2024年度末に300人の新規顧客を獲得する。 |
さらに細かい目標設定
上述した通り、営業部は細かい目標設定が従業員のスキルアップや業績への貢献につながります。そこで、今回はより細かいところまで目標設定した具体例をご紹介します。
新規開拓営業で月600万円の売上目標を追う場合、金額のままではKPIを設定しづらいため、契約社数に変換します。商材の価格が固定であれば「600万 ÷ 商材単価」で算出できますが、プランごとに価格が異なる場合は「過去の売上 ÷ 契約社数」で平均単価を出します。例えば平均単価が60万円なら、600万 ÷ 60万で10社の契約が必要です。
次に行動量に落とし込みます。商談獲得率が5%、受注率が20%の場合、10社契約には50社の商談(10 ÷ 0.2)が必要で、そのために1,000回の架電(50 ÷ 0.05)が必要です。営業日が20日なら1日50回の架電が目安になります。
初めは上司がこのような行動設計を行い、部下には実行させるだけでも構いませんが、徐々に部下自身に計算させることで、思考力と自律性を養うことができます。
人事部
人事部の社員でもSMARTの法則を活用して目標を設定できます。人事部の場合、採用人数や従業員エンゲージメントや有休消化率などが挙げられます。
| SMARTを用いてない目標(NG例) | 良い人材を多く採用する。 |
| Specific(具体的な) | ・「多く採用する」が抽象的なので「5人採用する」を目標にする。 ・「良い人材」が抽象的なので「会社の経営理念に共感してくれる即戦力の方を採用する」と具体的にする。 ・「即戦力の方」がまだ抽象的なので「業界経験3年以上で、現在の年収が450万円以上の人」と具体的にする。 |
| Measurable(測定可能な) | 「業界経験3年以上で、現在の年収が450万円以上の人を5人採用する」であれば測定可能。 |
| Achievable(実現可能な) | ・人材業界に働いている人にデータベースを見せてもらった所、業界経験3年以上で現在の年収が450万円以上の人は5,000人いるとの事だった。 ・また去年は業界経験3年以上で、現在の年収が450万以上の人を3人採用できていて、採用にかけれる予算も去年の1.5倍かけても良いとのことだったので達成可能だと判断。 |
| Relevant(関連した) | 会社が赤字だったら採用は逆効果だが、現在黒字で年間120%成長しているので、採用を強化する事が会社の強化につながる。 |
| Time-bound(期限を定めた) | 2024年12月までに達成を目標にする。 |
| SMARTを用いて設定した明確な目標 | 2024年12月までに業界経験3年以上で、現在の年収が450万円以上の人を5人採用する。 |
SMARTの法則に関連する法則
SMARTの法則に関連する法則がいくつかあるので、ご紹介します。
SMARTERの法則
SMARTERの法則は「SMART」の型に「ER」を追加した法則です。
このERは、下記のような意味を持ちます。
- Evaluated:評価される
- Recognized:承認された
Evaluatedは主に「上司に評価されたか」という意味合いを持ちます。Recognized(Rewarding)は「上司に承認をされたか」という意味合いを持ちます。
ビジネスを行う上では、部下が自分で目標を設定して行動してしまうと、その個人としては成功しているが組織全体としては不利益を被る事があります。
そのため、SMARTERの法則のように上司の評価・承認を得られたかどうかを定義の中に入れておく事で、部下が上司に評価・承認を得るという行動をとる事が増え効率的に目標設定を行う事ができます。
SMARTTAの法則
SMARTTAの法則は「SMART」の型に「TA」を追加した法則です。
このTAは、下記のような意味を持ちます。
- Trackable:追跡可能かどうか
- Agreed:合意された
Trackableとは目標に向けた取り組みの経過を把握できるかを示す概念です。現在の達成度や次に進むための行動を確認するために用いられます。
Agreedは、当事者間の合意があるかを確認するというものです。
メンバーが勝手に目標設定をしてしまうと、関係者に迷惑がかかる事があるので、万人が納得できる・取り組める目標を立てる事が重要です。
▼ 上司と部下とで合意の取れた目標設定をするには、1on1ミーティングがおすすめ!
SMARRTの法則
SMARRTの法則は「SMART」の型に「Realistic(現実的)」を加えた発展形です。Achievable(達成可能)と重なる部分も多いため、両者を同じ要素として扱っても問題ないでしょう。
似た視点をあえて加えることで、実行可能性への意識が高まり、より現実的で具体的な目標設定が可能になります。
FASTの法則
SMARTの法則に似ている法則で、FASTの法則というものがあります。
FASTの法則は下記の頭文字を取って構成されています。
- Frequent
- 目標が頻繁に議論されるているか
- Ambitious
- (不可能でない範囲で)野心的な目標であるか
- Specific
- 目標が具体的であるか
- Transparent
- 目標が組織の全員から見えるような透明性を保っているか
SMARTの法則との違い・使い分け
SMARTの法則とFASTの法則の違いは、目標が現実的な物か野心的なものかという点が大きく違います。
SMARTの法則のAchievable(目標が達成可能であるか)とは対照的に、FASTの法則のAはAmbitious(野心的な目標であるか、ただし不可能ではない範囲で)となっています。
FASTの法則を提唱したSull氏によると「現実味を重視した安全策をとるよりも、野心的な目標を追いかけている従業員の方が、それほど難しくない目標を掲げている同僚たちに比べて、はるかに優れたパフォーマンスを発揮する」と考えられています。
ただ、野心的な目標を設定しただけでは、実現が難しくなった際にメンバーのモチベーションが低下して、有効ではない施策になってしまうので、FrequentとTransparentが設定されています。
「Frequent:目標が頻繁に議論される」というのは、組織的や個人が目標を頻繁に振り返りコミュニケーションをとる事で、目標達成までの道のりをPDCAサイクルを回して向かっていく事ができるようにするための項目です。
「Transparent:目標が組織の全員から見えるような透明性を保っているか」に関しては、客観的な視点を欠かさないということがポイントです。
客観的な視点を取り入れる事で、その目標が会社の目標と沿っているかなどを確認します。
SMARTの法則を取り入れるメリット
このセクションでは、SMARTの法則を取り入れるメリットを解説します。
モチベーションが向上する
SMARTの法則を取り入れるメリットとして、モチベーションの向上が挙げられます。
明確な目標がなければ達成感を得にくく、従業員のモチベーション低下につながります。さらに、目標達成時の評価や報酬をあらかじめ伝えておくことで、仕事の意義を実感しやすくなり、離職防止にも効果があります。
メンバーの成長につながる
SMARTの法則を取り入れるメリットとして、メンバーの成長につながる事が挙げられます。
曖昧な目標を立てていたままだと、メンバーが正しくPDCAサイクルを回す事ができないので、メンバーの思考力が育ちにくいです。
SMARTの法則を運用することで、メンバーが目標の立て方を学習し、効率化を図る方法を検討するようになるので、メンバーが成長に繋がります。
メンバーが納得のいく評価を運用しやすい
近年、離職で一番多い理由が「自分への評価に納得できなかった」というものになります。
皆さんも、数字のない目標を掲げられて、自分は精一杯頑張ったつもりなのにそこまで評価されないとしたらどうでしょうか?また、達成不可能な目標を掲げられて、ボーナスを減らされたりしたら転職を考える人は少なくないと思います。
そのため、SMARTの法則を活用する事で、メンバーが納得のいく評価を運用するようにしましょう。
また、SMARTの法則を用いた目標管理とともに1on1を実施することで、これらの恩恵をより大きくすることができます。
SMARTの法則のポイントと注意点
このセクションではSMARTの法則のポイントと注意点を解説します。
必ずしもすべての要素を満たす必要はない
SMARTの法則は基本的には全ての要素を満たすように目標設定をした方が良いですが、すべての要素を満たさなくても良い場合もあります。
例として、バックオフィスなどの業務で目標が「トラブル対応能力を向上させる」だった際に、「トラブル対応をした回数」を目標として上げた会社があります。この会社では、メンバーが未然に解決できるトラブルを解決せず、トラブルが起きてから対応をするようになってしまい、本質から外れた目標設定になってしまいました。
このような事態を防ぐために、SMARTの法則を全て満たす必要があるか? を考えてから目標設定を行うと良いでしょう。
経験学習サイクルを回す事を意識する

経験学習サイクルを意識しながら行うと、目標設定の質を高めることができます。
経験学習サイクルと似ているサイクルとして、PDCAサイクルがありますが、PDCAサイクルは、計画(Plan)を立てて実行(Do)し、その結果をチェック(Check)、改善(Action)をします。そして、また計画(Plan)を立て、実行(do)する、といった具合にPDCAを繰り返していくことで、継続的な業務改善につながっていく手法です。
PDCAサイクルでは「業務改善」を重視する一方、経験学習サイクルは「経験から気付きを得て、深く掘り下げていき学習する」ことを重視する手法です。経験学習サイクルは、「経験→内省→教訓→実践」の4段階で構成されています。
経験フェーズでは、実際に経験して学びます。ちなみに、人間は経験から7割、他人や文献から3割学ぶと言われています。
次の内省フェーズでは失敗や成功から、自分自身が経験したことを多様な視点、俯瞰的な立場から振り返ることで原因、背景などを多角的に考察します。
教訓フェーズでは、経験した結果を内省して得たものをほかのケースでも応用できるよう教訓にします。
最後の実践フェーズでは、得た教訓をまた実践し次の経験学習サイクルの糧にします。
目標設定をして1ヶ月が経った後に、今回の目標設定で良かったところと悪かった所を書き出していく事で、次の方向性を決めていきながら思考力を鍛える事ができます。
【参加者満足度98.2%!】
明日から使える1on1で重要な「承認」「共感」「フィードバック」のテクニックをわかりやすく解説!
「今まで受けた研修で1番良かった!」「マネジメントの新しい考え方を得れた!」など現場管理職・マネージャーに大人気の1on1研修の第1回目の資料を無料公開中!!
>>1on1研修第1回『マネジメントと1on1って何ですか?』はこちらから無料ダウンロード
SMARTの法則と併用したいフレームワーク
このセクションでは、SMARTの法則と併用したいフレームワークをご紹介します。
MBO(目標管理制度)
MBOは、多くの企業の人事評価制度で採用されている目標管理方法です。MBO(目標管理制度)は「Management by Objectives and Self-control」の略で、1954年に経営学者ピーター・ドラッカーが著書『現代の経営』で提唱した手法です。従業員が自ら業務目標を設定し、上長がその達成を支援する仕組みで、日本ではKGIやKPIと同様に活用されることが多くあります。
例えば営業では「月間売上400万円達成」や「月間受注数10社」などの目標が設定されます。またパターンとしては「売り上げ月間400万達成」とそれを達成するのに必要な「月間30商談」などのKPIがMBOとして採用される事もあります。
MBOを設定する際も、SMARTの法則を活用して設定することで納得度の高いMBOをメンバーに提供する事ができます。
日本でよくあるMBOの誤解
日本では、MBOを間違った意味で使ってしまっている企業様が多いです。
MBOは、バブル崩壊後の1990年代に日本で急速に広がった考え方です。バブル崩壊後、多くの企業がコスト削減を迫られ、成果主義的な人事評価制度や報酬制度が導入される中で、評価の根拠を明確にする手法としてMBO(目標管理)が採用されました。
本来MBOは、従業員が自ら目標を設定する仕組みですが、日本では経営層や上司が一方的に目標を課すケースが多発しました。MBOにおいては「Management by Objectives and Self-control」のうち、とくに「Self-control(自己統制)」が重要であり、従業員が自ら目標を立てることで責任感や納得感が生まれます。
しかし日本では、この「Self-control」の要素が軽視され、MBOが単なる人事制度の1つとして認識されがちです。
本来MBOは、マネジメントの考え方であり、人事評価の手法ではありません。会社が設定する目標を上手に使って自己管理を促すことで、社員一人ひとりのやりがいやモチベーションを引き出し、その結果として目標を達成するというマネジメントの考え方がMBOです。
MBOについて詳しく知りたい方はこちらから↓
OKR
OKRはGoogleやFacebookなどGAFAも導入する注目の目標管理制度で、「Objectives and Key Results(目標と主要な成果指標)」の略です。インテルのアンディ・グローブ元CEOがドラッカーのMBOを基に独自にアレンジした手法で、MBOの一形態と捉えるのが適切です。
MBOが100%達成を前提にするのに対し、OKRは達成率70%程度を想定したストレッチ目標を設定し、挑戦を通じて予想以上の成果を狙います。インテルでは100%達成した部門は「目標が低すぎる」と注意されるほどで、平均4割の目標は未達となります。
KR(Key Results)は目標達成度を測る具体的な指標で、期限や手段を明確に設定します。例えば「売上200万円を達成する(O)」に対し「50社訪問する(KR)」といった形です。
OKRはMBOを補完する仕組みであり、自社の文化に合わせて「達成重視(MBO)」と「挑戦重視(OKR)」を使い分けることが有効です。
【OKRについて徹底解説!】
会社の目標でOKRを導入したいけど、どのように導入・運用すれば良いかわからない。そもそもOKRって何なのか?などのお悩みをマルッと解決いたします!
OKRの導入から運用まで成功までの道のりを完全解説した資料!
>>『売上を劇的に高める米国最先端の戦略実行手法「OKRパーフェクトガイド」』はコチラから無料でご覧いただけます!
効果的な目標管理なら「コチーム」!

- 1on1をしながら、目標の進捗を入力できる!
- 目標の結果を人事評価に反映!
- 目標の進捗・結果を全て見える化!
- 1on1の記録を人事評価時に活用できる!
よくあるご質問(FAQ)
SMARTの法則の5つの要素には、それぞれどのような意味がありますか?
A: S(Specific)は具体的な目標、M(Measurable)は測定可能な数値、A(Achievable)は達成可能な水準、R(Related)は上位目標との関連、T(Time-bound)は明確な期限を設けることを意味し、目標の質を高めます。
SMARTの法則を目標設定に取り入れることで、どのようなメリットが得られますか?
A: 目標が明確になることでモチベーションが向上し、達成感を得やすくなります。 また、曖昧さがなくなるためPDCAサイクルを効率的に回せるようになり、結果的にメンバーの成長と納得度の高い人事評価につながります。
SMARTの法則を目標管理制度(MBOやOKR)と併用する際のポイントは何ですか?
A: MBO(目標管理)やOKR(目標と主要な成果指標)を設定する際に、SMARTの法則の要素を取り入れることで、目標の具体性や測定可能性が高まります。 特にMBOでは自己統制(Self-control)の要素を重視し、従業員自ら目標を立てることで納得感を高められます。
SMARTの法則の「R(関連)」を人事部など目標が分かりづらい部署で活用する具体例を教えてください。
A: 人事部が採用人数を目標にする場合、「事務員採用は営業の業務効率化を図り、売上1.2倍の達成につながる」のように、上位目標(会社の売上)との関連性を明確に言語化し伝えることが重要です。
SMARTの法則と似ている「FASTの法則」との大きな違いは何ですか?
A: SMARTの法則がAchievable(達成可能)という現実的な目標を重視するのに対し、FASTの法則はAmbitious(野心的)なストレッチ目標を重視する点です。 FASTは、野心的な目標を追いかけることで優れたパフォーマンスを引き出すことを目的としています。
まとめ
今回はSMARTの法則を使った目標設定の方法を具体例付きで解説しました。実際に弊社が支援させていただいた知見や情報をもとに無料で情報を公開しておりますので、ぜひ他の記事もご覧いただけると幸いです。
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。