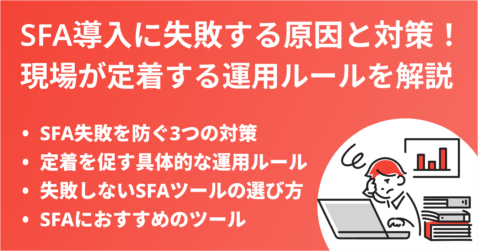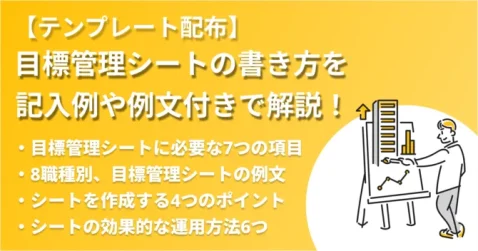目標管理において非常によく活用されているKPIやKGIですが、なんとなく「目標数値」くらいの理解度で使用してはいませんか?
本記事では、企業の目標達成において重要な役割を果たすKPIやKGI、さらにそれらを視覚的に分かりやすく表現できるKPIツリーについて、基本的な概念から実際の作成例まで詳しく解説していきます。
カンタンに効果的な目標管理を実現するテンプレート集を無料公開中!
>>無料で『目標管理シートテンプレート集』をダウンロードする
▼ この記事の内容
- KPIツリーの定義と目的: 企業の最終目標(KGI)達成に向けて必要な指標や中間目標(KPI)をツリー状の図で視覚的に分解・表現するためのフレームワークです。チーム全員が自分の役割と具体的な道筋を把握し、データに基づいたマネジメントを支援します。
- メリットとロジックツリーとの違い: KGI達成を阻害するボトルネックを早期に特定し、目標達成に必要な指標の漏れや重複なく洗い出せます。ロジックツリーが問題の原因特定を目的とし定性的な要素も扱うのに対し、KPIツリーはKGI達成を目的とし定量的な指標のみを扱います。
- KPIツリーの作り方のポイント: KGIを起点に、各指標間の関係性を四則演算で表現できる要素で分解していきます。分解する際には、遅行指標(結果)から先行指標(行動)へと落とし込み、単位を設定し、目標達成と関連性の薄い要素を含まないように注意します。
目次
KPIツリーとは?
KPIツリーは、企業の最終目標の達成に向けて、必要となる指標や中間目標を明確にするためのフレームワークです。
目標達成のために必要な要素を分解してツリー状の図で表現することで、最終目標から具体的な行動指標まで可視化できます。KPIツリーを活用することで、チームメンバー全員が自分の役割や期待される成果、目標達成のための具体的な道筋を把握することができるのです。
また、デジタル化が進む現代において、KPIツリーはデータに基づいたマネジメントを支援できるという側面も持っています。
そもそもKPIとは?
KPIは「Key Performance Indicator」という定義の略称であり、企業や組織において、目標達成度を評価するための定量的な指標のことを指します。
企業で働く中では様々なデータや数値が存在しますが、その中でも特に重要度が高く、目標達成に直結する指標をKPIとして設定します。KPIを適切に設定することで、チームメンバーの行動指針が明確になり、業績評価の基準としても活用できます。
また、KPIの設定には、SMART(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)の原則に従うことが重要です。具体的で測定可能であり、達成可能で関連性が深く、さらに期限が明確な指標を選ぶことで、よりクリアな業績評価が可能になります。
例えば、営業部門であれば売上高や商談数、マーケティング部門であれば問い合わせ件数やコンバージョン率などが代表的なKPIとして活用されています。
KGIとKPIの違い
KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)は、企業や組織が最終的に達成すべき目標を示す指標です。一方KPIは、そのKGIを達成するための中間指標としてKGIの一階層下に位置づけられるものです。
例えば、企業の最終目標(KGI)が「年間売上高10億円の達成」である場合、そこに至るまでの過程で達成が望ましい指標(KPI)として「月間の新規顧客獲得数」や「顧客単価」などが設定されます。
KGIとKPIの関係を理解することで、より効果的な目標達成に向けた戦略立案ができるようになるでしょう。
KPIツリーとロジックツリーとの違いは?
KPIツリーとロジックツリーは、どちらも物事を階層的に分解して考える手法ですが、その目的と構造に違いがあります。
ロジックツリーは、問題や課題を論理的に分解して原因を特定するためのツールであり、定性的な要素も含めて分析することができます。
一方、KPIツリーは、KGIの達成に必要な要素を定量的な指標として分解し、それらの関係性を可視化するためのツールです。要するに、KPIツリーでは定量的な指標のみが指標として用いられ、より具体的かつ詳細な目標設定や進捗管理が可能となります。
KPIツリーを作る目的やメリットとは?
KPIツリーを活用することで、組織全体の目標を具体的な行動指標へと落とし込むことができ、効率的なマネジメントが可能になります。特に、デジタル化が進む現代において、KPIツリーは数値による客観的な業績評価と戦略立案をサポートできる方法として注目されています。
KPIツリー作成のメリットについて、詳しく解説していきます。
KGI達成のためのボトルネックを明確化できる
KPIツリーの最大のメリットは、目標達成を阻害する要因(ボトルネック)を早期に特定できることです。
最上流であるKGIから各下階層のKPIへと分解することで、どの指標が目標達成に大きく影響しているのかが明確になります。例えば、もし売上高を向上させるためのKPIツリーを作成した際に、商談件数は十分であるにもかかわらず成約率が低いことが判明すれば、その改善に向けた施策を重点的に実施することができます。
また、KPIツリーは先行指標と遅行指標の関係性をも可視化するため、問題が発生する前に予防的な対策を講じることも可能であり、これにより効率的なリソース配分や業務改善が実現できます。
先行指標や遅行指標に関しては、KPIを作成する際のポイントとして後述しますので、ぜひ最後まで目をお通しください。
漏れや重複なくKPIを洗い出せる
KPIツリーのもう一つの重要なメリットは、目標達成に必要な指標を漏れなく特定できることです。KGI達成ための要素を分解していく過程で、必要な指標を体系的に整理することができ、重要な要素の見落としを防ぐことができます。
さらに、KPIツリーの作成過程で、各部門の担当者の役割と責任も明確になります。例えば、マーケティング部門のKPIと営業部門のKPIの関連性が可視化されることで、部門間の連携がスムーズになり、組織全体としての効率的な目標達成が可能になります。
また、KPIの重複を防ぐことができるため、効率的な業績管理が可能になります。同じような指標を複数の部門で管理することを避けることで、より効果的な評価システムを構築することができます。
このように、KPIツリーは単なる指標の整理ツールではなく、組織のマネジメント改善やリソース配分にも役立つツールとして機能するのです。
【目標設定・目標管理の全解説!】
●効果的な目標設定のやり方
●マネージャーの負担にならない目標管理のやり方
●効果が出る目標管理の実践方法
●米国最先端の目標管理
など目標設定・目標管理について徹底解説した無料資料
>>「170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド」はコチラから無料ダウンロード!!
KPIツリーの作り方
KPIツリーの作成プロセスは、組織やプロジェクト全体の目標を、個々の具体的な行動指標へと落とし込む重要な作業です。
最終目標であるKGIの設定から、それを達成するための具体的なKPIを特定し、そしてそれをツリー状に視覚的に整理することで、より実用的なKPIツリーが完成します。KPIツリーの作り方や作成のコツについて、以下で詳しく解説していきます。
KGIを設定する
KPIツリー作成の第一歩は、適切なKGIの設定です。
KGIは会社や各部門の最終目標となるため、経営戦略や事業計画と整合性のある具体的な数値目標として設定する必要があります。例えば、「年間売上高30億円の達成」や「営業利益率15%の実現」といった定量的な目標を設定します。
KGIを起点にKPIを分解していく
KGIが設定されたら、次はそれを達成するために必要なKPIへと分解していきます。
この過程では、KGIに影響を与える要素を論理的に特定し、それぞれを定量的な指標として設定します。例えば、売上高というKGIは、「顧客数」×「顧客単価」に分解できます。
さらに顧客数は「新規顧客数」と「既存顧客数」に、顧客単価は「商品単価」と「購入頻度」というように、より具体的な指標へと分解していきます。
ロジックツリーにより可視化する
最後のステップは、分解したKPIをロジックツリーの形で可視化することです。
この作業では、ExcelやPowerPointなどのツールを活用し、階層構造を視覚的に分かりやすく表現しましょう。具体的な作画方法としては、上位のKGIから下位のKPIへと矢印や線で繋ぎ、各指標間の関係性を明示します。
また、各指標には具体的な数値目標や測定期間、担当部署などの情報も併せて記載することで、より実用的にマネジメントツールとしてして活用できます。さらに、KPIツリーの共有や管理をデジタル上行うことで、リアルタイムでの進捗管理やデータの更新が容易になり、より効率的な運用が可能となります。
KPIツリーの作成ポイント
KPIツリーを効果的に活用するために、作成時に注意すべきポイントをいくつか紹介していきます。
①四則演算できる要素で組み立てる
KPIツリーの構築において最も重要なポイントは、各指標間の関係性を四則演算(加減乗除)で表現できることです。
例えば、売上高は「販売数量×販売単価」と計算でき、さらにこれらの要素はより細かく数値指標に分解できます。この原則を守ることで、目標値の設定や進捗管理が明確になり、さらに必要に応じてより細分化されたKPIを新設したり、現状に即して数値を微調整したりできます。
定性的な要素や感覚的な指標は数値化が困難なため、KPIツリーの構成要素としては適していません。また、四則演算による関係性が明確でないような指標を含めてしまうと、ツリー全体の論理的なバランスが崩れてしまい、効果的な管理が困難になる可能性があります。
②単位を設定する
各KPIには適切な単位を設定することが重要です。単位の設定が不適切だと、指標間の関係性が崩れ、正確な分析や評価が困難になります。
例えば、売上に関するKPIであれば「円」「件数」「率」などの単位を明確に区別し、それぞれの指標が持つ意味を正確に表現する必要があります。また、時間軸に関する単位(日次、月次、年次など)も統一したうえで管理し、比較が可能な形で設定することが重要です。
特に複数の部門が関わるKPIツリーでは、部門間で単位の認識を統一し、データの整合性や部門間でのシームレスな活用が確保されているか確認しましょう。
③分解する要素を遅行指標から先行指標に
KPIツリーの分解においては、遅行指標(結果指標)だけはなく、先行指標(行動指標)も扱うことが重要です。
遅行指標とは最終的に得られる成果を表す指標であり、売上高や利益率などが該当します。一方、先行指標は成果のための行動や取り組みについての指標で、商談件数や顧客接点数などが該当します。
最終目標であるKGIに近づくほど遅行指標となるため、KPIがKGIの達成に向けて分解された指標であることを踏まえると、KPIは先行指標を取り入れて設定する必要があります。
KGIやより上位のKPIを先行指標であるKPIに分解することにより、具体的かつ実現可能性の高いKPIや、それに基づくアクションを設定することが可能になります。
④KPIになり得ない要素に注意する
すべての指標がKPIとして適切とは限りません。KPIとして設定する指標は、目標達成との関連性が定量的に明確で、測定可能であり、かつ具体的に実践可能なアクションであることに注意が必要です。
例えば、「従業員の満足度」のような定性的な指標や、「天候」のような制御不能な要素は、直接的なKPIとしては適していないため、誤って使用していないか注意が必要です。
また、複数の指標が同じような内容を含んでいる場合は、最も重要度の高い指標のみを選択し、シンプルな構造を維持することを意識するようにしましょう。KPIの数が多すぎると管理が煩雑になり、かえって効率が低下する可能性があるため、本当に重要な指標のみに絞り込むことも必要です。
【その目標管理、実は成果が出ないやり方かも?】
国内の多くのマネージャーは目標設定・目標管理のやり方を教えられずに、いきなり目標管理を任されています。
そんなマネージャーの中に、成果が出ない目標管理で苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。そんな国内に満映している「間違いだらけの目標管理」について解説した資料を公開中です!
>>「間違いだらけの目標管理」はコチラから無料ダウンロード!
KPIツリーの例
KPIツリーの実践的な活用方法を理解するために、具体的な事例を見てみましょう。
ここでは、特に企業活動の中核を担う存在である営業部門と人事部門(採用)のKPIツリーの具体例を紹介します。これらの例を参考にすることで、自社の状況に合わせたKPIツリー作成のイメージが掴むことができるでしょう。
営業の場合

営業部門のKPIツリーでは、通常、売上高や利益率といった財務的なKGIを頂点に設定します。
ここでは、「年間売上高〇億円」というKGIがある場合を例に、KPIに分解していきましょう。
まず、売上高は「受注(顧客)数×顧客単価」に分解できます。さらに「受注(顧客)数」は「新規顧客数」と「既存顧客数」に、「顧客単価」は「商談単価」と「成約率」というように展開することができます。
これらのKPIを達成するために、営業部門では先行指標として「商談数」や「リード獲得数」などの指標を、より下層のKPIである具体的な行動目標として設定することができます。
また、「顧客訪問件数」や「提案書提出件数」といった具体的なアクションについての指標をより下層のKPIとして設定することで、日々の営業活動の方向性を明確にすることにも繋がるでしょう。
人事(採用)の場合

採用担当者のKPIツリーでは、「年間採用計画の達成」や「必要人材の確保」といったKGIを設定します。
例えば、「新卒採用○○名」というKGIがある場合、これを「応募者数」「内定率」という要素に分解していきます。
この「応募者数」というKPIに着目してさらに分解してみると、「求人サイトA経由数」や「自社HP経由数」として展開され、さらに「自社HP経由数」は「サイト訪問数」や「実際の応募率」といったより詳細なデータ指標に落とし込むことができます。
採用活動では、季節性や市場環境の変化が大きく影響するため、時期に応じて柔軟な目標設定を行う必要があります。
また、採用市場の動向や競合他社の状況なども考慮しながら、設定したKPIについては適宜見直しを行いましょう。
効果的な目標管理・納得度の高い人事評価なら「Co:TEAM(コチーム)」

- 1on1をしながら、目標の進捗を入力できる!
- 目標の結果を人事評価に反映!
- 目標の進捗・結果を全て見える化!
- 1on1の記録を人事評価時に活用できる!
よくあるご質問(FAQ)
KPIツリーを作成することの最大のメリットは何ですか?
A: KGI達成を阻害するボトルネック(制約要因)を早期に特定できることです。 ツリーによってどの指標が目標達成に最も影響しているかが明確になり、効率的なリソース配分や業務改善のための施策を重点的に講じることができます。
KPIツリーの構成要素を分解する際に、特に重要視すべきポイントは何ですか?
A: 各指標間の関係性が四則演算(加減乗除)で表現できる論理的な構造であることです。 これにより目標値の設定や進捗管理が明確になり、ツリー全体の論理的なバランスを維持することができます。
KPIツリーの分解における「遅行指標」と「先行指標」とは、それぞれ何を指しますか?
A: 遅行指標は最終的に得られる成果(結果指標)であり、売上高や利益率などが該当します。先行指標は成果のための行動や取り組み(行動指標)であり、商談件数や顧客接点数などが該当します。KPIには先行指標を取り入れることが重要です。
営業部門のKPIツリーを作成する際、KGIからどのようにKPIを分解していく具体例がありますか?
A: KGI(年間売上高)は、まず「受注(顧客)数 × 顧客単価」に分解できます。 さらに「受注(顧客)数」は「新規顧客数」と「既存顧客数」に、「顧客単価」は「商談単価」と「成約率」などに分解し、最終的に「顧客訪問件数」や「リード獲得数」といった先行指標まで落とし込みます。
KPIツリーに含めるべきではない要素や指標には、どのようなものがありますか?
A: 「従業員の満足度」のような定性的な指標や、「天候」のような制御不能な要素、または目標達成との関連性が薄い指標は、KPIとして適していません。測定可能で、具体的なアクションにつながる指標に絞り込むことが重要です。
まとめ
KPIツリーは、組織の目標達成を現場レベルから取り組むための重要なマネジメントツールです。
本記事では、KPIツリーの基本的な概念から具体的な作成方法、実践的な活用例まで広く解説してきました。
KPIツリーの導入は、単なる数値管理ツールの実装ではなく、組織全体の目標達成に向けた取り組みの一環として位置づけることが重要です。
また、経営層から現場まで全ての従業員が、最終目標(KGI)とその達成に向けた個別指標(KPI)を理解し、日々の業務において実践していくことで、KPIツリーの真の効果を発揮することができます。
そのため、現場の状況に即して適切に設計されたKPIツリーは、組織の目標達成と成長を支える強力なツールとなり得るでしょう。
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。