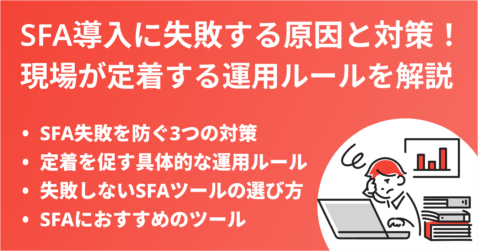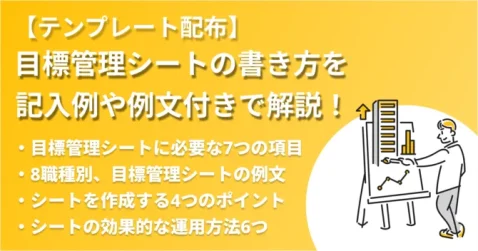人事評価は企業の人材を上手に活用する上で非常に重要となる業務の1つですが、「どのようにすれば公正で納得感のある評価を行えるのか分からない」という担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、人事評価の目的から具体的な書き方のポイント、職種別の例文まで幅広く解説していきます。
【全5職種対応・自動計算機能付き】
営業・事務・管理職など主要職種の評価項目例つき!
Excel / Googleスプレッドシートに対応し、そのまま使える人事評価テンプレートシートを無料公開中!
>>『人事評価のテンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!
▼ この記事の内容
- コメントの目的:評価の根拠を客観的に示し、人材育成と組織の風土形成に活用することです。 点数だけでは分からない成果とプロセスを明文化し、給与決定の根拠とします。また、企業が重視する価値観(例:チームワーク)を従業員の行動指針として浸透させます。
- 書き方の技術:結果だけでなくプロセスの両方を評価し、良い点と改善点の両方を書く「サンドイッチ法」が有効です。 抽象的な表現ではなく「顧客満足度4.8点」「前年比120%達成」など具体的な事実や数字で裏付けます。定性的な業務も行動目標に落とし込み、客観性を高めます。
- 職種別のコツ:定量評価が難しい職種(企画・事務・公務員)ほど、日頃の行動観察と目標設定が重要です。 事務職は正確性・効率化の貢献度、企画職は市場分析の的確さ、製造職は不良率の改善度など、それぞれの職種に特化した評価ポイントを設けます。
目次
人事評価の目的
人事評価(人事考課)は単なる従業員の査定ではなく、会社と従業員の双方にとって重要な意味を持つプロセスです。ここで適切な評価制度を運用することで、従業員の成長を促し、会社全体の業績向上につなげることができます。
ここでは、人事評価の主な3つの目的を紹介します。
- 従業員一人ひとりの業績や能力を客観的に評価し、適切な等級や給与を決定することです。公平な評価基準に基づいて従業員の貢献度を測ることで、納得感のある処遇を実現できます。
- 組織風土の形成です。評価プロセスを通じて会社の価値観や目標を共有し、従業員のエンゲージメントを高めることができます。
- 人材育成への活用です。評価結果をもとに従業員の強みや改善点を明確にし、効果的な育成計画を立てることができます。
これらの3つの目的について、詳しく解説していきます。
適切な評価・等級・報酬を決める
人事評価の最も基本的な目的は、従業員の業績や能力を適切に評価し、それに見合った等級や給与を決定することです。公平で納得感の高い評価を行うことで、従業員のモチベーションを維持・向上させることができます。
評価結果は昇給・昇進・人事異動といった処遇に直結するため、客観的な基準が欠かせません。例えば、営業職であれば売上や新規顧客獲得数などの数値化できる指標を用いることで、評価の客観性を高めることができます。
一方、事務職や企画職など定量的な評価が難しい職種については、業務の質や効率化への貢献度など、できるだけ具体的な基準を設定することが重要です。
また、評価の透明性も重要なポイントです。評価基準や評価プロセスを従業員に明確に伝えることで、「なぜこの評価結果になったのか」という疑問を解消し、納得感を高めることができます。評価面談などを通じて評価結果の根拠を丁寧に説明することも、従業員の理解を深める上で効果的です。
さらに、評価結果を給与や賞与に反映させる際のルールも明確にしておくことが大切です。成果に応じて適切に報酬として従業員に還元することで、従業員のモチベーションを向上させ、結果として会社全体の生産性向上につなげることができます。
円滑な組織風土を形成する
人事評価は、個人の処遇決定だけでなく、組織全体の風土形成にも大きな影響を与えます。適切な評価制度の運用は、チームワークや協調性を重視する文化の醸成につながるでしょう。
評価基準に「チーム内での連携」や「情報共有への貢献」といった項目を設けることで、個人の成果だけでなく組織への貢献も重視されていると従業員に明確に伝わります。その結果、部署やチーム全体の目標達成に向けた協力的な風土が育まれます。
また、評価プロセスを通じて会社の方向性や価値観を共有することも、従業員に組織風土を浸透させるうえで効果的な方法です。例えば、「顧客満足度の向上」や「業務効率化」などの会社が重視する価値観を評価項目に反映させることで、従業員の行動指針を会社のビジョンに沿った形で設定することができます。
このように、評価者は単に点数をつけるだけでなく、組織風土の形成者としての役割も意識することが大切です。
1on1ミーティングを中心に組織の理念を浸透させて、従業員のエンゲージメントを高める方法!
>>『「あきらめ組織」の理念浸透〜「王女奪還」につなげる1on1〜』はこちらから無料ダウンロード!
人材育成への活用
人事評価を通じて従業員の成長を促すことで、効果的な人材育成を実現することができます。
評価面談では、単に評価結果を伝えるだけでなく、今後の成長に向けたアドバイスやプロセスを伝えることが重要です。例えば、「プレゼンテーションスキルをさらに高めるために、社内勉強会に参加してみてはどうか」など、具体的な成長機会を提案することで、従業員の成長を促すことができるでしょう。
さらに、従業員の評価データを分析することで、組織全体の傾向や課題を把握することも可能です。例えば、「多くの従業員がプロジェクト管理スキルに課題がある」といった傾向が見られれば、全社的な研修プログラムを企画するなど、効率的な人材育成施策を講じることができます。
人事評価を単なる査定ではなく、従業員と会社が共に成長するための機会と捉えることで、組織全体の成長につなげることができるのです。
>>【マネージャーの負荷削減と組織の生産性向上を実現】3分でわかる「コチーム」がわかる資料3点セットを無料でダウンロードする
人事評価シートとは
人事評価シートは、従業員の業績や能力、態度などを客観的に評価するためのツールです。多くの企業で人事評価の基本的なツールとして活用されており、公平で透明性の高い評価を実現し、そして内容を書面で補完するためにも作成が欠かせません。
人事評価シートには通常、評価対象期間における目標とその達成度、業務実績、能力評価、情意評価などの項目が含まれています。また、評価者のコメント欄や本人の自己評価欄を設けている場合も多く、双方向のコミュニケーションツールとしての役割も果たしています。
構成は企業によって異なりますが、多くは5段階や10段階の数値評価と、事実や行動を記述するコメント欄の組み合わせです。数値評価だけでは伝わらない細かなニュアンスや具体的な事例をコメントで補足することで、より公平で納得感のある評価が可能になります。
なお、人事評価シートは人事評価面談の前に作成されることが基本です。以下の記事では、人事評価面談の進め方、ポイント、よくある失敗例などについて具体的に解説していますので、よろしければ本記事と合わせてご覧ください。
主要な人事評価の3つの評価基準
人事評価を行う際には、主に次の3つの評価基準が用いられます。
目標に対する達成度や成果を評価する「業績評価」、業務遂行に必要なスキルや知識、判断力などを評価する「能力評価」、仕事に対する姿勢や態度、チームへの貢献度を評価する「情意評価」です。
それぞれの基準は、異なる側面から従業員を評価するためのもので、これらをバランスよく組み合わせることで、総合的かつ公平な評価が可能になります。企業の特性や職種によって各基準の重み付けは異なりますが、いずれも従業員の多面的な評価には欠かせない要素となっています。
これらの評価基準について、さらに詳しく解説していきます。
業績評価
業績評価は、設定された目標に対する達成度や具体的な成果を評価する基準です。数値化しやすく客観性が高いため、多くの企業で評価の肝として位置づけられています。
業績評価の最大の特徴は、明確な数字や事実に基づいて評価できることです。例えば、営業職であれば売上目標の達成率や新規顧客獲得数、製造職であれば生産効率や不良品率の改善度合いなど、具体的な数値で成果を測ることができます。このような客観的な指標を用いることで、評価の公平性や納得感を高めることができます。
業績評価を効果的に行うためには、期初に明確な目標設定を行うことが重要です。目標は具体的で測定可能なものに設定し、いわゆるSMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に基づくことが望ましいでしょう。
業績評価のコメントを書く際には、具体的な数字や事実を示しながら、目標に対する達成状況を客観的に記述することがポイントです。例えば、「前年比120%の売上を達成し、特に新規顧客からの受注が30%増加した」など、具体的な成果を明記することで説得力のある評価となります。
ただし、業績評価だけでは従業員の総合的な価値を測ることはできません。というのも、短期的な数字だけを追求すると、表面化しにくい組織への貢献や、スキルアップや成長のための取り組みが軽視されてしまう恐れがあります。そのためにも、次に説明する能力評価や情意評価とバランスよく組み合わせることが重要です。
能力評価
能力評価は、従業員が業務を遂行する上で必要なスキルや知識、判断力などを評価する基準です。業績評価が「何を達成したか」を測るのに対し、能力評価は「どのような力を持っているか」を測ります。
能力評価の対象となるのは、専門知識や技術スキル、問題解決能力、コミュニケーション能力、リーダーシップなど、業務を行う上で必要となってくる様々な能力です。能力評価は、必ずしも直接的な成果や数字として現れるものではないものの、確かに業務や組織に貢献している人材としての価値を評価するという意味で、欠かすことができません。
能力評価を行う際には、職種や役割に応じた適切な評価項目を設定することが求められます。例えば、技術職であれば専門知識の深さや技術的な問題解決能力、営業職であれば顧客理解力や提案力、管理職であればマネジメント能力やリーダーシップなど、それぞれの職種に求められる能力を明確にすることで、より適切な評価が可能になります。
能力評価のコメントを書く際には、具体的な行動や事例を挙げながら、その人の能力を客観的に記述することがポイントです。例えば、「複雑な顧客要望を的確に理解し、技術部門と連携しながら最適な解決策を提案できている」など、抽象的な能力ではなく、実際の業務場面での発揮状況を具体的に記述することで説得力が増します。
また、能力評価は現状の能力だけでなく、成長の可能性や伸びしろも含めて評価することが大切です。特に若手従業員の場合、現時点での能力や資格はどうしても限定されてしまいますが、学習意欲や成長スピード等も加味してを評価することで将来の活躍に対する投資としても機能するでしょう。
能力評価は業績評価と比べて主観的になりがちですが、できるだけ具体的な事実や行動に基づいて評価することで、公平性と納得感を高めることができます。また、定期的なスキルチェックやテストなどの客観的な指標を併用することも効果的です。
なお、能力評価と混同されやすい評価手法として、近年多くの企業で注目を集めている「コンピテンシー評価」があります。コンピテンシー評価については以下の記事で具体的に解説していますので、気になりましたらぜひご覧ください。
情意評価
情意評価は、従業員の仕事に対する姿勢や勤務態度、チームへの貢献度などを評価する基準です。業績や能力といった「できること」ではなく、「どのように取り組んでいるか」という側面に焦点を当てます。
情意評価の対象となるのは、積極性、協調性、責任感、規律性、顧客志向性などの態度や姿勢です。これらは数値化が難しく、評価者の主観に左右されがちですが、組織の一員としての適性を測る上で重要な指標となります。
情意評価を効果的に行うためには、評価項目を具体的な行動レベルで定義することが重要です。例えば、「チームメンバーの意見に耳を傾け、建設的な議論ができる」「他部署からの依頼に対して迅速かつ丁寧に対応する」など、具体的な行動目標や達成条件を定義しておくことで、評価の客観性を高めることができます。
情意評価のコメントを書く際には、日常の業務における具体的な行動や事例を挙げることがポイントです。例えば、「顧客からの全てのクレームや問い合わせに対して必ず30分以内に対応を行っていることから、迅速かつ丁寧に対応し信頼関係の構築に努めていることが伺える」など、具体的なエピソードや事実を交えることで説得力のある評価となります。
このように、ともすれば主観的になりがちな情意評価ですが、具体的なエピソードや事実から引用すること、勤怠や対応のデータを活用すること、複数の評価者で評価を行うこと等の工夫によって客観性を高めることができます。もちろん、評価者自身のバイアス(先入観や思い込み)に注意し、公平な視点で評価することが前提となります。
情意評価は、短期的な業績だけでなく、長期的な組織への貢献や職場の雰囲気づくりにも大きく影響します。特に、チームワークや組織文化を重視する企業では、情意評価の比重が高くなる傾向があります。
納得度の高い人事評価シートの書き方
人事評価は単なる点数付けではなく、メンバーの成長を促し、モチベーションを高めるためのコミュニケーションツールです。
ここでは、評価者としてメンバーが納得できる評価を行うために、記載すべき内容やコツを4つ紹介していきます。
評価の根拠・理由を客観的に書く
人事評価において最も重要なのは、評価の根拠や理由を客観的に示すことで、従業員に納得して受け入れてもらうことです。
評価コメントを書く際には、抽象的な表現や主観的な印象ではなく、具体的な事例や数値を用いることがポイントです。例えば、「仕事が丁寧」という抽象的な表現ではなく「顧客からのクレーム対応において、過去の取引履歴を詳細に調査し、適切な解決策を提案したことで、顧客満足度調査で5段階中4.8の高評価を獲得した」など、具体的な行動や結果から引用し、さらには記録やデータ等も活用することで説得力が増します。
このような客観的な評価を行うためには、日頃から、部下の行動や成果を記録して準備しておくことが重要です。評価期間になって慌てて思い出すのではなく、普段から「いつ、どのような場面で、どのような行動をとり、どのような結果をもたらしたか」を具体的にメモしたり、記録やデータが残るようにシステム等を整備したりすることで、より正確で公平な評価が可能になります。
さらに、複数の視点から評価することも客観性を高める上で効果的です。このような評価手法は「360度評価」とも呼ばれ、同僚や他部署の管理職、顧客からのフィードバックなど、様々な角度からの情報を収集することで、より多面的で公平な評価ができます。
結果とプロセスの両方について触れる
人事評価においては、最終的な結果や数字だけでなく、そこに至るまでの行動プロセスやアプローチも必ず評価対象にしましょう。目標達成の有無や数字だけを評価すると従業員のモチベーションが短期的な成果に偏りがちになり、長期的な成長や組織への貢献といった比較的表出しにくい取り組みがおろそかになる恐れがあります。
よって評価コメントを書く際には、「何を達成したか(結果)」と「どのように達成したか(プロセス)」の両方に触れることがポイントです。
例えば、「年間売上目標120%を達成した」という結果があるとして、そこには何かしらの成功要因が存在するはずです。そして、そこに「顧客ニーズを深く理解するために定期的な訪問活動を前期比1.5倍に増やし、顧客との信頼関係を構築したことが大きな成功要因となった」というプロセスがあったとして、結果とそれを生み出したプロセスの両方を評価することで、より総合的な評価が可能になります。
また、目標は達成できなかったものの、優れたアプローチを行っていたり、何かしらの努力を行っていたりと、プロセス部分に優れた点がある場合も評価に反映させることが大切です。
例えば、「売上目標は90%の達成率だったが、新規顧客開拓のための市場調査を徹底的に行い、将来の成長につながる顧客リストを作成した」など、短期的な結果だけでなく、長期的な視点での取り組みも評価することで、バランスの取れた評価となります。
プロセスの評価は特に、若手従業員や新しい業務に挑戦している従業員にとって重要です。経験が浅い段階では結果を出すことが難しくても、正しいプロセスで取り組んでいれば、将来的な成長が期待できます。そうした可能性を評価して若手を激励することで、モチベーションの維持・向上につながります。
【参加者満足度98.2%!】
明日から使える1on1で重要な「承認」「共感」「フィードバック」のテクニックをわかりやすく解説!
「今まで受けた研修で1番良かった!」「マネジメントの新しい考え方を得れた!」など現場管理職・マネージャーに大人気の1on1研修の第1回目の資料を無料公開中!!
>>1on1研修第1回『マネジメントと1on1って何ですか?』はこちらから無料ダウンロード
良い点・改善点の両方を書く
人事評価において、良い点と改善点の両方をバランスよく伝えることは非常に重要です。悪い点ばかりを指摘すると、被評価者のモチベーションが低下し、建設的な改善につながりにくくなります。一方、良い点だけを強調すると、成長の機会を逃してしまう恐れがあります。
評価コメントを書く際には、まず被評価者の強みや成果を具体的に認め、その上で改善点や今後の期待を伝えるという流れが最適です。
例えば、「顧客対応において、丁寧かつ迅速な対応で高い評価を得ている。特に、クレーム対応では冷静な判断力を発揮し、問題解決に貢献している」という良い点をしっかり認めた上で、「今後は、より複雑な案件にも対応できるよう、商品知識をさらに深めることでさらなる活躍が期待できる」といった具合にさらなる成長に向けた改善点やアドバイスを行います。
さらに、改善点を伝える際には、批判的な表現ではなく、建設的なアドバイスとして伝えることがポイントです。
例えば「報告書の提出が遅い」という指摘を行うときは、「報告書の作成プロセスを見直し、より効率的な方法を検討することで、提出期限の遵守と内容の充実の両立が期待できる」など、具体的な改善策を示すことで、前向きな受け止め方をしてもらうことができます。
改善点を伝える際に活用できる技術として、「サンドイッチ法」と呼ばれる指導方法があります。これは、良い点→改善点→良い点という順序で伝えることで、改善点が際立ちすぎないようにする方法です。ただし、形式的になりすぎると逆効果になる場合もあるので、状況に応じて柔軟に対応することが大切です。
また、良い点と改善点のバランスは、被評価者の経験や能力レベルによっても調整すべきです。例えば、若手や新任者に対しては、良い点をより多く伝えて自信を持たせる一方、ベテランや管理職に対してはより高いレベルでの改善点を伝え、さらなる成長を促すことが効果的です。
定性的な業務の評価は達成条件を明確にする
定性的な業務、つまり数値化しにくい業務の評価は、評価者の主観に左右されがちで、被評価者の納得感を得ることが難しい場合があります。そのため、評価基準を明確にし、できるだけ客観的な評価を行うことが重要です。
定性的な業務の評価基準を明確にするためには、まず「何をもって良い成果とするか」を具体的な行動レベルで定義することがポイントです。
例えば「コミュニケーション能力」という抽象的な項目を評価軸とする場合、「会議での発言の的確さ」「報告書の分かりやすさ」「関係部署との情報共有の頻度と質」など、より具体的な行動指標に分解することで、評価の客観性を高めることができます。
また、評価基準を段階的に設定することも効果的です。例えば、「期待を大きく上回る」「期待を上回る」「期待通り」「改善の余地あり」「大幅な改善が必要」といった段階ごとに、具体的にどのような行動や成果が該当するかを明示することで、評価の透明性が増します。
評価コメントを書く際には、具体的な事例や行動を挙げながら、設定した評価基準に照らしてどのように評価したかを明記することがポイントです。
例えば企画職の評価コメントを作成する場合は、「新商品企画において、徹底的な市場調査に基づいた提案を行い、特に顧客ニーズの分析が的確だった。また、関係部署との調整も円滑に進め、当初のスケジュールどおりに企画を完成させた」というように具体的な行動とその効果を記述することで、評価に説得力を持たせることができます。
そして最も重要なポイントとして、定性的な業務の評価では、評価者のバイアス(先入観や思い込み)が含まれていないかを十分にチェックしましょう。「最近の印象」や「個人的な好き嫌い」に左右されないよう、評価期間全体を通じた行動や成果を客観的に振り返ることが大切です。
【職種別】人事評価シートの書き方例
職種によって求められる能力や成果は異なるため、人事評価シートの書き方も職種ごとに工夫する必要があります。
ここでは、代表的な職種別の評価ポイントと具体的な記入例を紹介します。実際に人事評価を任される上司や管理職といった立場の方に、是非参考にしていただきたい内容になっています。
➀営業職の場合
営業職の評価では売上や新規顧客獲得などの定量的な成果が偏重されがちですが、顧客との関係構築や提案力といった定性的な取り組みについても、バランス良く考慮することが重要です。
実際の例として、評価に含めるべきポイントと、それらのポイントを考慮した評価コメント例を紹介します。
▶評価ポイント
- 売上目標の達成度
- 新規顧客開拓数
- 既存顧客との関係維持・深耕
- 提案力・交渉力
- 市場動向の把握と分析力
▶具体的な評価コメント例
年間売上目標120%を達成し、特に新規顧客からの受注が前年比30%増と顕著な成果を上げている。顧客ニーズを的確に把握し、技術部門と連携しながら最適な提案を行う能力が高く評価できる。
また、定期的な顧客訪問を通じて信頼関係を構築し、リピート率の向上にも貢献している。
今後はより複雑な案件にも対応できるよう、商品知識をさらに深めるとともに、チーム内での知識共有にも積極的に取り組むことを期待する。
このように、具体的な数字や事例を交えながら、成果とそれを生み出した能力や行動を評価することがポイントです。また、今後の期待や成長の方向性も明確に示すことで、次期の目標設定にもつなげましょう。
②企画・マーケティング職の場合
企画・マーケティング職の評価では、創造性や市場分析力、プロジェクト推進力などが重要なポイントとなります。数値化しにくい業務が多いため、具体的な成果や行動基準を明確に記述することが大切です。
実際の例として、評価に含めるべき代表的なポイントと、それらのポイントを考慮した評価コメント例を紹介します。
▶評価ポイント
- 市場分析の的確さ
- 企画の新規性・実現可能性
- プロジェクト管理能力
- 関係部署との調整力
- 成果の測定と改善提案
▶具体的な評価コメント例
新商品企画において徹底的な市場調査と競合分析に基づいた提案を行い、経営層からも高い評価を得た。特に顧客インタビューを30件以上実施し、潜在ニーズを的確に捉えた点が優れている。
また、関係部署との調整も円滑に進め、当初のスケジュールどおりに企画を完成させた。マーケティング施策の効果測定も定期的に行い、PDCAサイクルを回しながら改善を重ねている点も評価できる。
今後はより中長期的な視点での市場予測にも取り組み、会社の成長戦略に貢献することを期待する。
企画・マーケティング職の評価では、数値化できる部分(調査件数、スケジュール遵守率など)も積極的に取り入れつつ、創造性やコミュニケーション能力などの定性的な部分もバランスよく評価することがポイントです。
③製造職の場合
製造職の評価では、生産性や品質、安全管理などが重要なポイントとなります。また専門性が高い傾向にあるため、技術の習得・向上なども十分に考慮すると良いでしょう。
実際の例として、評価に含めるべき代表的なポイントと、それらのポイントを考慮した評価コメント例を紹介します。
▶評価ポイント
- 生産目標の達成度
- 製品品質の維持・向上
- 安全規則の遵守
- 改善提案の件数と質
- 技術スキルの習得・向上
▶具体的な評価コメント例
生産ラインの効率化に積極的に取り組み、前年度比15%の生産性向上を達成した。特に段取り時間の短縮に創意工夫を凝らし、担当ラインの稼働率向上に大きく貢献している。品質面でも不良率を0.5%以下に抑え、高い水準を維持している。
また、安全面では常に5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を徹底し、職場の安全確保に努めており、さらに改善提案も年間10件以上提出し、そのうち3件が全社的に採用されるなど、積極的な姿勢が評価できる。
今後は若手社員への技術指導にも力を入れ、チーム全体のスキルアップに貢献することも期待できる。
このように、製造職の評価では、数値化できる指標(生産性、不良率、改善提案件数など)を積極的に活用しつつ、安全意識や改善への取り組み姿勢なども含めた総合的な評価を行うことがポイントです。
④公務員の場合
公務員の評価は民間企業のサラリーマンとは評価軸が異なり、法令遵守や公平性、市民サービスの質などが重要なポイントとなります。また、限られた予算や人員の中での効率的な業務遂行能力も評価の対象となります。
実際の例として、評価に含めるべき代表的なポイントと、それらのポイントを考慮した評価コメント例を紹介します。
▶評価ポイント
- 法令・規則の理解と遵守
- 市民対応の丁寧さ・公平性
- 業務の正確性・効率性
- 問題解決能力
- チームワーク・協調性
▶具体的な評価コメント例
窓口業務において複雑な制度内容を利用者に分かりやすく説明し、申請手続きをスムーズに進めることができている。特に、高齢者や外国人など配慮が必要な方の相談に対する対応が丁寧で、クレームの発生が皆無である点が高く評価できる。
また、申請書類のチェック漏れがなく、処理時間も平均より20%短縮されている。さらに、業務マニュアルの改訂にも積極的に取り組み、部署全体の業務効率化に貢献した。
今後はさらに幅広い業務知識を習得し、より複雑な案件にも対応できるよう成長することを期待する。
このように、公務員の評価では市民サービスの質と効率性のバランスを重視し、具体的な事例や数字を用いて客観的に評価することがポイントです。
⑤販売職の場合
販売職の評価では、売上目標の達成度や顧客対応の質、商品知識などが重要なポイントとなります。また、個人店ではない販売職は基本的に店舗ごとでのチームプレーの色合いが強くなるため、店舗運営への貢献やチームワークも評価の対象となります。
実際の例として、評価に含めるべき代表的なポイントと、それらのポイントを考慮した評価コメント例を紹介します。
▶評価ポイント
- 個人売上目標の達成度
- 顧客満足度・リピート率
- 商品知識の深さと提案力
- 在庫管理・ディスプレイ技術
- チームワーク・協調性
▶具体的な評価コメント例
個人売上目標を110%達成し、特に高単価商品の販売が前年比25%増と顕著な成果を上げている。顧客のニーズを丁寧にヒアリングし、最適な商品を提案する能力が高く、顧客アンケートでも満足度評価が5段階中4.7と高評価を得ている。新商品の知識習得にも積極的で、商品研修では常に上位の成績を収めている。
また、売り場のディスプレイ改善にも創意工夫を凝らし、店舗全体の売上向上にも貢献している。
今後は、さらに幅広い商品知識を習得するとともに、新人スタッフの育成にも力を入れることを期待する。
このように、販売職の評価では、売上などの数値目標の達成度と、顧客対応の質やチームへの貢献などのバランスを重視することがポイントです。具体的な事例や顧客からのフィードバックなども積極的に取り入れることで、多面的な評価を行うことができます。
⑥事務職の場合
事務職の評価では、業務の正確性や効率性、情報管理能力などが重要なポイントとなります。また、バックオフィス職に求められる能力として、関係部署との連携やサポート力も評価の対象となります。
実際の例として、評価に含めるべき代表的なポイントと、それらのポイントを考慮した評価コメント例を紹介します。
▶評価ポイント
- 業務の正確性・期限遵守
- 事務処理の効率性
- 情報管理・セキュリティ意識
- 関係部署とのコミュニケーション
- 業務改善への取り組み
▶具体的な評価コメント例
経費精算業務においてミスなく正確に処理を行い、月次締め作業も常に期限内に完了している。特に、前任者が3日かかっていた集計作業を、Excelのマクロを活用して工数削減し1日に短縮するなど、業務効率化に積極的に取り組んでいる点が高く評価できる。
また機密情報の取り扱いも適切で、セキュリティ意識が高い。関係部署からの問い合わせにも迅速かつ丁寧に対応し、「頼りになる」との評価を得ている。さらに、事務マニュアルの改訂にも取り組み、部署全体の業務標準化に貢献した。
今後は、より幅広い業務知識を習得し、部署の中核人材として成長することを期待する。
このように、事務職の評価では、正確性や効率性などの基本的な業務品質と、業務改善やサポート力などの付加価値のバランスを重視することがポイントです。
以下の記事でも、人事評価コメントの書き方について例を挙げながら解説しています。本記事では紹介しきれなかった職種についても記載していますので、さらに詳しく知りたい方はぜひご確認ください。
人事評価はシステムで評価を公正かつ簡単に!
人事評価業務は、多くの企業で大きな負担となっています。紙ベースでの評価シートの配布・回収や、Excel管理による集計作業など、煩雑な業務が評価者や人事部門の負担となり、本来の目的である「公平な評価」や「人材育成」に十分なリソースを割けないケースも少なくありません。
このような人事業務を効率化し、現場の負担を軽減するためにも、人事評価のDX(デジタルトランスフォーメーション)を検討してみてはいかがでしょうか。
人事業務のDX化は、単に紙をデジタルに置き換えるだけではなく、評価プロセス全体を見直し、より効果的な人材育成や組織開発につなげること、さらに適切なシステムを選定することが重要です。
煩雑な評価業務はシステムの活用がおすすめ
煩雑な人事評価業務をシステムの導入によってDX化することで、評価プロセスの効率化だけでなく、評価の公平性や透明性の向人事データに基づいた人材育成など様々なメリットが得られます。
人事評価システムの主な機能としては、評価シートのオンライン化、評価フローの自動化、評価結果の集計・分析、フィードバック機能などがあります。このような人事システムを導入する際には、自社の評価制度や組織規模に合ったものを選ぶことが重要です。
また、単にシステムを導入するだけでなく、評価者向けのシステム導入研修や評価基準の見直しなど、運用面での取り組みも併せて行うことで、より効果的な人事評価が実現します。
目標管理から人事評価までシームレスに行うことができる人事系のシステムとして、「コチーム」というサービスをおすすめします。
「コチーム」は無料トライアル期間を設けているため、自社のニーズに合うかをノーリスクで確認してから導入できる上に、導入企業への研修やサポートも充実しており、人事のプロのサポートを受けながら人事業務のDX化を実現できます。
公平な人事評価・評価業務の効率化なら「コチーム」!

- 1on1の記録や目標の進捗を人事評価にカンタンに確認でき、根拠のある評価を実現!
- 人事評価シートを自動生成・配布・収集でき、人事担当者の負担を軽減!
- あらゆる人事評価や評価調整(甘辛調整)に対応!
- 評価材料を集めるための1on1テンプレートで、日常から評価材料を集めるマネージャーを育成する!
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 人事評価コメントを書く際、上司が最も意識すべきポイントは何ですか?
A: 「客観的な根拠」と「今後の成長の方向性」を明確に示すことです。 評価者の主観的な印象ではなく、具体的な行動や数字を引用します。また、改善点を指摘した際は、必ず「では、来期どうすれば良いか」という成長に向けたアドバイスを添えましょう。
Q2. 営業職のように成果が数値で出ている場合、コメントは必要ですか?
A: はい、結果を褒めるだけでなく、その「成功プロセス」を明文化するために必要です。 単に「目標達成」で終わらせず、「なぜ達成できたか(例:顧客訪問を1.5倍に増やした)」というプロセスを評価します。これはチーム全体のノウハウ蓄積と、本人の再現性の向上につながります。
Q3. 事務職や公務員など、定性的な業務の評価基準を明確にするコツは?
A: 業務を「行動目標」に分解し、「達成条件」を具体的に定義することです。 例えば、「コミュニケーション能力」を「関係部署からの問い合わせに30分以内に対応する」など、Yes/Noで判断できる行動レベルに落とし込み、評価の主観性を排除します。
Q4. 評価コメントが形式的になり、部下との信頼関係が築けません。
A: 定期的な「1on1ミーティング」で、評価面談前の認識のズレを解消しましょう。 面談前に部下の自己評価と進捗を日常的に確認し、お互いの認識をすり合わせます。面談は一方的な通知の場ではなく、信頼関係に基づく双方向の対話の場にすることが大切です。
Q5. 評価コメントで、改善点を伝える際の注意点は何ですか?
A: 批判的な言葉や人格否定は避け、建設的なアドバイスに徹することです。 改善点を良い点で挟む「サンドイッチ法」を活用し、指摘ではなく「次はこれを試してみよう」という具体的な改善策を示すことで、部下が前向きに受け止められるように配慮します。
まとめ
本記事では、人事評価の書き方について目的から具体的なポイント職種別の評価コメント例まで幅広く解説してきました。
評価者として重要なのは、評価の根拠や理由を客観的に示すこと、結果だけでなくプロセスにも着目すること、良い点と改善点の両方をバランスよく伝えること、定性的な業務については評価基準を明確にすること等が挙げられます。これらのポイントを押さえることで、被評価者の納得感を高め、モチベーションの向上につなげることができます。
また、職種によって求められる能力や成果は異なるため、評価のポイントも変わってくることについても紹介しました。営業職であれば売上や顧客開拓、製造職であれば生産性や品質、事務職であれば正確性や効率性など、それぞれの職種に応じた評価基準を設定し、具体的な事例や数字を用いて客観的に評価することが重要です。
さらに人事評価業務の効率化や公平性向上のためには、人事評価システムの活用も有効です。評価プロセスの自動化やデータの一元管理により、評価者の負担を軽減し、さらには評価の質を向上させることにもつながります。
適切な評価を行うことは、従業員のモチベーション向上と組織の競争力強化に直結する重要な要素の一1です。本記事で紹介したポイントやコメント例を参考に、より効果的な人事評価を実践し、従業員と組織の成長に生かしていただければ幸いです。
【全5職種対応・自動計算機能付き】
営業・事務・管理職など主要職種の評価項目例つき!
Excel / Googleスプレッドシートに対応し、そのまま使える人事評価テンプレートシートを無料公開中!
>>『人事評価のテンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。