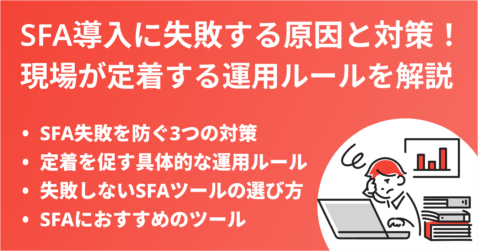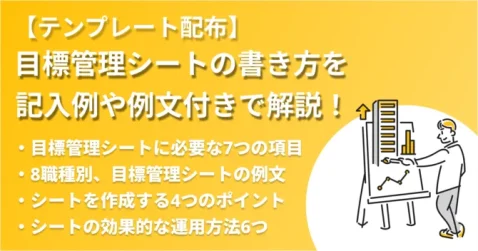管理職にとって目標設定は、組織の業績と成長を左右する重要なスキルです。自分や部下に適切な目標を設定できるかどうかで、チームの生産性やモチベーション、さらには組織全体のパフォーマンスが大きく変わります。
一方で現場では「どんな目標を設定すればよいか分からない」「目標を立てても達成できない」「部下の目標設定や評価に悩む」といった声が多く聞かれます。これは多くの管理職や経営者が共通して抱える課題です。
本記事では、管理職が目標設定を行う際の具体的なコツや手順、活用できるフレームワーク、実践的な事例を紹介します。SMARTの法則からKPIツリーまで、段階的に理解を深められる内容です。
これから目標設定に取り組む方はもちろん、すでに実践しているが効果的な方法を探している方にも役立つ内容となっています。
カンタンに効果的な目標管理を実現するテンプレート集を無料公開中!
>>無料で『目標管理シートテンプレート集』をダウンロードする
▼ この記事の内容
- 目標設定の3つのコツ: 意義目標、成果目標、行動目標の3種類を組織の状況に応じて使い分けること、実現可能性を考慮した達成可能なラインを見極めること、具体的な数値目標を設定することです。
- 目標設定の手順: 全社方針を深く理解し、組織の現状・課題を分析、「何を」「どのように」「いつまでに」達成するかを明確化し、共有した上で定期的に見直しを行います。
- 目標の種類と特徴: 意義目標はブレイクスルーを目指す理想的な目標、成果目標は数値で測定できる目標、行動目標は取り組みやすいが成果に直結しない可能性がある目標です。
- 目標設定のフレームワーク: SMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)の原則、ベーシック法(基本・戦略的・革新的)、KPIツリー(目標間の因果関係を可視化)の活用が有効です。
- 1on1の活用: 目標設定や進捗確認、課題解決を双方向のコミュニケーションで行い、形式的な目標の押し付けを避け実効性を高めます。公正な評価のフィードバックにも活用されます。
管理職が目標設定を行う際のコツ3選
目標設定が組織のパフォーマンスや社員のエンゲージメントに大きな影響を与えるため、適切な目標設定のスキルを身につけることは管理職にとって必須のスキルといえます。
ここでは、管理職が目標設定を行う際の重要なポイントを3つ紹介します。
目標の種類を理解し、組織の状況に応じた目標を設定する
目標設定において最も重要なのは、組織の現状を正確に把握し、適切な目標の種類を選択することです。目標には大きく分けて目標には「意義目標」、「成果目標」、「行動目標」という3つの種類があります。
「意義目標」は、抽象的ながら現状を打破できるブレイクスルーを目指すことができるような、比較的理想に近い目標になります。「成果目標」は、数値などで達成度を明確に示すことができる目標です。「行動目標」は、具体的な行動を示すため、取り組みやすく実現可能性は最も高いものの、必ずしも成果に結びつくとは限りません。
これらの目標はそれぞれに特徴があり、優劣をつけるものではなく、状況に応じて適切に使い分けることが重要です。
また、設定する目標が、組織のビジョンや価値観と整合性がとれているについても確認する必要があります。目標設定の際には、部門やチームの特性を考慮し、メンバーの成長段階に応じた適切な目標を設定することで、より効果的な目標管理が可能になります。
さらに、目標の種類によって評価方法や進捗管理の方法も変わってくるため、目標の性質を十分に理解したうえで設定することが求められます。
達成や実行可能性がある目標にする
目標設定の際は、チャレンジ精神を大切にすると同時に、実現可能性についても十分に考慮しましょう。
目標が高すぎると部下のモチベーションの低下を招き、逆に簡単すぎると成長の機会を逃してしまいます。よって、適切な目標設定のためには、部下自身の能力・経験・状態や自社のリソースを考慮した上で、実現可能且つ部下の成長に繋げられるラインを見極めましょう。
また、目標設定の際には部下との対話を通じて実現可能性を確認し、必要に応じて調整を行うことをお勧めします。特に新しいプロジェクトや取り組みの場合は、段階的に刻んだ目標設定を行い、小さな成功体験を積み重ねていくアプローチが効果的です。
具体的な数値を用いた目標にする
目標は可能な限り具体的な数値で表現することが重要です。
「売上を増やす」という抽象的な目標ではなく、「今期の売上を前年比○○%の○○円にする」というように具体的に数字で表せる目標を設定してみましょう。
目標を客観的に測定しやすくなることで進捗管理が容易になったり、目標達成に向けてより具体的なプランを立てられるようになるため、PDCAサイクルを回しやすくなります。
また、数値目標は客観的な評価基準となるため、客観的且つ公平な評価にも繋げることができます。数値化が難しい定性的な目標の場合は、達成基準や評価指標を明確に設定することで対応するようにしましょう。
目標の進捗状況は定期的にモニタリングし、必要に応じて軌道修正を行うことも忘れてはなりません。
管理職が目標設定をする際の手順
管理職が効果的な目標設定を行う際には、単に目標を設定するだけでなく、組織全体の方向性を理解して現状分析を行ったうえで、具体的なアクションプランまで落とし込む必要があります。
ここでは、管理職が目標設定を行う際の具体的な手順を5つのステップで解説します。これらの手順を踏むことでより実効性の高い目標設定が可能になり、組織全体のパフォーマンス向上につなげることができます。
1.全社方針の理解を深める
目標設定の第一歩は、会社全体の経営方針や戦略を正確に理解することです。管理職は、経営陣が掲げるビジョンや中期経営計画、年度方針などを深く理解し、自分自身だけでなく自部門やチームがどのように全社の目標達成に貢献できるかを考える必要があります。
特に重要なのは、単に方針を理解するだけでなく、その背景にある意図や狙いまで把握することです。
また、自部門に関連する他部門の方針や目標についても理解を深め、部門間の連携や相乗効果を意識した目標設定を心がけましょう。必要に応じて経営層や他部門の管理職とコミュニケーションを取り、方針の詳細や意図を確認することも重要です。
2.組織の現状・課題・理想を明らかにする
全社方針を理解したら、次は自部門やチームの現状分析を行います。
具体的には、これまでの実績データの分析・メンバーのスキルや能力の評価・リソースの状況・市場環境の変化などを多角的に検討し、現状分析を通じて組織が抱える課題や改善点を明確にすることで、目指すべき姿やビジョンとのギャップを特定できるでしょう。
この際、定量的なデータだけでなく、メンバーの意見や顧客からのフィードバックなども参考にすることで、より実態に即した分析が可能になります。
特定した課題やギャップを具体的なアクションプランまで掘り下げて、実現可能性の高い目標へと落とし込むようにしましょう。また、組織の強みや弱みを把握し、それらを踏まえた実現可能な目標設定を行うことが重要です。
【OKRについて徹底解説!】
会社の目標でOKRを導入したいけど、どのように導入・運用すれば良いかわからない。そもそもOKRって何なのか?などのお悩みをマルッと解決いたします!
OKRの導入から運用まで成功までの道のりを完全解説した資料!
>>『売上を劇的に高める米国最先端の戦略実行手法「OKRパーフェクトガイド」』はコチラから無料でご覧いただけます!
3.「何を」「どのように」「いつまでに」達成するのかを明確に決める
目標設定では、具体的な達成内容とそのプロセスを明確にすることが重要です。
「何を」については、数値目標や具体的な成果物を設定し、「どのように」は具体的な実行計画やマイルストーンを設定し、「いつまでに」については、期限を明確に定め途中経過の確認ポイントも設定します。
この際、SMARTの原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に従って目標を設定すると効果的です。目標達成にSMARTの法則を活用する方法については、より詳しく後述します。
また、目標達成に必要なリソースや予算、人員配置なども併せて検討することで、より実現可能性の高い計画を立てることができます。
4. 目標を会社と自チームに共有する
設定した目標は、上司や経営層への報告と承認を得たうえで、チームメンバーに共有しましょう。
目標を社内やチーム内で共有する際は、単に内容を伝えるだけでなく、その目標を設定した背景や理由、期待される効果についても丁寧に説明することが重要です。また、各メンバーの役割や責任範囲を明確にし、目標達成に向けた具体的な行動計画についても共有します。
チーム全体で目標を共有して理解を深めることで、メンバーの協力体制が出来上がったり情報交換が活発になるなど、目標達成へのモチベーションアップを期待することができます。
1on1などの定期的なミーティングやコミュニケーションを通じて、目標の進捗状況や課題を共有し、メンバーのモチベーションを維持するための機会を設けることも大切です。
【全16テンプレ・総勢94アジェンダを大公開】
カンタンに効果的な1on1を実現するテンプレート集を無料公開中!
>>『明日からすぐに使える1on1テンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!
5. 目標設定後も定期的に見直しを行う
目標設定は一度行えば終わりではなく、達成のために定期的な確認や見直しが必要になります。
目標を設定した時点では見えなかった問題が浮上したり、あるいは市場やクライアントの状況によって設定した目標の妥当性が変化するなんてことは少なくありません。そのため、定期的な会議や連絡を通して目標の進捗状況を確認し、必要に応じて目標や計画の見直しを適宜おこないましょう。
見直しの際は、達成度合いや現状の課題を客観的に分析して、さらにチームメンバーからのフィードバックも積極的に取り入れながら改善策を検討します。
また、進捗や現状が芳しくなかったとしても、安易な目標の下方修正は避け、チャレンジ精神を維持しながらも現実的な調整を行うことが重要です。
目標設定で活用できるフレームワーク
管理職が効果的な目標設定を行うために、フレームワークを活用してみましょう。
ここでは、管理職の役職や責任範囲に応じて活用できる代表的なフレームワークを複数ご紹介します。
これらのフレームワークを組織の状況や目的に応じて柔軟に組み合わせることで、より効果的な目標設定を実現することができます。
SMARTの法則
SMARTの法則は、目標設定の基本となる5つの要素を示したフレームワークです。
「Specific(具体的)」、「Measurable(測定可能)」、「Achievable(達成可能)」、「Relevant(関連性)」、「Time-bound(期限)」の頭文字を取ったもので、具体的には、「目標が明確で具体的であること、数値などで測定可能であること、現実的に達成可能であること、組織の目標と関連性があること、そして期限が設定されていること」を確認することができます。
例えば、「売上を増やす」という漠然とした目標は、「今期末までに主力商品の売上を前年比120%の○○円に増加させる」というように、SMARTの要素を満たした具体的な目標に置き換えることで、より効果的な目標となり得ます。
このフレームワークは、特に数値目標の設定に有効といえるでしょう。
ベーシック法
ベーシック法は、目標設定を段階的に行うフレームワークです。
「Basic(基本)」、「Strategic(戦略的)」、「Innovation(革新的)」という3段階を指し、先ず、基本目標として必ず達成すべき最低限の目標を設定し、次に戦略的目標として組織の成長に必要な目標を設定し、最後に革新的目標として大きな飛躍につながるチャレンジングな目標を設定します。
例えば、営業部門であれば、基本目標として「既存顧客の維持率95%以上」、戦略的目標として「新規顧客獲得数前年比120%」、革新的目標として「新規事業領域での売上○○円達成」といった具合になります。
このフレームワークの特徴は、リスクと成長のバランスを取りながら、段階的に目標を設定できる点にあります。
KPIツリー
KPIとは、Key Performance Indicator(重要業績評価指標)の略称で、組織や事業の目標達成度を評価するための主要な指標のことです。
例えば、営業部門であれば売上高や成約率、製造部門であれば生産性や不良品率、カスタマーサービス部門であれば顧客満足度や対応時間などが代表的なKPIとなります。
KPIツリーは、このKPIを階層的に整理し、組織の最終目標を達成するために必要な指標を体系的に可視化するフレームワークです。ツリー状の図を描くことで、最上位のKPIから、それを実現するために必要な下位のKPIへと順次展開していきます。
具体例を挙げると、最上位のKPIが「営業利益○○円」の場合、その目標を達成するために必要な第二階層のKPIとして「売上高」「原価率」「販管費率」を設定します。さらに「売上高」を達成するための第三階層のKPIとして「商品別売上」「顧客別売上」「成約率」を設定し、「原価率」の下には「在庫回転率」「仕入単価」「生産効率」といった具合に、具体的な指標を設定していきます。
このフレームワークの大きな利点は、目標間の因果関係が明確になり、各指標の重要性や優先順位を理解しやすくなることです。
また、最終目標を達成するために、どの指標を改善する必要があるのかが視覚的に把握できるため、より具体的なアクションプランの立案にも役立ちます。KPIツリーを作成する際は、上位のKPIと下位のKPIに因果関係があることを確認し、且つ測定可能で具体的な指標を設定することが重要です。
このように、KPIツリーは組織の目標を具体的な指標に落とし込み、実行可能な施策へと展開するための効果的なツールとして活用することができます。
管理職の具体的な目標設定例をご紹介
管理職の目標設定において、いくつか具体的な例を紹介していきます。
これらの例を参考にしながら、実際の目標設定では自社の状況や業界特性、組織の課題に応じてカスタマイズしましょう。
管理職全般で使える目標設定例
管理職全般に共通する目標設定例として、以下のようなものが挙げられます。
まず、財務面では「部門売上高を前年比110%の○○円に増加させる」「原価率を2%削減し○○%以下に抑える」などの数値目標があります。
人材育成面では「部下の1人あたり売上高を前年比105%に向上させる」「チームメンバーの資格取得率を80%以上にする」といった目標が考えられます。
他にも、業務改善では「業務プロセスの標準化により、主要業務の処理時間を20%削減する」「クレーム発生件数を前年比50%削減する」などの具体的な目標を設定します。
また、管理職はチームやプロジェクト全体単位でのマネジメント業務を抱えることも少なくないため、「従業員満足度調査のスコアを前年比10%向上させる」「チームの月次の1on1実施率100%を達成する」といったチームマネジメントに関する目標も効果的でしょう。
【その目標管理、実は成果が出ないやり方かも?】
国内の多くのマネージャーは目標設定・目標管理のやり方を教えられずに、いきなり目標管理を任されています。
そんなマネージャーの中に、成果が出ない目標管理で苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。そんな国内に満映している「間違いだらけの目標管理」について解説した資料を公開中です!
>>「間違いだらけの目標管理」はコチラから無料ダウンロード!
部長が使える目標設定例
部長クラスの目標設定例としては、業務面での戦略的な目標に加え、より大きい規模での組織や人材に関する目標も設定されるようになります。
例えば、「新規事業領域での売上比率を20%まで引き上げる」「海外市場での売上シェアを○○%まで拡大する」といった事業戦略に関する目標や、「部署間連携プロジェクトを立ち上げ、クロスセル率を15%向上させる」「デジタルトランスフォーメーションを推進し、業務効率を30%改善する」といった組織改革に関する目標が挙げられます。
また、「次世代リーダーを3名以上育成し、登用する」「女性管理職比率を○○%まで向上させる」といった組織・キャリア開発に関する目標も、他の管理職層や経営層と連携しながら取り組むこともあるでしょう。
これらの目標は、組織のビジョンや中期経営計画と方針をすり合わせながら設定することが求められます。
課長、マネージャー職が使える目標設定例
課長やマネージャー職の目標設定例としては、より具体的な業務改善や現場マネジメントに関する目標が中心となります。
例えば、「チーム全体の残業時間を月平均20時間以下に削減する」「業務の自動化により定型作業を50%削減する」といった業務効率化に関する目標や、「顧客満足度調査のスコアを85点以上に向上させる」「チーム内の提案件数を四半期で10件以上達成する」といった業績向上に関する目標が考えられます。
また、「メンバー全員のスキルマップを作成し、四半期ごとに更新する」「チーム内の有給休暇取得率を80%以上にする」といったチーム運営やマネジメントに関する目標も重要です。
これらの目標は、日常的な仕事やマネジメント業務と直結するものが多くなってきます。
目標設定は1on1がおすすめ
目標設定を効果的に行うためには、1on1ミーティングの活用がおすすめです。
1on1は上司と部下が定期的に行う個別面談で、目標の設定や進捗確認、課題解決などを行う重要な機会です。形式的な目標設定や一方的な目標の押し付けを避け、双方向のコミュニケーションを通じて、より実効性の高い目標設定を実現することができます。
ここでは、1on1を活用した目標設定と管理の具体的な方法について解説します。
目標設定は目標達成のために存在する
目標設定の本質的な目的は、組織とメンバーの成長を促し、成果を最大化することにあります。
1on1での目標設定では、メンバーの意見や考えを十分に聞き、その能力や意欲を適切に把握したうえで目標を設定することができます。さらに、目標達成に必要なサポートや計画についても、1on1の場で具体的に話し合うと良いでしょう。
このように目標の設定段階で深く話し合うことで、目標に対する理解や納得感を高めることで、メンバーの主体的な取り組みを促すというメリットもあります。
そのため、目標設定の際には企業の組織目標とメンバーの成長目標を適切にリンクさせ、双方にとって意味のある目標となるよう心がけましょう。
1on1で目標管理を行う
1on1で目標管理を行うことで、定期的な進捗確認と課題解決が可能になります。
週次や月次で1on1を実施して目標の達成状況や課題を確認し、また単なる報告会にならないよう、メンバーの悩みや課題感にも耳を傾けて必要なサポートを提供することが大切です。
また、目標の進捗状況に応じて、計画の見直しや目標の調整を行うことも重要です。1on1では、対話を通じて信頼関係を構築し、より効果的な目標管理を実現することができます。
また、1on1ツールやタスク管理システムなどを導入することで、1on1を実施する際の工数や負担を大幅に軽減することができます。
1on1で適正な評価をする
1on1は人事評価においても重要な役割を果たします。
定期的な1on1を通じて、目標に対する取り組み状況や成果を継続的にチェックすることで、より公正かつ適切な評価が可能になります。評価の際は、数値目標の達成度だけでなく、プロセスや成長度合いも含めて総合的に判断しましょう。
また、評価結果をフィードバックする際も1on1の場を活用することで、より建設的な対話が可能になります。評価の透明性と公平性を確保するため、評価基準や方法を事前に明確にしておくことも重要です。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 管理職が目標設定を行う際、最も重要な3つの目標の種類は何ですか?
A: 意義目標(理想的なブレイクスルー)、成果目標(数値で測定)、行動目標(具体的な行動)の3種類です。これらを組織やチームの現状に応じて使い分けることが重要です。
Q2. 目標設定を失敗しないために、「達成可能性」をどのように見極めるべきですか?
A: 目標が高すぎるとモチベーション低下、簡単すぎると成長の機会を逃すため、部下の能力やリソースを考慮し、実現可能かつ成長に繋げられるラインを見極めましょう。
Q3. 管理職が目標設定を行う際、最初にとるべき行動は何ですか?
A: 全社の経営方針や戦略、ビジョンの背景にある意図や狙いまで深く理解することです。自部門が全社目標にどう貢献できるかを考える土台となります。
Q4. 目標間の「因果関係」を明確にしたい場合、どのフレームワークが有効ですか?
A: KPIツリーが有効です。最終目標から、それを実現するために必要な下位のKPIへと階層的に整理し、どの指標を改善すべきかを視覚的に把握できます。
Q5. 目標設定を「一方的な押し付け」にしないために、どのような方法が推奨されますか?
A: 1on1ミーティングを活用しましょう。双方向のコミュニケーションを通じて部下の意見や納得感を高め、目標達成に必要なサポートや計画を共に話し合うことが重要です。
まとめ
ここまで、管理職が効果的な目標設定を行う際に押さえるべき様々なポイントを解説してきました。
まず目標設定の基本として、組織の状況に応じた適切な目標の種類を選択し、達成可能性と具体的な数値目標をバランスよく設定することを忘れないようにしましょう。
特に、チャレンジ目標とノルマ目標を適切に組み合わせることで、組織の持続的な成長を促すことができます。
また、目標設定のプロセスにおいては、全社方針の理解から始まり、現状分析、具体的な計画立案、共有を経て目標を設定し、そして定期的な見直しに関しても忘れないよう注意が必要です。
この際、BSCやOKR、MBOといったフレームワークを活用することで、より効果的な目標設定が可能になります。
最後に、目標設定は単なる数値の設定ではなく、組織とメンバーの成長を促進するためのツールであることを忘れてはいけません。
適切な目標設定と管理を通じて組織全体のパフォーマンス向上とメンバーの成長を実現することが、管理職に求められる重要な役割です。
今回ご紹介した要点を意識することで、より効果的な目標設定と目標管理が可能になります。
個人のアウトプット向上と組織の成長に向けて、ぜひ実践的に活用してみください!
効果的な目標設定・目標管理なら「コチーム」!

- 1on1をしながら、目標の進捗を入力できる!
- 目標の結果を人事評価に反映!
- 目標の進捗・結果を全て見える化!
- 1on1の記録を人事評価時に活用できる!
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。