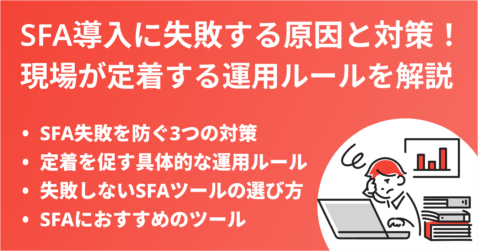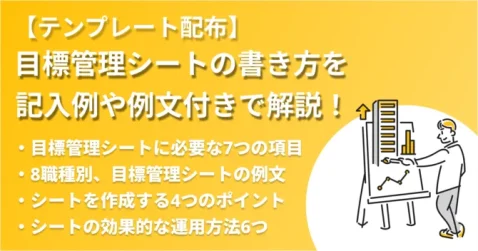人事評価制度の運用で欠かせないのが「目標設定」です。従業員が理解・納得できる目標を設定しなければ、不満や離職につながる恐れがあります。
一方で、適切な目標設定はモチベーションを高め、課題を明確にすることで確実な成長を促します。
本記事では、人事評価において目標設定が重要な理由、代表的な目標管理制度、目標設定のポイントを解説します。

≫無料で「目標マネジメントパーフェクトガイド」をダウンロードする
▼ この記事の内容
- 目標設定の目的:評価への納得感を高めて離職を防ぎ、社員の「やる気」と「成長」を最大限に引き出すための重要な土台です。 適切な目標があれば、自分が何をすべきかが明確になり、達成感を得やすくなります。逆にここが曖昧だと、どんなに頑張っても不満が残る原因になります。
- 設定のコツ:「SMARTの法則」を使い、誰が見ても達成できたかが分かるように「数値」や「期限」を具体的に決めることです。 「頑張る」といった精神論ではなく、「売上○○円」「納期○日」と測定可能な指標(KPI)に落とし込むことで、評価者の主観を排除し公平性を保てます。
- 運用の秘訣:目標は立てて終わりではなく、「1on1」で進捗を確認し、フィードバックを繰り返すことで形骸化を防げます。 期初の設定だけでなく、定期的な対話で進捗をすり合わせることが重要です。達成できそうなら褒め、遅れているなら軌道修正を行う「伴走支援」が成果を生みます。
目次
人事評価における目標設定とは?
人事評価とは、従業員の配置や能力開発に活かすために、成果やその過程を多角的に評価する仕組みです。成績、勤務態度、成長意欲などを基準に総合的に判断します。
評価にあたっては、管理者が従業員と目線を合わせ、「なぜこの目標にしたのか」「達成すればどのような報酬があるのか」を共有しながら目標を設定することが重要です。適切な手順で達成度を評価することで、納得感を高められます。こうした評価はモチベーションや成長意欲を引き出し、企業との信頼関係を深める効果も期待できます。
設定する目標は、従業員にとって適切な難易度であり、業種の特性に即したものであることが理想です。特に総務や情報システムのように成果を数値化しにくい部署では、努力をどう捉え、公平に評価するかが課題となります。
カンタンに効果的な目標管理を実現するテンプレート集を無料公開中!
>>無料で『目標管理シートテンプレート集』をダウンロードする
人事評価と人事考課の違い
人事考課は人事評価と似たようなものと考えられがちですが、厳密には以下のような違いがあります。
- 人事評価
- 従業員の配置や能力開発に活用するため、成果や成果を出すまでの取り組みなどを評価すること。
- 人事考課
- 従業員の能力や業績をもとに、昇給や昇進、賞与を決めること。
人事評価は従業員の能力を伸ばしたりより有用に活用したりするためのものです。一方、人事考課は従業員に対する報酬を検討するためのものと覚えると良いでしょう。
人事評価に代表される3つの評価基準
人事考課では、成績評価、能力評価、姿勢評価という3つの評価基準が用いられます。それぞれについて見ていきましょう。
成績評価(業績評価)
成績評価(別名:業績評価)では、期間内にどれくらい目標を達成できたか、どれだけの成果を出せたかを評価します。
基本的には数字で測るようにする事がおすすめです。営業であれば、売上目標額や新規開拓目標数など数値化された目標をどれくらい達成したのかが評価の基準になります。
バックオフィスのように数値化した評価が難しい場合は、取り組んだ業務の難易度や数、また、その業務によってどれくらい企業に貢献したのかなどを評価基準にするのが良いでしょう。
能力評価
能力評価では、従業員の成果ではなく能力を評価します。評価対象となる能力の例は以下のとおりです。
- 課題設定力
- 提案力
- 実行力
- 判断力
- 対人能力
- 指導力
- 組織力
- チーム力
成績評価では業務の結果を評価するのに対し、能力考課では結果を出すために必要な能力に注目します。例えば、営業成績自体は上がっていても、顧客からのクレームが増えている場合は、対人能力や折衝力が不十分だとして能力考課の評価は下がるでしょう。
また、近年では能力評価をうまく活用して、メンバーにチームで働くことを意識してもらう会社が増えてきています。背景としては、業績評価のみにしてしまうと、メンバーが自分の業績にだけ目を向けてしまい、新人のオンボーディングや数字には関係ないが会社のメリットになる事をやらなくなってしまう会社が多かったからです。
能力評価の中にチーム力や組織力を入れると、メンバーが自分のうまくいった事例をドキュメント化して他に転用するようになるため、おすすめです。
姿勢評価(情意評価)
姿勢評価(別名:情意評価)では、業務に対する意欲や姿勢を評価します。具体的には勤務態度やチャレンジ精神、協調性、献身性などから評価を行います。
しかし、姿勢評価をそのまま運用すると、メンバーの納得度が得れず不満が溜まる可能性が高いです。そのため、どんな事をする社員が会社に合うかという事を定義して、バリューや行動指針を作成する。
そして、バリューや行動指針に則った行動をとっているかを軸に判断すると良いでしょう。
人事評価における目標管理についての課題
人事評価における目標管理には、さまざまな課題があります。
制度に不備があり、適切な運用ができなければ、時間をかけて実施しても期待したほどの効果が得られません。また、従業員に「意味のない作業をやらされている」という印象をもたれてしまう事もあります。
下に、パーソル総合研究所が目標管理制度を実施している企業430社のマネジメント層を対象に、目標管理制度の課題について質問したアンケート結果を記載します。
回答結果によると、半数以上の企業で「目標管理が従業員のモチベーション向上や能力開発に結びついていない」と感じている事がわかります。また、「目標設定のプロセスが形骸化している」「多くの従業員が評価に不満を感じている」という声も多い結果になっています。
加えて、1,433名の従業員を対象に、目標管理制度に対する不満を聞いたアンケート調査の結果を下記に記載します。
最も目立つのは、「定量化するのが難しい業務がある」「具体的な目標を設定することが難しい」など目標の明確化についての不満です。加えて、「部署によって目標の難易度が違う」「同じポジションでも人によって目標の難易度が違う」と、部署や従業員によって目標水準が異なることについての不満も見受けられます。
他にも、「期中で目標の内容や期限が変わらざるを得ない」と柔軟な目標設定を求める声もあります。
特にベンチャー企業などの変化の激しい企業では柔軟性が求められます。上記のデータから、目標管理についてさまざまな課題が存在することがうかがえます。
【その目標管理、実は成果が出ないやり方かも?】
国内の多くのマネージャーは目標設定・目標管理のやり方を教えられずに、いきなり目標管理を任されています。
そんなマネージャーの中に、成果が出ない目標管理で苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。そんな国内に満映している「間違いだらけの目標管理」について解説した資料を公開中です!
>>「間違いだらけの目標管理」はコチラから無料ダウンロード!
「目標」と「目的」の違い
「目標」と「目的」を間違えて使ってしまう方が多いので、解説します。
目的とは、行動するうえで目指すべき到達地点を意味するのに対して、目標は目的というゴールに到達するための方法を意味します。言い換えれば、目的を達成するために必要な手段や指標が目標になります。
企業を例とすると、「年間売上50億円」という「目的」を達成するために、営業部門が「各営業マンの売上前年比1.2倍」、開発部門では「競合よりも質の高い商品の開発」という「目標」を設定します。
目標だけを伝えるのではなく、会社の目的とそれに沿った目標のどちらもを伝えるようにしましょう。
人事評価における目標設定をするメリット
人事評価において明確な目標設定をすることは、企業と従業員双方にとって多くのメリットがあります。
ここでは4つのメリットを紹介します。
モチベーションが向上する
目標設定のメリットとして、モチベーションの向上が挙げられます。
目標がなければ達成感を得られず、従業員のモチベーションは低下します。また、目標達成時の評価や報酬を事前に伝えておくことで、仕事に取り組むメリットをより明確に感じてもらえます。
メンバーの能力が上がる
人間はちょうどいいストレス負荷が与えられている時が、最も成長します。
そのため、ギリギリ達成できるかできないかくらいの難易度の目標を設定する事でメンバーの成長を促す事ができます。また、目標をどうやって達成するかを具体的に決めてもらう事もおすすめです。
営業部の例
例として、電話で商談機会を獲得できる確率が5%、商談から受注につながる確率が20%とします。この場合、10社と契約するには50社の商談 が必要です(10社÷20%=50社)。さらに、50社の商談を得るには1000回の架電が必要になります(50社÷5%=1000回)。
営業日を20日とすると、1日あたり50回の架電 が必要です(1000回÷20日=50回)。営業時間8時間のうち、商談2時間・会議や事務1時間を除くと、架電に使えるのは5時間。したがって、 1時間に10回架電 すれば目標達成となります。
上記のような細かい設定を最初は上司が行い、時間が経つにつれて部下自身にやらせるようにすることで、部下の思考力を向上させる事ができます。
離職率が低下する
近年の離職理由の大半は「会社から与えられた評価が納得できなかった」というものです。
そのため、評価とそれに基づく目標設定を行いメンバーと目線合わせをしておく事が重要です。また、もしその目標を達成したらどのような評価や報酬が得れるのか?をいうのも伝えておく必要があります。
「自分は目標の2倍を達成したのに、1.1倍の人と同じであればここまでやり切った意味がない」といった意見多く見受けられるので、目標を大幅に達成した人によりメリットがある評価制度にする事をおすすめします。
【どの会社でも実践できる離職防止施策を徹底解説!】
50 社以上の組織課題解決に伴走してきた弊社の知見をもとに、離職防止のためのアクションプランや具体施策などについて解説した全110Pにわたる「コンサルに頼らない離職防止パーフェクトガイド」はこちらから無料ダウンロード!
適切な目標設定をするためのポイント3選
目標設定をする際は、企業や部門など組織としての目標と合致している必要があります。
また、従業員が自分で目標を設定して上司に合意を取るようなスタイルの会社だと、従業員が自身の役割や業務内容を把握していないと、目標を設定する事ができません。そのため、まずは組織目標や役割分担を明確にして伝える事が大切です。
ここでは、適切な目標設定をさせるポイントを解説します。
企業の目標を周知する
どの会社にも企業としての経営目標があります。しかし、従業員が企業の経営目標を把握していないケースが意外と多く見受けられます。そのため、企業の経営目標を従業員に周知することが大切です。
全体での発表でも良いですが、常に見れるように会社のオフィスに貼ったり、オンラインであれば、何かしらのツールを用いて常に見れるようにしておきましょう。
また、経営目標は抽象的な内容ではなく、数値や期限を盛り込んだ具体的な内容にすることがポイントです。例えば、「1年間でコストを5%削減する」「1ヶ月間で売上を1.2倍にする」などが例として挙げられます。
さらに数字だけでなく「企業としてどんな世界を作りたいのか?」つまりミッションを伝えて共感してもらう事ができると、従業員のメンバーのモチベーションが上がるのでおすすめです。
1on1ミーティングを中心に組織の理念を浸透させて、従業員のエンゲージメントを高める方法!
>>『「あきらめ組織」の理念浸透〜「王女奪還」につなげる1on1〜』はこちらから無料ダウンロード!
各部門の目標を明確にして伝える
各部門は経営目標をもとに、部門ごとの目標を設定する必要があります。部門によっては目標設定が難しいこともあるでしょう。特に、バックオフィス部門では直接数値に表われない業務も多いため、具体的な目標が立てづらいです。
とはいえ、経費の削減や業務の効率化など数値化できるものを目標設定にする事もできます。また、関係部署や関係者からの評価を目標にする方法もあります。例えば、秘書なら役員からの評価、受付なら顧客からの評価をアンケートで取り、それを評価に反映させる事ができるでしょう。
さらに、部長が自分の部署の目標を発表するときは、目標を設定した背景や理由を伝えるとともに、その部署が目標達成する事での会社の影響を伝えると従業員のモチベーションを高める事ができるのでおすすめです。
個人の目標・役割・業務分担を明確にする
企業の目標と各部門の目標を設定したら、次は個人の目標を立てましょう。仮に営業部の月の目標が5000万だとして、10人で目標を達成する場合、
5000万÷10人=500万
単純に割ると一人当たり500万が目標になります。メンバーの経験値や能力、もらっている給料が同じであればこれでも良いですが、経験値や能力、もらっている給料にばらつきがある場合、それらに応じて傾斜をつける事がおすすめです。
またそれ以外でも、古参の方には新人教育の役割を与えたり、社内コミュニケーションが得意な方には他部門との連携を任せるなどして、適切な役割を与える事が重要です。
この際、気をつけないといけないのは、役割を全うしたものを評価する仕組みを作っておくことです。
そうしないと、新人教育や社内コミュニケーションを行った方が、売り上げが全く同じ評価だった時に不満を溜めてしまうからです。
人事評価の代表的な目標管理制度4つ
人事評価の代表的な目標管理制度として、「KGI(Key Goal Indicator)」「KPI(Key Performance Indicator)」「OKR(Objectives and Key Results)」「MBO(Management By Objective)」の4つがあります。
よく似た制度に見えますが、それぞれ異なる目的や考え方を持った制度です。
このセクションでは、KGI、KPI、OKR、MBOの4つの目標管理制度の特徴を解説します。
KGI(Key Goal Indicator)
企業にとってKGIは最終目標を指します。
「売上高」など数値で測れる指標を設定すれば、目標がブレにくくなります。たとえば営業部では「売上高を前年比120%にする」といったシンプルなKGIが適しています。
一方、売上数値を出しにくいカスタマーサポート部門では「顧客満足度を前年比10%向上させる」のようにアンケート結果を活用して定量化する方法が有効です。総務なども同様に、「コストを前年比10%削減する」と定量化をする事ができます。
数字で評価をする方が、評価がしやすいのと不満も生まれにくいので基本的には数字でKGIを設定するようにしましょう。
KPI(Key Performance Indicator)
企業にとってKGIは最終目標、KPIはKGIを実現するための中間目標の役割を果たします。「人事評価における目標設定をするメリット」のセクションで話した営業部の例で言うとKGIを売り上げ600万か受注数10社に設定し、KPIは月50社の商談、月1000回の架電、毎日50回の架電になります。
KPIは細かく設定した方が、メンバーが目標達成をイメージしやすくなります。ただし、KPIを評価にどの程度反映させるかは、会社の状況に応じて検討が必要です。
例えば「評価の50%を月の売上、残り50%を月1000回の架電」とした場合、架電が500回で売上2倍の人と、架電2000回で売上0.5倍の人の評価が同じになってしまいます。これでは本末転倒です。一方で、目標が「半年で1社獲得」のように長期的な場合には、架電数や商談数を評価に組み込むケースもあります。
改めてになりますが、KGI、KPIをどれくらい評価に組み込むかは会社の状況やビジネスモデルによって考えるようにしましょう。
MBO(Management By Objective)
MBOは、多くの企業の人事評価制度で採用されている目標管理方法です。MBO(目標管理制度)は、「Management by Objectives and Self-control」の略で、1954年に経営学者ピーター・ドラッカーが著書『現代の経営』で提唱した手法です。
内容としては、従業員本人が業務目標を設定し、上長が目標達成に向けたサポートをおこなう方法です。日本でMBOが採用される際は、KGIやKPIと同様の使われ方をすることが多くあります。
例えば営業では「月間売上400万円達成」や「月間受注数10社」といったMBOが設定されるケースが一般的です。さらに「月間売上400万円達成」と、それを実現するための「月間30商談」などのKPIをあわせてMBOとして設定する場合もあります。
日本でよくあるMBOの誤解
MBOは、バブル崩壊後の1990年代に日本で急速に広がった考え方です。
バブル崩壊後、コストカットせざるを得ない状況になった企業が多く、従来よりも成果主義的な人事評価制度や報酬制度が取り入れたのと同時に、評価の根拠を明確にするためにMBO(目標管理)が取り入れられました。その際、評価の根拠を明確にする手段としてMBO(目標管理)が取り入れられました。
本来MBOは従業員自身が目標を設定する制度ですが、実際には経営層や上司が一方的に目標を決めるケースが多発しました。MBOは「Management by Objectives and Self-control」の通り、「Self-control(自己統制)」が重要です。従業員が自ら目標を立てることで、責任感が生まれ、評価に対する納得度も高まります。
しかし日本では、この「Self-control」が軽視され、人事制度の一部として形式的にMBOが運用されるのが一般的になっています。本来MBOは、マネジメントの考え方であり、人事評価の手法ではありません。
会社が設定する目標を上手に使って自己管理を促すことで、社員一人ひとりのやりがいやモチベーションを引き出し、その結果として目標を達成するというマネジメントの考え方がMBOです。
▼ MBOについて詳しく知りたい方はこちら!
OKR(Objectives and Key Results)
OKRは、GoogleやFacebookなどGAFAも導入している注目の目標管理制度です。「OKR」は「Objectives and Key Results」の略で、日本語では「目標と主要な成果指標」を意味します。
OKRは、インテルの元CEOアンディ・グローブがドラッカーのMBOを応用して生まれた手法です。MBOと別物とされることもありますが、実際にはMBOの考え方の中にOKRが含まれると考えるのが適切です。
MBOが100%達成を前提に目標を設定するのに対し、OKRは約70%の達成を想定した「ストレッチ目標」を掲げます。あえて難しい目標に挑戦することで、想定以上の成果を引き出すことを狙っています。そのためインテルでは、目標をすべて達成すると「設定が甘い」と注意され、平均して4割の目標は未達に終わります。
そのため、インテル社では、期末に100%達成をする部門は、目標設定が低すぎたと厳重注意を受け、平均として4割の目標が未達成に終わります。
また、OKRの要素である「Key Results(KR)」は、目標(Objectives)の進捗を測る具体的な指標です。KRでは期日や手段を明確にし、定量的に測定できるようにします。例えば「月商200万円を達成する(O)」という目標に対し、「月間50社に訪問する(KR)」といった形で設定します。
OKRは、MBOをより効果的に実現するためにインテル流にアレンジした手法のことです。目標の100%を目指すようなMBOで行うのか、目標を70%のストレッチな物にして目指すようにするのかは会社の雰囲気に応じて使い分けると良いでしょう。
【OKRについて徹底解説!】
会社の目標でOKRを導入したいけど、どのように導入・運用すれば良いかわからない。そもそもOKRって何なのか?などのお悩みをマルッと解決いたします!
OKRの導入から運用まで成功までの道のりを完全解説した資料!
>>『売上を劇的に高める米国最先端の戦略実行手法「OKRパーフェクトガイド」』はコチラから無料でご覧いただけます!
目標設定で押さえるべき「SMARTの法則」
目標設定を失敗してしまうと、人事評価や会社の成長など様々なところにマイナスの影響が出てしまいます。
目標設定に役立つSMARTの法則について、解説するのでご活用ください。
- S:Specific(具体的)
- M:Measurable(測定可能)
- A:Achievable(達成可能)
- R:Related(上位目標との関連)
- T:Time-bound(期限)
S:Specific(具体的)
目標を設定する際に「一生懸命取り組む」「頑張る」「粘り強く取り組む」といった抽象的な表現を使ってしまうことがあります。しかし、抽象的な目標では振り返りの際に成果を判断できません。そのため、常に具体的な目標を設定することが重要です。
参考までに具体的な目標の例を下記に記載します。
「得意先のニーズを汲み取った企画立案を行い、効果的なプレゼンテーションをする」
「先月より企業訪問を増やして売上向上を目指す」
M:Measurable(測定可能)
目標を設定する際、測定によって進捗や実績を可視化できる物にする必要があります。Specific(具体的)で出した「先月より企業訪問を増やして売上向上を目指す」という目標なら、「訪問数を先月比1.2倍に増やして売上向上を目指す」と変更すれば測定可能になります。
また、定性的な目標を設定した場合でも、評価時には定量的に測定する方法があります。Specific(具体的)で出した「得意先のニーズを汲み取った企画立案を行い、効果的なプレゼンテーションをする」という目標のままだと、「効果的なプレゼンテーションができたか?」を判断する際、主観になってしまいます。
そのため、「得意先にアンケートを行い、5段階評価中の4以上の評価を獲得する」「プレゼンの結果として、月30万のアップセルを狙う」のようにすると良いでしょう。
A:Achievable(達成可能)
目標設定でよくある失敗の1つが、達成不可能な目標を立ててしまうことです。
例えば「1か月で売上を2倍にする」という目標。取引先増加などの根拠があれば問題ありませんが、理由もなく大きすぎる目標を掲げると、かえってメンバーのやる気を失わせてしまいます。そのため、達成できる目標を設定するようにしましょう。
R:Related(上位目標との関連)
会社の目標と部門の目標が一致しているか、部門の目標やチームの目標に自分の目標が一致しているかを確認しましょう。例えば、売り上げを1.2倍に向上させたいという会社の人事部門が、営業マンではなく他の人ばかり採用していたらどうでしょうか??
もちろん、マーケを強化する事で売り上げに向上させる、事務担当がいなくて営業マンが事務作業をやっているので、事務員を採用するなどであれば問題ありません。ただ、「売り上げを1.2倍に向上させたいという会社の人事部門が、営業マンではなく他の人ばかり採用している」のような状況がある際に、他の部門から「人事部門は自分たちの採用人数にしか目を向けていない」と言われてしまう事があります。
そのため、「事務担当がいなくて営業マンが事務作業をやっているので、事務員を採用している」のように、上位目標である「売り上げを1.2倍に向上させたい」との関連性を他の部署にも伝えれおくとハレーションが起きにくいです。
T:Time-bound(期限)
目標に期限を設けなければ、行動計画は立てられません。必ず目標に応じて明確な期限を設定しましょう。
年間や半年の目標を立て、そこから逆算して四半期・月間・週・日単位の目標に落とし込むと効果的です。期限も「5/30」ではなく「5/30 17:59」と時間まで指定することをおすすめします。
例えば営業で契約完了を目標とした場合、お客様が「5/30 22:00」に契約書へサインすると、バックオフィスでは「17:59まで」で計算していたためにズレが生じる、といった事態を防げます。
人事評価の納得感を向上させるには運用がカギ
弊社では評価制度の作成と運用を長年支援させていただく中で、一番よく聞く失敗事例は「多額の金額を使って評価制度を作ったが、運用で失敗した」というものです。そのため、評価より運用を重視する事で、人事評価の納得感を向上させる方法についてここでは解説します。
運用が重要な理由
前提として、難しい評価制度を作ると、そもそもメンバーが理解できない事もありますし、意外とマネージャーの理解が浅いということも多く見受けられます。
また、評価制度において一番大事なのは「従業員の評価に対する満足度」なため、評価制度を見て満足するわけではなく評価制度を活用してマネージャーから言われる言葉や、最終的な評価が満足度に関わります。
そのため、評価制度は最軽量なものでも、運用を正しく行えば、従業員の評価に対する満足度を向上させる事ができます。
1on1での運用
評価制度の運用でおすすめなのは1on1を用いる事です。日本ではあまり知られている方法ではありませんが、海外ではやっている会社も増えているので是非ご参照ください。
目標について擦り合わせる
まずは1on1で目標をすり合わせます。
営業部であれば、「売り上げ達成」のようにわかりやすいものが多いですが、バックオフィスなど、目標が曖昧になりやすい場合は特に目標のついての擦り合わせが重要になってきます。また、営業部門であっても、個人の売り上げだけでなく新しいメンバーのオンボーディングや他の部門との連携など他の目標がある場合もあるので、そこは擦り合わせるようにしましょう。
現在の状況や課題と改善点を考えてもらう
次に、目標に対して現在の達成状況や抱えている課題や、チャレンジしている事を聞きましょう。営業部で例を出します。
例:
現在20日中の10日が過ぎているが、売り上げは目標の30%である。原因としては、電話でのアポが少ないことにある。そのため、電話のアポが得意な方に話を聞きに行き、テクニックがわかったので現在チャレンジしている
このように状況やチャレンジしている事を聞き、時には「〇〇の観点ではどう?」と示唆したり、「〇〇とかやるのもありかもね」とアドバイスをして、メンバーを目標達成させる事ができるようにしましょう。
さらに、1on1で話した内容をメモしておくと、評価の際に活用できるのでおすすめです。
今の目標を達成した時の評価を擦り合わせる
目標に対して現在の達成状況や抱えている課題や、チャレンジしている事を聞いて話し合った後は、今の目標を達成した時の評価を擦り合わせる事をおすすめします。
人間は「報酬を手に入れる事ができそう」という実感があるとモチベーションを維持する事ができます。
そのため、「今の進捗だと目標120%以上達成できる可能性あるから、ぜひ目指してほしい。達成できた場合、うちの人事評価制度的に〇〇になると思う」と伝えると良いでしょう。
パフォーマンスマネジメントの事例
実は海外では、1on1で目標を擦り合わせながら目標達成を目指し、その結果や1on1メモに書いてあるチャレンジした事をもとに評価をするやり方を行っている会社は多いです。目標達成力が上がるだけでなく、評価への納得度合いが上がるのでおすすめの施策です。
このやり方をパフォーマンスマネジメントを呼び、米国のTOP500企業の20%が採用しています。
▼ パフォーマンスマネジメントについて詳しく知りたい方はこちら!
Adobe
例としてAdobe社会の事例を紹介します。
以前の状態
Adobe社では、マネージャーが1人のメンバーを年次評価するのに8時間を要していました。当時マネージャーは約2,000人おり、全体で年間 8万時間 もの工数がかかっていたのです。さらに、評価への不満から退職する社員や、目標を達成できない社員が出るといった課題もありました。
やったこと
- 高頻度で目標達成のための話し合いと、現状の評価を振り返る1on1を行った
- 1on1トレーニングを、マネージャー向けとメンバー向けのそれぞれで10回ほど行った
- 1on1の中で従業員からマネージャーに向けてフィードバックすることもできるようにした
結果
- 退職の急激な減少(72%削減)
- 1人あたり平均10%の売上向上
- 年間8万時間の評価工数の削減
人事評価における目標設定の例
目標は、職種の特性に合わせた内容を設定する必要があります。営業職のように目標を数値化しやすい職種と違い、総務などのバックオフィス部門は公平な評価をつけることが難しい側面があるためです。目標の数値化が難しい部門では、従業員に向けて具体的な目標設定の例を提示する必要があります。
企画・マーケティング
企画・マーケティングは、営業と同じく目標を数値で明示しやすい職種です。まずはマーケティング施策の中でも、何の施策に注力するかを決めましょう。
例えば
「SNSを解説して、半年でフォロワーを2万人獲得し、認知度を高める」
「メールマガジンの登録者数を1年間で現在の1.5倍に伸ばす」
「自社メディアの記事の10件以上が検索上位3位内に入るようにする」
といった目標が挙げられます。
さらに何の施策に注力するかを決めたら、次はさらに細かい目標設定を行いましょう。
X(Twitter)施策を行う場合で、例を紹介します。
X(Twitter)施策の場合は、まずはたくさんの人に見てもらう必要があるので、インプレッション率数やインプレッション率をKPIとして追います。見てもらえる量が少ない場合は、Xのアルゴリズムや内容を見直すと良いでしょう。
次に、インプレッション(見てもらった方)からプロフィールに飛んできてくれた転換率をKPIとして追います。プロフィールに飛んできてくれる方が少ない場合、見てはもらえているもののためになっていない情報を投稿してしまっている可能性があります。
最後に、プロフィールに飛んできてくれた方からフォロワーになった率をKPIとして追います。このように各KPIを提示しておくと、何が課題になっているのかわかるのでおすすめです。
※SNSの目標設定について、アルゴリズムの変更もあるので、例としてご参照ください。
エンジニア
エンジニアはその種類によって目標設定が変わります。今回は、エンジニアの中でもアプリ開発エンジニアの例を使って話します。
アプリ開発エンジニアの目標はサービスや機能のリリースになります。まずは、一年や半年間後のサービスのイメージを決めます。そこからつけたい機能を決めます。その後、お客様の要望や開発の難易度からつける機能の優先順位をつけます。そして、1ヶ月ごとになんの機能をリリースするかを決め、1日や一週間ごとにどこまで開発するかを決めます。
ただ、ここで気をつけないといけないのはエンジニアの開発では、エラーが必ず出るという事です。エラーを直す作業が、エラーの内容によって工数が大きく変わるため、スケジュールよりも大幅に遅れてしまう事があります。
スタートアップの初期など、開発の知見がない方がエンジニアの評価者の場合、この事実を知らずに「なぜそんなに遅れるんだ?」「遅れたから低い評価にする」と伝えてしまうとエンジニアの心が離れてしまうので気をつけましょう。
デザイナー
デザイナーもその種類によって目標設定が変わります。
今回は、エンジニアの中でもアプリ開発に関わるUIデザイナーの例を使って話します。デザイナーの目標もサービスや機能のデザイン部分をリリースする事になります。エンジニアと同じように、まずは、一年や半年間後のサービスのイメージとつけたい機能を決めます。その後、お客様の要望や開発の難易度からつける機能の優先順位をつけ、1ヶ月ごとになんの機能をデザインするかを決め、1日や一週間ごとにどこまでデザインするかを決めます。
デザイナーはデザインの修正などはありますが、エンジニアよりは修正に大幅に時間がかかることは少ないです。また、デザインが決まってからエンジニアが開発するフローなため、UIデザインが遅れると、エンジニアの開発も遅れてしまうので、遅れないように定期的にスケジュールに遅れがないかを確認するようにしましょう。
総務・労務
総務などの成果を数値化しづらい管理部門は、目標設定と評価が難しいとされています。
総務などの仕事を定量で測る方法もありますが、大前提、総務や労務などの仕事は大手柄を狙うよりもミスをしない事が重要です。よくある評価方法として、7割はミスをせずに業務を遂行できたかどうかで評価を行い、残りの3割はプラスで業務改善や従業員満足度をどれくらい向上させる事ができたか?という加点方式での評価を行うというものがあります。
もちろん上述した方法も良いですが、上記のやり方だと基本的には減点主義の思想になります。人間のモチベーションは減点方式よりも加点方式の方が向上する事がわかっています。また、減点方式だと自分の評価を下げないようにミスを隠蔽する人も増えてしまいます。
そのため、誰かがミスをした際に、「ミスしないルールを作った数」を評価にすると加点主義で評価をする事ができるので、会社の状況によって目標設定や評価についてルール設計をしましょう。
目標設定シートとは
設定した目標を管理するには「目標管理シート」がおすすめです。
日々、目標管理シートに記入する事で、達成までのプランや進捗度を管理する事ができます。目標管理シートで記録を残し、企業と従業員で共有することで、人事評価に役立てることも可能です。目標管理シートの項目と、書き方を解説します。
目標設定シートの構成
目標管理シートには、一般的に次の4つの項目を記入します。
- ①目標
- 「月の商談件数を40件から50件に増やして、受注を1件増やす」「簿記2級の資格をとるため、参考書を○月までに2冊読み切る」など、具体的な目標を設定します。
- 「月の商談件数を40件から50件に増やして、受注を1件増やす」「簿記2級の資格をとるため、参考書を○月までに2冊読み切る」など、具体的な目標を設定します。
- ②期日
- 目標の達成期日と、細かいマイルストーンの期日を記載します。
- 目標の達成期日と、細かいマイルストーンの期日を記載します。
- ③達成のために取り組むこと
- 「アポイントの電話を一日60件かける」「参考書を一日10ページすすめる」など、達成できたか判断しやすい行動指標を記載するのが重要です。
- 「アポイントの電話を一日60件かける」「参考書を一日10ページすすめる」など、達成できたか判断しやすい行動指標を記載するのが重要です。
- ④チェック方法
- 設定した目標と計画は、定期的に見直しを行うことが重要です。見直す際に、どこを重視するのかあらかじめ決めておくとチェックがスムーズになります。例えば、「電話を掛けた件数と、アポイントがとれた件数を書いておく」などすると、達成可否がわかりやすくなります。
目標設定シートの書き方の例
2020年8月 目標管理シート
目標:受注数10件(先月が9件)
期日:8月31日18:00
L 3日/20日経過
取り組むこと:毎日アポイントの電話を60件
チェック方法:8月3日
L 今日の架電件数:64件、アポイント獲得:3件
L 今週の架電件数:187件、アポイント獲得:8件
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 事務職や総務など、数値化しにくい部署の目標はどう設定すればいいですか?
A: 「ミスの削減数」や「業務改善の件数」などを数値化して設定しましょう。 減点方式にするのではなく、マニュアル作成による工数削減や、他部署からの問い合わせ対応の満足度など、プラスの行動を加点方式で評価すると意欲が高まります。
Q2. MBO(目標管理制度)とOKRの違いは何ですか?
A: MBOは「給与決定」のため、OKRは「企業の成長」のために使われます。 MBOは100%達成を前提に報酬と連動させますが、OKRは達成率60〜70%程度の高い目標(ストレッチゴール)を掲げ、挑戦を促す点に大きな違いがあります。
Q3. 「SMARTの法則」とは具体的にどのようなものですか?
A: 良い目標を立てるための「5つの要素」の頭文字をとったフレームワークです。 具体的か(Specific)、測定可能か(Measurable)、達成可能か(Achievable)、関連性があるか(Related)、期限があるか(Time-bound)を確認します。
Q4. 部下が目標に対して不満を持っています。どうすれば納得してもらえますか?
A: 納得感がない最大の原因は、目標に対する「フィードバック不足」にあります。 結果が出てから評価するのではなく、1on1ミーティングなどで定期的に進捗を確認し、「なぜこの目標なのか」「達成するとどんな良いことがあるか」をすり合わせましょう。
Q5. エンジニアやデザイナーの目標設定の具体例を教えてください。
A: 「納期遵守率」や「品質(バグの少なさ)」などを指標に設定します。 開発スケジュールの遅れがないか、修正回数は適切かなどを数値化します。また、新しい技術の習得や資格取得など「スキルアップ」への取り組みも評価対象として有効です。
まとめ
人事評価における目標設定は、企業・社員双方にとってとても重要なものです。適切な目標設定を行うことで、社員のモチベーション向上や離職低下に繋がるメリットがあります。
人事評価における目標設定は、職種によって数値化が難しい場合もあります。この記事の目標設定の例などを参考に、売り上げ向上や社員の成長などの効果が実感できる目標設定を行いましょう。
目標の設定、管理にはフィードバックツール「コチーム」がおすすめです。
効果的な目標管理なら「コチーム」!

- 1on1をしながら、目標の進捗を入力できる!
- 目標の結果を人事評価に反映!
- 目標の進捗・結果を全て見える化!
- 1on1の記録を人事評価時に活用できる!
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。