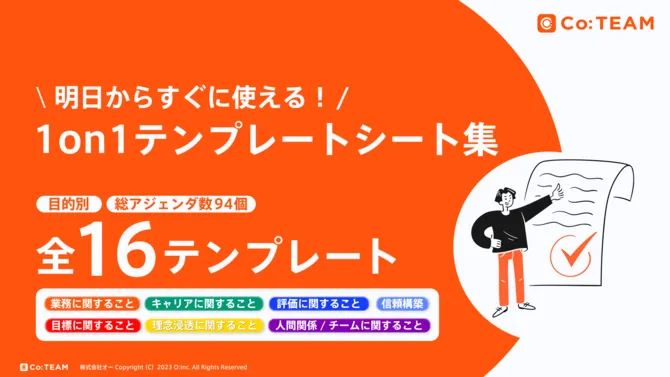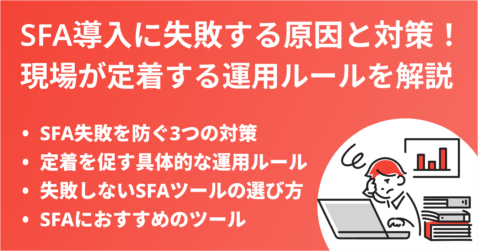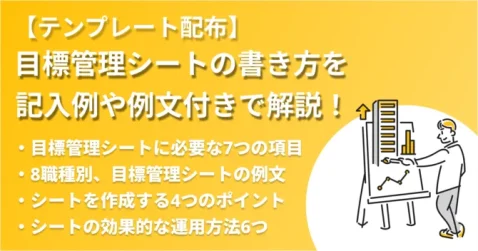人事評価制度を設計する際は、明確な基準を設けることが重要です。基準は大きく3つに分類され、これらを理解してバランスよく組み込むことで、社員が納得できる仕組みになります。ただし、公平性や透明性を確保する工夫も欠かせません。
本記事では、人事評価の代表的な3つの基準と具体的な内容を解説します。あわせて、基準設定時の注意点や効果的な運用のコツも紹介しますので、制度の見直しや新規導入の参考にしてください。
▼ この記事の内容
- 3つの基準:結果を測る「業績」、スキルを見る「能力」、姿勢を見る「情意」で構成されます。 これらをバランス良く評価することで、給与などの処遇決定の根拠を明示できます。また、評価を通じて企業が社員に求める価値観を浸透させる効果もあります。
- 基準作成の鍵:経営戦略から逆算し、社員の能力や役職に応じて柔軟に設定します。評価基準を明確にし、評価者間で統一することで「人事評価エラー」を防ぎます。誰が見ても公平だと納得できるよう、客観的な指標を用いることが重要です。
- 運用成功のコツ:評価者教育と「1on1ミーティング」による継続的なフィードバックです。 基準を正しく理解させるための研修を実施します。また、評価後の面談や日常の1on1で、評価の根拠や改善点を具体的に伝えることで、社員の成長を促します。
目次
人事評価の基準とは
人事評価基準とは、社員の業務成果や行動を評価する際の指標やルールです。組織やチーム、個人が果たすべき役割や目標に基づき設定され、評価の一貫性と公平性を保つ土台となります。
明確な基準を設けることで、評価者の主観による偏りを防ぎ、社員が納得できる評価制度を実現できます。
【全5職種対応・自動計算機能付き】
営業・事務・管理職など主要職種の評価項目例つき!
Excel / Googleスプレッドシートに対応し、そのまま使える人事評価テンプレートシートを無料公開中!
>>『人事評価のテンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!
人事評価基準を作る目的
人事評価基準を作る目的は、社員の能力や成果を適正に評価し、それを人事施策に反映させることにあります。具体的には、昇進や昇給、配置転換といった施策の判断材料とするだけでなく、社員の成長を促進し、企業全体の目標達成を支える役割も果たします。
また、評価基準が明確であれば、社員自身が目指すべき方向性を理解しやすくなり、業務へのモチベーション向上や生産性の向上にもつながります。
人事評価基準を適切に定めることによる効果
人事評価を行う目的を正しく理解し、適切な人事評価基準を設定することは、様々な利益をもたらしてくれます。
ここでは、人事評価基準を適切に定めることによる効果について、4つの観点からご説明します。
人事評価による処遇の根拠を明示できる
適切な人事評価基準を定めることによる1つ目の効果は、「人事評価による処遇の根拠を明示できる」点です。
人事評価の結果は、給与や昇給、昇格といった社員の処遇に直接関わります。評価基準を明確に設定し、それを社員に共有することで、これらの処遇の根拠を納得のいく形で示すことができます。例えば、賃金アップの条件や昇格に必要なスキル・成果が明確であれば、社員本人は目標を理解し、それに向けて努力しやすくなります。また、明示された基準は評価の公平性を保ち、処遇に対する不満や不信感を防ぐ効果も期待できます。
一方で、評価基準が不明確な場合、社員の間で処遇の決定が恣意的だと感じられ、不公平感を招く恐れがあります。このような状況は、社員のモチベーションを低下させるだけでなく、最悪の場合、離職率の上昇やチーム全体の生産性低下といった問題にもつながる可能性があります。そのため、適切な基準を設定し、運用することは従業員の貢献度を高め、企業の持続的な成長にとっても重要性の高いポイントと言えます。
従業員のマネジメントや人材育成に活用できる
適切な人事評価基準を定めることによる2つ目の効果は、「従業員のマネジメントや人材育成に活用できる」点です。
人事評価を通じて得られた情報を基に、社員に適切なフィードバックを行うことで、どの業務や行動が評価され、どの部分に課題があるのかを社員が具体的に理解しやすくなります。このプロセスは、社員自身が自らの強みや弱みを客観的に把握するうえで重要です。例えば、自分の課題を認識し、それを改善する努力を続けることで、結果として昇給や昇格などの評価につながる可能性が高まり、社員のモチベーション向上と成長が期待できます。
さらに、人事評価基準は、人材育成の視点でも大きな役割を果たします。評価基準に基づいた目標設定やフィードバックを通じて、社員は自分の現在の能力と企業が求めるスキルや役割とのギャップを理解できます。このギャップを埋めるための具体的なキャリアプランを描きやすくなるだけでなく、管理職にとっても、各社員の成長を支援するための効果的な育成プランを立案するうえでの指針となります。
また、評価基準に基づいて具体的かつ建設的なフィードバックを行えば、社員の努力が評価につながることが明確になり、仕事への意欲が高まります。このような双方向のプロセスが繰り返されることで、社員のスキル向上やキャリア形成が促進され、企業全体の成長にも貢献できる環境が整います。結果的に、従業員のエンゲージメントや職務への満足度が向上し、組織全体の活性化にもつながるでしょう。
【即戦力採用<速戦力育成】
新入社員・若手社員を1~3年で高速成長させるには、1on1とスキルマネジメントの掛け合わせがおすすめ!
スキルシートの作成から実際の運用までを解説した資料!
>>『「人」ではなく「スキル」をマネジメントする1on1』はコチラから無料ダウンロード!
企業文化や重視する価値観を醸成・浸透させることができる
適切な人事評価基準を定めることによる3つ目の効果は、「企業文化や重視する価値観を醸成・浸透させることができる」点です。
人事評価基準には、企業が掲げる方針や価値観が反映されます。例えば、チームワークを重視する企業であれば、協調性やコミュニケーション能力が評価基準に含まれます。一方、イノベーションを推進する企業であれば、独創性や挑戦する姿勢が評価対象となるでしょう。このように、評価基準を通じて企業が社員にどのような行動や働き方を期待しているのかを明確に伝えることができます。
さらに、人事評価基準が社内で共有され、それに基づいて評価が行われることで、企業が重視する価値観や行動規範が日々の業務に浸透します。社員は評価基準を意識して行動するようになり、結果的に、企業文化の一部として定着するのです。また、明確な基準があることで、社員は自身の行動が企業の目指す方向性に合致しているかどうかを振り返ることができ、価値観の共有が進むだけでなく、企業としての一体感も生まれます。
このように、人事評価基準は単なる評価の指標にとどまらず、企業の文化や理念を形作り、社員に浸透させるための有効なツールとなります。結果、社員の意識改革や行動の統一が図られ、企業全体の方向性を一致させることが可能となるでしょう。
1on1ミーティングを中心に組織の理念を浸透させて、従業員のエンゲージメントを高める方法!
>>『「あきらめ組織」の理念浸透〜「王女奪還」につなげる1on1〜』はこちらから無料ダウンロード!
人事評価エラーを防止できる
適切な人事評価基準を定めることによる4つ目の効果は、「人事評価エラーを防止できる」点です。
人事評価エラーとは、評価が偏ったり、評価者が適切な判断を下せなかったりする状況を指します。例えば、評価者の私情や心理状態、または評価者ごとの基準の違いによって、評価が公正さを欠いてしまうケースです。このようなエラーは、社員の不満を招き、組織全体の士気や信頼関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
こうしたエラーを防ぐには、明確かつ具体的な評価基準を設けることが重要です。評価基準がはっきりしていれば、評価者間で判断のばらつきを減らすことができ、公平で一貫性のある評価が実現します。また、評価を行う際には、感情に左右されるのではなく、具体的な事実や実績に基づいて判断することが求められます。
さらに、公正な評価を行うためには、評価者のスキル向上も欠かせません。そのため、評価者同士で基準のすり合わせを行う機会を設けたり、評価者研修を実施したりすることが効果的です。研修では、人事評価エラーの具体例やその対策について学び、評価基準を正しく運用する能力を養うことができます。
このように、適切な評価基準の策定と運用を通じて評価エラーを防止することで、公平な人事評価が可能になり、社員の信頼を得るとともに、企業全体の成長を支える評価制度を実現できるのです。
人事評価における3つの基準と具体的な項目
ここまでご説明してきたように、人事評価基準は適切に設定することで多くの効果が期待でき、企業が従業員を公平に管理するために不可欠です。
そして、この人事評価基準には、下記の3つの重要な評価があります。
- 業績評価
- 能力評価
- 情意評価
それぞれが、人事評価においてどのような役割を果たしているのか、詳しく見ていきましょう。
1. 業績評価
人事評価における基準の1つ目は、「業績評価」です。
業績評価とは、売上や訪問件数など数値で示せる成果を基に行う評価です。ただし、結果のみを重視すると成果主義に偏り、成長や育成につながりにくくなります。そのため、成果を示す「業績結果項目」と、行動や努力を示す「業績プロセス項目」の両方を設けることが重要です。プロセスを評価することで、スキルやモチベーションの向上も期待できます。
業績評価の具体的な項目例
業績評価の具体的な項目例としては、以下のようなものが挙げられます。
なお、先程ご説明したとおり、業績項目は「業績結果項目」と「業績プロセス項目」の2つに分けて設定することが効果的であるため、今回もその2つに分けてご紹介します。
【業績結果項目】
・個人売上高
・営業の訪問件数
・契約件数
・新規顧客獲得数
・コスト削減額 など
【業績プロセス項目】
・営業活動の実施頻度(例: 週次での顧客訪問回数)
・プレゼンテーションの質や回数
・問い合わせ対応の迅速さ
・チームでのプロジェクト進行度
・顧客フォローアップの実施状況 など
業績結果項目の比重を高くしすぎると、プロセスを無視した結果主義に陥るため注意が必要です。一般的には、管理職には比重を高め、初級職には低めに設定してバランスを取ります。
2. 能力評価
人事評価における基準の2つ目は、「能力評価」です。
能力評価とは、成果を上げるために必要な能力や知識、資格を評価するものです。評価項目は成果を出す基礎力を養うために設定されます。例えば営業活動では「顧客管理の徹底」が求められますが、その達成には課題を適切に報告・相談し、スケジュールを管理する能力が欠かせません。
ただし、能力があるだけでは評価の対象にはなりません。仕事の現場でその能力をどのように活用したか、具体的な成果や実行力が評価されます。例えば、スケジュール管理力があるというだけでなく、実際に漏れや遅れ、ミスがない形で仕事を遂行して初めて高い評価につながります。
能力評価の具体的な項目例
能力評価の具体的な項目例としては、以下のようなものが挙げられます。
- スケジュール管理力:タスクの優先順位付け、納期の厳守、ミスや遅延の防止 など
- 専門知識とスキル:業務に必要な特定の知識、業界動向の理解、開発技術の習得 など
- 資格:仕事に関連する専門資格の取得、法的または規制上の要件を満たすための資格取得 など
- 人材育成力:部下や後輩への指導力、フィードバックの提供やコミュニケーションスキル など
- 問題解決能力:業務上のトラブルへの対処、課題の早期発見と対応策の提案、チーム内外の協力を引き出す力 など
これらの能力項目は、実際の業務に活かされてこそ意味があります。ウエイトを高くしすぎると、自己学習や資格取得が目的化し、偏りが生じる恐れがあるため、バランスの取れた評価が必要です。
【最小限の労力で最大限の成果を出す評価の作り方】
●負担を抑えつつ効果を出す人事評価制度の制度設計・運用方法
●人事専任の社員がいなくても成果につなげられる人事評価の制度設計方法
●被評価者の評価結果への納得、その後の成長を促す人事評価の運用方法
評価制度の構築から運用までの全てがわかる無料資料
>>「人事評価のプロが教える、「成果と満足度を両立させる評価」の制度設計・運用ガイドブック」はこちらから無料ダウンロード!
3. 情意評価
人事評価における基準の3つ目は、「情意評価」です。
これは従業員の仕事への姿勢や勤務態度を評価するもので「会社が求める人間力」を測る基準といえます。具体的には、やる気、チームワーク、責任感、遅刻の有無などが含まれます。
情意評価では「行動に落とし込んで初めて評価できる」点に注意が必要です。例えば「積極性」を評価する場合、「新しい仕事に自主的に取り組んだか」といった具体的な行動基準を設けることで、主観に左右されない客観的な評価が可能になります。
また、情意評価の基準は全社員が理解・共有しておくことが理想です。自主的な浸透が難しい場合は、定期的な読み合わせや確認を行い、基準を社内に定着させることが効果的です。
情意評価の具体的な項目例
情意評価の具体的な項目例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 規律性:業務規則の遵守、自己管理能力 など
- 責任性:タスクの完遂、ミスへの対応、業務への誠実さ など
- 協調性:チームとの連携、コミュニケーション力、問題解決の協力 など
- 積極性:自己啓発への取り組み、新規提案、挑戦意欲 など
情意評価は、職場の風土や文化に大きな影響を与えます。特に共同作業が求められる環境では、これらの項目が重要視されるべきです。従業員一人ひとりの姿勢が職場全体の雰囲気や生産性に大きく影響するため、情意項目を適切に評価することは、健全な企業文化の維持・発展に欠かせません。
人事評価基準の作成手順
人事評価制度に不可欠な人事評価の基準ですが、公正な人事評価の実現には、適切な評価基準を構築し、運用していくことが求められます。
ここでは、人事評価基準の作り方について、細かな手順をご説明します。
STEP1:経営戦略・人事戦略から目的を明確化する
人事評価基準の作成における1つ目のステップは、「経営戦略・人事戦略から目的を明確化する」ことです。
人事評価制度を導入する目的が曖昧なままでは、基準が統一されず、円滑に運営できない可能性があります。そのため、「何のために評価を行うのか」を具体的に定義することが重要です。
目的を明確にする理由は、社員に「人事評価制度が何のために存在するのか」「企業がどのような人材や行動を評価し、社員をどう成長させたいのか」を理解してもらうためです。目的が明確であれば、社員自身も自分の行動や目標が会社の方針とどのように結びついているのかをイメージしやすくなり、評価制度への納得感が高まります。
また、業種や職種、企業が求める人材像によって評価制度の目的は異なります。そのため、経営陣や人事担当者が中心となり、目的を社内で十分に擦り合わせる必要があります。他社の事例を参考にすることは有益ですが、自社独自の状況や目標に合った目的を設定することが成功の鍵です。
目的を明確にすることは、人事評価制度を機能させるための最初の重要な一歩です。このステップを丁寧に進めることで、社員と企業の双方が評価制度を効果的に活用できる基盤を築くことができます。
STEP2:具体的に評価項目を設定する
人事評価基準の作成における2つ目のステップは、「具体的に評価項目を設定する」ことです。
評価の目的が明確になったら、次に取り組むべきは、その目的を実現するために必要な具体的な評価項目を検討・選定することです。
評価項目を設定する際には、企業のビジョンや理念を実現するために適した内容であるかどうかを慎重に検討する必要があります。例えば、「イノベーションを重視する企業」であれば、評価項目に「新しいアイデアの提案数」や「改善活動への参加状況」を含めることが考えられます。設定する項目が企業の方向性に沿っており、従業員の成長をサポートするものであるかを確認することが重要です。
また、評価項目の設計には従業員の意見を取り入れることも欠かせません。アンケートやヒアリングを通じて、現場の課題や問題点、従業員が求める評価の在り方を把握することで、実際の労働環境や業務に合った制度を構築できます。従業員が納得感を持てる制度を設計することで、運用が比較的スムーズに進み、制度の効果が長く持続する可能性が高まります。
STEP3:評価方法を決定する
人事評価基準の作成における3つ目のステップは、「評価方法を決定する」ことです。
評価方法を決定することは、評価基準を実際にどのように適用するかを明確にする重要なステップです。評価方法によって、社員のパフォーマンスをどのように測定し、どのような基準で評価するかが決まります。評価方法にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴を理解した上で、企業の文化や目的に合った方法を選ぶことが大切です。
具体体な評価方法の例については、後ほどご説明します。
この段階で評価方法をしっかりと決めておくことで、評価が一貫性を持ち、社員にとっても納得感のあるものになります。
STEP4:評価者を選定する
人事評価基準の作成における4つ目のステップは、「評価者を選定する」ことです。
まず、評価者を選定する際には、社員の業務内容や実績を深く理解している人物を選ぶことが重要です。特に、マネジメント層や上司が評価者として適任となります。業務の進捗や成果について十分に把握している立場にあるため、評価がより正確で公正なものになる傾向があるからです。
また、評価者は一人に絞るのではなく、複数名の評価者を選定することが一般的です。例えば、部門長やチームリーダーなど、さまざまな視点を持った人々に評価してもらうことが望ましいです。一人だけの評価だと、評価が偏ったり、社員の日常的な業務や実績を十分に反映できない可能性があります。複数の評価者がいることで、多角的な視点から評価を行い、より公平性を保つことができます。
さらに、評価者に対しては、評価基準に基づいて適切な評価を行うためのトレーニングを実施することが必要です。評価の仕方やフィードバックの方法について十分に理解してもらうことが、誤った評価を防ぎ、社員に対する建設的なフィードバックを提供するためには欠かせません。あらかじめ研修を行い、評価者が適切に評価できるよう準備をしておきましょう。
STEP5:評価期間を決定する
人事評価基準の作成における5つ目のステップは、「評価期間を決定する」ことです。
評価期間を設定することは、評価の一貫性と公平性を保つために重要です。評価期間は、通常、社員の業績や成果を反映させるために決定されます。多くの企業では、評価が給与や賞与、報酬に直結するため、評価期間を明確に定めることが必要です。
一般的には、評価期間は月単位や半期単位(例えば、1月〜6月、7月〜12月)で設定されることが多いです。毎月の業績を反映させる場合は、月次で評価を行うことになりますし、半年ごとにまとめて評価を行う場合もあります。例えば、短期間で業績の変化を反映させたい場合には月単位、長期的な目標達成度を評価する場合には半年単位の評価が適しているかもしれません。
それぞれの評価期間にはメリットがありますが、企業の業務内容や人事考課の特徴、評価の目的などに応じて最適な期間を選ぶことが大切です。
STEP6:評価のフィードバック方法を決定する
人事評価基準の作成における6つ目のステップは、「評価のフィードバック方法を決定する」ことです。
評価結果を社員に伝えるだけでなく、理解しやすく改善に繋がるように伝えることが重要です。具体的で建設的な内容を提供し、双方向のコミュニケーションを促し、前向きな言葉でフィードバックを行います。
また、評価が適切に行われたかを確認するレビュー方法も決定します。評価基準の適用状況や評価者の公平性を検証するため、評価者間レビューや上司・人事部門によるチェックが必要です。
評価結果を社員にフィードバックする方法と、評価結果の妥当性を検証するためのレビュー方法をあらかじめ定めておくことが重要です。これらは、人事評価を効果的に活用するために不可欠なプロセスです。
さらに、評価ツールの導入することで、評価プロセスの透明性を高め、管理を効率化できます。評価ツールを活用すれば、評価の過程の透明性が向上し、評価の履歴を管理しやすくなります。例えば、オンラインの評価システムや、評価フォームをデジタル化したツールなどを利用することで、評価の見える化を実現できます。自社の体制やニーズに合わせて、最適なツールを選ぶことが大切です。
人事評価基準を定める際のポイント
ここでは、人事評価の基準を決めるときのポイントや注意点についてご説明します。
適切な基準を作成できるよう、それぞれのポイントについて理解を深めていってください。
評価基準や項目は、複数のメンバーで決める
人事評価基準を定める際の1つ目のポイントは、「評価基準や項目は、複数のメンバーで決める」ことです。
評価基準や評価項目を設定する際、1人で決定してしまうと、評価が偏りやすく、客観性を欠く可能性があります。
例えば、ある基準が1人の評価者には重要でも、他の評価者にはそうでない場合があります。こうした偏りを避けるために、複数の視点を取り入れることが大切です。
複数人で決めることで、評価基準がバランスよく、広範囲にわたり、より公平で透明性が高まります。また、異なる意見を交わすことで、より適切な評価基準を作ることができます。
したがって、評価基準を設定する際は、多くの関係者を巻き込み、チームで決定することが信頼性と公平性を高めるために重要です。
複数の評価項目を設定する
人事評価基準を定める際の2つ目のポイントは、「複数の評価項目を設定する」ことです。
評価項目を複数設定することは、社員を公平に評価するうえで非常に重要です。単一の評価基準だけで評価を行うと、社員の多様な貢献を正当に評価できなくなる可能性があります。
例えば、評価基準が売上のみであった場合、コスト削減や業務効率化に貢献した社員の努力は評価されません。逆に、評価基準が勤務態度だけで決まる場合、売上や業績に貢献している社員が正当に評価されず、モチベーションが低下する恐れがあります。
このように、特定の基準に偏った評価は、社員のやる気を損ない、全体のパフォーマンスにも悪影響を与えます。そのため、評価項目を複数設定することで、社員一人ひとりの強みや多様な貢献を公平に評価することが可能になります。これにより、社員がどの部分で貢献しているのかが明確になり、強みを活かし、課題点を改善するための具体的なフィードバックが可能となります。また、社員にとっても、自分の仕事がどのように評価されているかを理解しやすくなり、より一層の成長意欲を引き出すことができます。
役職や業務内容に応じて評価基準を変える
人事評価基準を定める際の3つ目のポイントは、「役職や業務内容に応じて評価基準を変える」ことです。
部署や役職ごとに求められる成果や行動は異なるため、一律の基準を適用すると不公平感が生まれ、社員のモチベーションや生産性に悪影響を与えることがあります。
例えば、営業部門では売上や新規顧客数などの定量的な成果が重要視され、総務や人事部門では業務効率や社員満足度などの定性的な成果が評価されます。また、新入社員と係長では求められる能力が異なり、それぞれに応じた評価基準が必要です。
公平な評価を実現するためには、業務内容や役割を正確に把握し、評価基準を部署ごとに設定することが重要です。また、基準を社員に共有し、自分の役割に応じた目標を理解させることも効果的です。こうした取り組みで、公平でモチベーションを高める評価制度を作ることができます。
評価者教育・評価者研修を実施する
人事評価基準を定める際の4つ目のポイントは、「評価者教育・評価者研修を実施する」ことです。
評価基準を社内で統一するために、評価者に対して教育や研修を行うことは効果的です。評価者の中には不確かな方法で評価を行う場合があり、それがばらつきや不公平の原因となります。公正な評価を実現するには、評価基準や方法を正確に理解し、共通認識を持つことが不可欠です。
そのために、社内の有識者や外部のセミナー・サービスなどを活用して評価者研修を行うことを検討してみてはいかがでしょうか。人事評価の目的や注意すべき点、正しい考え方について学び、評価スキルを総合的に向上させることで、より公正かつ納得度の高い評価を遂行できます。
評価方法を社員に周知する
人事評価基準を定める際の5つ目のポイントは、「評価方法を社員に周知する」ことです。
評価方法が不明確だと、社員は自分の評価に納得できず、不満が生じることがあります。主な問題として、以下のような場合が挙げられます。
- 評価基準が不明確:何を基準に評価するのかが曖昧で、社員が理解できない
- 評価されるべき行動が不明:社員がどのような成果を上げればよいのかが分からない。
- 評価が一貫していない:主観的な評価に偏り、公正感が欠ける
これらの課題解決のためには、評価基準や方法を明確にし、社員に公開することが必要です。例えば、評価基準を文書で配布したり、定期的な説明会を開催することが効果的です。また、フィードバックを提供して評価結果を共有することも重要です。
評価方法が明確であれば、社員は目標に向かってモチベーションを高め、公平な環境で働くことができ、パフォーマンス向上につながります。
定期的に評価基準を見直す
人事評価基準を定める際の6つ目のポイントは、「定期的に評価基準を見直す」ことです。
評価制度は導入して終わりではなく、継続的な運用と改善があってこそ効果を発揮します。会社の理念や目標と一致しているか、市場や時代の変化に対応できているか、社員が納得しているかといった観点で定期的に検証しましょう。変更が必要な場合は、3〜4ヵ月前には新制度を固め、社員への周知を行うことが望まれます。
こうした見直しにより、社員は「自分たちの声が反映されている」と感じ、モチベーションが向上します。不満を解消することで、評価に納得できずエンゲージメントが低い社員が減少し、最終的には組織全体のパフォーマンスも向上するでしょう。
評価後のフィードバックを充実させる
人事評価基準を定める際の7つ目のポイントは、「評価後のフィードバックを充実させる」ことです。
従業員が人事評価に不満を感じている場合は、評価後のフィードバックを充実させることが効果的です。フィードバックの例としては、以下のような観点が挙げられます。
- 評価基準の説明
- 改善すべき点
- 次回までの目標
- 具体的なアドバイス
- 期待していること
各従業員に個別の面談を設け、上記のようなポイントを伝えましょう。評価に必要な情報を効率的に把握することはもちろん、より適切なフィードバックを実践することができます。人事評価の目的は、評価を通じて仕事のやり方を見直し、従業員の成長を促すことであり、納得感のある評価を実現するためにも、適切なフィードバックが欠かせないと言えるでしょう。
【参加者満足度98.2%!】
明日から使える1on1で重要な「承認」「共感」「フィードバック」のテクニックをわかりやすく解説!
「今まで受けた研修で1番良かった!」「マネジメントの新しい考え方を得れた!」など現場管理職・マネージャーに大人気の1on1研修の第1回目の資料を無料公開中!!
>>1on1研修第1回『マネジメントと1on1って何ですか?』はこちらから無料ダウンロード
1on1ミーティングを導入する
人事評価基準を定める際の8つ目のポイントは、「1on1ミーティングを導入する」ことです。
1on1ミーティングではシートなどを活用して記録を残し、期末に振り返ることで目標達成状況や工夫の有無を確認できます。また、評価期間中でも現状のまま進んだ場合の評価を伝えられるため、「自己評価とのずれ」が起こりにくくなります。さらに「最近、会社に貢献していることはある?」と質問することで、普段は見えにくい取り組みも評価に反映できます。
このように、1on1ミーティングを導入し、記録を残すことで社員の評価の根拠が明確になり、納得感のある評価を行ったうえで、被評価者への説明も簡単にできるようになります。
人事評価の主な方法
ここでは、最新の人事評価制度についてご紹介します。
今回ご紹介する人事評価制度は下記の4種類です。
- コンピテンシー評価
- MBO(目標管理制度)
- OKR
- 360度評価
それぞれの評価方法と特徴について、以下にご説明します。
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、優れたパフォーマンスを発揮する従業員の行動特性(コンピテンシー)を基準に行う人事評価です。成果を上げている人材の行動特性を評価項目として設定し、それに基づいて評価することで、同様に優秀な人材を育成することを目的としています。
下記は、コンピテンシー評価の基本的な評価要素の一覧です。
- タイムマネジメント
- リスクテイクの判断
- 対人交渉能力
- 説明責任を果たす能力
- ストレス管理
上記の評価要素を基に優秀な人の行動や価値観の共通点を抽出して判断するため、公平性を担保しやすいのが特徴です。さらに、社員のパフォーマンス向上や適切なキャリアパスの形成に効果的で、納得感のある評価制度の設計や効率的な人材育成にもつながります。
MBO(目標管理制度)
MBO(目標管理制度)とは、「Management by Objectives」の略で、従業員が組織目標と連動した個人目標を設定し、その進捗や達成度に応じて評価する制度です。
メリットとして、自己管理によるマネジメントが可能になり、従業員のモチベーション向上が期待できます。自ら設定した目標に責任を持ち、自主的・自律的に行動できる点が特徴です。
さらに、目標達成が企業目標にも直結するため、従業員と企業がともに成長でき、評価への納得感も高まります。
OKR
OKRとは、「Objectives(目標)and Key Results(主要な結果)」の頭文字をとったものであり、大きな目標とその達成を測るための具体的な指標を設定し、評価する手法です。企業が目指すべき目標と社員個人の目標をリンクさせ、すべての社員が一丸となって同じ方向を向き重要課題に取り組むことを目的としています。
特徴は、個人と企業の目標をリンクさせて、目標設定・進捗確認・評価という一連の流れを高い頻度で行う点にあります。OKRは、社員および企業全体がモチベーションをアップさせるために、「容易には達成できない高い目標」を掲げ、達成率が60〜70%程度となるのが理想とされています。
組織と従業員の目標に関連性を持たせ、進捗確認や成果に対する評価を頻繁に実施することで、一体感をもって計画的に業務を推進できるというメリットがあります。
【OKRについて徹底解説!】
会社の目標でOKRを導入したいけど、どのように導入・運用すれば良いかわからない。そもそもOKRって何なのか?などのお悩みをマルッと解決いたします!
OKRの導入から運用まで成功までの道のりを完全解説した資料!
>>『売上を劇的に高める米国最先端の戦略実行手法「OKRパーフェクトガイド」』はコチラから無料でご覧いただけます!
360度評価
360度評価とは、上司や人事担当者だけでなく、部下や同僚など複数の従業員が評価者となり、対象者を多面的に評価する制度です。
多様な視点を取り入れることで主観やバイアスを抑え、公正で客観的な評価が可能になります。そのため、評価対象者にとっても納得感が得やすく、モチベーションの維持・向上につながります。
一方で、従業員数が少ないと評価者が特定されやすい、評価情報の集約に手間がかかる、評価者間で馴れ合いが生じるといったリスクもあるため、運用には注意が必要です。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 人事評価の基準を作る「目的」は、昇給・昇格以外にありますか?
A: はい、社員の「成長促進」と「企業文化の浸透」が大きな目的です。 評価を通じて社員に求められるスキルや行動を示し、成長を促します。また、評価項目に企業理念を反映させることで、会社が大切にする価値観を組織全体に浸透させます。
Q2. 「業績評価」と「能力評価」は、どのように使い分けるべきですか?
A: 業績評価は「結果責任」を問う管理職、能力評価は「成長段階」の若手社員に重視します。 業績評価では売上などの結果を重視し、能力評価ではスキルや知識の習得度を評価します。両方を組み合わせることで、成果と育成のバランスをとることが可能です。
Q3. 評価基準を定める際に、一番気を付けるべき注意点は何ですか?
A: 評価者が一人で基準を決めず、「複数人の視点」を取り入れることです。 一人の主観で基準を決めると、評価が偏りエラーが生じる原因となります。複数のメンバーや関係者を巻き込んで議論し、公平性のある基準を設定しましょう。
Q4. 最近注目されている「コンピテンシー評価」とは何ですか?
A: 優れた成果を出す社員の「行動特性」を基準に評価する手法です。 成功者の行動(例:タイムマネジメント、対人交渉力など)をモデル化し、それを評価項目とします。目指すべき行動が明確になるため、社員の育成に効果的です。
Q5. 評価期間はどのくらいの頻度が適切ですか?
A: 給与や賞与に連動させる場合は「半年〜1年ごと」が一般的です。 ただし、目標の進捗確認やフィードバックは、1on1などを活用して月次や四半期ごとに行うことで、評価が直前の出来事に偏るのを防げます。
まとめ
この記事では、人事評価の基準について、作成方法や項目の具体例を踏まえてご解説してきました。
人事評価基準は、一度作成して終わりではありません。実際に運用を始めてから、課題や改善点に気づくことが多いものです。そのため、評価基準を含め人事評価制度は継続的に改善していくことが重要です。試行錯誤を重ねることで、より精度の高い評価制度を作り上げることができます。こうした改善を通じて、社員が納得し、モチベーションを高めることができる客観性と公平性のある評価制度を構築できるのです。
本記事を参考に、適切な人事評価基準の設定や今後の改善に取り組んでいただければ幸いです。
納得度の高い人事評価の実現なら「コチーム」!

- 1on1の記録や目標の進捗を人事評価にカンタンに確認でき、根拠のある評価を実現!
- 人事評価シートを自動生成・配布・収集でき、人事担当者の負担を軽減!
- あらゆる人事評価や評価調整(甘辛調整)に対応!
- 評価材料を集めるための1on1テンプレートで、日常から評価材料を集めるマネージャーを育成する!
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。