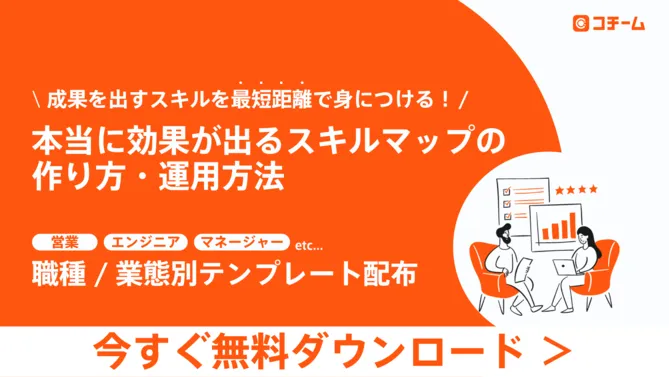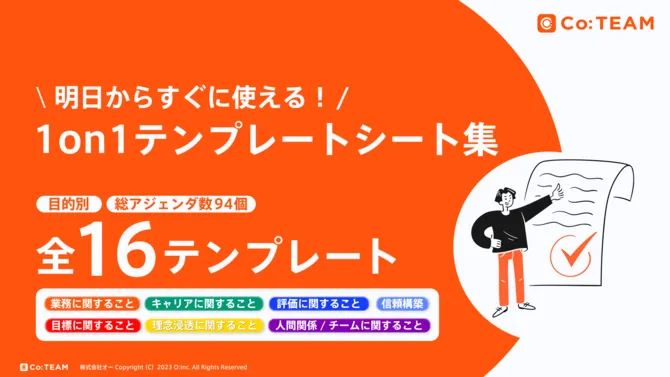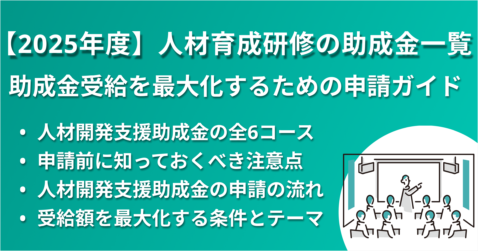現代の日本では、少子高齢化による労働人口の減少や採用難を背景に、従業員一人ひとりの「人材力」を高めることが求められています。そのためには行き当たりばったりではなく、体系的な人材育成計画の策定が必要です。
人材育成計画を立てることで、企業のビジョンや戦略に基づき「求める人物像」を明確にし、その人物像に沿ったスキルや知識を持つ人材を育成できます。
本記事では、人材育成計画の立て方や階層別の策定例など実践的な内容を紹介します。評価業務を行う方だけでなく、評価される側にとっても業務に役立つ知識となるため、ぜひ参考にしてください。
≫無料で「本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法」をダウンロードする
▼ この記事の内容
- 計画の目的:企業の経営戦略に基づき「求める人物像」を明確にし、効率的に人材を育成する戦略です。 労働人口の減少や労働時間の制約がある現代において、限られたリソースの中で従業員一人ひとりの「質」を高め、企業の競争力強化を達成するための土台となります。
- 立案の5ステップ:①求める人物像の確立 → ②スキルギャップの洗い出し → ③目標設定 → ④計画策定 → ⑤PDCA運用です。特にスキルマップなどを用いて現状のスキルを客観的に把握し、目標レベルとの差を明確にすることが、育成プログラムの設計において最も重要となります。
- 階層別の例:新人には「基礎スキル習得」、中堅には「専門性の深化とリーダーシップ」、管理職には「戦略的思考とマネジメント強化」が中心です。 新人にはOJTと集合研修を組み合わせ、中堅には外部セミナーや後輩指導を任せ、管理職には経営会議への参画など実践的な機会を提供します。
目次
人材育成計画とは
人材育成計画とは、従業員のスキルや能力を向上させるために中長期的な目線で策定する戦略のことです。
現代のビジネス環境では、少子高齢化による労働人口の減少やデジタル技術の急速な進化により、計画的な人材育成の重要性がますます高まっています。
人材育成計画では、企業のビジョンや経営戦略に基づき「求める人物像」を明確にし、必要なスキルや知識を特定します。その上で現状とのギャップを分析し、OJTや自己啓発支援などから最適なアプローチを選びます。
効果的な人材育成計画を立てるための具体的なステップについては詳しく後述しますので、まずは人材育成計画を作るべき理由やメリットについて理解を深めてみましょう。
>>【助成金活用で最大75%補助】満足度98.2%のマネジメント研修がわかる資料3点セットを無料でダウンロードする
人材育成計画を作るべき理由
人材育成計画を策定することには多くのメリットがあります。
近年「人的資本経営」という言葉がトレンドになっているように、人材とは、使い方次第で企業側の目標達成や業績向上に最もクリティカルに影響を与えることができる非常に重要なリソースです。
また、近年の採用難や終身雇用体制の崩壊により、人材というリソースの「数」に依存する時代は終わりました。そのため、1人ひとりの従業員の「質」を高めることこそが、企業の目標達成や競争力強化において最重要事項となってきているのです。
ただし、企業側が人材育成に掛けられるリソースも無尽蔵ではなく、効率的なプログラムや制度運用によって最大限の育成効果を発揮する必要があります。このような状況でまず手を付けるべきが、体系的に育成のロードマップを描くことができる人材育成計画なのです。
以下では、人材育成計画を作成すべき具体的な理由や生じるメリットについて、さらに詳しく解説していきます。
計画の進捗状況がわかりやすい
人材育成計画を策定する最大のメリットは、育成の進捗を可視化できることです。
明確な目標と基準を設定すれば、現状の段階や次に取るべき行動を分かりやすく示せます。進捗が明確になることで、遅れや強化すべき領域を特定しやすくなり、迅速な対応が可能です。従業員も自身の成長や立ち位置を把握でき、モチベーション向上につながります。
さらに、経営層にとっても人材育成への投資効果を測定しやすくなる利点があります。
【成果を出すスキルを最短距離で身につけるスキルマップの作り方!】
・スキルマップを導入しようと考えているけど、効果が本当に出るのかわからない
・スキルマップを導入しているけど、なかなか効果が出ない・形骸化している
とお悩みではありませんか?
実は、スキルマップを効果的に運用するためには抑えるべきポイントがあります!人材育成で100社以上支援実績がある弊社のノウハウを盛り込んだ、ココでしか読めない情報が満載の無料スキルマップ解説資料!
>>『本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法』はコチラから無料ダウンロード!(職種 / 業種別のテンプレート公開中)
育成担当者が代わってもスムーズに引き継げる
人材育成計画を明確化しておくことで、担当者が変わった場合でも一貫した育成方針を維持できるというメリットがあります。
特に中長期的な育成が必要なケースでは、途中で担当者が交代することも少なくありません。しかし、計画書には育成の目的や背景、具体的な施策、評価方法、これまでの経緯などが記録されているため、新しい担当者はそれを参照することで、再度ゼロから育成を始める必要がなくなります。
また、暗黙知になりがちな育成ノウハウや過去の成功・失敗事例なども共有されるので、組織としての学習を蓄積することができるというメリットも期待できます。例えば、「この社員には過去にこのような研修を実施し、このような成果と課題があった」という情報が引き継がれることで、新しい担当者はこの実践例を参考にした上で、さらに効果的な育成計画をたてることができるのです。
また、育成される側の従業員にとっても、担当者が変わるたびに方針が大きく変わるといった混乱を避けられるメリットがあります。育成計画が組織全体で共有されていれば、直接の担当者だけでなく、関連部署やさらに上位のマネジメントも含めて、社内で一貫したサポート体制を構築しやすくなります。
人材育成計画の立て方・ステップ
ここでは、効果的な人材育成計画の立て方を5つのステップに分けて解説します。
これから紹介する手順で取り組むことで、企業の経営戦略に沿った実効性の高い育成計画を策定することができます。
それでは、人材育成計画立案の5つのステップについて詳しく見ていきましょう。
①経営戦略をもとに求める人物像を確立
人材育成計画の第一歩は、企業の経営戦略や事業計画を踏まえた「求める人物像」の確立です。どんなに優れた育成プログラムも、企業のビジョンや戦略とマッチしていなければ、狙い通りの成果を得ることはできません。
まず、自社の経営理念や中長期的な事業戦略を再確認します。
「3年後、5年後にどのような事業展開を目指しているのか」「そのために必要な組織能力は何か」といった視点から、求められる人材像を具体化していきます。例えば、「グローバル展開を加速させる」という戦略があれば、「異文化コミュニケーション能力を持ち、海外市場の開拓ができる人材」といった人物像が導き出されるでしょう。
この段階において大切な点は、経営層や事業責任者といった各部門と密なコミュニケーションを取ることです。
人事部門だけで育成を考えるのではなく、各部門の責任者を巻き込んで、経営視点に加えて現場のニーズも反映させることが重要です。また、業界動向や技術トレンドなども考慮し、将来必要となるスキルや知識も先見的に取り入れるようにしましょう。
求める人物像を、抽象的な表現だけでなく、「具体的にどのような業務ができるか」「どのようなスキルレベルを持っているか」といった形で明確化することで、次のステップでの目標設定がスムーズになります。
②目標設定・必要なスキルの洗い出し
求める人物像が明確になったら、次は具体的な目標設定と必要スキルの洗い出しを行います。この段階では、抽象的な人物像を具体的な能力要件やスキル項目に落とし込んでいきます。
まず、職種や役割ごとに求められる主要な能力やスキル、資格等を特定します。例えば、営業職であれば「商品知識」「提案力」「顧客関係構築力」などが挙げられます。
さらに、各能力やスキルについては、レベル感も併せて設定しましょう。初級・中級・上級といったシンプルな区分分けをしたり、より詳細な5段階評価などを用いたり、さらに検定や資格等であれば級やスコアといった数値を段階的に設定したりすると良いでしょう。
重要なのは、各レベルで「具体的に何ができるようになるか」を明確にすることです。
例えば、「プレゼンテーションスキル・レベル3:社内会議で自分の担当業務について論理的に説明でき、基本的な質問に対応できる」といったように、到達点や条件をだれが見ても分かりやすく設定することが重要となります。
こうした具体的な行動や数値ベースの記述を行うことにより、評価の客観性を高めることができます。
③現状把握してギャップの洗い出し
目標とするスキルや能力が明確になったら、次に現状把握とギャップ分析を行います。現状把握には、評価面談、スキルアセスメント、360度評価、実務テストなどがあり、複数の手法を組み合わせることで客観性が高まり、主観によるバイアスや認識のズレを発見しやすくなります。その後、収集したデータをもとに目標レベルとの差を分析します。
ギャップ分析の進め方の例
①目標レベルの明確化:求めるスキルや行動の基準を定義する(例:営業担当なら「月20件の新規商談を創出できる」)。
②現状把握:面談やテストで従業員の実力を把握する(例:現状は月10件にとどまっている)。
③差の特定:目標と現状の差を数値や行動レベルで明示する(差=月10件)。
④原因分析:差が生じている要因を探る(例:顧客リスト作成のスキル不足、時間管理の課題)。
⑤解決策の設定:不足を補う施策を決定する(例:営業リストの効率的な作成研修、タイムマネジメント研修)。
この際、単に「できる/できない」の二択ではなく、「どの程度できているか」「どの部分が特に不足しているか」といった詳細かつ段階的な分析を行うことで、より個人の能力に合わせた育成計画を立てられます。
また、個人レベルだけでなく、部門や組織全体としての傾向も分析することで、共通の課題を発見できることもあります。例えば、「営業部全体でデジタルマーケティングの知識が不足している」といった組織的な課題が見えてくれば、部門単位での育成施策や取り組みを検討することができます。
ギャップ分析の結果は、次のステップでの育成計画策定の基礎となるため、できるだけ具体的かつ客観的なデータとして整理しておくことが重要です。
④目標・育成計画を段階的に策定
ギャップ分析の結果をもとに、具体的な育成計画を段階的に作成していきます。
ここでのポイントは、一度にすべてのギャップを埋めようとするのではなく、優先順位をつけて段階的に進めることです。
まず、短期(3〜6ヶ月)、中期(1〜2年)、長期(3〜5年)といった時間軸で目標を設定します。特に、短期目標は具体的かつ達成可能なものにし、中~長期に応じて難易度を上げていくことで、早期の成功体験の積み重ねを通じてモチベーションを高める効果を狙っていきましょう。
次に、各目標達成のための具体的な育成施策を検討します。
OJT、集合研修、eラーニング、外部セミナーなど、様々な手法の中から最適な組み合わせを選ぶことが重要で、例えば「基礎知識はeラーニングで学び、実践スキルはOJTで身につける」といった複合的なアプローチも効果的でしょう。
また、育成計画には「いつ、誰が、何を、どのように行うか」を明確に記載することが重要です。特に、上司や先輩社員によるOJTやコーチングの役割は具体的に定義し、育成担当者自身も何をすべきかを理解できるようにします。
さらに、定期的な進捗確認のタイミングや評価方法も計画に含めておくことで、PDCAサイクルを回しやすくなります。例えば、「上司との毎月の面談で進捗を確認し、必要に応じて計画を調整する」といった決まりを組み込んでおくことで、より目標の達成可能性を高めたり、設定したプログラムや計画の実践漏れを防ぐことができます。
【目標設定・目標管理の全解説!】
●効果的な目標設定のやり方
●マネージャーの負担にならない目標管理のやり方
●効果が出る目標管理の実践方法
●米国最先端の目標管理
など目標設定・目標管理について徹底解説した無料資料
>>「170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド」はコチラから無料ダウンロード!!
⑤実践・フィードバックを繰り返してPDCAを回す
計画を立てたら、実際に行動に移していきましょう。①~④の過程をPDCAサイクルとして繰り返すことで、育成を最適化し、去年あるいは前半期よりも、さらに最適化された育成計画を立てられるようにします。
PDCAサイクルとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)というプロセスのことで、このサイクルを繰り返し回すことによって業務の洗練化を図っていく考え方です。

また、各段階において、現状に応じて目標や計画を柔軟に見直しをすることも大切です。
当初想定していなかった課題が見つかったり、環境変化により新たなスキルが必要になるといった不測の事態が起こることは、決して珍しいことではありません。そのような場合は当初の計画に固執せずに、その時々のメンバーに合った目標やサポートへと都度調整するようにしましょう。
人材育成計画の作成に必要なスキル・要素
効果的な人材育成計画を策定する上で、いくつか重要となるスキルや要素があります。
人材育成計画の策定は、単に研修メニューを選定したり目標やハードルを設定することではなく、経営戦略と人材開発を結びつける重要な業務です。そのため、社内全体を見渡せる幅広い視点と様々なスキルが必要となるのです。
ここでは、人材育成計画を作成する際に特に重要となる3つのスキルや要素について詳しく解説します。
現状把握スキル
人材育成計画を作成する上で最も基本となるのが、現状を正確に把握する能力です。現状把握が不十分だと、的外れな育成施策を立ててしまい、リソースの無駄遣いにつながります。
現状把握能力には、定量的・定性的データの収集力や分析力などが含まれます。例えば、スキルアセスメントの結果、業績データ、従業員満足度調査などの定量データと、面談やヒアリングから得られる定性的な情報を総合的に分析する力が求められます。
また、表面的な現象だけでなく、その背景にある本質的な課題を見抜く洞察力も重要です。例えば、「営業成績が低い」という現象の背後に、「商品知識の不足」「提案スキルの弱さ」「顧客ニーズの把握不足」など、様々な要因が隠れている可能性があります。
このように、現状把握のためには、多角的な情報収集と、さらに収集した情報をもとに本質をとらえた分析を行うことが欠かせません。
自社の状況に合わせて適切な調査方法やヒアリング機会を選択し、現状を正確に把握するために定期的にデータを更新していくことが求められます。
計画・ロードマップ策定スキル
現状把握を行って目標とのギャップを特定したら、それを埋めるための具体的な計画やロードマップを策定するスキルが必要になります。これは単なるスケジュール作成ではなく、戦略的な思考と実務的な現場知識の両方が求められる、難易度が高い業務であると言えます。
まず、短期・中期・長期の目標を適切に設定し、それらを達成するためのマイルストーンを段階的に明確にする必要があります。
次に、限られたリソース(時間、予算、人員など)の中で最大の効果を得るための優先順位付けと資源配分のスキルが必要です。すべての課題を一度に解決することは現実的ではないため、「何を先に取り組むべきか」「どの施策に重点的にリソースを投入すべきか」といった判断が求められます。
また、様々な育成手法(OJT、Off-JT、自己啓発支援など)の特性を理解して目的に応じて最適な組み合わせを選択する必要があるため、人材育成方法や教育手法に関する知識も重要です。例えば、基礎知識の習得にはeラーニングが効率的ですが、応用力や判断力の育成には実務経験やケーススタディが効果的といった使い分けができるようになると良いでしょう。
【即戦力採用<速戦力育成】
新入社員・若手社員を1~3年で高速成長させるには、1on1とスキルマネジメントの掛け合わせがおすすめ!
スキルシートの作成から実際の運用までを解説した資料!
>>『「人」ではなく「スキル」をマネジメントする1on1』はコチラから無料ダウンロード!
経営戦略・戦略人事を理解する
人材育成計画が真に組織の成長に貢献するためには、経営戦略や戦略人事の考え方を理解してリンクさせる必要があります。人材育成は単独で考えられるものではなく、企業の経営戦略を実現するための施策としての意味合いが非常に強いためです。
自社のニーズに応える人材育成計画を立てるためには、自社の経営戦略や事業計画を正確に理解し、それを人材としての要件に落とし込まなければなりません。例えば、「新規市場への参入」という戦略があれば、「新市場の知識」「新規顧客開拓スキル」「リスク管理能力」などの人材要件を導き出すことができます。
このように、企業の求める人材像やビジョンに沿った育成を進めるためには、経営層や事業部門のリーダーとの対話を通じて経営課題や事業ニーズを深く理解し、それに応える人材育成計画を立案・提案する能力が求められます。
人材育成を実施するときのコツ
効果的な人材育成計画を策定するためには、いくつかの重要なポイントが存在します。
ここでは、人材育成計画策定において特に押さえておくべ代表的な3つのポイントについて詳しく解説していきます。
①スキルマップを用いて、求める人物像やスキルを明確化する
人材育成計画を立てる際に強力なツールとなるのがスキルマップです。スキルマップとは、職種や役割ごとに必要なスキルや知識を体系的に整理したものであり、スキルや資格を主軸とした育成の方向性を示す羅針盤の役割を果たします。
スキルマップ作成のポイントは、まず職種や役割ごとに必要なスキルや能力を整理し、さらにそれらの専門性や程度といった「深さ」まで設定することです。
スキルマップを活用すると必要なスキルや現状の保有状況が一目で分かるようになるため、人材育成においては非常に効果的です。
また、育成の方向性が明確になるだけでなく、従業員自身も自分のキャリアパスや成長目標を具体的にイメージできるようになります。構築にやや知識や理解が求められるところが難点ですが、以下の記事も参考にしてぜひスキルマップを作成・活用してみてください。
▶ スキルマップについて、詳しくはこちらから!
②フレームワークを活用する
人材育成計画の策定においては、フレームワークを活用することで、体系的に落とし込んだ計画立案が可能になります。ここでは、「ベーシック法」と「SMARTの法則」という多くの企業で活用実績のある2つのフレームワークを紹介していきます。
ベーシック法
ベーシック法は、「目標項目」「達成基準」「期限設定」「達成計画」の4ステップに沿って目標を設定するフレームワークです。
①目標項目の設定:
目標項目では、現状に応じて目標のタイプを4つ(強化・改善・維持・開発)から選んで明確にします。
▶︎ 4つの目標タイプ
・強化:
現状をさらにレベルアップさせるための目標項目です。一般的には、現状に解決すべき問題や課題感がない場合に選択されることが多いです。
・改善:
現状のプロジェクトやサービスについて課題が明らかになっており、改善・解決を目指すための目標項目です。
・維持:
現状維持が最適、あるいは精一杯な場合に選択される目標項目です。
・開発:
他3つと違い、既存のプロジェクトや製品に関する目標ではなく、全く新しいことを始める際に選択される目標項目です。
②達成基準の設定:
「どのような状態を達成とするか」という基準を明確にしましょう。
基準を具体的かつ納得感を持たせるために、定量的な数値やラインを設定すると良いでしょう。
③期限の設定:
目標の内容だけでなく、それを「いつまでに達成しなければならないか」についても明確に設定しましょう。
④達成計画の具体化:
この段階では、「目標達成のための行動計画」を明確にします。ここまでのステップで、「何を」「どこまで」「いつまでに」といった基礎的な目標を立てることは可能ですが、それだけでは実際に行動には移せません。ここでは、立てた目標に向かって、実際に行動に移すことを可能にする具体的にどのように行動するかという計画を立てましょう。
SMARTの法則
SMARTの法則は目標設定のためのフレームワークで、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限がある)の頭文字をとったものです。
このフレームワークに従って目標を設定することで、抽象的な目標を具体に落とし込むことができ、進捗管理や成果評価がしやすくなります。
例えば、「コミュニケーション能力を高める」という抽象的な目標は、「3ヶ月以内に、部門会議で自分の担当業務について5分間のプレゼンテーションを行い、上司から80点以上の評価を得る」といった具体的な目標に落とし込むことができます。
③厚生労働省公開の資料を参考にする
人材育成計画を策定する際には、厚生労働省が公開している各種資料を活用することで、業界標準に基づいた体系的な計画を立てることができます。特に「職業能力評価基準」「キャリアマップ」「職業能力評価シート」は、多くの業種・職種をカバーした実用的なツールとして広く活用されています。
これらの資料は厚生労働省のウェブサイトから無料でダウンロードできるため、コストをかけずに質の高い育成計画の基盤を整えることができ、特に人材育成の専門知識や経験が限られている中小企業にとっては貴重なリソースとなります。
職業能力評価基準
職業能力評価基準は、業種・職種ごとに必要とされる知識やスキルを体系的に整理したもので、現在50以上の業種について公開されています。
この基準を参照することで、自社独自の視点だけでなく、業界全体で求められる標準的な能力や技術要件を把握することができます。
▶ 厚労省HP「職業能力評価基準」はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syokunou/index.html
キャリアマップ
キャリアマップは、職種ごとのキャリアパスを可視化したもので、各段階で求められる能力や経験が示されています。
このマップを参考にすることで、従業員の中長期的なキャリア開発の道筋を明確にし、段階的な育成計画を立てることができます。
▶ 厚労省HP「キャリアマップ」はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07792.html
職業能力評価シート
職業能力評価シートは、個人の能力を客観的に評価するためのツールで、職種ごとに具体的な評価項目と基準が設定されています。
このシートを活用することで、現状把握とギャップ分析を効率的に行うことができます。例えば、「プレゼンテーション能力」という項目について、レベル1からレベル4までの具体的な行動基準が示されており、自己評価と上司評価を比較することで客観的な現状把握が可能になるでしょう。
▶ 厚労省HP「職業能力評価シート」はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08021.html
【階層別】人材育成計画の例
人材育成計画は個人にコミットしたものでないと意味がないため、対象となる従業員の階層や経験によって内容を変えることが必要です。
よって、ここでは階層別の人材育成計画の具体例を、新入社員・中堅社員・管理職に分けて紹介します。それぞれの階層における育成のポイントや具体的な施策例などを詳しく解説していきます。
新人社員の例
新卒・若手社員の育成では、基礎的なビジネススキルの習得と、そして何よりもまずは組織に適応してもらうことが重要です。よってこの段階では、専門性や技術力というよりも、仕事に対する基本的な姿勢やビジネスマナー等を学ぶことが重要になってきます。
育成計画の例としては、「入社1年目:基礎スキル習得と業務理解」「2年目:担当業務の自立的遂行」「3年目:小規模プロジェクトのリーダー経験」といったように段階的な目標を設定し、さらに短い期間ごとに詳細かつ具体的なマイルストーンを設定することによって、「とりあえず直近で取り組むべきこと」を明確にできれば理想的です。
半期ごとのマイルストーンの例として、まずは入社後3〜6ヶ月を基礎研修期間として、ビジネスマナー、コミュニケーション、タイムマネジメント、ビジネス文書作成などの基本スキルを集中的に習得させます。
この時期は集合研修とOJTを組み合わせ、理論と実践の両面からスキルを定着させましょう。例えば、午前中に集合研修で学んだ内容を、午後のOJTで実際に試してみるといったインプットとアウトプットを連動させた育成が非常に効果的です。
次の6ヶ月〜1年は、実務経験を通じた成長期間として、徐々に責任ある業務を任せていきます。
この時期のポイントは、適度な難易度の課題を与え、成功体験を積ませることです。例えば、「先輩のサポート役として小規模プロジェクトに参加する」「社内会議の資料作成を担当する」といった、戦力の一人として徐々に重要な仕事を任せながらも、しかし決して高すぎないハードルを設定することが大切です。
また、この段階の評価とフィードバックは必ず頻繁に行うようにしましょう。
入社したての新社会人は、会社に適応できなかったり、学生時代からの環境変化や、業務上で力不足を感じるといった様々な理由から最も離職のリスクが高くなっています。
少なくとも月1回程度の定期面談を設け、成長の進捗を確認したり具体的な改善点を伝えることは、新入社員に「きちんと目をかけられている」という意識を持ってもらえ、会社への定着を図るという点でも非常に効果的です。
このような定期的な面談やフィードバックのサイクルを習慣化させるためにも、1on1ミーティングの導入が非常に強力な施策となるかもしれません。1on1ミーティングは定期的に上司と部下で一対一で面談を行う人事施策ですが、社員の離職を防いだり、目標達成をサポートできるといった特徴があります。
中堅社員(リーダー)の例
中堅社員の育成では、専門性をより深めたり、リーダーシップやマネジメント能力を重視した計画が効果的です。自身の担当領域でのエキスパートとしての能力と、後輩指導や小規模チームのリーダーとしての能力の両方に重点を置きましょう。
まず、専門性強化の面では、業界や職種に特化した高度な知識・スキルの習得を支援することが大切です。外部セミナーの受講や専門資格の取得支援、社外プロジェクトへの参画といった制度・機会等を積極的に活用しましょう。
次に、リーダーシップやマネジメント能力開発の面では、後輩指導やプロジェクトリーダーとしての経験を段階的に積ませることが重要です。例えば、「新人のOJT担当を任せる」「小規模プロジェクトのリーダーを務める」「部門横断的な中~大規模プロジェクトのメンバーとなる」といった実践的な機会を通じて、リーダーシップスキルを養成しましょう。
また、この段階では「教える側」になることで自身の知識やスキルを整理・体系化する効果も期待できます。そのため、社内勉強会の講師を務めたり、業務マニュアルの作成を担当したりする機会を設けることも中堅社員の成長に非常に効果的でしょう。
また、社員の中には、プレイングマネージャーやリーダーとしてのキャリアを望まず、プレイヤーとしての専門性や技術力を深めたいという志向の人もいるでしょう。そのような人のために、キャリア開発の観点では「専門性を極める道」と「マネジメントを目指す道」の選択肢を示し、個人の志向や適性に合わせたキャリアパスを提示することが大切です。
例えば、「スペシャリストコース」と「マネジメントコース」を設け、それぞれに応じた育成プログラムを用意するといった工夫を行うことで、個人の能力やモチベーションを最大限向上させるだけでなく、「自分の希望に沿ったキャリアパスが柔軟に叶う」という印象を通じて、社員のエンゲージメントを向上させることもできるでしょう。
具体的な育成計画の例としては、プレイングマネージャーとしてそれぞれの能力をバランスよく伸ばしたい場合は、「専門スキルの高度化(外部研修・資格取得)」「後輩指導・育成スキルの習得(メンター研修)」「プロジェクトマネジメント能力の向上(PMリーダー経験)」といった要素を組み合わせた2〜3年の計画を立てることが効果的でしょう。
管理職の例
管理職の育成では、マネジメントスキルの強化と戦略的思考力の養成を重視した計画が効果的です。この段階では、個人プレーヤーとしての成果だけでなく、チーム全体のパフォーマンスを高めるリーダーシップと、経営的視点からの意思決定能力が不可欠となってきます。
まず、マネジメントスキルの面では、「人材育成」「目標管理」「評価・フィードバック」「チームビルディング」「コンフリクト解決」などの実践的なスキルを強化します。これらのスキルは座学だけでは身につきにくいため、ケーススタディやロールプレイを取り入れた参加型の研修、あるいはマネジメントや人材育成のプロによる外部研修等が効果的です。
次に、戦略的思考力の面では、経営層との対話機会や経営会議へのオブザーバー参加、事業戦略策定プロジェクトへの参画などを通じて、自社にコミットメントした経営視点を養います。
例えば、「自部門の中期事業計画を立案する」「全社的な課題解決プロジェクトに参画する」といった実践的な機会を提供し、最終的には会社の中核として経営を担う人物になることも見据えて成長を促しましょう。
管理職の育成計画の例としては、「リーダーシップ開発プログラム(1年間)」「経営戦略理解・策定力強化(半年間)」「組織開発・変革推進力養成(1年間)」といった人材開発やマネジメントに重きを置いた長期的な計画が効果的です。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 人材育成計画を立てる際、最初に決めるべきことは何ですか?
A: 経営戦略と連動した「求める人物像」を明確に確立することです。 「5年後にどのような事業展開を目指すか」という視点から逆算し、そのために必要な「スキル」「知識」「行動特性」を具体化します。これが育成施策の軸となります。
Q2. 新入社員の育成計画で、特に気をつけるべきポイントは何ですか?
A: 「組織への適応」と「早期の成功体験」を積ませることです。 入社後、最も離職リスクが高い時期であるため、ビジネスマナーなどの基礎スキル習得に加え、適度な難易度の課題を与えます。また、月1回の1on1などでフィードバックを頻繁に行い、定着を図ります。
Q3. 育成計画に「スキルマップ」を活用するメリットは何ですか?
A: 育成の進捗が可視化され、効率的にスキルギャップを特定できる点です。 職種ごとに必要なスキルをレベル分けして整理することで、従業員は「次に何を学ぶべきか」を具体的に把握できます。育成担当者も、施策への投資効果を測定しやすくなります。
Q4. 中堅社員の「リーダーシップ」を育成するための具体的な施策は何ですか?
A: 「後輩指導の担当」や「小規模プロジェクトのリーダー経験」を積ませることです。 教える側に立つことで、自身の知識が整理され、マネジメントスキルが向上します。また、キャリアパスとして「専門性を極める道」と「マネジメントを目指す道」を示すことも重要です。
Q5. 計画を「立てて終わり」にせず、効果を最大化するコツは何ですか?
A: 計画を実践した後、フィードバックを繰り返す「PDCAサイクル」を回すことです。 定期的な進捗確認の場(1on1など)を設け、目標や施策が現状に合っているかを柔軟に見直しましょう。計画と現場の実態にズレが生じないよう、継続的に改善することが不可欠です。
まとめ
本記事では、人材育成計画の基本概念から具体的な立て方、階層別の作成例まで幅広く解説してきました。人材育成計画を立てることは、企業の持続的な成長と競争力強化のために、いまや不可欠となってきています。
効果的な人材育成計画を策定するためには、まず経営戦略と連動した「求める人物像」を明確にし、現状とのギャップを分析した上で、段階的な育成プログラムを設計することが重要です。
また、計画を立てるだけでなく、実践とフィードバックを繰り返しながらPDCAサイクルを回していくことで、継続的に現状を改善しながら育成効果を最大化させることができます。
人材育成は一朝一夕で成果が出るものではありませんが、計画的かつ継続的に取り組むことで、着実に組織全体の能力向上と競争力強化につながります。特に変化の激しい現代のビジネス環境においては、柔軟かつ先を見据えた人材育成が、企業の生存と今後の成長を左右する重要な鍵となりつつあるのです。
本記事で紹介した考え方や事例を参考にしながら、自社の状況に合った効果的な人材育成計画を策定し、組織と個人の成長にお役立ていただければ幸いです。
効果的なスキルマップの作成・運用なら「コチーム」!

- 会社ごとのオリジナルスキルマップを独自学習させたAIを用いて作成!
- 1on1機能とスキルマップ機能の連携で、スキルの習得を促進!
- スキルの獲得状況を一元管理!
- 1on1の省力化機能で現場管理職の負担を最小限に抑えて運用可能!
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。