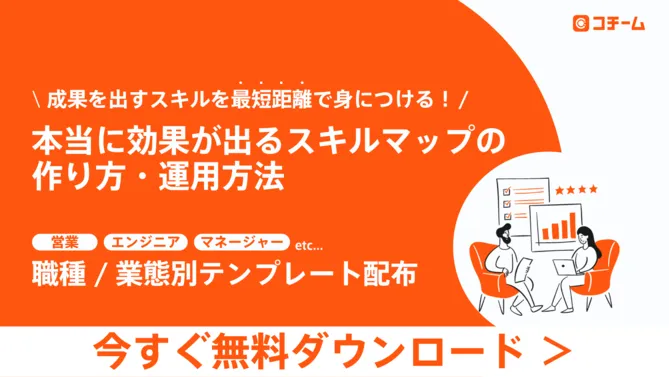スキルマップ(力量管理表)は、人材の育成や配置に欠かせないツールで、厚生労働省も導入を推進しています。従業員のスキルを可視化・数値化し、学習や成長を促す役割を担います。
一方で「評価基準をどう作ればよいか分からない」と悩む担当者も少なくありません。評価段階を何段階にするか、各段階の基準をどう設定するかは、多くの企業が直面する課題です。
本記事では、スキルマップにおける2段階〜5段階評価の特徴と活用シーンを解説し、評価基準を設定する際の重要なポイントを紹介します。
この記事を読めば、各評価段階のメリット・デメリットや、スキルマップを最大限活用するための実践的なノウハウを身につけられます。ぜひ最後までご覧ください。
≫無料で「本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法」をダウンロードする
▼ この記事の内容
- スキルマップの評価基準: 人材育成や適切な配置をする基盤であり、属人化を避けるため、各評価段階(2〜5段階)の特徴と活用シーンを理解することが大切です。
- 評価段階の選び方: 評価の目的に応じて、単純な標準化には2段階、習熟度の詳細な把握には5段階など、評価したいスキルと基準をセットで検討します。
- 基準作成の要点: 評価者間の認識のズレを防ぐため、スキル項目を具体化し、マニュアル作成や評価者研修を通じて一貫した運用を実現します。
目次
スキルマップの評価基準を設定する必要性とは?
スキルマップとは、従業員の業務遂行能力を点数化して一覧表にしたもので、社内の人材が持つスキルの習熟度や不足しているスキルを可視化するツールです。全社共通スキルから業務分担ごとの専門スキルまで、幅広くマネジメントすることができます。
このスキルマップを効果的に活用するためには、適切な評価基準の設定が不可欠です。単に「できる・できない」の2択だけでは、「どのスキルを、どの程度習得しているか」を正確に把握することができません。そのため、評価基準は、スキル項目や評価段階とセットで設定して明確化し、評価者が一貫した判断を行えるようにする必要があります。
適切な評価基準を導入することで得られるメリットは以下のように多岐にわたります。
- 効率的な人材育成計画の立案が可能になる
- プロジェクトや部署への適切な人材配置
- 公平な人事評価の実現、それによる社員の自己成長へのモチベーション向上
- 社員が自己評価と上司の評価を比較し課題を可視化できる
- 事業成長に必要なスキルの特定や、それに基づく採用計画の策定など、経営戦略の立案にも活用できる
つまり、スキルマップの評価基準設定は、単なる人事評価のツールにとどまらず、組織全体の持続的な成長と競争力強化のための重要な基盤となるのです。
では、どのような評価基準設定が自分の組織にとって適切なのでしょうか? 各段階数のスキルマップの特徴をそれぞれ見ていきましょう。
>>無料で『本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法』をダウンロードする(職種 / 業種別のテンプレート公開中)
スキルマップの評価基準における各段階の特徴
それでは、スキルマップの各段階数の特徴を見ていきましょう。スキルマップは会社の状況や評価したい仕事内容、導入する目的によって適切な段階数が変わります。
では、どのようにスキルマップの段階数を決めれば良いのでしょうか。下の図のように、スキルマップの評価段階数は評価したいスキルと評価基準をセットで考えると適切な段階数を決めることができます。
| 評価したいスキル | 評価(段階数は3) | 評価基準 |
|---|---|---|
| 資料作成 | ○ | 1人ででき、初心者に教育できるレベル |
| △ | おおむね1人でできるが、時々上司のサポートが必要 | |
| ✕ | 今はまだできていない |
この表のように、段階数は評価したいスキルとどこまで細かく評価したいかによって決まります。では、各段階数の具体的な特徴を見ていきましょう。
2段階評価
2段階評価とは、「できる・できない」「はい・いいえ」「ある・ない」といった二項対立で行うシンプルな評価方法です。この評価方法は、特定の資格保有や特殊技能の取得、特定業務の経験有無など、明確に判断できる項目において特に効果的です。
2段階評価の最大の利点は、その明確さです。基準が単純でわかりやすいため、評価者が迷うことなく判断でき、客観性と公平性を保ちやすくなります。さらに、短時間で多くの項目を評価できるため、運用面でも効率的です。
一方で、この評価方法には明確なデメリットも存在します。「ある」か「ない」かの二択評価のみであるため、スキルの習熟度や知識の程度を段階的に把握することができません。
例えば、ある業務を「できる」と評価された場合でも、その業務を「どの程度のレベルでできるのか」「指導できるレベルなのか」「独力でできるのか」といった詳細な情報は得られないのです。
ただし、スキルマップ全体を2段階評価のみで構成することは一般的ではありません。多くの場合、基本的な資格や前提条件の確認には2段階評価を用い、より重要なコアスキルや専門能力については3段階以上の詳細な評価方法と組み合わせて使用することが効果的です。これにより、単なるスキルの有無だけでなく、その習熟度や発展可能性まで含めた総合的な人材評価が可能になります。
【成果を出すスキルを最短距離で身につけるスキルマップの作り方!】
・スキルマップを導入しようと考えているけど、効果が本当に出るのかわからない
・スキルマップを導入しているけど、なかなか効果が出ない・形骸化している
とお悩みではありませんか?
実は、スキルマップを効果的に運用するためには抑えるべきポイントがあります!人材育成で100社以上支援実績がある弊社のノウハウを盛り込んだ、ココでしか読めない情報が満載の無料スキルマップ解説資料!
>>『本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法』はコチラから無料ダウンロード!(職種 / 業種別のテンプレート公開中)
3段階評価
3段階評価とは、「○・△・×」「高・中・低」「上・中・下」など3つの選択肢を設けて行う評価方法で、スキルマップにおいて幅広く採用されています。
この評価方法の最大の特徴は、スキルの「程度」を問えるようになる点です。例えば先ほどの表で紹介したように、「○:1人でできる」「△:ほぼ1人でできる」「×:できない」というように、習熟度の段階を表現することができます。
3段階評価の利点は、そのシンプルさと直感的な分かりやすさです。4段階以上と比べて判断に迷いが少なく、評価の負担を軽減し、一貫性も保ちやすくなります。特に、スキルマップを初めて導入する企業や、多数の評価者が関わる大規模組織に適しています。
一方で、3段階評価の主なデメリットは、評価基準が明確でない場合に「中」の評価に偏りやすい傾向があることです。その理由は、評価者が極端な判断を避け、無難な中間評価を選びがちになるからです。この偏りを防ぐためには、「上(高)」や「下(低)」の評価基準を具体的かつ明確に定義することが重要です。
効果的な3段階評価を実施するためには、各段階の評価基準を具体的な行動や成果物と紐づけることが重要です。例えば「○:他者に指導できるレベル」「△:自力で実行できるレベル」「×:サポートが必要なレベル」というように、誰が評価しても同じ結果になるような客観的な基準を設定することで、評価の信頼性と有用性を高めることができます。
4段階評価
4段階評価とは、「A・B・C・D」「4・3・2・1」「よい・どちらかというとよい・どちらかというと悪い・悪い」など4つの選択肢を設けて行う評価方法です。
4段階評価の最大のメリットは、評価の中央化傾向を効果的に防止できることです。3段階や5段階評価では「中」や「普通」といった中央値に評価が集中しがちですが、4段階評価ではそれを強制的に回避させることができます。
例えば「A:人に指導できる」「B:1人でできる」「C:指導を受けながらできる」「D:できない」というように設定することで、評価者は「良い方」か「悪い方」かの判断を明確にせざるを得なくなります。これにより、より明確な人材配置や育成計画の立案が可能になります。
一方、4段階評価のデメリットとしては、中間の選択肢がないことで評価しづらさを感じる評価者も少なくないという点が挙げられます。特に日本の組織文化では、はっきりとした優劣をつけることに抵抗感を持つ場合もあり、評価者からの支持や理解が得られにくい場合があります。また、「どちらかというとよい」「どちらかというと悪い」という微妙な違いの判断基準を明確にしなければ、評価者によって判断基準がバラバラになるリスクもあります。
4段階評価を導入する際には、各段階の評価基準を具体的な行動指標や成果物と紐づけて明確に設定することが重要です。また、評価者に対しては事前に4段階評価の意義と評価基準について十分な説明を行い、評価の一貫性と納得感を高める工夫が必要です。これにより、スキルマップの信頼性向上と、より効果的な人材育成・活用が実現できるでしょう。
5段階評価
5段階評価は、スキルマップにおいて最も一般的に採用されている形式の1つであり、多くの企業や組織で馴染みのある評価基準となっています。
5段階評価の最大のメリットは、評価の粒度が細かく、より詳細なスキルレベルの把握が可能になる点です。詳細な評価基準により、評価される側の社員も自分のスキルレベルを具体的に理解しやすくなり、納得感が高まります。
一方で、5段階評価の主なデメリットは、3段階評価と同様に、中央値に評価が集中しやすい傾向があることです。さらに、評価基準が細分化されることで、かえって最高値や最低値の判断が難しくなり、結果的に中間的な評価に偏ってしまうケースも少なくありません。
5段階評価を効果的に運用するためのポイントとしては、中央値への偏りを防ぐための工夫が重要です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 各評価段階に明確な行動基準や成果物の例を紐づける
- 評価者研修を実施して評価基準の統一を図る
- 定期的に評価分布を分析して偏りがないかチェックする
これらの施策により、5段階評価の利点を最大限に活かしたスキルマップ運用が可能になるでしょう。
スキルマップの評価基準を作成する際のポイント
スキルマップを構築する際には、評価の一貫性を確保するために明確な評価基準を作成することが不可欠です。評価者間でのばらつきを最小限に抑え、信頼性の高いスキルマップを実現するための評価基準の作成にあたって重要なポイントや手順について解説します。
スキル項目を具体的にする
評価者によるバラつきを防ぎ、信頼性の高いスキルマップを構築するためには、スキル項目の具体化が不可欠です。抽象的なスキル項目は評価の曖昧さを生み出す原因となります。例えば、単に「顧客対応スキル」という大きな枠組みだけでは、評価者によって想定する業務範囲や評価基準が異なり、結果として評価にばらつきが生じやすくなります。
具体的なスキル項目設定のアプローチとしては、階層構造を活用することが効果的です。大項目として「顧客対応スキル」を設定した場合、その下に小項目として「丁寧な言葉遣い」「電話対応」「クレーム対応」「質問への的確な回答」などと細分化することで、より明確な評価が可能になります。
この細分化によって、評価者は具体的な行動や成果を基準に判断できるようになり、評価の一貫性が高まります。
また、スキル項目の洗い出しを実施する際のコツは、自社の事業目的や業務フローに密接に関連したものを選定することです。現場の従業員へのヒアリングや実際の業務マニュアルを参考にしながら、「このスキルは本当に業務に必要か」「自社の競争力向上に貢献するスキルか」という観点から検討します。一人ひとりの主観や思い込みではなく、実務に基づいた客観的なスキル項目の設定が、実効性の高いスキルマップ構築の基盤となります。
こうして具体化されたスキル項目は、評価の精度向上だけでなく、社員の育成目標の明確化や、必要なトレーニングプログラムのガイドライン構築にも役立ちます。スキル項目の具体化は、スキルマップ全体の質と有用性を高める最初の重要なステップとなります。
スキル項目ごとに適した評価段階を決める
スキルマップの効果を最大化するためには、各スキル項目の特性に合わせて最適な評価段階を設定することが重要です。すべてのスキルを同じ評価段階で測ることは必ずしも適切ではなく、スキル項目の性質や目的に応じて柔軟に評価段階を決定する必要があります。
評価段階の選定に際しては、スキルマップの活用目的を明確にすることが出発点となります。先程説明した通り、スキルマップの評価段階数は評価したいスキルと評価基準をセットで考えると適切な段階数を決めることができます。
企業のニーズや組織文化に応じた評価段階の選定は、スキルマップを形骸化させないための重要な要素です。形式的な統一性よりも、各スキル項目の本質を捉えた評価システムの構築を心がけましょう。
現場の一部でテスト運用を開始する
スキルマップを全社的に展開する前に、現場の一部でテスト運用を実施することは、成功への重要なステップです。どれだけ綿密に設計したスキルマップであっても、実際の運用環境で想定外の問題が発生する可能性があります。限られた範囲での試験的導入により、本格展開前の不備や課題を早期に発見し、修正することができます。
テスト運用の最大のメリットは、作成者の意図と実際の評価者の理解にギャップがないかを確認できる点です。スキルマップの作成者は自身が設計した内容を熟知しているため、評価基準の説明が曖昧であったり、解釈に幅があったりする点を見落としがちです。実際の評価者に記入してもらうことで、「作成者の意図する通りに評価ができるか」「分かりにくい点や評価しにくい項目はないか」などを客観的に検証できます。
テスト運用の対象者としては、実際にスキルマップを使用する評価者が望ましいですが、調整が難しい場合は親しい同僚などでも代用可能です。重要なのは、様々な視点からのフィードバックを収集することです。評価者によるバラつきや認識のズレが発見された場合は、評価基準の文言を見直したり、具体例を追加したりするなど、必要な修正を加えます。
マニュアルの作成や社内説明会を実施する
スキルマップの導入を成功させるためには、適切な評価基準の設定だけでなく、その運用方法を組織全体で共有することが不可欠です。
スキルマップを活用する際には、人事担当者や各部門・部署の上長など様々な立場の人が評価者となるため、評価の一貫性を確保するための取り組みが重要になります。そこで効果を発揮するのが、詳細なマニュアルの作成と社内説明会の実施です。
マニュアル作成の最大のメリットは、評価基準の標準化と認識のズレ防止です。マニュアルには、スキルマップ導入の目的や背景、各評価段階の基準、評価時の注意点、活用方法などを明記します。特に評価基準は、具体的な事例や行動指標を示すことで、評価者の解釈の違いを最小限に抑えられます。
また、スキルマップを更新する際には、必ずマニュアルの見直しも同時に行い、常に最新情報を反映させることが重要です。
社内説明会の実施は、マニュアルの内容を補完し、評価者の理解を深める効果があります。一度の研修ですべての内容を完全に把握することは難しいため、説明会ではマニュアルの使い方も含めて丁寧に解説し、実際の評価シーンを想定したワークショップなども取り入れると効果的です。また、評価者からの質問や懸念点を直接聞く機会を設けることで、マニュアルの改善点を把握することもできます。
必要に応じて評価者研修などを実施する
管理職などの評価者の質がスキルマップの有効性を大きく左右するため、評価者研修を実施することをおすすめします。特に社内に評価の適任者が少ない場合や、評価基準の解釈にばらつきが見られる場合には、計画的な研修プログラムを通じて評価者のスキルの底上げを図ることが効果的です。
評価者研修では、「なぜスキルマップを活用するのか」という目的の共有から始まり、「スキルマップをどのように活用するのか」「各評価基準の具体的な意図」まで、体系的な理解を促します。特に重要なのは評価の実践練習で、実際のケーススタディを用いて評価の演習を行うことで、評価基準の具体的な適用方法を体得できます。
このプロセスを通じて評価者間の認識のズレを最小化し、組織全体で一貫した評価が行えるようになります。
研修実施後も、評価者からの質問や意見を積極的に収集し、それらのフィードバックを活かして評価項目や評価基準を継続的にブラッシュアップすることが重要です。相談窓口を設置するなどして寄せられた現場の声を放置せず、評価システムの改善に活かすことで、より使いやすく実効性の高いスキルマップへと発展させることができます。
このような改善サイクルを回すことで、評価者が評価しやすい環境が整い、質の高いデータ収集が可能になります。
効果的なスキルマップ作成・運用なら「コチーム」!

- 会社ごとのオリジナルスキルマップを独自学習させたAIを用いて作成!
- 1on1機能とスキルマップ機能の連携で、スキルの習得を促進!
- スキルの獲得状況を一元管理!
- 1on1の省力化機能で現場管理職の負担を最小限に抑えて運用可能!
よくあるご質問(FAQ)
Q1: スキルマップの評価基準は、なぜ設定する必要があるのでしょうか?
A: 人材育成や配置を適切にするためです。 従業員が持つスキルの習熟度を正確に可視化し、公平な人事評価を実現するための基盤になります。
Q2: 評価段階を3段階や5段階にすると、評価が中央に偏ってしまうのはなぜですか?
A: 極端な判断を避け、無難な中間評価を選びがちになるからです。 これを防ぐには、最高値や最低値の評価基準を具体的かつ明確に定義することが重要です。
Q3: 評価者によって判断がブレてしまう(属人化する)のを防ぐにはどうすれば良いですか?
A: スキル項目を具体的な行動指標や成果物と紐づけて明確にします。 また、マニュアルの作成や評価者研修を実施し、評価基準の解釈を組織全体で統一することが大切です。
Q4: 評価段階は、全スキル項目で統一する必要があるのでしょうか?
A: 必ずしも統一する必要はありません。 各スキル項目の特性や評価する目的に合わせ、柔軟に2段階から5段階を組み合わせて設定するのが効果的です。
Q5: スキルマップを全社導入する前に、どのような手順を踏むべきですか?
A: 現場の一部でテスト運用を始めることを推奨します。 実際の評価者からのフィードバックを受けて、作成者と評価者の間にギャップがないかを検証し、評価基準をブラッシュアップします。
まとめ
本記事では、スキルマップの評価基準の設定方法について詳しく解説してきました。スキルマップは単なる評価ツールではなく、組織の人材育成、適材適所の配置、戦略的な採用計画など生産性の向上の基盤となる重要な経営資源です。
自社の特性や目的に合わせた適切な評価基準の設定により、スキルマップは初めて意味をなします。本記事で紹介した方法論を参考に、貴社ならではの効果的なスキルマップ運用を実現し、組織運営の向上につなげていただければ幸いです。
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。