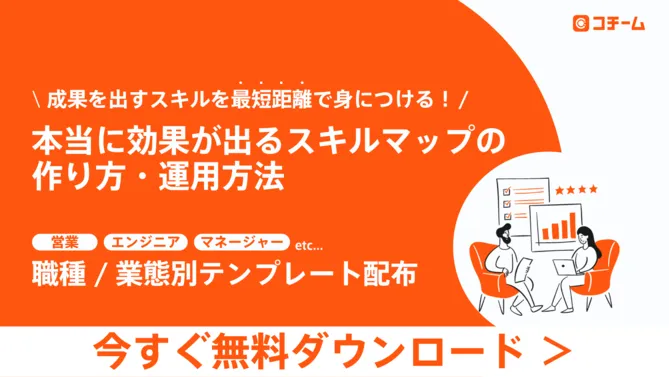スキルマップとは、従業員のスキルを表形式で可視化したもので、人材育成や要員計画に役立ちます。活用すれば、人材配置や採用の最適化、教育プランの策定、従業員のモチベーション向上が可能です。特に専門技術が求められ、従業員数の多い製造現場では大きな効果を発揮します。
本記事では、売上拡大を目指す製造業の経営者・役員・人事担当者に向けて、導入ステップや項目例、運用のポイントを解説します。さらに無料テンプレートも紹介するので、生産性や利益率の向上を図りたい方はぜひ参考にしてください。
≫無料で「本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法」をダウンロードする
▼ この記事の内容
- 製造業でスキルマップが必要な理由: 専門技術が求められる現場において、業務の属人化を防ぎ、人材育成や要員計画を最適化し、売上向上につなげることが目的です。
- スキルマップ作成の重要な手順: 成果を出すハイパフォーマーを分析し、インパクトの大きいスキルを洗い出して項目化し、客観的な評価基準を設定することが肝心です。
- 効果を最大化する運用のコツ: 作成と管理の労力を認識し、1on1ミーティングと連携させたスキルマネジメントや、定期的な見直しで現場への定着を図ります。
目次
スキルマップとは?
スキルマップとは、業務に必要なスキルを洗い出し、従業員ごとの習熟度を一覧化した表です。対象スキルは全社共通のものから職種ごとの専門スキルまで多岐にわたり、企業によっては「能力マップ」「技能マップ」「力量表」などとも呼ばれ、海外では「スキルマトリックス(Skills Matrix)」と呼ばれます。
導入の目的は、人材育成と人員配置の最適化です。個々のスキルや課題を明確化することで業務効率を高められ、さらに全社的なスキルを一元管理することで、強化すべき能力が把握でき、効果的な教育プランや研修の立案につながります。
このような背景から、製造業の多くの企業がスキルマップを導入しているのです。有名な導入事例としては、スキルマップを活用したトヨタ自動車の「多能工」の育成があります。
トヨタのスキルマップについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。↓
スキルマップとISO9001の関係
「ISO9001(Quality management systems – Requirements)」は、国際標準化機構が発行する品質マネジメントシステムの国際規格です。この認証の取得にあたっても、スキルマップは有用となります。
ISO9001の目的は、製品やサービスの品質を保証して顧客満足度を高めることです。そのため、「製品品質に影響がある仕事に従事する人の力量を把握し、必要な教育・訓練を実施すること」が求められます。力量とは、特定の業務を遂行するために必要な技能、知識、資格、経験のことです。製造業では、製図の知識、品質管理の資格、機械やCAD(コンピュータ支援設計)等のツールを使うスキルなどが該当します。
この力量管理を実現する上で、スキルマップは非常に有効です。従業員のスキルレベルの把握が人材育成に役立つとともに、品質を保つのに十分なスキルがあると証明する資料になります。
このように、製品の国際的な信頼性を高めるためにもスキルマップは役立つのです。
製造業で活用するスキルマップのメリットとデメリット
ここからは、製造業でスキルマップを利用するメリットとデメリットをそれぞれお伝えします。
製造業でスキルマップを導入するメリット
スキルマップの最終目的は「従業員の育成」です。従業員の育成を通じて、会社の売上を向上させることが狙いとなります。
その上で、一般的なスキルマップを導入するメリットとしては下記のものがあります。
- 必要なスキルを一覧で可視化することで、業務の標準化ができる
- 個々の業務に必要なスキルを備えた従業員を配置することで、業務の効率化ができる
- 部門や部署などの組織単位でスキルマップを作成することで、外部環境と比べた組織全体の強みと弱みを把握することができる。組織として不足している、または、将来的に不足するスキルが明らかになり、人材育成計画・教育計画の立案や採用活動に役立つ
- 公平な人事評価が可能になるとともに、従業員が自分のスキルを客観視することでスキルアップへのモチベーションが上がる。結果、セルフマネジメントが促進される
特に、働き方の流動化が進む今の時代、転職や休職、退職等でスキルが不足するリスクが高くなっています。マイナビによる「転職動向調査2025年版(2024年実績)」によると、「2024年の正社員の転職率は7.2%で高水準を維持し、40-50代で増加」しているようです。
(出典:https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250312_92959/)
なかでも、「頻繁に新しい機械や技術が投入される」「専門性が高い」という条件が揃う製造業では、業務の属人化によるスキル不足を防ぐ必要があります。スキルマップは業務の標準化とそれに則った人材育成を行う上で、製造業で重要な機能を果たすのです。
製造業でスキルマップを導入するデメリット
一方、スキルマップの導入には以下のようなデメリットも存在します。
・作成と管理に時間がかかる
・導入後短期間での効果測定が難しい
業務フローごとに自社に必要なスキルを洗い出して成長段階を適切に定義・数値化するには、たくさんの労力が必要とされます。特に、数値化が困難なスキルが多い場合、基準を設定するのに時間がかかるでしょう。社員の不満につながらないような適切な設定と透明性の確保をして、慎重に進めていかなければなりません。
対策の例として、スキル獲得の具体的な方法を記載する必要があります。作成後も、新入社員の登録はもちろん、定期的な一人ひとりのスキルチェックやスキルマップ自体の更新等の管理業務が求められます。
上記のように作成と管理に労力がかかるスキルマップですが、長期的な取り組みによって次第に数字に現れてきます。このことを認識した上で、長期的なメリットを見据えて運用することが大切です。
製造業向けスキルマップの具体的な作成方法
以下の5つのステップで、製造業向けスキルマップが作成できます。
- ステップ1:スキルマップの導入目的を明確にする
- ステップ2:必要なスキル項目を洗い出す
- ステップ3:スキル項目を分類する
- ステップ4:評価基準と評価方法を策定する
- ステップ5:スキルマップを作成して定期的に見直す
それぞれのステップに分けて、作り方を詳しく解説していきます。
ステップ1:スキルマップの導入目的を明確にする
最初にスキルマップの目的を明確化することが、効果的な活用に不可欠です。目的と関連しない内容の盛り込みを防ぐことができます。
まずは、スキルマップを作成する対象が何を達成すればよいのかという理想像を明らかにしていき、スキルマップ作成の方向性を決めましょう。目的の具体例としては「製造現場のマネージャーのスキルギャップを特定して教育プランを立てる」「新入社員のスキルを可視化し効果的な研修を行う」などが考えられます。
こうして、スキルマップが解決すべき課題が明らかになり、必要なスキルの選定やレベルの分類、運用方針の設定が可能になります。
ステップ2:必要なスキル項目を洗い出す
目的が明確になったら、スキルマップで管理すべきスキルを洗い出します。業務内容ごとに異なるため、実際の業務フローに則して項目立てましょう。例えば、製造業で考えられるフローは「資材の調達・管理」「生産計画の立案」「加工・組立」「品質検査」「出荷・納品」などです。
ただし、単に洗い出したスキルだけでスキルマップを作成するのは危険です。スキルマップの目的は「成果を出せる人材を育成し、組織を成長させること」であり、スキルのリスト化ではありません。そのまま進めると、成果につながるスキルが不明確なまま、効果のないスキルマップになってしまいます。
さらに、項目を増やしすぎると「どのスキルを優先すべきか」が分かりにくくなります。必要以上にスキルを詰め込まないことが重要です。
そこで重要なのが、ハイパフォーマー(効率的に高い成果を上げている従業員)が、各業務フローでどのような行動を実施しているのかを分析すること。ヒアリングやアンケート調査、工場等の現場での業務観察を行い、業務の進め方や工夫、どのようなスキルがどの場面で発揮されているかを確認します。そして、成果を出すためにインパクトが大きいスキルを、スキルマップの項目として設定していきましょう。
上記のように、成果につながる具体的な行動を業務フローごとに分析することで、効果的なスキルマップが作成できます。
ステップ3:スキル項目を分類する
次に、洗い出したスキルを分類し、どのスキルがどの分野に属しているかを分かりやすくします。分類方法は、ステップ1で決めたスキルマップの作成目的に合わせて設定しましょう。下記はその例です。
- 業務項目ごとの分類:生産管理、設備保全、物流管理
- 要素や技術ごとの分類:機械加工技術、溶接技術、品質管理技術
- 作業項目ごとの分類:組立作業、検査作業、梱包作業
- 製品カテゴリーごとの分類:電子機器製造、重機製造、医療機器製造
さらに、これらの分類のなかで「初級編」「中級編」「上級編」といった階層構造を決めておくと、次に目指すべきスキルを判断しやすくなります。階層数に決まりはありませんが、あまり多いと管理しにくくなるため注意が必要です。2~3階層を目安に作成しましょう。
スキルを分類して段階的に整理することで、従業員の成長促進と運用の効率化ができます。
ステップ4:評価基準と評価方法を策定する
スキル項目を分類・階層化した後は、スキルを獲得したという評価基準と、評価者を含めた評価方法を決定します。
評価基準を設定する際は、誰が見ても同じ評価をできるような客観性と、習熟度に応じた段階性を持たせるのがポイントです。評価者の主観が入り込まないよう、できるだけ定義を明確にしていきましょう。段階性を持たせる際の視点としては、「サポートを必要とするか」「他者を指導できるか」などが考えられます。
なお、段階分けの数には下記のような種類と特徴があります。
- 2段階評価 資格保有や特殊技能の取得、特定業務の経験有無など、明確に判断できる項目に適する
- 3段階評価 直感的に分かりやすく評価作業の負担が軽減される一方、「中」の傾向に偏りやすい
- 4段階評価 中央化傾向を防止できるが、「どちらかというと良い/悪い」の微妙な違いが判断しにくい
- 5段階評価 詳細なスキルレベルが把握できる一方、「中」の傾向に偏りやすい
2段階評価、4段階評価の中央化傾向や、4段階評価の判断のしにくさを克服するためにも、評価基準を具体的な行動指標や成果物と紐づけ、客観的に判断できるようにすることが重要です。
その上で、評価の透明性を確保するためには、評価者を明らかにすることも重要です。上司による評価、同僚による評価、自己評価、部下による評価、これら複数の視点を組み合わせた360度評価など、様々な手法が考えられますが、スキルマップの導入目的や労力を加味して設定しましょう。
スキルマップの評価基準について特に詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。↓
ステップ5:スキルマップを作成して定期的に見直す
最後に、これまでの手順を踏まえてシートを作成します。スキルと従業員を一覧で把握できるようにしましょう。エクセルやドキュメント作成ツールを使うことが一般的です。本記事でもスキルマップのテンプレートを掲載しておりますので、引き続きお読みください。
シート作成後は、一部署やチーム単位でのテスト的運用をすると良いです。フィードバックに基づく修正対応や質疑応答の負担を減らすことができます。よくある質問を含めた、現場向けの簡単な運用マニュアルを作成しておくこともおすすめです。
そして、運用開始後に重要なのが定期的チェック。スキルマップは個人や組織の成長、業務の変化に合わせてアップデートしていくものなので、柔軟に調整できる仕組みを整えましょう。例えば、スキル項目やユーザインタフェースの増減、フォーマットの修正・変更などがあり得ます。
こうして作成後も定期的に見直し、現場が活用しやすい環境を整備することで、スキルマップをより効果的なスキル管理ツールにブラッシュアップできます。
【成果を出すスキルを最短距離で身につけるスキルマップの作り方!】
・スキルマップを導入しようと考えているけど、効果が本当に出るのかわからない
・スキルマップを導入しているけど、なかなか効果が出ない・形骸化している
とお悩みではありませんか?
実は、スキルマップを効果的に運用するためには抑えるべきポイントがあります!人材育成で100社以上支援実績がある弊社のノウハウを盛り込んだ、ココでしか読めない情報が満載の無料スキルマップ解説資料!
>>『本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法』はコチラから無料ダウンロード!(職種 / 業種別のテンプレート公開中)
製造業向けスキルマップの具体的な項目例
スキルマップの項目は様々ですが、特に製造エンジニアに必要とされる「品質管理」「生産計画管理」「機械・設備に関する知識」の3つに絞って、以下に解説していきます。
品質管理
モノづくりの現場において「品質管理」のスキルは特に重視するべきものの一つです。製品の品質は、顧客の信頼や企業の収益に大きく影響します。例えば、スマートフォンのバッテリー不良で発火事故が発生した場合、製造企業は製品回収で多額の損失を被るとともに、安全への信頼性低下から収益が激減してしまうでしょう。
品質管理を分類としてさらに具体的な項目を立てる場合には、「品質保証プロセスの理解」「品質検査技術」「不良品発生原因の分析と改善」などが考えらえます。項目が多すぎても、どのスキルを優先して身につければ良いのかが分かりにくくなるため、重要なもの3~5個に絞って設定することをおすすめします。
このように、品質管理のスキルを育成することは、安定した事業運営につながるのです。
品質管理について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。↓
生産計画管理
受注から製造、納品までを一貫して管理する生産計画管理も、企業の収益向上につながる大切なスキルです。例えば、適切な需要予測に基づく生産をすることで、生産にかかる労働力や在庫管理コストを削減することができるでしょう。
生産計画管理を分類としてさらに具体的な項目を立てる場合には「製造工程スケジュールの作成」「生産効率の分析」「在庫管理」などが考えられます。さらに、計画変更時の対応力や調整能力も含めて評価すると、現場の実態をより正確に反映できます。
これらの項目は製造ラインの稼働状況や案件の達成に直接影響します。現場の声に合わせて、慎重に項目を決めましょう。
機械・設備に関する知識
製造業の現場では、生産効率や安全性に関わる、機械や設備の操作・管理に関する知識も必須です。
メンテナンスの不足や操作ミスは、不良率の増加や生産性の低下につながってしまいます。また、製造業は建設業と並んで、労働災害発生件数が多い業種です。職場の安全性を高める上でも、機械・設備に関する知識は重要となります。
機械・設備に関する知識を分類としてさらに具体的な項目を立てる場合には「機械の操作と保守」「設備のトラブルシューティング」「安全管理」などが考えられます。機械整備技能士や電気主任技術者といった、関連資格の有無を入れても良いでしょう。
このように、機械・設備を適切に扱える人材を育成することで、生産ラインの安定稼働が期待できます。
無料公開されている製造業向けスキルマップのテンプレート
テンプレートを活用することでスキルマップ作成の時間を削減し、スムーズな導入が実現します。
有料のクラウドサービスもありますが、まずは無料のテンプレートを試す企業が多いでしょう。特にExcel形式など既存ツールを使ったものは手軽に導入でき、利用のハードルが低いため広く活用されています。もちろん自社に合わせてカスタマイズも可能です。
ここでは、厚生労働省の「職業能力評価シート」とコチームのスキルマップの2つをご紹介します。
厚生労働省の職業能力評価シート(Excelテンプレート)
厚生労働省のホームページでは「職業能力評価シート(スキルマップ)」の無料テンプレートをダウンロードできます。Excel向けのテンプレートになっており、スキル項目や評価基準を自由に変更可能です。
対応するのは、16の業種と19の事務系職種。19の職種の中でもそれぞれ1~3個の職務があり、別々のスキルマップが用意されています。それぞれ2~4個のレベル分けがされており、職務によってはレベル3のなかに「マネージャー」と「スペシャリスト」があるなど、さらに細かく分類されています。
デフォルトではスキルの評価基準は3段階で、以下の通りです。
| 〇 | 一人でできている | 下位者に教えることができるレベルを含む |
| △ | ほぼ一人でできている | 一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル |
| × | できていない | 常に上位者・周囲の助けが必要なレベル |
なお、16の業種のうち製造業に該当するテンプレートは、「ねじ製造業」の一つとなっています。下記に列挙しているのは、19の事務系職種とその中の職務のラインナップです。
| 職種 | 職務 |
|---|---|
| 経営戦略 | 経営戦略 |
| 人事・人材開発・労務管理 | 人事・人材開発 / 労務管理 |
| 企業法務・総務・広報 | 企業法務 / 総務 / 広報 |
| 経理・資金財務・経営管理分析 | 経理 / 資金財務(トレジャリー)/ 経営管理分析 |
| 情報システム | 情報システム |
| 営業・マーケティング・広告 | 営業 / マーケティング / 広告 |
| 生産管理 | 生産管理プランニング / 生産管理オペレーション |
| ロジスティクス管理 | ロジスティクス管理 / ロジスティクス / オペレーション |
| 国際事業 | 国際経営管理 / 貿易 |
厚生労働省の「職業能力評価シート」は必要な知識や基準などの細かい例が記載されています。併せて公開されている導入・活用マニュアルやキャリアマップとともに、スキルマップ作成の参考になるでしょう。
コチームのスキルマップテンプレート
弊社コチームのスキルマップも無料で公開しています。新入社員向けやマネージャー・管理職向け・マーケティング職向けなど、さまざまな業種・職種・役職を育成するためのテンプレートがあります。
他のスキルマップと異なり、会社ごとにカスタマイズせずとも、すぐに使えるものが多いです。現在、そのうちの一部のスキルマップを無料で配布していますので、ぜひ下記リンクよりダウンロードいただけますと幸いです。
スキルマップの効果を最大化する運用ポイント
ここからは、スキルマップ作成後の効果的な運用について特別に弊社のノウハウを公開して、以下の3つのコツを紹介します。導入の失敗を防ぐためにしっかりとご確認ください。
- 1on1ミーティングと掛け合わせて運用する
- 社内説明会を実施する
- 定期的に見直しを行う
それでは、それぞれのコツについて詳しく説明していきます。
1on1ミーティングと掛け合わせて運用する
現場の管理職やメンバーがスキルマップを効果的に活用するには、1on1ミーティングによる個別対話が重要です。直接話し合うことで、スキル課題を具体的に把握できます。
この場では、上司と部下が「どのスキルを習得するか」を明確にし、日常業務での実践内容を振り返ります。具体的には、以下のような流れで進めます。
設定したスキルが業務の中でどのように活用されたかを確認
↓
実践してみて難しかった点や課題を整理
↓
上司からフィードバックを受け、行動改善のヒントを得る
このようなプロセスを経て、1人ひとりの課題や目標設定に基づいた支援体制を整備できます。従業員は着実にスキルを習得し、実践力が高まるでしょう。1on1ミーティングを通じてスキル管理の透明性を高めることは、全体の信頼にもつながります。
弊社では、この手法を「スキルマネジメント」と呼び、まさに「究極のOJT(On the Job Training)」と考えています。スキルマップを作成するだけでなく、1on1を通じて実際にスキルを育成し、成長を促すことが重要です。
【即戦力採用<速戦力育成】
新入社員・若手社員を1~3年で高速成長させるには、1on1とスキルマネジメントの掛け合わせがおすすめ!
スキルシートの作成から実際の運用までを解説した資料!
>>『「人」ではなく「スキル」をマネジメントする1on1』はコチラから無料ダウンロード!
社内説明会を実施する
スキルマップ導入や運用継続のためには、社内説明会を定期的に行うことも重要です。
目的や評価基準、運用ルールなどを明確に伝えると、誤解や不安を未然に防ぐことができます。文書や動画などでマニュアルを用意し、分かりやすい共有を心掛けましょう。説明会は双方向のコミュニケーションの場として活用すると、さまざまな意見を吸い上げやすくなり、運用改善につながるでしょう。
もし、スキルマップを上層部だけに公開するなど透明性のない運用をしてしまうと、従業員からの信頼度が低下する可能性もあります。不明点があった場合は、新たなルールを策定するなど、全従業員が納得できる運用を目指すことが肝心です。
組織内の認識を統一し、スキルマップの一貫した運用を続けていきましょう。
定期的に見直す
スキルマップは定期的な見直しと更新が求められます。業務環境や技術、市場、社会情勢の変化によって、必要なスキルも変化していくためです。現場のフィードバックや提案に合わせてスキル項目を追加・修正、時にはテンプレート自体の変更をして、精度向上を目指しましょう。
例えば製造業の現場ではDXが推進され、自動化が急速に進んでいます。こうした変化に伴って現状のスキル要件と評価基準にズレが生じると、適切な人材配置や育成が難しくなり、スキルマップが形骸化する可能性が高まります。定期的なブラッシュアップを行い、最新の状態を保つよう心がけましょう。
ただし、注意点として、頻繁な変更は従業員に混乱を与える可能性があります。見直し時期をあらかじめ定め、適切なタイミングでアップデートを行いましょう。
効果的なスキルマップ作成・運用なら「コチーム」!

- 会社ごとのオリジナルスキルマップを独自学習させたAIを用いて作成!
- 1on1機能とスキルマップ機能の連携で、スキルの習得を促進!
- スキルの獲得状況を一元管理!
- 1on1の省力化機能で現場管理職の負担を最小限に抑えて運用可能!
よくあるご質問(FAQ)
Q1: 製造業でスキルマップを導入すると、具体的にどのようなメリットがありますか?
A: 業務の標準化と効率化が実現できます。 必要なスキルを可視化することで、適切な人材配置が可能になり、ISO9001の力量管理にも役立ちます。
Q2: スキルマップを作成する際、スキル項目を増やしすぎない方が良いのはなぜですか?
A: 「どのスキルを優先すべきか」が分かりにくくなるためです。 成果につながるインパクトが大きいスキルに絞り、重要度の高い項目を3〜5個程度に設定することが推奨されます。
Q3: 業務の属人化を防ぐために、スキルマップ作成で特に重視すべき点は何ですか?
A: スキル項目を具体的な業務フローと紐づけることです。 業務に必要なスキルを一覧化し、誰でも同じレベルの業務遂行ができるよう標準化することが重要です。
Q4: スキルマップ導入後、効果が出るまでどのくらいの期間がかかりますか?
A: 短期間での効果測定は難しいです。 スキルマップは人材育成という長期的な取り組みであり、継続的な運用と定期的な見直しによって、徐々に数字として成果に現れてきます。
Q5: 現場の管理職やメンバーがスキルマップをうまく活用するための運用方法はありますか?
A: 1on1ミーティングと連携させて運用するのが効果的です。 上司と部下が対話することでスキル課題を具体的に把握し、行動改善のフィードバックを行うことで習得を促します。
まとめ
この記事では、製造業においてスキルマップが必要な理由や、スキル管理のコツ、テンプレートなどをまとめて解説しました。
現在、労働人口の減少や採用難により、人材育成の必要性・緊急性が増してきています。変化の激しい製造業界ではなおさら、従業員のスキルデータを一元管理して、人材育成に役立てることが大切です。
スキルマップは人材育成から人材配置、ISO9001への対応まで幅広く活用できるツールとなっています。有効活用して組織全体の生産性を向上させ、ビジネスの成長を実現しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。スキルマップの作成・運用を検討されている方、またはお悩みの方は、ぜひ弊社サービスの『コチーム』をご活用ください。スキルマネジメントを成功させるための強力な支援ツールとして、お役に立てるはずです。 ご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。