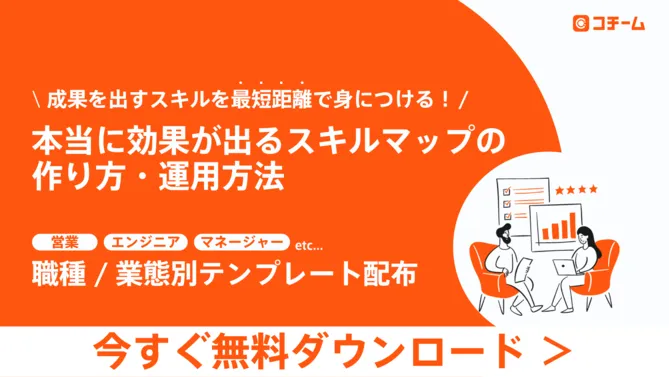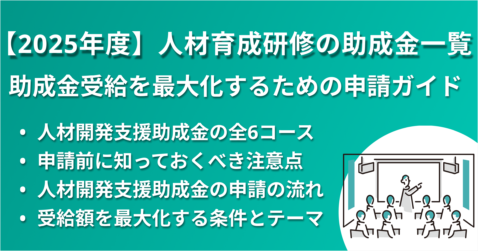企業の持続的な成長と競争力を維持するためには、効果的な人材育成が不可欠です。しかし、多くの企業では人材育成の担当者不足やシステムの不備により、一貫性のある戦略的な育成プログラムを構築できていないのが現状です。
このような課題を解決し、適切な人材育成施策を実行できるツールが「人材育成フレームワーク」です。社員が成長し、最終的に成果をあげるまでに必要な育成施策とその流れをモデル化したものになりますので、自社の状況と照らし合わせて育成方法を検討したい方はぜひご活用ください。
≫無料で「本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法」をダウンロードする
▼ この記事の内容
- フレームワークの重要性:成功事例のモデルを取り入れ、体系的かつ効率的な人材育成を可能にします。手探りの状態を脱し、育成の質を担保できます。指導方針が明確になることで属人化を防ぎ、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。
- 8選の機能:HPI(経営連結)、カッツモデル(階層別スキル)、70:20:10(実務重視)などがあります。 氷山モデルで潜在的な動機を分析したり、カークパトリックモデルで研修の投資対効果(ROI)を測定したりと、目的に合わせて適切なモデルを選ぶことが重要です。
- 活用成功の鍵:経営目標とフレームワークを連動させ、PDCAサイクルを回すことです。 フレームワークを目的化せず、企業の理想の人材像を達成するための手段と捉えましょう。実施後には必ず効果測定を行い、継続的な振り返りと改善(PDCA)を欠かさないようにします。
目次
人材育成におけるフレームワークの重要性
人材育成において、フレームワークを導入することは、成功法のモデルを取り入れることになるので、体系的かつ効率的な人材育成が実現可能になります。そのため、優秀な人材を育てるために最適な教育手法を判断でき、企業全体のパフォーマンス向上にも直結するのです。
例えば、リーダーシップ育成をしたい場合は、70:20:10の法則を自社の育成教育に取り入れるのが良いでしょう。この法則は、優秀なリーダーがどのような環境で生まれたかを調査した結果、最もリーダー育成が効果的な環境は実務経験を通じて育成する環境だと示しています。反対に、この法則は研修を通じてしかスキルや知識を学習する機会がない環境はリーダー育成が効果的でないとされています。
このように、フレームワークの重要性は学術研究などで効果的とされたモデルを導入することで自身の組織のパフォーマンスを向上できる点です。
>>無料で『本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法』をダウンロードする(職種 / 業種別のテンプレート公開中)
人材育成の目的
フレームワークは人材育成を効率的に進めるための手段です。目的を明確化することで適切な手段を選択できるように、自分の組織の成長に効果的なフレームワークを取り入れる際には人材育成の目的をしっかり確認する必要があります。人材育成の主要な目的について、詳しく見ていきましょう。
経営目標達成と人事戦略の実現
人材育成の最も重要な目的は、企業として目指す経営目標の達成と、そのために必要な人事戦略の実現です。経営戦略やビジネスモデルがどんなに優れていても、それを実現できる人材がいなければ達成することはできません。企業として何を目指すのか、そのためにどのような人材が必要なのかの「求める人材像」から逆算して人材育成を行うことが重要です。
例えば、自社のECサイトを作ってEC販売で売り上げを上げたい企業があります。しかしECサイトの作成や運営に精通した社員がいないという課題があります。この場合、ECサイトの技術的な教育を含めた人材育成を行いつつ、EC販売の部門を任せられるようなリーダーシップのある人材の育成が不可欠です。
この例のように企業が目指す経営目標の課題が人材の場合、人材育成は目標の達成とそれに必要な人材確保の架け橋となることができます。
従業員の能力やモチベーションの向上
人材育成は、社員のスキルや自社で働くモチベーションを向上させることができます。
社員研修やOJT(実務を通じた訓練)などのさまざまな人材育成手法を通じて、社員自身が現在どのような段階にいるのか、仕事を効率的に進めるにはどうすれば良いのかなどを体系的に理解できるようになり、学んだことを実際の業務に活かすことでスキルが向上していきます。
また、会社が能力向上の機会を提供することで、社員は自分のキャリアアップを会社が提供してくれていると感じやすくなり、会社に信頼を寄せ、期待に応えようとモチベーションを向上させます。
社員のモチベーション向上は、業務の生産性を高めるとともに離職率を抑えるため、業績の向上にも直結します。人材育成によって、社員一人ひとりが仕事のやりがいや充実感をより強く感じられるようになり、企業価値を高めるとともに組織の活性化も期待できるでしょう。
人材育成にフレームワークを活用するメリット
人材育成は、経営目標の達成や社員のスキル・モチベーション向上に欠かせない経営戦略の1つです。しかし、多くの企業では「時間が取れない」「基準がない」「仕組みが整っていない」といった課題を抱えています。
そこで有効なのが「フレームワーク」です。フレームワークとは、成功事例を基に構築されたガイドラインや共通の枠組みのこと。人材育成に導入することで、育成の効率化や効果の最大化につながります。
組織内で育成方法が確立できる
人材育成にフレームワークを導入すれば、組織内で一貫した育成方法を確立できます。成功パターンをモデル化したフレームワークにより、手探りの状態を脱し、明確な指針に基づいた育成が可能になるでしょう。
また、指導方針が明確になることで施策が形になり、担当者が変わっても同じ品質の育成を提供できます。組織全体として育成の質を担保できる点も大きなメリットです。
ただし、フレームワークはあくまで「型」であるため、自社の状況に応じて柔軟に調整することが効果的な人材育成につながります。
人材育成が効率的に行える
フレームワークを活用することで、より効率的な人材育成を推進することができます。フレームワークは人材育成における成功モデルを型化しているため、ゼロから考案する必要がなく、自社の育成に当てはめて施策の推進や検証に注力できます。
計画的に取り組みやすくなり、人材育成の方法について考える時間も大幅に短縮できます。また、自社の育成における成功パターンの発見にもつながりやすく、より効果的な育成を推進できるでしょう。
特に、複数の部門や拠点を持つ大規模な組織では、フレームワークを共通言語として活用することで、組織全体で一貫した人材育成を行うことができます。
現場管理職・育成担当が育成しやすくなる
フレームワークを導入することで、現場の管理職や育成担当者の負担が軽減され、より効果的で効率化された人材育成が可能になります。その理由は2つあります。
1つ目は、社員が期待される行動や能力が明確になることで、育成の方向性が明確になり、客観的な評価や指導が可能になります。2つ目は、組織的な知識・経験の蓄積により個人の経験や知識に依存せず、組織として育成ノウハウを蓄積できることです。
これにより社内での育成方法が確立されることにより、育成の役割を担う現場管理職・育成担当が育成しやすくなります。
人材育成のフレームワーク一覧
それでは、具体的なフレームワークを解説します。今回解説するフレームワークは以下の通りです。
| フレームワーク名 | 特徴 | 活用シーン |
|---|---|---|
| HPI | 現状と理想のギャップを分析するフレームワーク | 目標に沿って人材のパフォーマンスを改善したい時 |
| 氷山モデル | 目に見える要素だけでなく、潜在的な原因を分析する | 複雑な問題の根本原因を突き止めたい時 |
| カッツモデル(カッツ理論) | 3つの仕事スキルと3つの管理スキルで必要な能力を可視化する | 管理職に必要な能力を可視化したい時 |
| カークパトリックモデル | 教育のレベルを4段階に分け、細かく効果を測定する | 研修の費用対効果を知りたい時 |
| 思考の6段階モデル | 思考を6つの段階に分け、それぞれの能力を段階的に高める | 人材の思考力を段階的に高めたい時 |
| 70:20:10の法則 | リーダー育成における最適な環境を示している | 実務経験での育成を重要視する場合 |
| 経験学習サイクル | 経験に基づいた効果的な学習過程を示している | 社員に主体的に学習させたい場合 |
| SMARTの法則 | 目標を細く設定し着実にステップアップさせる | 明確で段階的な目標を設定したい時 |
人材育成のフレームワーク8選
それでは、人材育成によく用いられる8種類の代表的なフレームワークを紹介します。人材育成担当者や人材育成計画に携わる方は、ぜひ参考にしてください。適切なフレームワークを活用することで、社員一人ひとりが最大限の潜在能力を発揮できる環境を整え、企業の競争力を飛躍的に高めることができるでしょう。
HPI (Human Performance Improvement)
ASTDという団体が提唱したHPI(Human Performance Improvement)は、人材の現状から組織のあるべき姿を導き出し、改善することに重点を置いています。HPIの大きな特徴は、単なる人事的な視野にとどまらず、経営計画直接連結していることで、経営目標の実現から逆算された育成方法を確立できます。
例えば、組織の達成すべき目標が海外進出であれば、それを実現するためにはどのような能力を身につける必要があるのかを分析し、それに基づいた育成・指導を行うことができます。
HPIは以下の順序で整理をしていき、経営目標から人材育成の施策までをつなげていきます。
- 組織が必要とする人材を考える
- 組織の理想と現状とのギャップの洗い出しと原因の分析
- 理想とのギャップを埋めるための教育施策の立案
- 教育施策の実行と管理
- 教育施策の評価および改善
▶︎ 特徴:
現状と理想とのパフォーマンスの差を洗い出し、ゴールから逆算した課題解決案を作れる
▶︎ 活用シーン:
現在の従業員のパフォーマンスと理想的な状態に明確なギャップがある組織で、経営目標と人材育成戦略を明確に連動させたい時
氷山モデル
氷山モデルとは、物事の全体像を捉え、本質的な解決策を導き出すためのフレームワークです。「氷山の一角」という言葉が示すように、海面から見える部分は全体の約1割に過ぎず、残りの9割は水面下に隠れているという考え方がベースになっています。この考え方を人材育成に応用することで、表面的な課題だけでなく、その根本原因にまで踏み込んだ効果的な育成施策を設計することができます。
氷山モデルは、以下のように人の行動や能力を目にみえる課題と目には見えない課題に分類します。
【水面上、目に見える部分】
- 成果、実績
- スキル
- 行動
【水面下、目に見えない部分】
- 動機・価値観
- 行動特性
- 自己認識
氷山モデルの最大の特徴は、目に見える部分だけでなく、目には見えない「動機や価値観」「行動特性」「自己認識」といった潜在的な部分が実際の行動や成果に大きく影響を与えていると考える点です。
▶︎ 特徴:
表面的な問題の解決ではなく根本的に問題を解決したい時
▶︎ 活用シーン
パフォーマンス改善が思うように進まず、根本的な解決がしたい時
カッツモデル・カッツ理論
カッツモデル(カッツ理論)は、米国の経済学者ロバート・カッツ氏が提唱した、マネジメントにおいて必要とされるスキルを階層的に表しているフレームワークです。このモデルは、役職に応じて重要となるスキルの比率が変化することを示しており、効率的な人材育成計画の立案に役立ちます。
カッツモデルでは、ビジネスパーソンに必要なスキルを以下の3種類に分類しています。
【3つの必要スキル】
- テクニカルスキル(業務遂行能力・専門能力)
- ヒューマンスキル(対人関係能力・人間理解能力)
- コンセプチュアルスキル(概念化能力)
さらに、これら3つのスキルの重要度が、役職によって異なるという点にあります。カッツモデルでは、以下の3つの役職に必要なスキルの優先順位を示しています。
【3つの役職とそれに必要なスキルの優先順位】
- ロワーマネジメント(下級管理職)
- 1位:テクニカルスキル
- 2位:ヒューマンスキル
- 3位:コンセプチュアルスキル
- ミドルマネジメント(中間管理職)
- 1位:ヒューマンスキル
- テクニカルスキルとコンセプチュアルスキルはほぼ同等
- トップマネジメント(経営層)
- 1位:コンセプチュアルスキル
- 2位:ヒューマンスキル
- 3位:テクニカルスキル
▶︎ 特徴:
マネジメント層において階層別に必要とされるスキルを体系化している
▶︎ 活用シーン:
部長、課長、中間管理職などのポジション別での効果的な育成制度を作りたいとき
カークパトリックモデル
「カークパトリックモデル」は、教育・研修の効果を評価するための体系的なフレームワークです。人材育成施策の効果を4つのレベルに分けて段階的に測定することで、研修の有効性を総合的に評価できます。
このモデルの最大の特徴は、単なる参加者の満足度だけでなく、最終的な業績向上にまでつながったかどうかを測定できる点です。そのため、人材育成の投資対効果(ROI)を明確にしたい企業にとって、非常に有用なフレームワークとなっています。
カークパトリックモデルでは、教育・研修の評価を以下の4つのレベルに分けています。
- レベル1:Reaction(反応)
- レベル2:Learning(学習)
- レベル3:Behavior(行動)
- レベル4:Results(結果)
多くの企業では、レベル1とレベル2の評価は研修実施後すぐに行い、次回のプログラム改善に活かすための形成的評価として活用しています。一方、レベル3とレベル4、研修プログラムの継続可否を判断するための総括的評価として活用されることが多いです。
カークパトリックモデルの最大のメリットは、人材育成の成果と業績との関連性を数値化することにより、明確な効果測定ができる点です。
▶︎ 特徴:
教育のレベルを4段階に分け、細かく効果を測定できる
▶︎ 活用シーン:
人材教育の効果と業績の費用対効果を明確にしたい場合
【成果を出すスキルを最短距離で身につけるスキルマップの作り方!】
・スキルマップを導入しようと考えているけど、効果が本当に出るのかわからない
・スキルマップを導入しているけど、なかなか効果が出ない・形骸化している
とお悩みではありませんか?
実は、スキルマップを効果的に運用するためには抑えるべきポイントがあります!人材育成で100社以上支援実績がある弊社のノウハウを盛り込んだ、ココでしか読めない情報が満載の無料スキルマップ解説資料!
>>『本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法』はコチラから無料ダウンロード!(職種 / 業種別のテンプレート公開中)
思考の6段階モデル
「思考の6段階モデル」は、教育心理学者のベンジャミン・ブルーム氏が提唱した人間の思考過程を6つのレベルに分けたフレームワークです。思考過程に基づいてステップアップしていきます。
下記が、思考の6つの階段であり、最初の知識から最後の評価までを6つの段階で思考レベルを分けています。
- 知識:事実・言葉・方法などを記憶できているか
- 理解:内容を理解し、自分の言葉で説明できるか
- 応用:学んだ知識を別の状況でも活用できるか
- 分析:全体から要素を抽出し、関係性を説明できるか
- 統合/結合:部分を組み合わせて新しい価値を創造できるか
- 評価:基準に基づいて情報の価値を判断できるか
このモデルは研修プログラムや教育カリキュラムを設計する際に有効です。育成対象者の現在の思考レベルを把握し、次の段階へと導くアプローチを組み込むことで、効率的な人材育成が可能になります。
▶︎ 特徴:
思考過程に基づいた、段階的な研修を設計できる
▶︎ 活用シーン:
思考力を段階的に強化させる研修を設計したい時
70:20:10の法則(ロミンガーの法則)
米国のロミンガー社が提唱した「70:20:10の法則」は、優れたリーダーがどのように成長したかを調査した結果から生まれました。経営者やリーダーたちに「リーダーシップ発揮のために何が役立ったか」を尋ねた結果、次のような明確な割合が判明しました。
- 70%:仕事の経験
- 20%:他者からの学び
- 10%:研修
リーダーの成長に最も効果的なのは実務経験であり、研修だけでは人材は大きく育たないということです。つまり、座学中心の研修に多大なコストをかけるよりも、成長につながる実務経験を積める環境を整備することが人材育成の鍵となります。
▶︎ 特徴:
リーダー育成における最適な環境をモデル化している
▶︎ 活用シーン:
実務経験に基づいた育成を実施したい時
経験学習サイクル
アメリカの教育学者であるコルブが提唱した「経験学習サイクル」は、人が経験からどのように学ぶかというプロセスを4つのステージで説明し、効果的な学習には以下の4つを循環することが不可欠だと示しています。
- 経験(具体的経験):具体的な経験をする
- 内省(内省的観察):行動の振り返り・フィードバック
- 概念化(抽象的概念化):何を学んだかを明らかにする
- 実践(能動的実験):次に行うときに学びを応用する
これらのサイクルを回すことで、自身の経験を使える知見に変容させることで、人が成長することができるということを示しています。すべての従業員に使えるフレームワークですが、OJTが中心の若手の育成について整理する際に非常に有効なフレームワークです。
▶︎ 特徴:
社員が自らの経験から自発的に学び成長できる最適なプロセスを示している。
▶︎ 活用シーン:
社員の自発的な成長を促進したい時
経験学習サイクルを組織の人材育成に活用するには、以下のようなことを考慮するとより効果的な育成を実施できるでしょう。
意図的な経験の機会を設計する
ただ業務を任せるのではなく、成長につながる機会を意図して設計します。
振り返りの文化を醸成する
「何がうまくいったか」や「何が課題だったか」を、定期的に省察する場を設けます。1on1ミーティングを活用することがおすすめです。
概念化を支援する
上司やメンターが、質問を通じて学びの一般化・概念化を促します。また、学びを次の行動に活かせる形に整理することにより、経験を経験値に変えることができます。
実践の機会を与える
その学びを活かせるような機会が、すぐに与えられるようにします。
SMARTの法則
「SMARTの法則」は、目標設定において考慮すべき5つの要素の頭文字を取ったものです。この法則に従って目標を設定することで、曖昧さを排除し、達成に向けた明確な道筋を立てることができます。
- S(Specific):具体的・明確
- M(Measurable):測定可能
- A(Achievable):達成可能
- R(Relevant):関連性
- T(Time-bound):期限
この法則の最大の強みは、目標設定レベルを段階的に上げながら人材を育成できることです。
例えば、新人営業担当者の育成で以下のようなSMART目標を設定できます。
7月末までに(T)商品Aのセールストークを習得し(S)評価で80点以上を獲得する(M)
トレーニングプログラムを受講し週3回の練習を行うことで(A)8月からの実際の顧客訪問に備える(R)
このように具体的な目標を設定することで、何をすべきかが明確になり、育成の効果が高まります。
▶︎ 特徴:
抽象的な目標を具体的な行動計画に変換できる
▶︎ 活用シーン:
抽象的な課題から具体的な問題解決案や解決までの道のりを知りたい時
人材育成のフレームワークを活用する流れ
自身の環境に適したフレームワークを導入するには、以下の6つのステップを参考にしてください。
- ステップ1:経営目標を確認する
- ステップ2:理想の人材像(ゴール)を明確化する
- ステップ3:理想と現状のギャップを把握し、育成課題を明確にする
- ステップ4:育成計画や目標を策定する
- ステップ5:採用するフレームワークや育成手法を決定する
- ステップ6:人材育成の実施と定期的な振り返りを実施する
ステップ1:経営目標を確認する
まず、自社の役員たちと話し合い自社の経営目標を再確認しましょう。社内である程度目標の共有ができている場合でも、部署で意見が違う場合があります。
人材育成を効果的にするために、経営目標を会社で確認することは、全体で会社全体が統一されたゴールを持ち、そのゴールから逆算されたフレームワークを選択する上でとても重要なステップです。
ステップ2:理想の人材像(ゴール)を明確化する
経営目標が明確化されたら、その目標を達成するために必要な理想的な人像を明確化しましょう。経営目標を達成するために必要なスキルを洗い出し、それを備えている人材はどのようなスキルやビジョンを持っているかを考えましょう。
これにより人材教育のプラン開発が容易になる上、理想の人材と現状のパフォーマンスとのギャップを意識しやすくなります。
ステップ3:理想と現状のギャップを把握し、育成課題を明確にする
経営目標と人材のパフォーマンスの理想と現実のギャップを確認できたら、その間を埋めるための育成課題を明確にしましょう。理想の人材を生み出すにはどのようなスキルをどの期間内に身につけさせるのか、そのためにはどのような教育制度が必要か、現状からできることは何かを考えましょう。
例えば、氷山モデルのように目に見えるパフォーマンスの課題よりも社員が抱えている潜在的な課題の解決を優先するべきかも知れません。ゴールから逆算しどのように差を埋めるのが効果的か考えましょう。
ステップ4:育成計画や目標を策定する
効果的な人材育成を実現するためには、まず適切な育成計画と明確な目標を策定することが不可欠です。この段階で綿密な計画を立てることは、後の運用におけるトラブルを未然に防ぎ、フレームワークを最大限に活用するための基盤となります。
経営目標から逆算し、具体的な日程を決めて「いつまでに」「何名の社員が」「どのようなスキルを身につけているかが理想か」を考察し、人材育成計画を作りこみましょう。
計画立案に十分な時間を投資することで、後の実行段階がスムーズに進み、人材育成の成功確率が大幅に向上します。
ステップ5:採用するフレームワークや育成手法を決定する
育成計画と目標を策定した後の重要ステップが、企業の状況や目的に最適なフレームワークと育成手法の選定です。この段階で適切な選択をすることで、人材育成の効率と効果を最大化することができます。
達成すべき経営目標と求める人物像の設定に基づき、「どのフレームワークが自社に合っているのか」を最終確認しましょう。
例えば、新入社員に実践的な経験を積ませたい企業が、新入社員一人一人にメンターを配置できる余裕があれば、社員の失敗時に1on1でコーチングし、自主的な改善を促せられる経験学習サイクルのモデルが最適でしょう。
また、フレームワークは組み合わせて使うことができます。例えば、まずSMARTの法則で経営目標を設定しそれと育成制度を連結させるHPIのテクニックを用いて目標達成に効果的な指導法や育成法を考えることができます。
ステップ6:人材育成の実施と定期的な振り返りを実施する
適切なフレームワークを選定し育成計画を策定したら、次は実行フェーズに移ります。しかし、ただ計画通りに実施するだけでは十分ではありません。効果的な人材育成のためには、実施状況の記録と定期的な振り返りが不可欠です。
人材育成を開始したら記録を付けましょう。どのようなトレーニングを行い、社員がどのような気づきを得たのかを記録として蓄積することで、徐々に育成の精度が高まります。定期的な振り返りは単なるチェック作業ではなく、次の成長サイクルを生み出す重要なプロセスです。記録と振り返りを通じて、人材育成フレームワークの効果を最大化し、持続的な組織と人材の成長を実現しましょう。
また、フィードバックを積極的に行いましょう。育成対象者と育成担当者両方ともフィードバックできる環境が持続的でより効果的な人材育成制度を追求できる最適な環境です。
フレームワークの活用を成功させるポイント
選択したフレームワークを機能的にするためのポイントは以下の2つです。
- ポイント1:企業の実施目的・フレームワークの特徴に合った手法を選ぶ
- ポイント2:PDCAサイクルを回す
企業の実施目的・フレームワークの特徴に合った手法を選ぶ
人材育成フレームワークの導入は、単に流行りのメソッドを取り入れるだけでは成功しません。企業の経営目標・人材育成方針に合ったものを選ぶ必要性があります。事業の経営目標や人材育成方針と合わないフレームワークを採用しても、人材育成が効率的に進まない可能性が高いでしょう。
正しいフレームワークの選択は、組織の現状と目指す姿を深く理解することから始まります。表面的な流行や他社事例に惑わされず、自社の特性や課題に最も適したフレームワークを選択し、必要に応じてカスタマイズすることがおすすめです。
PDCAサイクルを回す
人材育成フレームワークを導入しただけで終わりではありません。真の成功を収めるには、継続的な改善が不可欠です。そのための有効な手法が「PDCAサイクル」の活用です。「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(修正)」の繰り返しにより、取り組みの質を向上させる手法です。PDCAを回すことで、人材育成の効率をより高められます。
特に人材育成においては、当初の想定通りにいかないケースも多いため、このサイクルを意識的に回すことが成功への鍵となります。
人材育成にフレームワークを活用する際の注意点
人材育成にフレームワークを活用する際の注意点は以下の3点です。
- 経営目標の達成や人事戦略の実現など本来の目的を忘れない
- 従業員の急成長を期待しすぎない
経営目標の達成や人事戦略の実現など本来の目的を忘れない
人材育成フレームワークを導入する際に陥りやすい落とし穴の一つが、「フレームワーク自体が目的化してしまう」ことです。人材育成の目的は、企業の目標達成や人事戦略の実現、および育成対象者の成長です。フレームワークを活かすそもそもの目的をぶらさないように、定期的に自分たちの計画を見直しましょう。
フレームワークに固執せず、柔軟に対応する
フレームワークのルールを守りすぎて自身の組織にマッチしなくなってしまう場合があるので注意しましょう。フレームワークはあくまで人材育成を効率的に進める手本にすぎません。フレームワークのルールよりも経営目標の実現を中心に考え柔軟に対応しましょう。
会社が成長し組織構造に変化があったり、理想の人材の定義が変わったりした場合その都度自分達が採用したフレームワークを見直しこの先もこのフレームワークを活用していいのかを考えましょう。
従業員の急成長を期待しすぎない
人材育成フレームワークを導入する際、多くの企業が陥りがちな罠があります。それは、フレームワーク導入後、社員の能力や成果が劇的に向上することを期待してしまうことです。しかし、現実的な期待値を持ち、長期的な視点で人材育成を捉えることが大切です。
効果的な人材育成なら「コチーム」!

- 会社ごとのオリジナルスキルマップを独自学習させたAIを用いて作成!
- 1on1機能とスキルマップ機能の連携で、スキルの習得を促進!
- スキルの獲得状況を一元管理!
- 1on1の省力化機能で現場管理職の負担を最小限に抑えて運用可能!
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 人材育成のフレームワークを活用する最大のメリットは何ですか?
A: 育成方法が組織内で確立でき、指導の質の「属人化」を防げることです。 成功モデルに基づいた明確な指針ができるため、指導担当者が変わっても一貫した品質の育成を提供できます。結果として、人材育成が効率的に推進できます。
Q2. 「氷山モデル」は、人材育成においてどのような課題解決に役立ちますか?
A: 表面的なスキル不足ではなく、その根底にある「動機や価値観」といった潜在的な原因を分析したい時に有効です。 目に見えない部分が実際の行動に影響を与えると考え、潜在的な要因にアプローチすることで、根本的なパフォーマンス改善を導くことができます。
Q3. 「70:20:10の法則」が示す、リーダー育成において最も重要な要素は何ですか?
A: 70%を占める「仕事の経験(実務経験)」が最も重要です。 優れたリーダーは、研修(10%)ではなく、実務経験(70%)と他者からの学び(20%)を通じて成長します。育成の鍵は、座学よりも成長につながる実践的な環境を整備することにあります。
Q4. マネジメント層の育成計画を立てる際、どのフレームワークが有効ですか?
A: カッツモデル(カッツ理論)が有効です。 ロワー・ミドル・トップといった役職の階層別に、必要なスキル(テクニカル、ヒューマン、コンセプチュアル)の比率が変化することを示しており、効率的な育成目標の設定に役立ちます。
Q5. フレームワークを活用する際の注意点は何ですか?
A: フレームワーク自体を「目的化」せず、企業の経営目標達成の手段と位置づけることです。 また、フレームワークのルールに固執しすぎず、自社の組織構造や文化に合わなくなる場合は、柔軟にカスタマイズすることが成功の鍵となります。
まとめ
今回は人材育成に悩んでいるマネジメント職の方に向けて人材育成フレームワークの種類と基本的な機能から具体的な活用法を紹介しました。人材育成は中長期的に行う必要があるため短期的な成果が見えません。目標を見失ったり育成方法を変えてしまうことのないよう、この記事を参考に是非自社に適した教育制度を構築してください。
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。