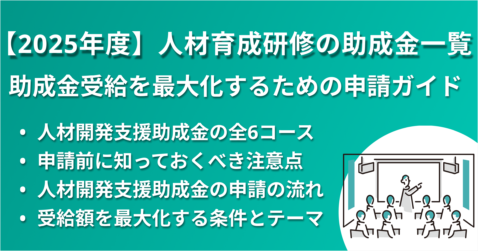管理職は経営層と現場をつなぐ中核的存在であり、その育成は組織の成長と存続に直結します。しかし、多くの企業にとって優秀な管理職の育成は大きな課題です。本記事では、管理職に求められるスキルや能力の基本から、具体的な育成手法や事例までを解説します。「育成に力を入れたいが、何から始めればよいか分からない」という担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
>>【助成金活用で最大75%補助】満足度98.2%のマネジメント研修がわかる資料3点セットをダウンロードする
▼ この記事の内容
- 管理職に求められる4つの能力: 人材育成能力(キャリアビジョン把握とフィードバック)、マネジメント能力(経営資源の効率的活用と部下のモチベーション向上)、組織運営力(リソース配分・業務最適化)、リスクマネジメント(トラブル予防と危機回避)です。
- 管理職育成の主な課題: 優秀なプレイヤーからチームで成果を出すマネージャーへの意識転換が難しいこと、働き方の多様化によるマネジメント手法のアップデートが必要なこと、責任感から業務過多になりセルフマネジメントを欠きがちなことです。
- 効果的な育成方法: 経営会議などにオブザーバーとして参加させ経営視点を持たせること、階層別やテーマ別の研修を定期的に実施すること、部門横断のプロジェクトをマネジメントさせ全社最適の視点を学ばせることです。
- 事例から学ぶポイント: 小田急電鉄は自発的な変化と承認欲求を満たす意識改革を、ヤフーはコーチング型の1on1による自律性の促進を、名港海運は階層別の実践的プログラムと自社理解を重視しています。
目次
管理職に求められるスキルと能力
管理職とは、全社目標を達成するためにチームメンバーや部下を適切に指導しながら、経営層と現場をつなぐ架け橋の役割を担う存在です。そのため、現場と経営両方の視点を持ち、さらにはマネージャーとして人材開発や意思決定を円滑に進めることも求められます。
ここでは、多くの企業や人事の担当者が重要視している、マネジメントや組織運営などを含む4つの能力を順に解説します。
人材育成能力
管理職の役割として、企業の業績や組織全体の成果を引き上げるマネジメントを担うだけではなく、人材育成能力を高めて従業員を成長させることにも大きな意味があります。特に新任のマネージャーの場合は、研修で得た知識を自分の指導スタイルにどう反映させるかがポイントになるでしょう。
具体的には、部下のキャリアビジョンを把握しながら、長期的な目標設定やロードマップを一緒に考えることが、チームのエンゲージメント向上に直結します。日々の業務を通じて、積極的にフィードバックを行うことも大切です。さらに、自分自身が実践した成功体験や失敗から学んだ知識を共有することで、組織全体のスキルレベルを底上げしやすくなります。
会社として人材育成の仕組みを整備し、必要に応じて外部のプロを活用することで、多様な背景を持つ社員を効果的に指導できる管理職を育てるのが理想的です。
マネジメント能力
マネジメント能力とは、「組織の目標を達成するために、経営資源を効率良く活用する能力」のことであり、管理職にとって最も基本となるスキルです。言い換えると、人材を適切に配置し、チームの目標設定をスムーズに行い、社内外の関係者と協力して成果を出すための指揮をとる能力とも言えます。
特に、部下のエンゲージメントを高め、個々のモチベーションを上手に引き出す技術は、管理職にとって非常に重要であると言えるでしょう。管理職ともなると、抱える部下やチームの数も少なくなく、様々な特性やスキルを持った社員を多くマネジメントすることになります。よって、状況やメンバーに応じてリーダーシップスタイルを柔軟に活用することがポイントとなります。
例えば、緊急時にはトップダウン型の指示が功を奏す場合もありますが、自律性を重んじる職場ではメンバーが主体的に動けるように意思決定を委ねることが好まれます。また、部下によっては細かく管理されたい人もいれば、ある程度任せてほしいタイプもいるでしょう。
このように、状況や対象によって柔軟に対応しながら上手に部下の能力やモチベーションを引き出せるかどうかが、管理職としての能力をはかる代表的な指標の一つであると言えるでしょう。
組織運営力
組織運営力とは、組織やチーム、部署全体を効果的に機能させるための能力です。
具体的には、人材や予算、時間等のリソースの適切な配分を行い、業務プロセスを最適化したり、さらには組織やチームごとの文化や基盤を醸成することで、メンバーのエンゲージメンを強化することなどが求められます。
また、時代の変化が速いビジネス環境では、方針転換や計画の見直しをいかに早く行えるかが勝敗を分けるため、常に状況を俯瞰しながら柔軟に意思決定をする力が求められます。
さらに、管理職は現場と経営層の懸け橋となる存在であるため、両者の思惑や要望を擦り合わせる能力も、チームや部署を運営する上で必要になってくるでしょう。
経営視点で事業の方向性を把握しつつ、部下や現場の人間がその意図を理解できるように丁寧に伝えたり、理解を促したりする必要があります。
リスクマネジメント
管理職がリスクマネジメントを怠ると、大きなトラブルや取り返しのつかないミスに繋がってしまう可能性があります。しかし逆に、管理職がリスクマネジメント能力を備えることで、プロジェクトや組織のセーフティネットとして、トラブル予防や危機回避を行えるようなるとも言えます。
そもそもリスクマネジメントとは、トラブルやミスの種になりそうなネガティブリスクに対し回避または低減のための策を講じたり、ネガティブな事象が発生した際に、原因を可視化し、組織としての対処法を瞬時に判断することにより、被害の最小化に向け行動したりすることを指します。リスクマネジメント能力は、企業全体としても守りの戦略として大きな価値を生む要素なので、管理職になる前から学び始めるのも有効でしょう。
また、想定外の事象であってもプラスに働くものはポジティブリスクと呼ばれ、ポジティブリスクを積極的に活用したり、プラスの効果を最大化させるような戦略を打ち出したりといった機転や応用を利かせることも、リスクマネジメントの重要な要素です。
>>【マネージャーの負荷削減と組織の生産性向上を実現】3分でわかる「コチーム」がわかる資料3点セットを無料でダウンロードする
管理職育成の課題
管理職の育成は、一般社員の育成に比べて求める能力やスキルが特殊だったり、さらに要求値も高かっったりすることから、様々な課題が存在しています。
ここでは、特に気を付けるべきである以下の3つの課題について順に解説します。
意識転換が必要
管理職になる多くの人は、優秀なプレイヤーとして評価され、昇進してきた人材です。しかし、プレイヤーとしての成功体験が、マネージャーとしての役割を果たす上での障壁になることがあります。
プレイヤーとして優秀だった人でも、マネージャーとなった途端に組織運営やメンバーのマネジメントが思うようにいかず、戸惑うことは珍しくありません。これは、プレイヤー時代は自分の目標を達成すればよかったのに対し、管理職としては部下やチーム全体の成果を最大化する必要があるというのも要因の一つかもしれません。
プレイヤーからマネージャーへの転換には、「自分で成果を出す」から「チームで成果を出す」という大きな意識の変化が必要です。
しかし、これまで自分で手を動かして問題解決してきた人が、部下に任せて見守るという姿勢に切り替えるのは容易ではありません。「自分でやった方が早い」と考えて部下の仕事を奪ってしまったり、逆に「任せた」と言って放置してしまったりするケースも少なくありません。
そこで、マネージャーに求められるのは、個人の適性やモチベーションに合わせて業務を采配したり、必要最低限のサポートやフィードバックを与えたりすることで、メンバーが自立的に動けるように導くことです。こうした思い切った業務の切り分けや任せ方は初めて管理職に就いた人には大きなチャレンジですが、意識転換を図っていくことで、自分もチームもより良い成果を出せるようになるでしょう。
マネジメント方法にもアップデートが必要
働き方の多様化やテクノロジーの進化により、従来のマネジメント手法が通用しなくなってきています。リモートワークやフレックス制が浸透し、働く場所や時間が人によってバラバラになると、従来の管理手法がそのまま通用しない場面が増えてくるでしょう。
例えば、毎朝全員が顔を合わせることが前提の管理方法では、オンライン上でフレキシブルに働くメンバーをしっかりフォローできないかもしれません。
加えて、国籍やバックグラウンドが多様な人材が協働するようになった今、同じ指示やマネジメント方法で全員をまとめようとすると、意見が噛み合わずにストレスが生じることもあります。
さらに、DX化によって社内システムやコミュニケーションツールはデジタルツールに切り替わってきており、これらに疎く使いこなせなければ、マネジメントやチームメンバーとのコミュニケーションも困難になってしまいます。そのため、自社システムの特性やできることを理解して使いこなし、業務効率化や意思決定に活かすスキルが求められます。
業務過多になる
管理職としての責任感が強い人ほど、チームの課題やトラブルをすべて抱え込み、業務過多に陥るケースが少なくありません。
特に、リモートワークやフレックスなど働き方が変化する中で、コミュニケーションの取り方が複雑化し、余計にタスクが増えるジレンマも考えられます。こうした状況を放置すると、マネージャー本人の成長機会が失われるだけでなく、会社全体の生産性や部下のモチベーションにも悪影響が及ぶリスクが高まります。
また、管理職が業務過多に陥ると、部下のマネジメントに注力するあまり自身の成長や健康管理がおろそかにしてしまい、「セルフマネジメント不足」を招いてしまう可能性もあります。特に、プレイングマネージャーとして自らも業務を担当している場合、この問題は深刻になります。
管理職の中には、自分自身が現場の業務も担当しながらチームを率いる、いわゆるプレイングマネージャーの立場にある人も多いでしょう。
こうした状況では、チーム内の課題やメンバーへのフォローをしつつも、自分が前線で実務をこなさなくてはならず、想像以上に多忙を極めます。忙しさに追われながらマネジメントを行うと、成果は出ているように見えても、自分の健康管理やキャリア形成、そして新しいスキルの習得など、セルフマネジメントを見落としがちです。
そのため、自分自身の時間や体力、モチベーションをコントロールし、必要に応じて業務を他のメンバーに任せる決断をすることもマネージャーの大切な役目だと言えます。重要なのは、業務の棚卸しを進めると同時に適切な権限移譲を行い、チームメンバーにタスクを分担してもらうことです。
社内制度や周囲のリソースを上手に活用しながら、自分やチーム状況に合ったマネジメントを実践し、業務のバランスを調整できるような管理職が真に優秀であると言えるでしょう。
マネジメントの優秀さは、実は才能によるものではなく「スキル」であることはご存知でしょうか? 下記より、管理職のスキル向上に効果的な「スキルマップテンプレート」を無料で手にいれることができます。真に優れた管理職をどのように育成するのか、詳細が気になる方はぜひご覧ください。
会社にノウハウがない
企業によっては、若手社員への教育カリキュラムは整っていても、本格的な管理職育成の研修や仕組みを社内に持ち合わせていない場合があります。
一般社員向けに実施していた支援制度や評価手法では、役職者が求められる意思決定やリーダーシップの習得には不十分というケースも多いでしょう。管理職として必要なノウハウやスキルは、単なる職務手順の理解だけでなく、意思決定モデルの学びや経営視点、そして組織全体を俯瞰する考え方など、多岐にわたります。
こうした要素を社内でまかない切れないと感じたときは、人事部門が率先して外部のプロに相談し、効果的なトレーニングプログラムやキャリア支援を導入するのがおすすめです。
自社特有のカルチャーとプロのナレッジやノウハウを上手に融合させることで、マネージャー候補が早い段階から高いレベルのマネジメント思考を身につけ、優秀な経営人材へと育ちやすくなるでしょう。
管理職の育成方法
管理職を育成するには、多様な切り口でアプローチを行うことが大切です。単に座学の研修を受けさせるだけでは人材が育ちにくい場合もあるため、インプット(座学や研修)とアウトプット(実践経験)を上手く織り交ぜながら育成方法を策定しましょう。
ここでは、特に効果的な取り組みとしてよく挙げられる3つの手法を紹介します。
経営視点を持たせる場に参画させる
管理職が経営視点を身につけるということは、会社の長期的な方針や全社目標を念頭に置いて行動できるようになるという意味です。
日常の業務では部下の担当を割り振ったり、社内外の調整を進めたりする役割が中心になるかもしれません。しかし、それと同時に、会社が今どんなビジネスモデルで収益を上げようとしているのか、どのような市場や顧客に注力する戦略を描いているのかを理解しているかどうかで、意思決定の質は大きく変わります。
そのため、管理職候補者や新任管理職を対象にインハウスで経営シミュレーションを行わせたり、経営会議や重要な意思決定の場にオブザーバーとして参加させたりするなど、経営視点を強く意識するような場での経験を積ませることが効果的でしょう。
こうした機会を増やすことで、管理職として意思決定する際に、現場と経営の両面を踏まえた高いレベルの判断ができるようになるはずです。
管理職向け研修を定期的に実施する
管理職研修の重要性は多くの企業が認識しており、リーダーシップやマネジメントを中心としたプログラムを継続的に導入しているところも珍しくありません。また、研修の効果を高めるためには単発ではなく継続的なプログラムとして設計し、研修で学んだことを実務に活かす機会のサイクル(実践と振り返り)を設けることが重要です。さらに、研修内容を定期的に見直し、最新のマネジメント理論や事例を取り入れていくことも大切となります。
管理職育成のための研修には様々なものがありますが、実際に広く取り入れられている代表的な4つのプログラムを紹介します。
1.階層別研修:
新任管理職、中堅管理職、上級管理職など、それぞれの段階に応じた内容の研修を提供。経験や役割に合わせたカリキュラムにすることで、より実践的な学びを得られる。
2.テーマ別研修:
リーダーシップ、コーチング、評価・フィードバック、チームビルディングなど。特定のテーマに焦点を当てた研修を実施し、管理職が特に課題を感じている分野を重点的に学ぶことができる。
3.アクションラーニング:
実際の業務課題を題材に、少人数のグループで解決策を考え、実行するプロセスを通じて学ぶ方法。理論だけでなく実践的なスキルが身につく。
4.外部研修や講座の活用:
外部の研修プログラムやビジネススクール、動画講座など。個人の興味関心や習得したいスキルに合わせてフレキシブルな参加が可能。
部門横断規模のプロジェクトをマネジメントさせる(自部署・部分最適ではなく、全社最適視点を養成)
自分の部署やチーム内の業務だけを管理していると、自部署の利益を最大化させるような部分最適の考えになりがちです。 そこで、部門横断規模のプロジェクトに管理職を参画させることで、全社最適の視点を学ばせる方法が効果的となります。
複数の部門や専門分野の人たちがチームを組むため、利害やカルチャーの違いなど、課題も多く発生する可能性があります。しかし、だからこそ問題解決力や調整力が鍛えられ、管理職として大きく成長できるメリットがあるのです。
また、その過程で他部門の役割や業務内容、顧客とのやりとりなどを具体的に体験し、会社全体の仕組みを把握できるようになります。これにより、日常のマネジメントにおいても、部下の成長や事業への貢献をより総合的に考えられるようになるでしょう。
このように、部門横断プロジェクトを通じて、自部署・部分最適(ミクロ)の視点から、全社最適(マクロ)の視点へと思考の幅を広げることができます。また、異なる部門との協働を通じて、組織全体のネットワークを構築する機会にもなります。
管理職の育成に関する取り組み事例紹介
ここで、実際に管理職育成で成果を上げている企業の事例を見ていきましょう。管理職の育成施策は、実際に行った企業の事例を参考にすると具体的なイメージを得やすいのではないでしょうか。
ここでは、異なる業界や規模の3社の取り組みをピックアップして紹介します。自社で活用できそうな手法やポイントを探してみてください。
事例① 小田急電鉄
小田急電鉄では、運転車両部の「助役」(中間管理職)に対して、意識改革とモチベーション向上のための取り組みを行いました。
「助役」は現場業務全般と部下のマネジメントを担う重要な役職ですが、昇進の機会が限られているため、10年以上同じ業務を続けることも多く、モチベーションの低下やマンネリ化が課題となっていました。また、これが部下にも影響し、ヒューマンエラーのリスクが高まっているという課題もありました。
そこで、「助役真髄塾」を立ち上げ、特に経験豊富なベテラン助役を中心に招集しました。招集の際には「この職場ではあなたが主役である」という意識を持ってもらうため、一人ひとりに宛てたメッセージ付きの招待状を送付するなど、細かな工夫を凝らしました。
その結果として、当初は消極的だったベテラン助役も塾に参加した後は自ら率先して行動するようになり、仕事に誇りを持って取り組む人が増えました。特に、「自分たちで考えながらやる方が、より前向きに行動できる」という意識が組織全体に広がり、ミドルマネジメントを中心とした組織の活性化につながりました。
この事例から、管理職の意識改革には「自発的な変化を促す」ことと「承認欲求を満たす」ことが重要であることがわかります。特に、長年同じ立場にいる管理職には「あなたは会社に求められている」という認識を持ってもらうことが効果的です。
事例② ヤフー株式会社
ヤフー株式会社では、1on1ミーティングを通じた管理職と部下のコミュニケーション強化に取り組んでいます。
1on1ミーティングとは、毎週30分間ほど実施される上司と部下の1対1の面談であり、ヤフー株式会社はこの取り組みを通して、業務の進捗や成果・失敗を振り返りながら部下の気づきを促し、個人の能力を最大化させることを目指しています。
同社の1on1ミーティングの特徴として、「部下が主役」という点があります。上司からの一方的な指示や評価ではなく、部下自身が考え、気づきを得るためのサポートに重点を置き、また業務上の課題だけでなく、キャリアや成長に関する対話も重視しています。
この取り組みにより、部下の自律性と主体性が高まり、「指示待ち」ではなく自ら考えて行動する組織文化が醸成されるようになりました。
また、上司と部下の信頼関係が強化され、問題の早期発見や迅速な解決にもつながっています。
この事例から、管理職育成において「コーチング型のマネジメントスキル」を身につけさせることの重要性がわかります。部下の成長を支援して自律的な行動を促すスキルは、現代のマネジメントにおいて必要不可欠であると言えます。
事例③ 名港海運株式会社
名港海運株式会社では、業界の変化に対応できる管理職を育成するためのプログラムを実施しています。
取り組みとしては、中堅リーダー向けの「中核人材育成研修」と、部長・副部長クラス向けの「経営人材育成研修」という2段階のプログラムを展開しています。
特に経営人材育成研修では、経営視点の獲得と戦略的思考力の向上に重点を置き、座学だけでなく実際の経営課題に取り組むプロジェクト型学習も取り入れています。また、外部講師による最新の経営理論の学習と、社内の経営層によるメンタリングを組み合わせることで、自社のマインドやビジョンを色濃く反映させながら最新且つ最効率的の方法を取り入れる、「いいとこどり」の研修プログラムを策定できています。
これらのプログラムを通じて、参加者は自社の経営課題を深く理解し、さらに解決策をするための戦略的な視点を要請することができます。また、部門を超えた横方向のつながりも強化されるため、組織全体の連携を向上させる効果もあります。
この事例から、管理職育成においては「階層に応じた体系的なプログラム」と「実践的な学習機会」、そして何よりも「自社理解」が非常に重要であることがわかります。
管理職の育成は、人材開発やマネジメントのプロの力を借りるのがおすすめ!
一般社員の育成であれば自社だけで賄えるケースは多いですが、管理職の育成となると責任の範囲も大きく会社の将来を左右しうるため、経験やノウハウを豊富に有するプロの力を借りるのも視野に入れてみましょう。
人材開発やマネジメント研修を専門に行う企業は、豊富な事例や研究に基づき、自社の課題時状況や育成したい人材像やスキルに応じた多様なプログラムを提案してくれます。特に、忙しい担当者が社内で管理職研修や人事評価制度の整備まで手が回らない場合に、外部に依頼することで高い費用対効果が期待できます。
また、外部講師やコンサルタントの視点を取り入れると、自分たちだけでは気づけなかった課題を特定できる可能性も高まります。
さらに、社内だけに閉じこもっていると、世の中の最新トレンドや管理手法を取りこぼすリスクがありますが、外部パートナーを利用すれば、マーケットや他社事例を踏まえた最適な育成ロードマップを設計しやすいでしょう。
管理職として必要なスキルや経験値を早期に習得させたいのであれば、専門家との連携を検討することをおすすめします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 管理職に昇進した際、最も大きな「意識転換」として何が求められますか?
A: 「自分で成果を出す」というプレイヤー時代の成功体験から、「部下やチーム全体の成果を最大化する」というマネージャーとしての視点への切り替えが求められます。
Q2. 管理職が業務過多になり、「セルフマネジメント不足」に陥るリスクが高いのはなぜですか?
A: チームの課題やトラブルをすべて抱え込みがちであり、プレイングマネージャーとして現場の業務も担当することで、自身の成長や健康管理がおろそかになるからです。
Q3. 管理職の育成において、なぜ「経営視点を持たせる」ことが重要になるのですか?
A: 会社の長期的な方針や全社目標を念頭に置いて行動できるようになるためです。現場と経営の両面を踏まえた、高いレベルの判断ができるようになります。
Q4. 「部門横断プロジェクト」のマネジメントを経験させることの狙いは何ですか?
A: 自部署の利益を最大化させる部分最適の考え方から、他部門の利害や仕組みを理解した全社最適の視点へ思考の幅を広げさせることです。
Q5. 社内に管理職育成のノウハウがない場合、どうすれば効果的なプログラムを策定できますか?
A: 外部の専門家に相談し、最新のマネジメント理論や事例、プロのノウハウを取り入れることがおすすめです。自社特有のカルチャーと外部の知見を融合させましょう。
まとめ
本記事では、管理職に求められる能力や育成方法、さらには有効な事例と外部依頼のメリットまで解説してきましたが、いかがでしたか?
組織の中で管理職が果たす役割は、大きな経営視点と現場の声をつなぐ非常に重要な橋渡しのポジションです。ここに抜けや漏れがあると、せっかく優秀な人材を採用しても活かし切れず、組織の成果が伸び悩むことにもなりかねません。だからこそ管理職の育成は、今後の企業成長を実現するためのキーとなる非常に重要なテーマであると言えるのです。
近年は中間管理職やマネージャーの在り方や取り巻く環境も大きく変化しているため、従来のやり方だけでは通用しなくなる場面が増えています。
そこで、研修や他部署との連携、外部の専門家への相談など、多面的なアプローチを行うことで、管理職としての視座が高まり、チームや会社にとってより良い成果を生み出す土台が確立できるでしょう。
本記事の内容が、皆さんの悩みを解決する手がかりになれば幸いです。
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。