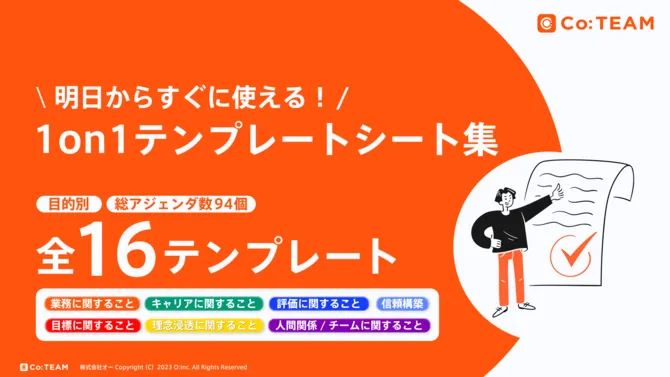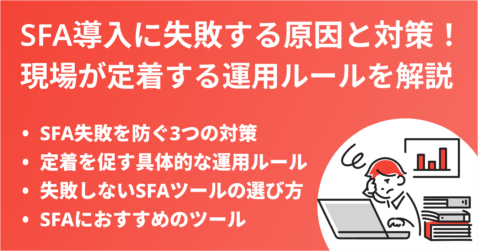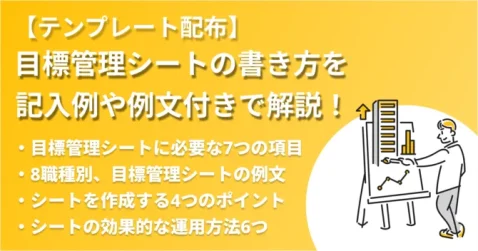企業が持続的に成長し、優秀な人材を確保するには、人事評価制度が不可欠です。人事評価とは、社員の成果やスキル、働き方を総合的に評価し、給与や昇進に反映させる仕組みです。評価基準や手法は企業ごとに異なりますが、適切に設計・運用すれば、社員のモチベーション向上や経営層による的確な人材配置に大きく貢献します。
本記事では、人事評価の代表的な種類と特徴を事例とともに解説します。公正で効果的な評価制度導入のヒントを得て、組織のパフォーマンス向上や社員のキャリア形成に役立ててください。
【全5職種対応・自動計算機能付き】
営業・事務・管理職など主要職種の評価項目例つき!
Excel / Googleスプレッドシートに対応し、そのまま使える人事評価テンプレートシートを無料公開中!
>>『人事評価のテンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!
▼ この記事の内容
- 評価の目的:報酬決定に加え、経営戦略の実現と人材育成に社員の行動を方向づけることです。 公正な評価を通じて社員のモチベーションやエンゲージメントを高め、企業が求める人材像を評価基準に組み込むことで、組織全体の目標達成を支援します。
- 4つの基準:結果を測る「業績」、行動特性を見る「行動」、スキルを見る「能力」、姿勢を見る「情意」です。 単なる成果(業績)だけでなく、プロセスの質(能力)や企業理念への共感度(情意)など、多角的な視点を取り入れることが納得感を生む鍵となります。
- 評価手法:MBO、OKR、360度評価、コンピテンシー評価など多様な手法が存在します。 コンピテンシー評価(優秀な人の行動を基準とする)や360度評価(多角的な視点)を導入することで、評価の客観性と公平性を高めることができます。
目次
人事評価制度とは?
「人事評価制度」は、従業員の業績や能力を評価し、その結果を給与や昇進、賞与などに反映させる仕組みです。しかし、その役割は評価にとどまらず、企業の経営戦略を実現するための重要な手段でもあります。特に、新しい戦略を実現するためには、従業員の行動や考え方を変えることが求められます。
評価制度は、成果評価(定量評価)を通じて具体的な業務内容を変革し、行動評価(定性評価)で日々の姿勢や取り組み方に変化を促します。これにより、従業員一人ひとりの行動を戦略に沿ったものへと導き、長期的には組織全体の価値観や文化の進化にもつながります。評価制度は、戦略実現に向けた行動を方向付け、企業成長を支える基盤となるのです。
>>【マネージャーの負荷削減と組織の生産性向上を実現】3分でわかる「コチーム」がわかる資料3点セットを無料でダウンロードする
人事評価を行う目的とは?
人事評価の目的は、従業員の成果や能力を適切に評価し、報酬やキャリア形成に反映するだけでなく、経営戦略を実現するために組織全体の行動を方向付けることにあります。成果評価によって業務プロセスを変革し、行動評価を通じて日々の姿勢や考え方を改善することで、従業員一人ひとりが企業の目標に沿った行動を取れるようにします。
また、公平で透明性のある評価は、従業員のモチベーションを高め、長期的な組織の成長に貢献します。評価制度を活用して従業員の行動変容を促し、戦略実現を支える仕組みを構築することが人事評価の本質的な役割と言えるでしょう。
適切な人事評価による効果
人事評価を行う目的を正しく理解し、適切な人事評価制度を運用することで、様々な効果が期待できます。
ここでは、適切な人事評価制度の運用による効果について、3つの観点からご説明します。
効果的な人材育成を行うことができる
適切な人事評価制度の運用による1つ目の効果は、「効果的な人材育成を行うことができる」です。
人事評価は、人材育成において欠かせない役割を果たします。目標設定やフィードバックを通じて、従業員は自身の能力と企業が求めるスキルや役割とのギャップを把握できます。その結果、不足している能力を認識し、キャリアプランを具体的にイメージしやすくなります。また、管理職にとっても、従業員の成長を支援する教育・育成プランを構築するための重要な情報源となります。
さらに、評価基準に基づいた適切なフィードバックを行うことで、従業員のモチベーションを高める効果が期待できます。評価が昇給や昇格といった具体的な結果につながることが従業員に明確に伝われば、自らの意識や行動を変え、評価向上に向けた努力を促進できるでしょう。
このようなプロセスを通じて従業員の能力が向上し、企業が求める人材育成を成功させることが期待できると同時に、従業員の仕事への意欲やエンゲージメントが高まり、キャリア形成の良いきっかけとなります。
適切な人員配置や処遇を決定できる
適切な人事評価制度の運用による2つ目の効果は、「適切な人員配置や処遇を決定できる」です。
人事評価を活用すれば、データをもとに、従業員一人ひとりの得意分野や経験、成果を把握し、客観的な基準に基づいて適切な配置が可能になります。特に、年功序列に頼らず個人の能力や実績を重視する傾向が強まる中で、評価制度は役職や責任を公平に割り当てるための重要な仕組みです。
例えば、評価結果を基に次世代リーダーを選定し、重要なポジションで経験を積ませることができます。また、埋もれていた優秀な人材を発掘し、適切な役職に登用することで、組織全体の活性化を図ることも可能です。
さらに、人事評価による公平な処遇決定は、従業員のモチベーション向上や不満の軽減につながります。明確な基準に基づく報酬や昇格の決定は、従業員の納得感を高め、人材の定着にも寄与します。
このように、人事評価は人材配置や処遇を現状維持ではなく成長を促す方向へと導く重要なものであると言えます。
従業員のモチベーションを高められる
適切な人事評価制度の運用による3つ目の効果は、「従業員のモチベーションを高められる」ことです。
人事評価が適切に行われ、従業員が評価に見合った処遇を受けられると、個々のモチベーションが高まります。特に、評価基準が明確で公平であるほど、従業員は納得感を得やすく、仕事に対する意欲ややりがいを見出しやすくなります。
近年では、キャリアプランの形成やワークライフバランスの充実といった要素が従業員のモチベーションに大きく影響しています。単に処遇を改善するだけでは十分ではなく、従業員が自身の成長や働きがいを実感できる評価制度の設計が求められています。
納得感のある評価を通じて、従業員は能力やスキルの向上を目指し、主体的に行動するようになります。その結果、組織全体の活性化につながり、企業の成長にも寄与します。
人事評価の4種類の基準
ここまでご説明してきたように、人事評価基準は適切な設定により様々な効果が期待でき、企業が従業員に対して公平な人事管理を実施するうえでは、不可欠なものといえます。
そして、この人事評価基準には、下記の4つの重要な評価があります。
- 業績評価(成果評価)
- 行動評価(コンピテンシー評価)
- 能力評価
- 情意評価
それぞれが、人事評価においてどのような役割を果たしているのか、詳しく見ていきましょう。
業績評価(成果評価)
人事評価における基準の1つ目は、「業績評価(成果評価)」です。
業績評価(成果評価)とは、数値で示すことができ、その成果をもとに評価されることを指します。具体的には、個人売上や営業の訪問件数などが業績(成果)項目に該当します。業績(成果)評価の項目を設ける際には、結果だけでなく、その結果に至った実態、プロセスも評価できるようにすることが重要です。そのため、「業績結果項目」と「業績プロセス項目」の2つに分けて設定することが推奨されます。
結果だけを重視すると、成果主義に偏った評価となり、従業員の成長や指導、育成につながりにくくなるというデメリットがあります。対して、結果に至るまでの行動や努力のプロセスを評価することで、従業員のスキル向上やモチベーションの向上が期待できます。
業績評価(成果評価)項目の具体例
業績評価(成果評価)項目の具体例としては、以下のような項目が挙げられます。
なお、先程ご説明したとおり、業績項目は「業績結果項目」と「業績プロセス項目」の2つに分けて設定することが効果的であるため、今回もその2つに分けてご紹介します。
業績結果項目
・個人売上高
・営業の訪問件数
・契約件数
・新規顧客獲得数
・コスト削減額 など
業績プロセス項目
・営業活動の実施頻度(例: 週次での顧客訪問回数)
・プレゼンテーションの質や回数
・問い合わせ対応の迅速さ
・チームでのプロジェクト進行度
・顧客フォローアップの実施状況 など
数値で表す項目を設定し、その評価においてウエイトを非常に高くしすぎると、プロセスを無視した結果主義の評価になってしまうため注意が必要です。また、通常、管理職には業績項目のウエイトを高く設定し、初級職には低く設定することでバランスを保ちます。
業績評価(成果評価)がおすすめのケース
業績(成果)評価がおすすめのケースはこちらです。
| おすすめのケース | メリット/理由 | 評価項目の具体例 |
|---|---|---|
| 会社の業績を向上させたい場合 | ・社員一人ひとりの成果を明確に評価することで、目標達成意識を高め、業績向上を促進できる ・数値に基づく評価基準は透明性が高く、公平な評価につながるため、社員の納得感を得やすい | ・業績結果項目:個人売上高、新規顧客獲得数、契約件数、コスト削減額 ・業績プロセス項目:営業訪問の実施頻度、プレゼンテーションの質と回数、顧客フォローの実施状況 |
| 社員の成長を促したい場合 | ・適度に高い目標設定を通じて、社員がチャレンジしながら実力を伸ばす機会を提供できる ・結果だけでなくプロセスを評価することで、社員のスキルアップや持続的なモチベーション向上につながる | ・業績結果項目:契約締結数、新規プロジェクト獲得数、売上目標達成率 ・業績プロセス項目:問い合わせ対応の迅速さ、顧客満足度に寄与する行動、チーム内での貢献度 |
行動評価(コンピテンシー評価)
人事評価における基準の2つ目は、「行動評価(コンピテンシー評価)」です。
行動評価(コンピテンシー評価)とは、仕事において優れたパフォーマンスを発揮する従業員の行動特性(コンピテンシー)を基準とした人事評価です。コンピテンシーをもとに、評価項目を設定して評価を行います。成果を出している人材の行動特性をもとに評価を行なうことで、同じように優秀な人材を育成することを目的としています。
優秀な人の態度や行動、価値観などの共通点を抽出し、それをもとに判断するという流れのため、評価の公平性を担保しやすいメリットがあります。
また、行動評価(コンピテンシー評価)の導入は、社員のパフォーマンス向上や適切なキャリアパスなどに効果的です。納得感のある人事評価制度の設計にもつながるため、社員がやる気をなくすのを防ぎ、効率的な人材育成を実現させることにも役立ちます。
行動評価(コンピテンシー評価)項目の具体例
行動評価(コンピテンシー評価)項目の具体例としては、以下のような項目が挙げられます。
- タイムマネジメント
- リスクテイクの判断
- 対人交渉能力
- 説明責任を果たす能力
- ストレス管理
こうした評価要素を踏まえることで、企業は社員に求める行動指針やスキルをより具体的に明示し、組織全体のパフォーマンスを底上げする効果が期待できます。評価項目を定義する際には、企業のビジョンや目指す組織風土を明確にし、それに即した行動指標を設定することが重要です。
行動評価(コンピテンシー評価)がおすすめのケース
行動(コンピテンシー)評価がおすすめのケースはこちらです。
| おすすめのケース | メリット/理由 | 評価項目の具体例 |
|---|---|---|
| 自社で必要な行動特性やスキルが可視化されている場合 | ・社員が成果を上げる際の行動特性やスキルが明確であれば、行動評価(コンピテンシー評価)を通じて、高いパフォーマンスを生む行動を促進できる ・成果だけでなく、その成果に至るプロセスを評価できるため、公平で納得感のある評価制度が構築できる | ・リスクテイクの判断力:適切なリスクを取りながら目標を達成する力 ・タイムマネジメント:期限内に業務を効率的に完遂する能力 |
| 次世代の人材育成を推進したいフェーズにある場合 | ・高業績者に共通する行動特性を全社に浸透させることで、若手や新入社員が具体的な行動基準を持ちやすくなる ・ノウハウを共有する仕組みとして機能し、次世代リーダーの早期育成を支援できる 評価項目の具体例 | ・対人交渉能力:チームメンバーや外部関係者と効果的に交渉を進めるスキル ・説明責任を果たす能力:自らの行動や判断を明確に説明し、他者を納得させる力 |
能力評価
人事評価における基準の3つ目は、「能力評価」です。
能力評価とは、実績を残すために必要な能力、知識、資格などに対する評価です。能力評価の項目は、従業員が業務で成果を出すための基礎的な力を養うために設定されます。例えば、営業活動においては、「顧客管理の徹底」が成果項目として求められることがありますが、これを達成するためには、問題点や課題を上司などに適切に報告・相談し、スケジュールを管理する能力が不可欠です。
ただし、能力があるだけでは評価の対象にはなりません。仕事の現場でその能力をどのように活用したか、具体的な成果や実行力が評価されます。例えば、スケジュール管理力があるというだけでなく、実際に漏れや遅れ、ミスがない形で仕事を遂行して初めて高い評価につながります。
能力評価項目の具体例
能力評価の具体的な項目例としては、以下のようなものが挙げられます。
| スケジュール管理力 | タスクの優先順位付け、納期の厳守、ミスや遅延の防止 など |
| 専門知識とスキル | 業務に必要な特定の知識、業界動向の理解、開発技術の習得 など |
| 資格 | 仕事に関連する専門資格の取得、法的または規制上の要件を満たすための資格取得 など |
| 人材育成力 | 部下や後輩への指導力、フィードバックの提供やコミュニケーションスキルなど |
| 問題解決能力 | 業務上のトラブルへの対処、課題の早期発見と対応策の提案、チーム内外の協力を引き出す力など |
これらの能力項目は、実際の業務に活かされることで初めて意味を持ちます。ウエイトを高く設定しすぎると、業務よりも自己学習や資格取得が目的となり、偏りが生じてしまう恐れがあるため、バランスの取れた評価が求められます。
能力評価がおすすめのケース
能力評価がおすすめのケースはこちらです。
| おすすめのケース | メリット/理由 | 評価項目の具体例 |
|---|---|---|
| 資格の有無によって担当できる業務が変わる場合 | ・資格取得が業務範囲の拡大や生産性向上につながり、組織全体の付加価値提供を促進できる ・資格を評価対象にすることで、その取得を目指す社員のモチベーションが向上し、優秀な人材の定着にもつながる | ・資格取得:国家資格(例:税理士、宅地建物取引士)や業務遂行に必要な専門資格の保有 ・法規遵守能力:資格を活かした法的・規制上の対応スキル |
| 社員の知識・技術・資格の習得を促進したい場合 | ・専門知識やスキルの強化が評価に直結するため、社員の学習意欲を高め、自己成長を促進できる ・専門スキルや知識の向上が、社員一人ひとりのパフォーマンスを底上げし、組織全体の成長につながる | ・専門知識とスキル:業界動向の理解、技術の習得度合い ・人材育成力:部下や後輩への適切な指導とコミュニケーション能力 |
| 成果が数値化しにくい職務の場合 | ・売上などの数値成果だけでは評価が難しい業務でも、必要な知識や技術を評価することで公平な評価が可能になる ・業務の重要な要素であるスキルやノウハウを評価基準とすることで、社員の努力が適切に報われる仕組みを構築できる | ・問題解決能力:課題の早期発見と対応策の提案力 ・スケジュール管理力:タスクの優先順位付け、納期遵守 |
【最小限の労力で最大限の成果を出す評価の作り方】
●負担を抑えつつ効果を出す人事評価制度の制度設計・運用方法
●人事専任の社員がいなくても成果につなげられる人事評価の制度設計方法
●被評価者の評価結果への納得、その後の成長を促す人事評価の運用方法
評価制度の構築から運用までの全てがわかる無料資料
>>「人事評価のプロが教える、「成果と満足度を両立させる評価」の制度設計・運用ガイドブック」はこちらから無料ダウンロード!
情意評価
人事評価における基準の4つ目は、「情意評価」です。
情意基準とは、従業員の仕事に対する姿勢や勤務態度における評価を指します。これはいわば、「会社が求める人間力」を評価する項目といえます。具体的には、仕事に対するやる気やチームワーク力、責任感の大きさ、遅刻の有無などが含まれます。情意評価の項目は、自社の社員としてふさわしいかどうかを判断する重要な基準であり、全社員がまずクリアすべき最低限の要件でもあります。
情意項目を評価する際には、「行動に落とし込んで初めて評価できる」という注意点を覚えておくことが重要です。例えば、「積極性」を評価する場合、単にその人が積極的であると感じるだけでは不十分です。「新しいことや経験のない仕事に自主的に取り組んだかどうか」といった具体的な行動基準を設定することで、主観が入り混じらない、客観的で明確な評価が可能になります。
また、情意項目の評価基準については、全社員が丸暗記するくらいの意識を持つことが理想的です。しかし、従業員が自主的にこれを実践するのは難しい場合もあります。そのため、定期的な読み合わせや確認を行い、評価基準の浸透を図るとよいでしょう。
情意評価項目の具体例
情意評価の具体的な項目例としては、以下のようなものが挙げられます。
規律性:業務規則の遵守、自己管理能力 など
責任性:タスクの完遂、ミスへの対応、業務への誠実さ など
協調性:チームとの連携、コミュニケーション力、問題解決の協力 など
積極性:自己啓発への取り組み、新規提案、挑戦意欲 など
情意評価は、職場の風土や文化に大きな影響を与えます。特に共同作業が求められる環境では、これらの項目が重要視されるべきです。従業員一人ひとりの姿勢が職場全体の雰囲気や生産性に大きく影響するため、情意項目を適切に評価することは、健全な企業文化の維持・発展に欠かせません。
情意評価がおすすめのケース
情意評価がおすすめのケースはこちらです。
| おすすめのケース | メリット/理由 | 評価項目の具体例 |
|---|---|---|
| 社会人としての基本姿勢に課題を感じる職場環境 | ・「遅刻が多い」「モチベーションが低い」など、基本的な勤務態度に課題がある場合、情意評価を導入することで、従業員の仕事に対する姿勢を改善できる ・情意評価を給与や昇格に反映させることで、社員に具体的な改善目標を与え、モチベーション向上を促せる | ・規律性:時間厳守や業務規則の遵守 ・責任性:タスクの完遂度やミスへの適切な対応 |
| 「思い」や「熱意」を重視した評価制度を導入したい場合 | ・能力や成果だけでなく、社員の情熱や企業理念への共感といった定量化が難しい側面を適切に評価できる ・情意評価を通じて、組織への共感度や前向きな姿勢を評価することで、社員のモチベーションを高め、組織全体の結束力向上が期待できる | ・協調性:チーム内での連携力、問題解決に向けた積極的な協力姿勢 ・積極性:新規提案への意欲、自己啓発への取り組み |
人事評価手法の種類
ここでは、最新の人事評価手法についてご紹介します。
今回ご紹介する手法は下記の6種類です。
- コンピテンシー評価
- MBO(目標管理制度)
- OKR(目標と成果指標)
- 360度評価
- バリュー評価
- ノーレイティング
それぞれの評価方法と特徴について、以下にご説明します。
MBO(目標管理制度)
MBO(目標管理制度)とは、「Management(管理)by Objectives(目的)」の頭文字をとったものであり、従業員自身が組織目標とリンクした個人目標を決め、その進捗状況や達成状況に応じて評価する制度のことを指します。
MBO(目標管理制度)のメリットとしては、自己管理によるマネジメントが可能になることや、従業員のモチベーションが向上することが挙げられます。従業員は自分で自分の仕事を管理するため、決定した目標を達成するために強い責任感のもと、自主的かつ自律的に行動することが期待されます。
また評価に対する納得度が高いという点もMBO(目標管理制度)の特徴です。従業員の目標達成は、同時に企業側の目標達成にも通ずるため、両者がともに成長していける評価制度と言えます。
MBO(目標管理制度)がおすすめのケース
MBO(目標管理制度)がおすすめのケースはこちらです。
| おすすめのケース | メリット/理由 | 評価項目の具体例 |
|---|---|---|
| 企業全体の目標と個人の目標をしっかり連動させたい場合 | ・組織のビジョンや戦略目標を具体的な数値や指標に落とし込み、各従業員がそれを個人目標として設定することで、企業全体と個人の方向性を一致させやすくなる ・目標設定と達成が組織全体の成長に直結するため、従業員の仕事に対する意識と責任感が向上する | ・売上や利益目標の達成率 ・プロジェクト完遂率とその品質 |
| 社員の主体性や自律性を高めたい場合 | ・従業員自身が「何をどのように達成するか」を具体的に考えて目標を設定するため、自律的な行動が促され、主体性が向上する ・目標達成に向けた努力が社員のスキルアップやモチベーション向上につながり、組織全体の生産性も底上げされる | ・新規提案の実施件数とその実現度 ・業務改善の取り組み成果 |
| 評価の透明性と納得感を重視したい場合 | ・目標設定から結果評価までのプロセスが明確になるため、評価の公平性と透明性が向上し、従業員の納得感を得やすい ・上司との定期的な面談で進捗状況や課題を共有するため、評価に対する誤解が減り、信頼関係が強化される | ・目標進捗状況の共有回数(上司との面談記録) ・定期的な進捗レビューでの目標修正の適切さ |
【目標設定・目標管理の全解説!】
●効果的な目標設定のやり方
●マネージャーの負担にならない目標管理のやり方
●効果が出る目標管理の実践方法
●米国最先端の目標管理
など目標設定・目標管理について徹底解説した無料資料
>>「170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド」はコチラから無料ダウンロード!!
OKR(目標と成果指標)
OKR(目標と成果指標)とは、「Objectives(目標)and Key Results(主要な結果)」の頭文字をとったものであり、大きな目標とその達成を測るための具体的な指標を設定し、評価する手法です。企業が目指すべき目標と社員個人の目標をリンクさせ、すべての社員が一丸となって同じ方向を向き重要課題に取り組むことを目的としています。
特徴は、個人と企業の目標をリンクさせて、目標設定・進捗確認・評価という一連の流れを高い頻度で行う点にあります。OKR(目標と成果指標)は、社員および企業全体がモチベーションをアップさせるために、「容易には達成できない高い目標」を掲げ、達成率が60〜70%程度となるのが理想とされています。
組織と従業員の目標に関連性を持たせ、進捗確認や成果に対する評価を頻繁に実施することで、一体感をもって計画的に業務を推進できるというメリットがあります。
OKR(目標と成果指標)がおすすめのケース
OKR(目標と成果指標)がおすすめのケースはこちらです。
| おすすめのケース | メリット/理由 | 評価項目の具体例 |
|---|---|---|
| 企業ビジョンや戦略を迅速に現場へ浸透させたい場合 | ・「高い目標(Objective)」と「具体的な成果指標(Key Results)」をシンプルに設定することで、経営層から現場までの目標を一貫して共有しやすくなる ・組織全体が同じゴールを目指しやすくなり、企業ビジョンの浸透が加速する | ・部門別目標の達成度:企業戦略に基づくKPI(例:売上成長率、顧客満足度向上) ・個人目標の貢献度:チームの目標達成に寄与した具体的成果 |
| 変化の速い市場や環境に対応したい場合 | ・四半期や月単位で目標を設定・見直すことで、柔軟な対応が可能になり、環境の変化に迅速に適応できる ・短期的な目標管理がイノベーションを生むきっかけを作り、競争力を高める | ・OKRの達成進捗率:短期目標(例:新製品リリース、マーケットシェアの拡大) ・適応力:市場変化に応じた新戦略の実行度 |
| └チーム間の連携を強化したい場合 | ・OKRを全社的に公開し、誰がどの目標を追っているのかを見える化することで、部門やチームを超えたコラボレーションが促進される ・目標の重複や認識のズレを防ぎ、業務の効率化と成果の最大化を実現する | ・部門横断プロジェクトの進捗と成果(例:共同キャンペーンの実施率) ・他チームとの連携度(例:コラボタスクの達成率) |
【OKRについて徹底解説!】
会社の目標でOKRを導入したいけど、どのように導入・運用すれば良いかわからない。そもそもOKRって何なのか?などのお悩みをマルッと解決いたします!
OKRの導入から運用まで成功までの道のりを完全解説した資料!
>>『売上を劇的に高める米国最先端の戦略実行手法「OKRパーフェクトガイド」』はコチラから無料でご覧いただけます!
360度評価
360度評価とは、関係する複数の従業員が評価者となり、評価対象者を多面的に評価する制度のことを指します。上司や人事担当者など上の立場の人からだけでなく、部下や同僚なども評価者に含まれます。
公正な評価のためには、多面的な視点を取り入れ、偏りを防止することが重要です。1人の評価者による評価の場合、評価者の主観やバイアスが評価に影響を与えることで、公平性が保たれなく恐れがあります。
それに対して、360度評価では、多くの人が評価に関わるため、客観性が担保されて公正な評価になりやすい仕組みであると言えます。評価対象者にとっても納得しやすい評価となるのでモチベーションの維持向上にもつながるでしょう。
ただし、「従業員数が少ないと誰が評価者かわかってしまう」「全評価者の情報を集約しなければならない」「評価者間で馴れ合いが生じる場合もある」などのリスクが考えられるため、注意が必要です。
360度評価がおすすめのケース
360度評価がおすすめのケースはこちらです。
| おすすめケース | メリット/理由 | 評価項目の具体例 |
|---|---|---|
| 上司単独の評価エラーを防ぎたい場合 | ・上司のみの評価ではバイアスや見落としが生じるリスクがあるが、360度評価では同僚、部下、他部署の関係者など複数の視点を取り入れることで、より公平で客観的な評価が可能になる ・多面的なフィードバックを受けることで、評価対象者も自身の強みや課題を幅広く把握し、成長のヒントを得られる | ・リーダーシップ:部下への適切な指導や目標達成への貢献度 ・対人スキル:同僚や他部署との連携力、円滑なコミュニケーション |
| 風通しの良い組織を作りたい場合 | ・社員同士が互いの仕事ぶりを評価し合うことで、オープンなコミュニケーション文化を促進できる ・フィードバックを通じて、心理的安全性が高まり、率直な意見交換が活発になることで、職場環境の改善や協働の促進が期待できる | ・協調性:チームメンバーへの貢献度や柔軟な対応力 ・問題解決能力:業務上の課題への対応策や改善提案の実施状況 |
バリュー評価
バリュー評価とは、企業が設定した価値観を基準に社員の行動を評価する方法です。企業が定めた行動規範や価値観に基づいて業務に取り組み、それをどの程度実践できているかを見極めることで、組織が大切にしている文化や考え方を社内に浸透させやすくなります。
従来の年功序列や成果主義とは異なり、バリュー評価では仕事の結果だけでなく、結果に至る過程や行動そのものを重視します。社員が企業の価値観を意識しながら行動する機会が増えるため、考える力や行動力を育む効果が期待できます。また、共通のバリューを意識することで、組織としての一体感やブランド力の強化につながります。
一方で、バリュー評価には定量的な評価が難しいというデメリットも存在します。社員の行動を客観的に判断するための指標を設けにくく、評価者の主観や印象に左右されやすいというリスクがあるのです。
公平性を保つためには、事前に明確な評価基準を定めるだけでなく、複数の評価者による多面的なフィードバックを行うなど、運用面での工夫が求められます。
バリュー評価がおすすめのケース
バリュー評価がおすすめのケースはこちらです。
| おすすめのケース | メリット/理由 | 評価項目の具体例 |
|---|---|---|
| 掲げているバリューの実践度を高めたい場合 | ・企業が掲げる価値観や行動規範を社員全体に浸透させることで、組織の一体感が高まり、企業文化がより強固なものになる ・成果評価だけでは捉えられない、業務に対する姿勢やプロセスを評価することで、行動力や考える力を養う効果が期待できる | ・チームワークの実践:同僚との連携や相互支援の質 ・顧客重視の姿勢:顧客ニーズを理解し、価値ある提案を行った行動 |
| 成果評価だけではカバーしきれない行動を評価したい場合 | ・目に見える業績以外の、組織を支える行動や価値観の実践度を評価でき、社員の成長を多角的に捉えることができる ・行動そのものに焦点を当てることで、短期的な成果だけではなく、長期的な人材育成にもつながる評価が可能となる | ・問題解決に向けた行動:課題を迅速に発見し、解決に向けた具体的なアクションを取ったか ・変革への貢献:組織改革や業務効率化への積極的な取り組み |
ノーレイティング
ノーレイティングとは、等級や階級による評価(レイティング)を行わない人事評価制度のことを指します。この制度では、従業員に「A」評価、「B」評価といったランクを付ける代わりに、頻繁にフィードバックを行い、その都度評価を積み上げていくことで目標の軌道修正を行います。
ノーレイティングは、評価者と被評価者の対話を重視しており、相互のコミュニケーションが活発化する特徴があります。常に認識をすり合わせているため、双方が納得できる評価が可能となります。また、細かい評価項目が固定されていないため、環境の変化に柔軟に対応できる評価制度とされています。
ノーレイティングがおすすめのケース
ノーレイティングがおすすめのケースはこちらです。
| おすすめのケース | メリット/理由 | 評価項目の具体例 |
|---|---|---|
| 定量的なスコア付けでは評価しにくい職務や業務内容が多い場合 | ・クリエイティブ職やコンサルティング職など、成果が数値化しにくい業務では、質的な成果やプロセスを重視できるノーレイティングが適している ・定量評価の代わりに継続的なフィードバックを行うことで、成長度合いや業務プロセスの質に焦点を当てられる | ・クリエイティブ職:新しいアイデアの提案数、クライアント満足度 ・コンサルティング職:課題解決提案の実効性、顧客との信頼構築の深さ |
| 社員同士の協力やイノベーションを重視したい場合 | ・スコアリング制度のような競争を煽る仕組みを廃止し、協力的な組織風土を醸成できる ・継続的なフィードバックやコーチングを通じて、社員間のコミュニケーションが活性化し、新しいアイデアやイノベーションを生み出しやすくなる | ・チームプレイ:チームメンバーへの貢献度、プロジェクト全体への協力姿勢 ・イノベーション:新規プロジェクトへの取り組み、新しい手法の提案と実行 |
人事評価の具体例
ここまでご説明してきた人事評価の種類を踏まえ、ここでは人事評価の具体例をご紹介します。
今回ご紹介する例は、下記の3つです。
例1. 一般的な人事評価の構成
例2. 行動評価(コンピテンシー評価)を加え、役職によるウエイトを考慮した場合
例3. 360度評価を加えた場合
例1. 一般的な人事評価の構成
営業職の場合:
| 評価項目 | 評価項目の具体例 | ウエイト |
|---|---|---|
| 業績(成果)評価 | ・売上目標達成率 ・新規顧客獲得数 | 70% |
| 情意評価 | ・顧客対応の迅速さ ・チーム内での協調性 | 70% |
この構成では、業績評価を重視しつつ、情意評価で補完する形を取ることで、目に見える成果と行動プロセスの両方をバランス良く評価します。また、評価結果を「等級制度」とリンクさせることで、キャリアステップや報酬に直結しやすい仕組みとなっています。このようなシンプルかつ分かりやすい構成は、多くの企業で採用される理由にもなっています。
例2. 行動評価(コンピテンシー評価)を加え、役職によるウエイトを考慮した場合
【役職:初級職(一般社員)】
| 評価項目 | 評価項目の具体例 | ウエイト |
|---|---|---|
| 業績(成果)評価 | ・目標達成への努力や行動プロセス ・業務達成率 | 40% |
| 情意評価 | ・チーム内での協調性 ・勤務態度の安定性 | 40% |
| 行動(コンピテンシー)評価 | ・自己成長に向けた学習意欲 ・新しい業務への積極性 | 20% |
【役職:中級職(主任・リーダークラス)】
| 評価項目 | 評価項目の具体例 | ウエイト |
|---|---|---|
| 業績(成果)評価 | ・チーム目標の達成率 ・指導力や指示出しの適切さ | 50% |
| 情意評価 | ・部下や同僚との信頼関係構築 ・職場全体の雰囲気づくりへの貢献 | 50% |
| 行動(コンピテンシー)評価 | ・業務改善提案の実施 ・部下のスキルアップへの貢献 | 20% |
【役職:管理職(マネージャー以上)】
| 評価項目 | 評価項目の具体例 | ウエイト |
|---|---|---|
| 業績(成果)評価 | ・部門全体の目標達成率 ・予算管理の正確さ | 60% |
| 情意評価 | ・組織全体の連携促進 ・部下のモチベーション向上の取り組み | 20% |
| 行動(コンピテンシー)評価 | ・長期的視点での戦略提案 ・新規事業の推進力 | 20% |
このように、多面的に社員のパフォーマンスを捉えられるため、レイヤーごとの役割や成長度合いをよりきめ細かく把握しやすくなります。また、役職によるウエイト設定を行うことで、各階層に応じた目標や行動特性を評価に反映しやすいという特徴があります。
例3. 360度評価を加えた場合
| 評価項目 | 評価項目の具体例 | ウエイト(部下評価を含む) |
|---|---|---|
| 業績(成果)評価 | ・売上目標達成率 ・新規顧客獲得数 | 60% |
| 情意評価 | ・顧客対応の迅速さ ・チーム内での協調性 | 30% |
| 行動(コンピテンシー)評価 | ・問題解決に向けた行動 ・リーダーシップの発揮度 | 10% |
360度評価を導入した場合、上司からの評価だけではなく、部下や同僚など複数の視点を取り入れることで、評価の客観性と透明性を高めることができます。この例では、部下からの評価を業績評価と情意評価のそれぞれに10%組み込む形を採用しています。これにより、評価対象者が上司や顧客だけでなく、部下との関係性やリーダーシップの発揮具合も評価対象となります。
効果的な目標管理・納得度の高い人事評価なら「Co:TEAM(コチーム)」

- 1on1をしながら、目標の進捗を入力できる!
- 目標の結果を人事評価に反映!
- 目標の進捗・結果を全て見える化!
- 1on1の記録を人事評価時に活用できる!
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 人事評価を行う「本質的な目的」は何ですか?
A: 処遇の決定に加え、企業のビジョン実現に向けて「社員の行動を方向づける」ことです。 評価基準に企業理念やビジョンを反映させることで、社員は何をすべきか、会社が何を期待しているかを理解できます。これにより、社員の意識統一と成長が促されます。
Q2. 業績評価、能力評価、情意評価の3つの違いを簡単に教えてください。
A: 業績は「結果(数字)」、能力は「スキル(知識)」、情意は「態度(姿勢)」を測ります。 業績は売上達成率、能力は問題解決力、情意は協調性や規律性といった項目を評価します。これらを組み合わせることで、成果とプロセスの両方を評価できます。
Q3. 最近話題の「OKR(目標と成果指標)」の特徴は何ですか?
A: 容易には達成できない高い目標(ストレッチ目標)を掲げることです。 達成率60〜70%を理想とし、社員の挑戦意欲を引き出します。目標設定や進捗確認を高い頻度で行い、組織と個人の目標を密接に連動させる仕組みです。
Q4. 「360度評価」は、どのような企業や目的におすすめですか?
A: 組織の風通しを良くしたい企業や、リーダーシップを育成したい場合に有効です。 上司だけでなく、同僚や部下など複数の視点から評価することで、上司一人の主観による評価エラーを防ぎ、客観性と公平性を高める効果があります。
Q5. 評価制度を作った後の、運用の鍵となるものは何ですか?
A: 評価者教育と、評価基準の「定期的な見直し」を継続することです。 市場環境や経営戦略が変われば、評価制度も古くなります。社員の納得感や市場の変化を踏まえて、柔軟に制度を改善していく姿勢が重要となります。
まとめ
この記事では、人事評価の種類について、それぞれの基準や手法のポイントを具体例を交えてご解説してきました。
人事評価制度は、一度作成して終わりではなく、実際に運用を進めるなかで現場の課題や改善点が見つかるものです。そのため、評価基準を含めた人事評価制度を継続的にアップデートし、より精度の高い仕組みへとブラッシュアップしていくことが重要になります。
こうした改善を通じて、社員が納得できる「客観性」や「公平性」を担保しつつ、組織全体のモチベーション向上につながる評価制度を構築することができます。ぜひ本記事を参考に、自社に最適な人事評価基準の設定や、今後の運用・改善に取り組んでいただければ幸いです。
【全5職種対応・自動計算機能付き】
営業・事務・管理職など主要職種の評価項目例つき!
Excel / Googleスプレッドシートに対応し、そのまま使える人事評価テンプレートシートを無料公開中!
>>『人事評価のテンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。