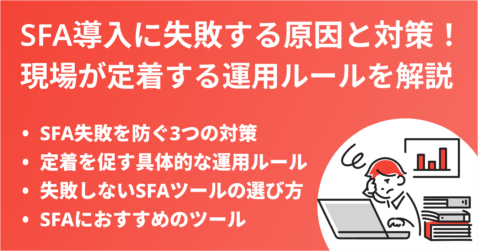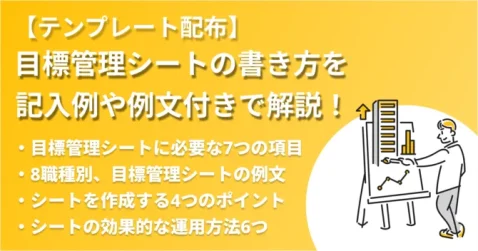人事制度は、会社で働く全ての従業員に関わる制度であるため、手軽に見直したり、修正する事が難しいという特徴があります。
したがって、人事制度を設計する際には、施工後の従業員の納得感やこれまでの人事プロセスとの整合性を考慮した慎重な設計が求められています。
本記事では、人事制度の設計方法について、その種類・目的導入の手順や注意点を網羅的に、詳しく解説します。
【最小限の労力で最大限の成果を出す評価の作り方】
●負担を抑えつつ効果を出す人事評価制度の制度設計・運用方法
●人事専任の社員がいなくても成果につなげられる人事評価の制度設計方法
●被評価者の評価結果への納得、その後の成長を促す人事評価の運用方法
評価制度の構築から運用までの全てがわかる無料資料
>>「人事評価のプロが教える、「成果と満足度を両立させる評価」の制度設計・運用ガイドブック」はこちらから無料ダウンロード!
▼ この記事の内容
- 3つの要素と目的:等級、評価、賃金の3つを連動させ、経営戦略の実行を目指します。個人のモチベーション向上、チームの戦略実行、企業全体の成長を目的とし、採用から定着までの各フェーズで一貫性のある制度設計が求められます。
- 設計の全体手順:まず「方向性を定める」ことから開始し、制度の設計、シミュレーション、運用へと進みます。 最初に経営方針と理想の人材像を明確化します。次に等級、評価、賃金、昇格などの制度を順に設計し、法的チェックとコストシミュレーションを経て、現場での運用・改善に着手します。
- 成功の注意点:制度が複雑すぎないか、経営方針に合致しているか、社員の納得感が得られるかが鍵です。 評価基準は具体的かつ客観的に設定し、相対評価ではなく「絶対評価」を保証することで納得感を高めます。プロセス評価も導入し、社員の育成を前提とした制度にしましょう。
目次
人事制度の要素
人事制度を設計する方法を知る前に、人事制度を構成する要素の認識が必要です。
人事制度の要素は以下に示す3つがあります。
等級制度
1つめは等級制度です。
等級制度は人事制度の骨格ともいわれ、その目的は能力、職務、役割ごとに人材を序列化し、業務を遂行する際の権限や責任、さらには処遇などの根拠となる制度です。
組織として、重視する内容によって主に3つの制度があります。
- 能力等級制度(メンバーシップ型)
- 職務等級制度(ジョブ型)
- 役割等級制度(ミッショングレード制)
制度導入にあたって、目的や各制度のメリットを踏まえ、適切な制度を導入しましょう。
評価制度
2つめは評価制度です。
評価制度には主に以下の3つがあります。
- 業績評価
- 能力評価
- 情意評価
重視すべき評価項目を明確にすることで社員が業務に当たる際に重視する事項が明瞭になります。
経営方針に沿った制度を慎重に選択しましょう。
賃金制度
3つめは賃金制度です。
賃金制度は社員にとって直接的なリターンを得られる重要な項目です。
社員の貢献度や成長度に応じて適切な報酬を払う必要があります。
また、等級や役職によって配分の仕方が変わるなど複雑化しやすい部分ですが非常に重要な制度と言えます。
賃金の内訳には、
- 基本給
- 手当
- 賞与
- 退職金
があります。
【全5職種対応・自動計算機能付き】
営業・事務・管理職など主要職種の評価項目例つき!
Excel / Googleスプレッドシートに対応し、そのまま使える人事評価テンプレートシートを無料公開中!
>>『人事評価のテンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!
人事制度の目的
人事制度設計には、組織内のスケールごとの目的があります。
スケールの小さい順に、従業員個人への目的、チームへの目的、そして企業全体への目的です。
本パートではそれぞれのスケールでの重要なポイントについて紹介します。
社員のモチベーションの維持・向上
1つめの個人スケールでの目的は社員のモチベーションの維持・向上です。
人事制度を設計することで企業が求めている理想的な人材像が明確にされます。
それによって、社員がどこに注力すべきかがわかり、かつ昇給や昇格といったリターンへの直接的なアプローチが可能となるためにモチベーション向上に繋がります。
経営戦略の実行
2つめのチームスケールでの目的は経営戦略の実行です。
社員のモチベーションの維持・向上によって社員全体が同じベクトルで業務に取り組むことができ、会社全体でみたときに経営層の意図に沿った業務が可能となります。
その結果、経営戦略を社員全体に人材像として伝えられ、それに沿った報酬体系を準備できるようになります。
企業の成長
3つめの企業スケールでの目的は企業全体の成長です。
経営戦略の実行が可能なことにより、業績という点で企業の成長が促進されやすくなります。
企業の成長が進むと、実際に業績を出している社員や会社の理想の人材像に当てはまっている社員に報酬が与えられるために成長に直接関与できている実感がわくのです。
人事制度の設計方法・手順
ここまでは人事制度を構成する要素と目的について述べてきました。
実際に設計するにあたってどのような手順をとればよいのでしょうか。
本パートでは、人事制度の設計方法とそれらの順序を解説していきます。
方向性を定める
最初にやるべきことは、人事制度設計の方向性を定めることです。
方向性を決定づける具体的な項目は、経営方針との合致、理想的な人材像の決定です。
これらが的確に行われないと、経営方針や全社的な目標と制度が合致せず効果が低くなってしまいます。
現状を把握する
次にやるべきことは、社内の現状を把握することです。
従業員からのヒアリングをまとめ、自社が抱える人事上の課題を明確にしましょう。
周囲の状況を把握する方法としてヒアリングはとても効果的です。
抱えている課題を明確にすることで、より効果的な方法で課題を解決できます。
等級制度を設計する
3番目にやることは、等級制度を設計することです。
等級制度の選定は自社の組織風土や経営方針に合わせて適切な等級制度を選びましょう。
不適切な等級制度を導入してしまうと、組織の規模が拡大したときに社内の序列付けができず、組織全体の運営が円滑にならない事態に陥ってしまいます。
将来的な組織構築なども視野に入れて選定しましょう。
評価制度を設計する
4番目は評価制度の設計です。
評価制度の設計では、等級制度や求める人材像、組織風土に基づいて評価制度・評価手法・具体的な評価項目などを決定していきましょう。
評価制度を曖昧にしてしまうと、評価基準が不明瞭なので報酬に反映される明確な基準がわからないために、社員のモチベーション低下へ繋がります。
賃金制度を設計する
5番目にするのは賃金制度の設計です。
社員のモチベーションの要とも言える制度です。
社内外の要因を総合的に考慮し、等級や評価制度で決まった評価基準を給与や報酬に反映できる制度にしましょう。
賃金制度を不明瞭なものにしてしまうと、賃金の増減の基準が明確にならず、人件費の過度な増加にとってとどまらず社員の不満が蓄積してしまいます。
昇格制度を設計する
6番目では昇格制度を設計しましょう。
通常のキャリアプランだけではなく、ハイパフォーマーに対して飛び級昇格の制度も準備しておくと良いでしょう。
小刻みな昇格のみでは大きなモチベーションは生まれません。
ハイパフォーマーに対して的確に対応するためにも広いキャリアパスが展開できるように設計しましょう。
人材育成・開発・福利厚生を定める
7番目の手順では人材育成・開発・福利厚生を決めます。
人材育成・開発に関する細かい制度や手法を定めると同時に、会社や社員に必要な福利厚生の具体的な部分を定めましょう。
企業として人材育成・開発:全社的な人材育成の基準や方針が一致していないと、効率的な人材育成はできません。
社員のライフワークバランスを重視する観点から福利厚生の整備も必須です。
福利厚生の整備をないがしろにしてしまうと具体的な運用に統率がとれません。
明文化し、法的チェックを行う
8番目のステップは法的チェックです。
これまでの7ステップの内容を明文化して法律の専門家に内容をチェックしてもらいましょう。
この工程を飛ばし、万が一、制度確立後に法的問題が見つかってしまうと、制度の修正は余儀なくされ、大幅なコストをともないます。
シミュレーションを行う
9番目はシミュレーションの実施です。
設計した人事制度に基づき、人件費や人材育成・福利厚生へのコストの変化などを長期的な視点からシミュレーションをして、問題がないかチェックしましょう。
シミュレーションをせずに運用してしまうと、事前に解決できたはずの課題を残したままにしてしまいます。
設計した人事制度によってはコストが大きくかかり、経営を圧迫する事態になってしまい長期的に運用することは困難となります。
運用・改善を行う
最後となる10番目は制度の運用・改善です。
実際に社内での運用を開始し、社員からのフィードバックやデータを収集することで改善点をみつけ、改善に着手していきましょう。
フィードバックを無視したり、改善点を放置して適切でない制度を運用し続けてしまうと、社員の不満感が高まり、モチベーションの低下に繋がります。
人事制度設計のポイント・注意点
本パートでは、工程を進めるにあたって注意点はどのようなものがあるのかを7つ解説します。
経営方針に合っているか
1つめの注意点は、経営方針との合致です。
会社が目指すべき方向を社員レベルに落とし込んだときに人事制度が乖離していないかという点に重点を置きましょう。
経営方針と制度のベクトルを合わせることによって会社レベルから個人レベルまで統一感のある経営ができます。
社員の納得感が醸成できるか
2つめのポイントは社員との意志統合です。
社員から賛同が得られておらず、報酬が成果や努力と見合っていない場合、社員の納得感の醸成に時間がかかるどころか制度の制定が困難になってしまいます。
社員と反発した状態で運用に移ってしまうと、社員のモチベーションが低下し、離職の増加につながってしまいます。
会社のフェーズに合っているか
3つめは会社のフェーズとの照らし合わせです。
自社が現在成長させるべき段階なのか、安定させるべき段階なのかによって導入すべき人事制度は変わってきます。
自社の規模や段階をふまえて導入する制度を決めましょう。
会社のフェーズに合っていない制度を導入してしまうと、人事制度がうまく機能せず、期待される利益が出なかったり、全体の生産性が落ちてしまいます。
社会環境に合っているか
4つめの注意点は社会環境と合っているかへの注意です。
現在求められている働き方改革やダイバーシティに対応する制度となっているか、業界の成熟度や傾向をふまえて制度設計ができているかに着目しましょう。
社会環境に対応していることを対外的にアピールできることで優秀な人材を確保する一助となります。
人材育成を考えられているか
5つめは人材育成制度のチェックです。
形骸化せず、現場レベルでの理解・運用可能な人材育成の制度になるかを確認しましょう。
現場のニーズに合わない人事制度を導入してしまうと、人材育成がうまくいかず、次の世代の管理職・幹部候補が育たないために長期的な会社の成長が見込めなくなってしまいます。
制度の内容が複雑すぎないか
6つめは制度全体の確認です。
制度は明文化するだけではなく、会社の人間全員で共有するものです。
人事制度が現場の社員全員に理解可能なものにするために体系化・具体化しましょう。
適切に共有されなかったり現場の社員が理解できないと、人事制度が部分的に形骸化してしまったり、期待された効果が得られなかったりします。
ノーレイティングの導入も考慮する
ノーレイティングとは、社員の評価においてランクをつけない評価制度のことを指します。
その時々に応じた目標設定をして随時フィードバックを行うというものです。
ノーレイティングのメリットは企業を取り巻く環境の変化が激しい場合、目標達成からフィードバックの早いサイクルに非常に有効な点です。
一方、デメリットとして、評価者の負担が増加し、かつ導入時の混乱も含むコストがかかることが挙げられます。
人事評価制度の評価手法
では、具体的に人事評価を行う上での評価手法にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは5つの評価手法についてそれぞれの特徴と併せて、メリットとデメリットを説明します。
1. MBO
“Management by Objectives”(目標管理制度)の略で、個人あるいはチームごとに目標を設定し、それに対する達成度合いなどで評価を決める制度です。
この制度は経営学者、ピーター・ドラッカーが提唱した概念です。
企業の方針と個人の業務の方向性の合致が可能なのが大きな特徴といえます。
自身の目標について社員自身と上司ですり合わせをしながら決めていく、上から押し付けられるノルマとは異なり、社員が自ら目標を設定するので、主体的な行動に繋がります。
メリットとしては個人の目標と会社の動きがリンクすることによるモチベーションの向上が図れる点が挙げられます。
一方、デメリットとしては達成しやすい目標ばかり設定すると、目標の難易度がバラバラになり、人事評価として機能しなくなるということです。
2. OKR
“Objectives and Key Resuts”(目標と主要な結果)の略です。
他の目標管理や計画方法と比べて高頻度で設定、追跡、再評価をする(チェックインミーティングで細かく進捗の確認を行う)評価手法です。
OKRは人事評価制度として以下2つの特徴があります。
- 全社員が同じベクトルで明確な優先順位の元、ペースを保って進める
- 定量的に測定できる評価基準を用いる
そのメリットは、高い頻度で目標の設定、追跡、再評価を行うのでフレキシブルに目標設定が可能で社員のエンゲージメント向上に寄与するということです。
デメリットとして挙げられるのは、短期間で目標や評価を行う必要があるために業務負担が増え、人的、時間的コストがかかることです。
3. 360度評価
360度評価とは、上司だけでなく、評価対象者の同僚や部下など仕事上で関係を持つ多方面の社員が人事評価をする制度で、多面評価ともいわれます。
従来の評価制度では上司が部下を評価する制度が一般的でしたが、この評価手法は様々な角度から対象者を評価できます。
メリットとして、上司だけでなく、近しい同僚や慕っている先輩からの評価が含まれるので納得感を高められます。
デメリットは評価のほとんどが周囲の人間からのものなので、主観が評価に影響する可能性が高いことです。
4. コンピテンシー評価
コンピテンシー評価は会社が職務や部署ごとに定義した行動特性(コンピテンシー)を基準に評価を行う人事評価手法です。
この評価手法では社員の持つスキルそのものではなく、持ちうる技術や知識をどのように活用して行動したかに焦点を当て、以下のような具体的な行動傾向(コンピテンシー)について着目します。
- 効率的な業務構築ができる
- 周囲の人との親和性がある
- 相手の意見を受け入れられる
- チームの一体感を醸成できる
評価者の目につく部分に評価の重きが置かれるので、高い業績を上げる人材の行動特性が基準となる特徴があります。
メリットは、高いパフォーマンスを発揮している社員の行動を基準に評価するため、お手本と言える社員が明確にわかることから、効率的に人材育成できる点です。
一方、デメリットとして、評価基準があいまいになりやすく、上司の主観で決まってしまう点が言えます。
また、行動特性の検討・修正へのコストが高いことが挙げられます。
5. バリュー評価
バリュー評価は企業の価値観を落とし込んだ行動規範であるバリューを基準としてそれを実践できているかを評価する手法を指します。
コンピテンシー評価ではハイパフォーマーを基準とするのに対し、バリュー評価は会社の価値観を重視するのが特徴です。
よって、高い成果を残しても会社の行動基準に沿っていない場合は高い評価にはつながらないことがあります。
メリットとしては、行動規範が示されているので、全社的な価値観・方向性の一致が可能ということです。
デメリットは、行動や、過程が評価対象となるので数字などによる客観的な評価が難しい点が挙げられます。
評価基準・評価項目作成のポイント
評価基準や項目を作成する際にはどのようなことに注意をすればよいのでしょうか。
最後となる本パートで4つのポイントについて解説します。
1. 評価基準を具体的かつ明確にする
1つ目は評価基準の明瞭化です。
部署内では同一の評価基準で評価されるため、公平性を期すため評価基準の具体的かつ明確な説明が必要です。
評価基準があいまいで、企業の定めた基準通りに評価されていないと感じてしまったとき、モチベーションが低下してしまう恐れがあります。
2. 客観性を重視する
2つ目は客観性の確保です。
評価に個人的な感情が入ってしまう場合、評価が不公平なものになってしまう可能性が高まります。
制度においては評価者が個人的な感情を入れないような客観性の高い項目を導入すべきでしょう。
客観性が担保されていないと、社員にとっての評価に対する不公平感はモチベーションの低下や、それによる生産性の低下につながる恐れがあります。
3. 絶対評価を行う
3つ目は絶対評価の保証です。
ほかの社員と比べるのではなく、明確な評価基準に基づいた絶対的な評価をすることが必要です。
絶対評価は客観性をともないやすくするため、社員の納得感にもつながります。
相対評価をしてしまった場合、その部署における人材の能力や外部環境によって社内で大きな評価の差が生まれてしまい、不公平感につながってしまいます。
4. プロセスも考慮する
4つ目はプロセスにも目を向けることです。
具体的に数値化されている結果ばかりを評価に反映しがちですが、その結果までの過程や行動を分析し、評価の対象として考慮することは重要です。
結果偏重の評価になってしまうと、外部要因などで結果が出なかった社員にとって不公平感が生じてしまいます。
人事評価制度の成功事例
実際に前述の人事評価制度を導入して成功した企業にはどのようなものがあるのか。最後に事例を一つ紹介します。
より多くの人事評価制度の事例を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
Chatwork株式会社(OKR運用)
Chatwork株式会社は、ビジネスコミュニケーションツールとして大きなシェアを持つサービス「チャットワーク」を展開している会社です。
OKRのフレームワークを人事評価制度に導入することによって組織が抱える課題を解決しました。
急速に会社が成長し、社員数が増加する中で、社員が50~60名を超えたあたりから「誰が何をやっているのか」が見えづらくなってきたという背景があります。
それとともに、会社の戦略や方針が社員に浸透しづらい状況になってきたことをうけて、OKRの導入に至りました。
OKRを最初に導入した当初は、目標の達成率を評価項目としていたために目標が保守的になってしまうなど、運用がうまくいかなかったそうです。
その後、目標達成率を評価と連動させず、「どれだけチャレンジしたか」を評価することで浸透を実現し、現在では一つのコミュニケーションツールとしてOKRが用いられています。
(参照:https://www.hito-link.jp/media/interview/okr-chatwork)
自社での設計が難しいとき
担当者に時間がないなど、自社での設計が難しいときもあるでしょう。
その様な場合に採るべき2つの対処法について解説します。
人事制度設計のセミナーを受講する
第一の方法は自社の社員に外部セミナーを受講させます。
昨今、人事制度に関するセミナーは活発に開催されているのでコストも抑えられます。
人事制度は法改正やトレンドの影響を受けやすく、外部のセミナーを受けることで新鮮な情報に触れられるのでより新しい情報を仕入れられます。
また、セミナーを受けた従業員はノウハウが身に着くので今後人事制度の改正が必要になった時、再び活躍してもらったり、職場で共有してもらうこともできます。
外部の人事コンサルタントに相談する
第二の手段として外部のコンサルタントへの依頼があげられます。
外部コンサルタントはその道のプロフェッショナルであり、相談することにより専門的な知識やノウハウ、最新のトレンドまで活用できます。
第三者の目線で現状を把握して人事制度の設計ができるので社内のしがらみや利権に影響を受けない客観的な制度が設計可能です。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 人事制度を設計する際、「等級制度」は何を基準に選ぶべきですか?
A: 会社の組織風土や将来的な戦略(何を重視するか)を基準に選びます。 能力を重視するなら「能力等級制度(メンバーシップ型)」、職務内容を重視するなら「職務等級制度(ジョブ型)」、役割を重視するなら「役割等級制度(ミッショングレード制)」が適しています。
Q2. 人事制度設計で最も時間と労力をかけるべき手順はどこですか?
A: 最初の「方向性の決定」と、最後の「運用・改善」のステップです。 方向性が定まらないと制度全体が機能せず、また、どんなに良い制度を作っても社員のフィードバックを無視して運用を放置すると、必ず形骸化してしまいます。
Q3. 評価制度の設計で「公正性」を担保するために、必ず入れるべき項目はありますか?
A: 評価者による主観や感情を排除するため、「客観性の高い項目」を導入すべきです。 特に、明確な基準に基づく絶対評価を保証し、結果(業績)だけでなくプロセスや行動も考慮に入れます。また、評価者研修を実施し、評価者間の目線を統一することも重要です。
Q4. 制度を「作って終わり」にせず、社員の納得感を持たせるコツは?
A: 制度を明文化した後、法的なチェックと「コストシミュレーション」を行うことです。 社員のモチベーションに直結する賃金制度が、長期的に経営を圧迫しないかを事前に検証します。社員には、評価基準が合理的であるという根拠を明確に伝えることが大切です。
Q5. 最近の人事評価のトレンドである「ノーレイティング」とは何ですか?
A: 評価ランク付けをなくし、頻繁な対話とフィードバックで評価・育成する手法です。 変化の激しい外部環境に対応するため、目標設定やフィードバックを随時行います。上司の負担は増えますが、社員のエンゲージメント向上に有効とされています。
まとめ
ここまで人事制度の構成要素とその目的設計手順とポイントについて紹介してきました。
人事制度を的確に制定、運用することで、従業員個人レベルだけでなく、チーム、延いては企業全体での生産性の向上につながります。
本記事で紹介した手順や注意点を参考にして人事制度の設計を考えてみてはいかがでしょうか。
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。