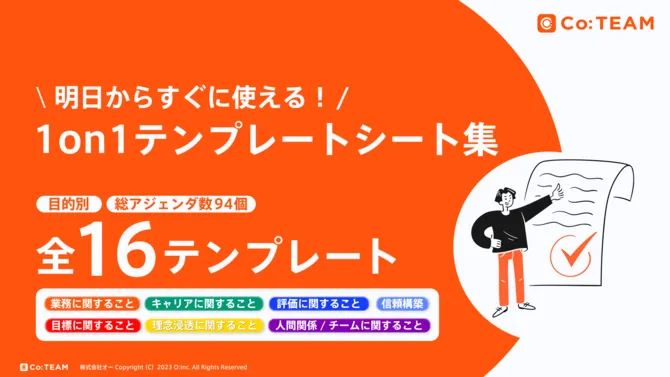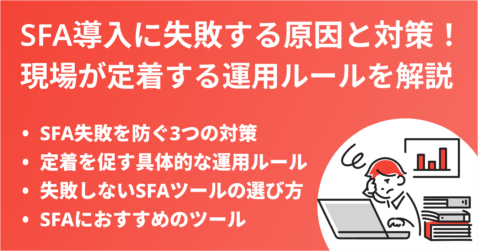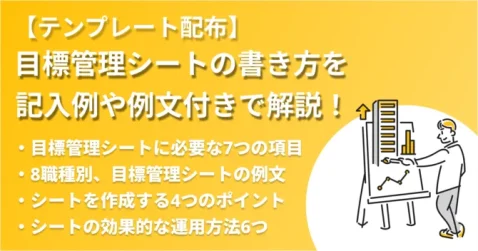人事評価制度は、従業員のモチベーションや組織全体のパフォーマンスに直結する重要な仕組みです。評価の基準やプロセスだけでなく、「いつ・どのタイミングで行うか」というスケジュール設定も欠かせません。適切な時期に実施することで、従業員の成長を促し、組織の目標達成に近づけます。
本記事では、人事評価のスケジュール設定の流れや効果的な組み立て方、押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
▼ この記事の内容
- 運用サイクル: 人事評価は年1回または2回の実施が基本です。適切な時期に評価を行うことで、社員の納得感を高め、組織全体の目標達成を後押しします。
- 制度の機能: 等級・評価・報酬の3つを連動させます。これらが正しく機能することで、公平な処遇を実現し、社員の意欲と定着率を向上させます。
- 運用の手順: 目標設定からフィードバックまでを一貫させます。定期的な1on1で進捗をすり合わせ、評価結果への「納得感」を醸成しましょう。
- 成功の秘訣: 「制度が3割、運用が7割」と言われます。仕組み作りだけでなく、評価者研修や説明会を行い、現場での丁寧な運用を徹底しましょう。
目次
人事評価制度とは?
「人事評価制度」は、従業員の業績や能力を評価し、その結果を給与や昇進、賞与などに反映させる仕組みを意味します。しかし、その役割は評価にとどまらず、企業の経営戦略を実現するための重要な手段でもあります。特に、新しい戦略を実現するためには、従業員の行動や考え方を変えることが求められます。
評価制度は、成果評価(定量評価)を通じて具体的な業務内容を変革し、行動評価(定性評価)で日々の姿勢や取り組み方に変化を促します。これにより、従業員一人ひとりの行動を戦略に沿ったものへと導き、長期的には組織全体の価値観や文化の進化にもつながります。評価制度は、戦略実現に向けた行動を方向付け、企業成長を支える基盤となるのです。
【全5職種対応・自動計算機能付き】
営業・事務・管理職など主要職種の評価項目例つき!
Excel / Googleスプレッドシートに対応し、そのまま使える人事評価テンプレートシートを無料公開中!
>>『人事評価のテンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!
人事評価制度の位置づけ
人事評価制度は、組織の「人事制度」を支える基幹要素です。評価の結果は、等級や役職、給与・賞与などの処遇に直接反映されることが多く、従業員のモチベーションや企業全体のパフォーマンスを左右する大切な仕組みです。
さらに、これらの人事制度は、人材の採用や配置異動、新卒・新入社員の育成・定着など、さまざまな人事施策・人材マネジメントを下支えする重要な基盤でもあります。そのため、制度設計の段階で「どのような人材を求め、どのように成長させるか」という考え方を十分に組み込むことが欠かせません。
具体的な事例として、「ジョブローテーションを積極的に行い、幅広い視点を持つ人材を育てたい」と考える組織では、異なる部署や業務を経験する中で培われる「全体最適を判断できる能力」を高く評価するような人事評価制度を整えると効果的です。こうした制度設計によってジョブローテーションが促進され、組織が志向する人材像の育成につながります。
一方で、職種別のテクニカルスキルのみを重視する評価制度にしてしまうと、異動のたびに専門性が十分に発揮できず、評価が下がりやすくなる恐れがあります。結果として、ジョブローテーションの意義や組織が目指す方向性と矛盾が生じる可能性もあるでしょう。
このように、人事評価制度を設計・運用する際は、組織の将来像や人材育成方針に関連する評価項目や基準を策定することが大切です。
【最小限の労力で最大限の成果を出す評価の作り方】
●負担を抑えつつ効果を出す人事評価制度の制度設計・運用方法
●人事専任の社員がいなくても成果につなげられる人事評価の制度設計方法
●被評価者の評価結果への納得、その後の成長を促す人事評価の運用方法
評価制度の構築から運用までの全てがわかる無料資料
>>「人事評価のプロが教える、「成果と満足度を両立させる評価」の制度設計・運用ガイドブック」はこちらから無料ダウンロード!
人事評価制度の3つの機能
企業が従業員に対して公平な人事管理を行ううえで、人事評価制度は欠かせない基盤です。特に、定期的な「評価の時期」や「結果のフィードバックのタイミング」をどう設定するかによって、評価の公平性や従業員の納得感が大きく左右されます。
そんな人事評価制度には、以下の3つの重要な機能があり、これらをどのタイミングでどのように運用するかが企業の成長と従業員のモチベーション向上につながります。
- 等級制度
- 評価制度
- 報酬制度
それぞれが、人事評価制度の構築においてどのような役割を果たしているのか、詳しく見ていきましょう。
等級制度
「等級制度」とは、従業員をランクや役割に応じて分類するための制度です。具体的には、各従業員の職務内容、成果、能力などに基づき、等級や職種を設定し、企業内での序列を明確にします。この仕組みによって、従業員の評価や報酬が大きく左右されるため、人事制度の中で非常に重要な役割を果たしています。
等級制度のメリットは、従業員にとっての成長指標となる点にあります。等級ごとの基準が明確になることで、従業員はより高い等級を目指して自身のスキルや能力を向上させるための目標を持ちやすくなります。
また、どのようなステップでキャリアを積み重ねていくのか等のイメージが見えやすくなり、長期的なキャリアプランを描く助けとなります。結果として、従業員のモチベーション向上や、企業内での成長を促進する効果が期待できます。
さらに、等級制度は企業にとっても有益です。従業員の能力や成果に応じた適切な配置や昇進を実施できるため、組織全体のパフォーマンス向上につながります。また、公正な評価基準があることで、従業員同士の不満軽減などの対策となり、組織内の一体感や働きやすさを向上させる効果も期待されます。
評価制度
「評価制度」とは、企業の掲げる目標や方針に対して、各従業員がどの程度貢献しているかを評価するための仕組みです。この制度を通じて、従業員一人ひとりの成果や行動が、自社の価値観や目標にどの程度一致しているかが判断されます。
例えば、多くの成約を獲得した営業担当者が高い評価を受けるケースなどが考えられますが、評価の基準は企業ごとに異なります。そのため、企業は何を重要視し、どのような行動や姿勢を評価するのかを、従業員に明確に伝えることが必要です。これにより、従業員は何を指針として仕事をすべきかを理解しやすくなります。
一般的な人事評価制度では、この評価の度合いが従業員の等級や報酬を大きく左右します。評価制度がしっかりと整備されていないと、従業員が成果を上げても正当な評価を受けられないため、モチベーションの維持が困難になる可能性があります。また、評価基準が不明確であると、従業員間の不公平感や不満を生み出し、組織の士気が低下するリスクもあります。
そのため、企業は評価制度を公正かつ透明性のあるものにすることが重要です。これにより、従業員が自らの努力が評価されると感じられる環境を整え、企業全体のパフォーマンス向上や目標達成に寄与することが期待されます。
報酬制度
「報酬制度」とは、等級や評価に基づいて従業員への給与や賞与などの報酬を決定するための制度です。この制度は、従業員のモチベーションに大きな影響を与える重要な役割を果たします。
報酬制度が適切でない場合、たとえ従業員が能力を発揮し、努力して等級や評価が向上したとしても、その成果が報酬に反映されなければ、不満や不公平感を抱く原因となります。そのため、報酬制度は等級制度や評価制度と密接に連携し、これらの制度で評価された内容が報酬にしっかりと反映される仕組みであることが求められます。
適切な報酬制度を設けることで、従業員は自身の成果や能力が正当に評価されていると感じることができ、さらなる努力や成長意欲を持ちやすくなります。また、公平で透明性のある報酬制度は、企業全体の士気向上にもつながり、長期的な組織の安定と成長を支える要素となります。
このように、報酬制度は企業が従業員に対して評価と報酬のバランスをとるための不可欠な仕組みであり、その設計と運用が企業の成長に直結するものといえるでしょう。
「現場の評価制度のまま売上を上げたい」「売上と納得度を上げる評価制度を作りたい」とお考えの方必見!
今ある人事評価を変えずに、少し足すだけで驚くほど売上と納得度が高まる「加点評価・インセンティブ型」人事評価の作り方について解説した資料!
>>売上・納得度を劇的に高める「加点評価・インセンティブ型」人事評価制度の作り方マニュアルはこちらから無料ダウンロード!
※一般的なインセンティブ制度とは異なるため「あ〜インセンティブね」と思わず、ぜひ一読いただけますと幸いです!(本や他社ではあまり語られていない部分がたくさんあります!)
人事評価制度の運用スケジュール
人事評価制度を効果的に機能させるためには、明確な運用スケジュールを定めることが重要です。「いつ」「誰が」「どのような評価プロセスを実施するのか」をあらかじめ決めておくことで、従業員の納得感やモチベーションを高めるだけでなく、人事部門や管理職の運用負荷を最適化することにもつながります。
ここでは、一般的な運用の流れとスケジュール設定のポイントを解説します。
運用スケジュールの具体的なイメージ
人事評価の実施回数は、評価の効果性や運用の負担を考慮して、年間で1回または2回を基本とするケースが多く見られます。どのタイミングで評価を行い、いつ処遇に反映させるかは、企業の事情や組織規模に合わせて決定することが大切です。
以下は、人事評価を年2回実施する場合の運用スケジュールの具体例です。
| 評価期間 | 評価対象期間 | 評価実施 | 評価フィードバック | 処遇反映 |
| 上期 | 4月〜9月 | 10月 | 11月 | 冬期賞与反映(12月) 6月の昇進試験 |
| 下期 | 10月〜3月 | 4月 | 5月 | 夏期賞与反映(6月) 給与改定に反映 |
※
・評価期間 :従業員が実際に業務を行う期間
・評価対象期間 :評価の基準となる成果や行動が観察される期間
・評価実施 :管理職や評価担当者が評価を行う時期
・評価フィードバック:評価結果を従業員に伝え、次の行動や目標設定に活かすための面談時期
・処遇反映 :評価結果に基づき、賞与や給与、昇進・昇格を決定・通知するタイミング
運用スケジュール作成のポイント
このような運用スケジュールの作成においては、いくつかのポイントがあります。
以下に、3つの観点からご説明します。
適切な人事評価の運用フロー構築
運用スケジュール作成の1つ目のポイントは、「適切な人事評価の運用フロー構築」です。
人事評価の運用フローを構築する際は、目標設定・中間面談・最終評価・フィードバック・処遇反映といったステップを整理し、担当者やタイミング、必要な準備を明確にすることが大切です。こうした流れを可視化すると、管理職や従業員が同じ認識を持ちやすくなり、評価基準のあいまいさや手戻りを防げます。
また、目標設定からフィードバックまで一貫したプロセスを意識し、年度計画や賞与支給の時期などと連動させることで、評価結果に対する納得感を高めつつ、組織全体が同じ方向をめざす体制を築けます。
フィードバックサイクルの確立
運用スケジュール作成の2つ目のポイントは、「フィードバックサイクルの確立」です。
人事評価では、目標設定から評価、フィードバックまでの一連の流れを途切れさせず、定期的な面談や1on1の機会などを通して途中経過の共有することで、早めに軌道修正を図ることが大切です。評価期間終了後も、結果をもとに次の目標や課題を明確にし、改善点を次回へ活かすサイクルを続けます。
さらに、フィードバックのタイミングをあらかじめスケジュール化することで、管理職や人事部門の活動を計画的に進めやすくなり、従業員の納得感と組織全体のパフォーマンスを高められます。
定期的な改善とメンテナンスの実践
運用スケジュール作成の3つ目のポイントは、「定期的な改善とメンテナンスの実践」です。
整備した人事評価制度やスケジュールは、企業や従業員の状況変化に応じて定期的に見直すことが欠かせません。評価基準や指標の再検討、従業員からのフィードバック収集、ツールやシステムのメンテナンスを行い、新規事業や組織改編などにも柔軟に対応することで、制度の形骸化を防ぎ、従業員の納得感やモチベーションを維持できます。
こうした継続的なアップデートと改善が、人事評価制度の信頼性と組織全体のパフォーマンス向上を支える原動力となるでしょう。
人事評価制度の運用スケジュールの作成後に実施するべきこと
ここまで、人事評価制度のスケジュール作成のポイントについてご説明してきましたが、スケジュールの作成を行った後にも実施すべきことがいくつかあります。
以下に人事評価制度の運用スケジュールの作成後に実施するべきことについて、具体的にご紹介します。
評価説明会の開催
人事評価制度の運用スケジュールの作成後に実施するべきことの1つ目は、「評価説明会の開催」です。
評価説明会は、評価制度の運用スケジュールや、評価基準・評価方法について従業員に説明する場です。この会を通じて、従業員が評価プロセスに対する理解を深めることで、評価制度への信頼感を高めることができます。また、従業員からの質問や意見を受け付けることで、制度に対する疑問の解決やフィードバックを得る良い機会にもなります。
人事評価制度の運用スケジュールや評価手法の特徴・重要性をきちんと現場に説明することで、その後の評価制度への納得感や浸透が促進されるので、必ず評価運用開始前に実施するようにしましょう。
評価者研修の実施
人事評価制度の運用スケジュールの作成後に実施するべきことの2つ目は、「評価者研修の実施」です。
評価制度の運用後に社内での評価基準を一定に保つためには、評価者教育や評価者研修が非常に効果的です。評価者の中には、評価基準や方法に対する理解が不十分な場合があり、その結果、評価にばらつきが生じる可能性があります。公平な人事評価を実現するためには、評価者が評価基準や評価方法について正確に理解し、共通の認識を持つことが重要です。
そのため、社内の有識者や外部の専門家を活用して評価者研修を実施することをおすすめします。この研修では、人事評価の目的や注意すべきポイント、正しい評価の考え方・進め方について学ぶことができます。評価者のスキルを総合的に向上させることで、より公正で納得度の高い評価を実施できるようになります。
このように、運用スケジュールの作成後に評価説明会と評価者研修を組み合わせて実施することで、評価制度の理解と信頼を高め、組織全体の評価精度を向上させることができます。
【参加者満足度98.2%!】
明日から使える1on1で重要な「承認」「共感」「フィードバック」のテクニックをわかりやすく解説!
「今まで受けた研修で1番良かった!」「マネジメントの新しい考え方を得れた!」など現場管理職・マネージャーに大人気の1on1研修の第1回目の資料を無料公開中!!
>>1on1研修第1回『マネジメントと1on1って何ですか?』はこちらから無料ダウンロード
重要なのは制度3割・運用7割!
ここまでご説明してきた内容を踏まえ人事評価制度の運用スケジュールを作成することで、適切な制度設計と構築の実現に近づきます。しかし、それだけでは十分ではありません。
人事制度における成功は「制度が3割、運用が7割」と考えられており、評価制度作成後の運用の方が非常に重要ということです。
人事制度は人間を対象とするものであり、単に制度を正しく設計・導入したからといって、自動的に適切な運用がなされるわけではありません。コンピュータのプログラムであれば、正しくコーディングすれば常に正しい結果が得られますが、人事評価はそれとは異なります。したがって、まずは確かな制度を構築することが不可欠です。
正しい制度を土台にした運用があれば、従業員のモチベーションを高め、業務の効率化を図ることができるでしょう。したがって、人事評価制度の構築においては、スケジュールをもとにした制度の設計と運用の両方に注力し、それぞれのバランスを大切にすることが求められると言えます。
納得度の高い人事評価の実現なら「コチーム」!

- 1on1をしながら、目標の進捗を入力できる!
- 目標の結果を人事評価に反映!
- 目標の進捗・結果を全て見える化!
- 1on1の記録を人事評価時に活用できる!
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 人事評価のスケジュールは、いつ設定するのが一般的ですか?
A: 決算や賞与の時期に合わせて、年2回行うのが一般的です。 例えば「4月〜9月」を評価対象期間とし、10月に評価を実施、12月の冬期賞与に反映させるといったサイクルが多くの企業で採用されています。
Q2. スケジュールを決めた後、運用開始前にすべきことはありますか?
A: 全社員向けの「説明会」と管理職向けの「評価者研修」が必須です。 制度の目的や評価基準を事前に周知し、評価者による「甘辛のバラつき」を無くす準備をしておくことで、従業員の不公平感を防ぎます。
Q3. 立派な制度を作っても、うまくいかない原因は何ですか?
A: 「制度3割・運用7割」の原則が守られていないためです。 どんなに精緻な評価シートを作っても、現場でのフィードバックや対話がおろそかだと形骸化します。運用フローを定着させることに注力してください。
Q4. 評価結果のフィードバックは、どのタイミングで行うべきですか?
A: 評価決定後、処遇(給与・賞与)が確定する前に速やかに行います。 結果を伝えるだけでなく、その理由を丁寧に説明し、来期の目標設定につなげることで、部下の成長意欲と評価への納得感を高められます。
Q5. 評価制度を経営戦略の実現に活かすにはどうすれば良いですか?
A: 会社の戦略に沿った行動を、評価項目に具体的に組み込みましょう。 例えば「ジョブローテーション」を推進したいなら、特定スキルだけでなく「全体最適の視点」や「適応力」を高く評価する仕組みに調整します。
まとめ
この記事では、人事評価制度のスケジュールについて、効果的な設定方法と運用における重要なポイントについて解説してきました。
人事評価制度は、企業の競争力を高め、従業員の成長を促進するうえで欠かせない仕組みです。特に、評価を「いつ」「どのように」行うかというスケジュール設定は、評価の公平性や従業員の安心感・納得感に大きく影響します。適切なスケジュールを設定し、運用の質を高めることで、人事評価制度は従業員一人ひとりの成長と組織全体のパフォーマンス向上を支援します。
本記事を参考に、スケジュール作成のもと評価の目的や流れを明確にし、フィードバックを重視することで、信頼性と納得感の高い制度づくりを目指しましょう。
【全5職種対応・自動計算機能付き】
営業・事務・管理職など主要職種の評価項目例つき!
Excel / Googleスプレッドシートに対応し、そのまま使える人事評価テンプレートシートを無料公開中!
>>『人事評価のテンプレートシート集』はコチラから無料ダウンロード!
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。