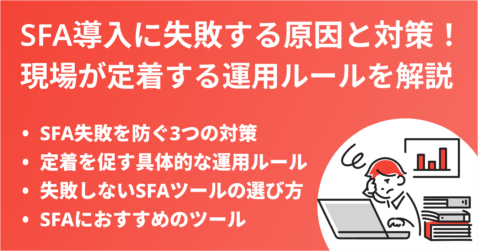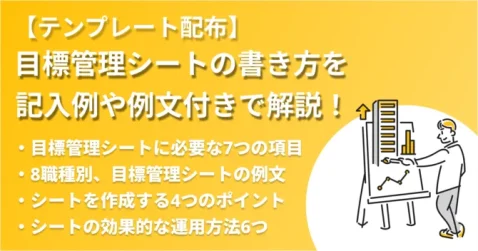近年、SNSの普及により、小さな不祥事でも企業の利益や信用に大きな影響を及ぼすリスクが高まっています。そのためコンプライアンス遵守は一層重視され、企業や従業員の意識が企業価値を左右すると言っても過言ではありません。
本記事では、企業と従業員がコンプライアンスを守るための目標設定について解説します。ぜひ参考にしてください。
カンタンに効果的な目標管理を実現するテンプレート集を無料公開中!
>>無料で『目標管理シートテンプレート集』をダウンロードする
▼ この記事の内容
- コンプライアンス対策が不可欠な理由: VUCA時代やSNS普及による情報の即時性により、小さな不祥事が企業価値を大きく毀損し、最悪の場合は倒産リスクにつながるためです。
- 目標設定の具体的な手法: 組織全体で「社会的信用の向上」などの組織目標を定め、それを分解して個人目標に落とし込み、SMARTの法則を活用して具体的な行動目標にします。
- 実効性を高める運用方法: 目標への納得感を高めるため上司と部下が話し合い、設定した目標が評価制度に明確に紐づく仕組みを作り、従業員の自律的なセルフ・コントロールを促します。
目次
コンプライアンス対策が注目されている理由
コンプライアンスに注目が集まったのは、企業の不祥事に対するマスメディア、消費者、投資家の批判や行政による厳正な取り締まりが大きなきっかけでした。そういった状況下にであったため、コンプライアンスを遵守し、リスクを適切に管理することにより、健全な経営が実現し、対策を講じることで企業価値を高めることができるという積極的なコンプライアンス遵守の考え方が国際的に広まったことにより、近年コンプライアンスの必要性が叫ばれるようになってきています。
450社のマネジメント支援から体系化した、組織を潰す問題社員の早期発見・対処法!
>>無料で『組織崩壊の原因となるモンスター社員の特徴6選』をダウンロードする
コンプライアンスが重要な理由
この章では、なぜコンプライアンスが企業によって重要なのか、コンプライアンス違反が企業にとってどのようなリスクなのか3つに分けて解説していきます。
1.大きな会社でも倒産のリスクがある
帝国データバンクの発表によると、2023年の企業倒産(負債総額1,000万円以上の法的倒産)のうち、342件がコンプライアンス違反によるもので、前年度比16.6%増と過去最多を記録しました。
調査では違反を「粉飾」「業法違反」「談合」「資金使途不正」「脱税」「労務関連不正」「偽装」「過剰営業」「不正受給」「不法投棄」「贈収賄」「その他」に分類しています。2023年で最も多かったのは「業法違反」84件、次いで「粉飾」81件です。特に「不正受給」は30件と前年比2.5倍に急増しました。コロナ禍で特例的に認められた雇用調整助成金などの補助金や支援金の不正利用が相次いで発覚したためです。
コンプライアンス違反が発覚すると、消費者離れや業務停止、融資困難、株主からの追及、従業員の離職などが生じ、事業継続は困難になります。これは中小企業だけでなく、大企業でも例外ではありません。最悪の場合、従業員が刑事責任を問われることもあります。
このような事態を防ぐには、経営陣だけでなく従業員全体のコンプライアンス意識を高め、不正が起こらない仕組みを整えることが重要です。
2.VUCA時代でセキュリティ対策が大変になった
VUCA時代とは、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字を取った言葉であり、社会やビジネスにとって、未来の予測が難しくなる状況のことを指します。グローバル化が進んだ現代においては、変化が激しく、複雑で今までのパターンに無かったような問題が頻発し、特に企業にとってはリスク管理や1つ1つの判断の決定の重要性が増しています。こういった状況下において、セキュリティに関する課題は企業にとって至上命題の1つとなっています。
技術の進歩が急速に進む一方で、新しいサイバー攻撃の手法や目的が多様化しており、たとえば、ランサムウェア攻撃の高度化やAI・ソフトウェアを活用した攻撃シミュレーションなど、攻撃者側のスキルも向上、攻撃対象が単なるITシステムに留まらず、IoTデバイスやクラウドサービスにまで広がり、企業全体のセキュリティを確保するための視点やプロセスが複雑化しています。
こうした状況を加速させている要因の一つとして、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が挙げられます。業務の効率化などの観点で、企業全体でクラウドサービスやIoTの導入が進む中、セキュリティに関する理解が社内で異なることも多く、組織全体で統一的に実施することが求められています。しかし、採用管理システムや経費精算システムのように、各部門やプロジェクト単位で異なるシステムが導入されるケースが多く、会社のIT部門も全体像を把握することが難しい状況が生まれています。このため、セキュリティ管理の基準やポリシーを全社的に統一し、内部統制を徹底することが課題となっています。
このような課題に対処するためには、高度な専門知識を持つ人材が必要です。また、前述したように社員間での認識にも差があるため、セキュリティ担当者だけに依存せず、従業員全体の意識向上や、定期的なコンプライアンス教育を通じて、全社的にセキュリティ文化を醸成することが不可欠です。
3.情報がすぐ広まる時代
近年、SNSやネットワークのさらなる普及により、情報の拡散されるスピードはより一層即時性を帯びてきています。この情報の即時性は企業にとって両刃の剣であり、適切に活用すればブランド価値を高めるツールとなります。一方、最近では、情報が単に広がるだけでなく、操作されたり意図的に拡散されたりすることで、企業に対する攻撃手段として「武器化」されるリスクが高まっています。特に、フェイクニュースや悪意ある編集による情報操作は、企業の名声を著しく損なう可能性があります。
不祥事や規範違反が明るみに出た場合、即座に社会的な反発を招くだけでなく、炎上やボイコットといった直接的な経済的損失をもたらします。さらには、ステークホルダーとの関係悪化や株主からの信任喪失といった長期的な影響も見過ごせません。
また、情報の伝播速度が速い現代では、不測の事態への対応が遅れると、そのダメージが拡大するだけでなく、信頼回復が困難になります。そのため、通常時から法令や透明性、倫理性を重視し、正しい行動を取ることにより、信頼を蓄積させ、企業価値を向上させるこができます。たとえば、ハラスメントに対する取り組みや環境保全等の社会貢献活動を積極的に発信することで、信頼を築き、ブランド価値を高めることが可能です。情報が広まりやすいことによるデメリットも先述したようにありますが、それを逆手に取る形で利用することも可能です。
さらに、コンプライアンスの強化は、内部的な効果も持っています。戦術したように現代は情報の透明性のが高まってきており、不正や規範違反は早い段階で内部告発や会社外部へのリークにより公になる可能性が高まっています。このようなリスクを最小化するには、コンプライアンスを単なるルールの徹底ではなく、企業全体の価値観として浸透させることが重要です。従業員一人一人がその意義を理解し、日々の業務で実践できるようにすることで、組織全体の倫理基準を向上させることができます。
コンプライアンス対策の目標設定
コンプライアンス対策は、先述したように日々重要性を増してきている一方で、そこに対する目標設定に関しては一般的にまだ広まっていないことに加え、定性的なものも多く、具体的にどのように設定すればよいのか悩まれている方も多いと思います。この章では、コンプライアンス対策の目標設定手法について解説します。
1.組織目標を決める
コンプライアンス対策の目標設定をするにあたり、まずは組織目標を策定し、「組織として何をしていくのか」を明確にする必要があります。この段階では、企業全体の方向性や優先事項を明確にし、それを基に実効性の高い対策を講じることが求められます。組織目標は明確に設定するためには、設定した企業方針を細分化し、各部署などの組織に対して起業方針に合わせた目標を設定するようにお求めることが必要になります。適切な目標設定が行われることで、全社員が共通の基準を持ち、コンプライアンスに基づいた行動を実現しやすくなります。
また、組織目標を策定する際には、どのようなレベル感で設計するのかを慎重に検討する必要があります。たとえば、全社的な目標では、「社会的信用の向上」といった顧客・取引先・株主を意識した抽象度の高い目標が適しています。一方で、部署単位で考える場合、「ハラスメント防止体制の強化」や「労務関係の法律違反ゼロ」といったように、実現可能で具体的な目標を設定することが重要です。これにより、各部署がその責任範囲内で具体的な施策を展開できるようになります。
さらに、組織の規模や構造に応じて、目標設定のアプローチを柔軟に変える必要があります。たとえば、企業単位の目標ではガバナンス全体の強化に焦点を当てるべきですが、課単位では業務の効率化や規則遵守を徹底するための施策が適切です。トップダウン形式で全体方針を明確に打ち出すことも重要ですが、現場の実情に即したボトムアップ形式の目標設定を組み合わせることで、現実的かつ効果的なコンプライアンス体制を構築できます。
2.個人目標を決める
個人目標を設定する際には、設定した組織目標の達成に繋がるよう、組織目標を要素分解し、それを具体的な行動に落とし込むことが重要です。組織目標を基に、各個人が自分の業務範囲内でどのように貢献できるかを明確に考えることで、個人目標と組織目標の間に直接的な連動性が生まれます。このアプローチにより、個人目標の達成が最終的に組織目標の実現に寄与する構造を作ることが可能になります。
例えば、組織目標が「ハラスメント防止体制の強化」である場合、個人目標としては「定期的にハラスメントに関する研修を受講し、その内容を他の社員に共有する」といった具体的な行動に分解することが考えられます。このような具体性を持たせることで、目標達成に向けた行動がより計画的かつ効率的に進められます。
さらに、目標設定を行う際には、個々の役割や業務内容を正確に把握し、それに即した行動を含める必要があります。これを実現するためには、チーム内での目線合わせを実施することが重要です。例えば、個人の役割や職務内容に基づいた目標を設定することで、責任範囲を明確にし、役割を逸脱した目標設定を回避できます。また、チームや部署内でコメントを交換し、各メンバーが自身の目標を理解し納得できる環境を作ることが、目標達成へのモチベーションを向上させる鍵となります。
この際、上司や管理職の関与も欠かせません。目標設定のプロセスでは、上司が部下に対してフィードバックを提供し、目標が現実的で達成可能であるかを確認する役割を果たします。加えて、進捗管理システムやタスク管理ツールを活用し、目標の進行状況を可視化することで、チーム全体での達成感を共有しやすくなります。
最後に、個人目標を設定する際には、その粒度に注意する必要があります。組織目標は比較的抽象的である場合が多いため、個人レベルではより具体性を持たせることが必要となります。たとえば、組織目標が「労務関係の法令違反ゼロ」である場合、個人目標は「毎月末に勤怠記録の不備を確認し、発見した場合は上長に報告する」や「法令改正に関する情報を継続的に収集し、四半期に1度部内に共有する」といったタスク単位の目標に分解することが効果的です。
こうした具体的なタスクにすることで、個人は優先順位を明確にし、日々の業務の中で着実に目標達成へ向けた行動を実行できます。
【その目標管理、実は成果が出ないやり方かも?】
国内の多くのマネージャーは目標設定・目標管理のやり方を教えられずに、いきなり目標管理を任されています。
そんなマネージャーの中に、成果が出ない目標管理で苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。そんな国内に満映している「間違いだらけの目標管理」について解説した資料を公開中です!
>>「間違いだらけの目標管理」はコチラから無料ダウンロード!
コンプライアンス対策における目標設定のコツ
この章では、コンプライアンス対策における目標設定のコツについて解説します!
SMARTの法則を活用する
コンプライアンスに関する目標設定は、営業職のように定量的な目標設定が難しく、定性的な目標になってしまうことが多いため、定性的な業務を定量的に把握できるような目標設定を行うことが重要です。この際、効果的な目標設定手法として「SMARTの法則」を利用することがおすすめです。「SMARTの法則」とは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)の頭文字を取った目標設定のためのフレームワークであり、SMARTの法則を用いて目標を定めて取り組んだ結果、従業員のパフォーマンスが大幅に上がると分かっています。
たとえば、法務関連のコンプライアンス強化を目指す組織目標に対し、SMART基準に基づいた個人目標であれば、「毎月1件、法令改正に関する最新情報を収集し、部内に共有する」や「四半期に1回、内部監査をサポートし改善点を記録する」といった目標を設定することができます。このように、目標に対して期限や具体のアクションを明確化することで、進捗を測定しやすく、達成可能であるかを判断しやすくなります。
上司・部下で話し合って目標設定を行う
目標設定における成功の鍵の一つは、上司と部下が納得した目標設定を行うことです。目標設定を行う際、納得感のある目標でなければ「Self-control(セルフ・コントロール)」の意識が薄れ、各個人が目標に対して自律的に自身をマネジメントすることが難しくなってしまいます。
従業員が自律的に目標に向かって行動するためには、その目標が本人にとって納得できるものである必要があります。目標への納得感を高めるためには、部下自身が目標を設定し、それを上司が確認するプロセスを通じて、双方が合意できる目標を設定することが効果的です。こうすることで、部下は目標に対して責任感を持ち、達成意欲を高めることができます。
一方で、部下だけが納得する目標では、組織目標とのズレが生じる可能性があります。そのため、上司は部下が設定した目標を確認し、必要に応じてアドバイスや調整を行いながら、組織目標との整合性を保つ役割を果たします。ただし、目標の修正や計画の再設定においても、部下自身を主体とした検討を促すことが重要です。
具体的な実践方法としては、1on1ミーティングを実施し、上司と部下が個別に時間を確保して目標について話し合う場を設けることが挙げられます。この場では、組織目標やチーム目標の意図を共有し、部下の意見を尊重しながら目標設定を行います。さらに、定期的なフィードバックを通じて進捗を確認し、必要に応じて目標を見直す仕組みを構築することで、目標設定が形骸化するのを防ぎます。
上司と部下が十分なコミュニケーションを取りながら目標を設定することで、部下の成長を促進し、組織全体の目標達成にもつながる結果を生み出すことができます。
【読むだけで1on1力が1.5倍UP!?】
明日からの1on1が見違えるほど良くなる!
1on1のやり方、コツについて260スライド以上の大ボリュームで、1on1の流れや改善点など大切なことが丸わかり!
>>『【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド』はコチラから無料ダウンロード!
目標が評価制度に紐づくようにする
目標設定が効果的に機能するためには、それが評価制度と明確に結びついていることが重要です。従業員が設定した目標が評価基準に直接関連していない場合、目標達成に向けたモチベーションが低下する恐れがあります。そのため、評価制度の基準を明確化し、目標との連動性を持たせることが必要です。
たとえば、評価制度が「成果主義」に基づいている場合、個人目標には具体的な成果を定義し、それを測定可能な形で設定する必要があります。一方、「プロセス重視」の評価制度であれば、目標には行動や取り組みの姿勢を反映させることが求められます。このように、評価制度の特徴に応じて目標を設計することで、目標が従業員の行動を評価に結びつける橋渡しとなります。
さらに、評価制度との連携を強化するために、目標設定時に評価基準を共有することが重要です。たとえば、目標達成の進捗や成果を定期的に記録し、評価時にそれらを活用できる仕組みを構築します。また、上司が目標と評価基準の関連性を説明し、従業員が自分の目標がどのように評価に反映されるかを理解できるようにすることが求められます。
最終的には、目標が評価制度に紐づいていることで、従業員のやる気や責任感が向上し、目標達成への意識が高まります。このプロセスを通じて、個人と組織の両方にとって価値のある結果を生み出すことが可能となります。
コンプライアンス違反防止ための施策
この項目では、コンプライアンス違反防止のための具体的な施策について解説していきます!
1.研修
コンプライアンス違反を防止するためには、定期的なコンプライアンス研修を通じて従業員の意識向上と理解促進を図り、企業全体での風土醸成を進めることが重要です。この研修では、まずコンプライアンスの基本概念や、違反行為・トラブルがもたらす企業への影響について全員が理解できるよう教育を行います。
特に、違反が引き起こす社会的信頼の喪失や、法的責任による財務的損失といったリスクを具体的に伝えることで、従業員一人ひとりが「自分の行動が企業全体に影響を与える」という認識を持てるようにすることが求められます。全社的な研修としては前述したような者になりますが、より具体的な研修を行う場合には、業務に密接に関係する法規や規制に特化した項目を盛り込むことが重要です。
たとえば、経理部門であれば金融商品取引法や内部統制に関する知識、営業部門であれば競争法や贈収賄防止法に関する具体的な遵守事項を取り上げます。このように、部門や役職ごとにカスタマイズされた内容を提供することで、組織目標との繋がりも生まれ、従業員は自分の業務に直結する具体的な行動指針を学ぶことができます。
また、研修の効果をより向上させるためには、実際の事例を用いたケーススタディを活用することがおすすめです。違反行為の発生原因や防止策を具体的に学び、問題解決能力やリスク感知能力を養うことが可能です。たとえば、過去の内部告発事例や、SNSでの情報漏洩が企業に与えた影響をシミュレーション形式で学ぶことで、参加者が実際の業務で起こり得るシナリオをリアルに想定できます。これにより、従業員は単に知識を習得するだけでなく、日常で事例を思い出すような場面も増えるため、近いシチュエーションでの判断力を強化できます。
このような研修を実施する場合、一度きりとなってしまうことも少なくないですが、風土醸成という観点でも、定期的なフォローアップやeラーニングを組み合わせることが非常に重要となります。社員が日中忙しく、集合研修が難しい場合には、eラーニングを活用することで、全社員が好きなタイミングで受講できる柔軟性を確保しつつ、定期的に新しい知識をアップデートすることが可能になります。また、学習の進捗や理解度を測るためにオンラインテストやチェックリストを導入し、習熟度に応じた追加研修やサポートを提供することも効果的です。
さらに、コンプライアンス研修の効果を高めるためには、経営陣の積極的な関与も欠かせません。経営層が研修に参加し、コンプライアンスを重視する姿勢を示すことで、従業員にとって「コンプライアンスは企業文化の重要な一部である」というメッセージが明確になります。これにより、トップダウンでのリーダーシップと、ボトムアップでの従業員意識の双方を強化することが可能です。
2.ツール
コンプライアンス違反を防止するためには、適切なツールを活用することも非常に効果的です。業務に合わせたツールの導入により、従業員の行動を可視化し、違反リスクを早期に察知できる体制を整えることができます。例えば、法務系であれば契約管理システムや内部通報制度をサポートするプラットフォームの導入が挙げられます。これにより、契約書の締結状況や法令遵守の進捗をリアルタイムで把握できるだけでなく、管理業務の負担を軽減し、ヒューマンエラーを最小限に抑えることができます。
特に、複数の契約や法規制を同時に管理する必要がある大規模な組織においては、こうしたツールの導入が内部統制の強化に直結します。
近年で考えると、法令の改正も多く行われているため、法令改正情報を自動通知する機能を持つツールなどがおすすめです。これを導入することにより、最新の法規制に迅速に対応できる体制を構築することができます。例えば、AIを活用した法規追跡ツールやリスク管理ダッシュボードを導入すれば、企業が遵守すべき規制の変更を即座に把握し、対応策を講じることが可能になります。これにより、改正法令の見落としや対応の遅れによるリスクを大幅に軽減することができます。
ツールの導入は単なる違反防止策にとどまらず、業務の効率化や全社的な意識改革にもつながります。従来であればアナログで行なっていた業務をデジタル化することで、アナログ時代には追跡できなかった不正行為などを追跡できるようになるため、従業員の「バレなければ大丈夫」という意識自体を改革することができます。このような取り組みを通じて、組織は社会やステークホルダーからの信頼を獲得し、競争力を維持し続けることができるでしょう。
3.仕組み化・ルールづくり
コンプライアンス違反を防止するためには、仕組み化とルールづくりを徹底し、組織全体で統一された行動基準を確立することが不可欠です。具体的には、まず全従業員が遵守すべき行動規範やガイドラインを策定し、規定のような形式で文書化することなどがあります。この際、従業員が実際に活用しやすい形でルールを作成することが必要です。たとえば、業務に関連する具体的なシナリオを盛り込んだハンドブックや、重要ポイントを簡潔にまとめたチェックリストを作成することで、従業員が迷うことなく行動できる明確な指針を提供できます。
また、策定したルールが形骸化しないよう、運用を支える内部監査や定期的なチェック体制を構築することも重要です。これには、日常業務に組み込まれたセルフチェックの仕組みや、定期的な外部監査を活用することが効果的です。特に、問題が発覚した際に「報告すると罰せられる」といった懸念を持たせないよう、罰則だけでなく、再発防止策や教育を組み込んだ改善アプローチを併用することが重要です。このような取り組みは、従業員にとって心理的安全性が生まれるだけでなく、積極的に問題解決に関与することによるメリットにもなるため従業員の意識変容に繋がります。
さらに、ルールを従業員全員に浸透させるためには、単なる通知や配布だけでなく、組織全体でコンプライアンスの重要性を日常的に共有する取り組みが必要です。たとえば、定期的な全社ミーティングや社内ニュースレターを通じて、コンプライアンスの成功事例やリスク事例を紹介し、組織全体で「なぜコンプライアンスが重要なのか」を理解する機会を設けることが効果的です。特に、トップマネジメントが積極的にメッセージを発信し、自ら率先して行動規範を実践する姿勢を見せることは、従業員の意識を高める上で大きな効果を持ちます。このようなリーダーシップは、組織全体でのルールの定着を後押しします。
4.適性検査
信頼が重要になるような金融などの業界であれば、そもそもの採用の段階で適正検査を行い、コンプライアンス意識が高い人材を採用することも打ち手となります。適性検査を導入することで、候補者や従業員の価値観や行動特性、リスクに対する認識を明確にし、個々の適性を的確に評価することが可能となります。この情報をもとに、コンプライアンス意識の高い人材を選抜したり、適切な役割や責任を割り当てたりすることで、組織全体の倫理基準を底上げすることができます。
また、適性検査の結果を活用することで、従業員ごとに異なるリスク傾向に応じた対策を講じることができます。たとえば、リスク管理の重要性を十分に認識していない従業員に対しては、追加の研修やフォローアップを実施し、リスクに対する感度を高めることが効果的です。こうした個別対応を通じて、従業員一人ひとりが日常業務において適切な判断を下せるようになり、結果的に組織全体のコンプライアンス体制を強化することが期待されます。
適性検査のもう一つの側面は、組織における人材配置の最適化です。たとえば、適性検査のデータを活用して、コンプライアンスに高い意識を持つ人材をリスクの高い業務やポジションに配置することで、リスクを管理しやすい環境を構築することができます。一方で、リスク傾向のある従業員に対しては、メンター制度や定期的なフィードバックを組み合わせることで、早期発見と防止を可能にします。また、適性検査を通じて得られるデータは、組織全体の文化醸成にも活用できます。たとえば、定期的に従業員全体の適性データを分析し、組織の中でどのような行動特性や価値観が求められているのかを把握することができます。このデータを基に、行動規範のアップデートや、新たなコンプライアンス施策を策定することが可能になります。
効果的な目標管理・納得度の高い人事評価なら「Co:TEAM(コチーム)」

- 1on1をしながら、目標の進捗を入力できる!
- 目標の結果を人事評価に反映!
- 目標の進捗・結果を全て見える化!
- 1on1の記録を人事評価時に活用できる!
よくあるご質問(FAQ)
Q1: コンプライアンス違反が起きた場合、企業はどのようなリスクに直面しますか?
A: 事業継続が困難になるほどの深刻な影響を受けます。 消費者離れや業務停止、融資困難、従業員の離職などが生じ、大企業でも倒産のリスクがあります。
Q2: 定性的なコンプライアンス目標を、どのように定量的に管理すれば良いですか?
A: 「SMARTの法則」の活用が有効です。 例えば、「法令改正情報を毎月1件収集し、部内に共有する」のように、測定可能で期限(Time-bound)を持たせた具体的な行動目標に変換します。
Q3: 組織目標と個人目標を設定する際、意識すべき連動のさせ方は何ですか?
A: 個人目標が組織目標の達成に貢献するよう要素分解します。 組織目標が「ハラスメント防止」なら、個人目標は「定期的に研修を受講し、内容を他者に共有する」といった具体的な行動に落とし込みます。
Q4: コンプライアンス違反を防ぐために、研修以外でどのような施策が有効ですか?
A: 「仕組み化・ルールづくり」と「ツールの活用」が有効です。 業務ごとの行動規範を文書化し、法令改正通知ツールなどを導入して、ヒューマンエラーと「バレなければ大丈夫」という意識を排除します。
Q5: 目標設定を形骸化させず、従業員の意識を高めるためのコツは何ですか?
A: 目標設定のプロセスで従業員の納得感(Self-control)を高めることです。 上司と部下が1on1ミーティングで目標を話し合い、その目標が人事評価と明確に結びつく仕組みを作り、責任感を向上させます。
まとめ
企業にとって、コンプライアンスの遵守は今後重要性を増していきます。1つのコンプライアンス違反で企業価値を毀損しないためにも、目標設定などの対策を行い、より良い企業風土を醸成していきましょう。
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。