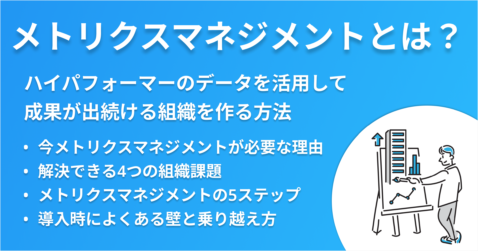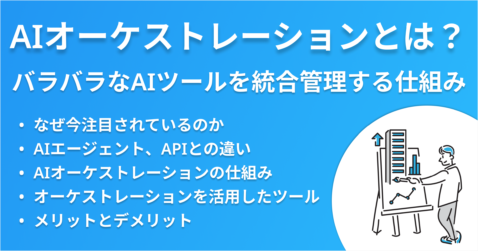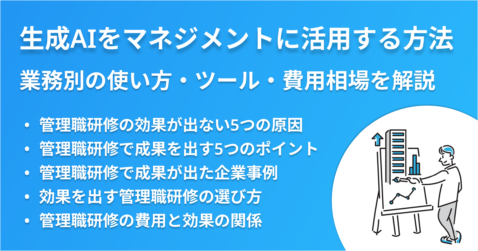「傾聴」とは、相手の話に注意深く耳を傾けることを指します。以前はビジネスで重視されることは少なかったものの、近年では重要なコミュニケーション技術として注目されています。
話し手の気持ちや考えを深く理解し、信頼関係を築くことは、仕事を円滑に進めるうえでも不可欠です。本記事では、傾聴の意味や3つのレベル、傾聴力を高める6つのポイントを解説します。
>>【助成金活用で最大75%補助】満足度98.2%のマネジメント研修がわかる資料3点セットをダウンロードする
▼ この記事の内容
- 傾聴とは: 相手の言葉の裏にある本当の思いや気持ちを理解しようと努める姿勢で、相手を尊重し安心感を与え信頼関係を構築する必須スキルです。
- 傾聴の3つのレベル: レベル1(内的傾聴)は自分に焦点が当たっている状態、レベル2(集中的傾聴)は非言語的手がかりにも注目し相手に集中している状態、レベル3(全方位的傾聴)は場の雰囲気や潜在的な思いまで捉える最高レベルです。
- 傾聴の3つの種類: 受動的(黙って聞く)、反映的(言い換えて確認する)、積極的(質問・フィードバックを交える)があり、状況に応じて使い分けます。
- 傾聴力向上の6つのポイント: 会話の割合(相手が3分の2以上)を意識すること、うなずき・あいづち、ミラーリング、ペーシング、態度と姿勢の改善、バックトラッキング(本質を探る)の実践です。
- 内的傾聴からの脱却: 思考を一時停止し自分の価値観から先走った解釈をせず、非言語的なサインに注目することで、相手に焦点を当てる集中的傾聴へと移行できます。
傾聴とは
「傾聴」とは、単に相手の話を「聴く」ことや自分が聞きたいことを聞くのではなく、積極的に「耳を傾け」、相手の言葉の裏にある本当の思いや気持ちを「理解しようと努める」姿勢のことを指します。傾聴には、以下の3つの要素が含まれています。
- 相手の話に集中する
- 話し手の言葉に真剣に耳を傾け、相手の立場に立って理解しようと努めること。雑念を排除し、相手の話に集中することが大切です。
- 話し手の言葉に真剣に耳を傾け、相手の立場に立って理解しようと努めること。雑念を排除し、相手の話に集中することが大切です。
- 相手の気持ちを推測する
- 言葉だけでなく、表情や仕草、口調からも相手の本当の気持ちを推測し、理解しようと努めること。言外の意味も汲み取り、話しやすい環境を作ることが重要です。
- 言葉だけでなく、表情や仕草、口調からも相手の本当の気持ちを推測し、理解しようと努めること。言外の意味も汲み取り、話しやすい環境を作ることが重要です。
- 共感的理解を示す
- 単に話を聞くだけでなく、相手の気持ちに共感し、それを適切な態度で示すこと。うなずきや相づち、簡単な質問などで、相手の気持ちを理解しようとする姿勢を示します。
そのため、「傾聴」は、単なるコミュニケーションスキルではなく、相手を尊重し、理解しようとする姿勢が根底にあります。話し手を受け入れ、安心感を与えることで、より深い信頼関係が構築され、個人だけではなく、組織にも好影響を与え、パフォーマンス向上が期待できます。
>>【マネージャーの負荷削減と組織の生産性向上を実現】3分でわかる「コチーム」がわかる資料3点セットを無料でダウンロードする
傾聴の3つのレベル
傾聴とは人間関係が存在するうえでは、とても重要なことの一つです。
このパートでは「傾聴の3つのレベル」を解説していきます。
- レベル1:内的傾聴
- レベル2:集中的傾聴
- レベル3:全方位的傾聴
レベル1:内的傾聴
レベル1の内的傾聴は、相手と会話していて、傾聴をしているつもりでも「自分に焦点が当たっている」レベルです。これは傾聴とは言えず、日常会話レベルです。
この状況に陥っている人の会話例として、
「あっ、昔の私と同じだな」
「私なら絶対にそんな風には考えない」
「これは私の経験からするとちょっと的外れかな」
このように、自分の経験や価値観、判断に寄りすぎた発言をしており、相手の話を聞いているにも関わらず、逆に自分に焦点が当たってしまっています。
この内的傾聴レベルで会話していると、相手の話を聞いていないので、話の流れについていけず、会話の間が生まれやすくなり、ぎこちない会話になってしまい、相手は「話をきちんと聞いてもらっている感」を得られなくなっており注意が必要です。
内的傾聴から脱却し、より深い傾聴につながるためには、以下の2つの解決方法を実践するとよいでしょう。
- 思考を一時停止する
- 自分の経験や価値観から先走った解釈をするのではなく、一旦思考を手控えて相手の話に集中します。自分勝手な推測をあまりしないようにしましょう。
- 相手の非言語的手がかりに注目する
- 次のレベル2でもお伝えしますが、言葉だけでなく、相手の表情、身振り、声の調子などの非言語的サインにも意識を向けることが重要です。これらの手がかりから相手の気持ちを推し量ろうと心がけます。
ただ逆に、1on1など面談を受ける立場の方は、レベル1の自分自身に集中している方が何か考え事をしてる状態のため好ましいです。
レベル2:集中的傾聴
レベル2の集中的傾聴とは、言葉の内容だけでなく、非言語的な手がかり(表情、しぐさ、感情の変化、声のトーン、調子など)にも注目し、相手に興味・関心・好奇心を持って聴くことができてる状態です。
いわゆる、「相手に焦点を当てて集中している状態」のことです。
例えば、話し手が笑顔で話しているように見えても、その目が何か暗い表情をしていれば、実は表面上の振る舞いと内面の気持ちが異なることに気づくことができます。言葉とは裏腹に、実は違う感情を抱えていることに気づき、自然と質問が出てくる感覚です。
ただし、非言語的サインの読み違いに気をつける必要があり、勘違いしてしまうリスクがあります。
集中的傾聴は、相手の言葉と合わせて、ひとつひとつの振る舞いを丁寧に観察し、そこから本当の気持ちを推し量ることで、より深い理解につながります。
レベル3:全方位的傾聴
レベル3の全方位的傾聴は、話し手の言葉だけでなく、その場の雰囲気や体の動きまでも捉え、多角的に理解を深めようとするレベルです。言葉以外の要素、たとえば、目線、場の空気、周囲への影響にも注目できる状態です。
日本特有の「空気を読む」という言葉が近いかもしれません。
レベル3の全方位的傾聴の具体的状態として、
「相手の声のトーン、行動に元気を感じるか?」
「少しずれた回答をしたがこの真意はなにか?」
レベル3では、聴き手が高次な状態に入り、言葉の裏にある話し手の本質を自然と読み取れるようになる段階です。五感が研ぎ澄まされ、話し手が醸し出す空気や雰囲気、感覚、言外の意味までも敏感に感じ取ることができます。
例えば、ある提案がなされた際に、その事例の具体的内容だけでなく、提案者の人生観や組織に対する想いなど、基底にある価値観にまで着目することが重要です。そうすることで、提案の本質的な意図を汲み取ることができるのです。言語と非言語だけでなく、背景にある潜在的な思いまでを聞き取ることは、非常に高度な傾聴力が求められるでしょう。
全方位的傾聴のレベルでは適切な質問をしながら、双方向的なコミュニケーションを重ねていく必要があります。
全方位的傾聴は、最高レベルの傾聴スキルであり、相手との深い信頼関係の上に成り立つ極めて高次な能力です。そのため、ある程度の訓練が必要になってきます。
ただ、訓練し意識し続けると、直観が身に付き、自然と全方位傾聴ができるようになるので、ぜひ継続することを意識しましょう。
【参加者満足度98.2%!】
明日から使える1on1で重要な「承認」「共感」「フィードバック」のテクニックをわかりやすく解説!
「今まで受けた研修で1番良かった!」「マネジメントの新しい考え方を得れた!」など現場管理職・マネージャーに大人気の1on1研修の第1回目の資料を無料公開中!!
>>1on1研修第1回『マネジメントと1on1って何ですか?』はこちらから無料ダウンロード
傾聴の3つの種類
傾聴技術は、心理学やコミュニケーションスキルを学ぶ上で非常に基本的で必要な要素です。ビジネスパーソンにとって、信頼関係構築や人間関係の改善に欠かせない技術です。
このパートでは、傾聴の3つの傾聴の種類を詳しく解説し、実践のコツをお伝えします。
- 受動的傾聴
- 積極的傾聴
- 共感的傾聴
受動的傾聴
受動的傾聴は、話し手の言葉に集中し、相手の話を最後まで黙って聞くことに重点を置いた傾聴のスタイルです。聞き手は、話し手の発言を遮ることなく、じっくりと耳を傾けます。
受動的傾聴のポイントは、相手の話を中断せずに最後まで聞くことです。聞き手が話に割って入ったり、質問をしたりすることなく、話し手に一方的に語らせます。これにより、話し手は自分の考えを最後までストレスなく話すことができます。
また、受動的傾聴では通常、聞き手は相槌を打ったり、頷いたりするなどの最小限の反応を示すだけにとどめます。言葉で割り込むことなく、小さな合図で「聞いている」ことを伝えます。
一方、聞き手は内面で活発に情報処理を行います。話の要点を整理し、話し手の気持ちや伝えたいことを推測するなど、積極的な思考活動を行います。
受動的傾聴は、話し手が自分の考えを整理したり、気持ちを吐き出したりする際に効果を発揮します。
話の途中で確認が必要な場合には、能動的な対話が求めらるため、状況に応じて、違う傾聴の形態を使い分けましょう。
反映的傾聴
反映的傾聴とは、聞き手が話し手の発言内容や感情を、自分なりの言葉で確認しながら傾聴する方法です。話し手の言葉をそのまま繰り返すのではなく、聞き手が解釈して言い換えることが特徴です。
具体的には、聞き手が「○○ということですね」「△△と感じていらっしゃるのですか?」と、話し手の問いを自分なりに言い換えて確認を取ります。これにより、話し手の本当の意図を正確に捉えることができます。
話し手は、自分の言葉を言い換えられることで、聞き手に理解されていると実感できます。また、聞き手の解釈に誤りがあれば、その場で修正することができ、相互理解を深めながら対話を進められるのが利点です。
さらに、反映的傾聴は、話し手の気持ちに共感し、受容的な態度で臨むことも大切です。感情の部分を確認する言葉を添えることで、話し手は自分の感情が汲み取られたと感じられます。
しかし、聞き手が解釈を間違えると、かえって誤解を生む可能性もあります。また、確認の言葉が多すぎると、かえって話の流れを妨げてしまう危険もあるため、上手な確認の仕方が求められます。
このように、話し手の発言内容と感情を、聞き手なりに解釈し確認しながら傾聴していくことで、より深い理解と対話につながる反映的傾聴は、効果的なコミュニケーションを図る上で重要な技法となります。
積極的傾聴
積極的傾聴とは、話し手の発言内容や感情を的確に捉え、理解しているかどうかを確認しながら、質問やフィードバックを交えて積極的に対話を進めていく傾聴の形態です。
具体的には、話し手の発言に対して、聞き手が「なぜそう考えたのですか?」「具体的にはどのような状況だったのですか?」など、質問を投げかけながら詳細を引き出していきます。単に話を聞くだけでなく、積極的に対話を重ねることで、お互いの理解を深めていきます。
また、「私にもよくわかる気持ちです」「それはとても大変だったと思います」といった共感を示す言葉を添えることも、積極的傾聴の重要なポイントです。話し手の気持ちに寄り添いながら、思いを汲み取ろうとする姿勢が大切です。
さらに、話の要点をまとめたり、確認したりするフィードバックを適宜入れることで、話し手に対して自分が理解しているかどうかを誤解がないよう、確認しましょう。
そのため、積極的傾聴は、問題解決やアドバイス、交渉などの場面で特に有効です。お互いの考えや立場を正確に把握し合うことが求められる状況で、コミュニケーションを深化させるための強力なツールとなります。
ただし、度が過ぎると話し手に話を遮られたように感じさせ、かえって反発を招く可能性もあります。タイミングや分量を見極めながら、柔軟に活用することが肝心です。
うまい傾聴は離職防止にもつながります。積極的に傾聴を活用していきましょう。
傾聴力を高めるポイント
傾聴力を高めるポイントとして次の6つが挙げられます。
- 話しすぎないよう会話の割合を意識する
- うなずきやあいづちを返す
- バックトラッキングを意識する
- ミラーリングを意識する
- ペーシングを意識する
- 態度と姿勢を意識する
今パートでは1つずつ詳しく解説していきます。
話しすぎないよう会話の割合を意識する
傾聴力を高めるためのポイントの一つが、「話しすぎないよう会話の割合を意識すること」です。
具体的に説明すると、自分の発言を控え、相手の話を聞く時間を意識的に作ることです。
理想的な会話の割合は、自分が話す時間を3分の1程度に抑え、相手の発言を3分の2以上占めるようにすることが推奨されています。これにより、相手の言葉に集中し、しっかりと聞き入ることができるようになります。
自分のことばかり話していると、相手に伝わりにくくなる原因にもなります。また、話を途中で遮ってしまったり、相手が言いたいことを最後まで聞かずに話を横取りしてしまうリスクもあります。
会話の割合を意識することで、つい話しがちな自分を制御し、相手に十分に発言する機会を与えられるようになります。相手の言葉をしっかりと受け止めることが、より深い理解と信頼関係の構築につながるでしょう。
うなずきやあいづちを返す
相手の話に集中し、「うなずきやあいづちを返す」という理解しているサインを適宜示すことも、傾聴力を高める上で重要なポイントです。コーチングやマネジメントの場面では、部下やクライアントの発言に対して、うなずきやあいづちなどの適切なリアクションを返すことが求められます。
例えば、目標達成に向けたワークショップで部下が自身の課題や解決策を説明している際、その言葉に焦点を合わせ、うなずきやあいづちを継続的に返すことで、話を遮ることなく集中して聞けるようになります。話し手は、リスナーの反応から自分の話が理解されていることを実感でき、安心して発言を続けられます。
一方、無言で聞いているだけだと話し手は不安になり、焦って話すため、本来伝えたいことが分かりづらくなる可能性があります。うなづきなどの適切なリアクションは、コミュニケーションを円滑に進めるためのサインとして重要な役割を果たします。
バックトラッキングを意識する
「バックトラッキング」とは、話し手の言葉やテーマから、話の本質やゴールを探ることです。相手の言葉の裏にある理由やヒントを探り、話の焦点を見失わないことが大切です。
例えば、部下が仕事の継続や別の部門への異動について相談してきた場合、単に「条件次第」と答えるのではなく、その経験から導き出された解決策があるかもしれません。上司としてマネジメントの観点から関連するアドバイスができれば、社員の活躍につながるでしょう。
このように、相手の本音を汲み取ることで、より建設的な対話が可能となります。バックトラッキングを意識し、話し相手の「成長」と「可能性の実現」を促す環境を整え、話し手が自分自身で問題解決できるように手助けをすること(積極的傾聴)により傾聴力を高めることができるでしょう。
ミラーリングを意識する
「ミラーリング」とは、相手の言動や姿勢を意識的に真似ることで、心理的な「同調」を図る手法です。これにより、話し手は安心感を覚え、より深い内容を打ち明けやすくなります。
例えば、会社で部下が仕事の継続について相談してきた際、単に冷静な態度でいるのではなく、相手の言葉遣いやボディーランゲージを意識的に映し返すことで、共感の念が生まれます。
このようにミラーリングにより、お互いの立場や心情を共有し、Win-Winの解決策を導き出しやすくなるのです。
傾聽は単に「聴く」だけでなく、相手の心に「寄り添う」ことが大切です。少々難しいかもしれませんが、ミラーリングを意識した対話を心がけることで、信頼関係が構築でき、よりよい決断につながります。
ペーシングを意識する
「ペーシング」とは、話し手のペースやリズムに合わせて対応することです。相手の話し方や発言のスピードに同調し、焦点を合わせることで、より深い理解と共感が生まれます。
例えば、部下が仕事のストレスについてゆっくりと打ち明ける場合、上司も落ち着いた口調で耳を傾け、焦らずに反応することが重要です。ただ、話し手が早口で話す際は、相手のペースに乗り遅れないよう集中して聞きましょう。
このようにペーシングを意識することで、話し手は理解され受け入れられていると感じ、さらに本音を語ってくれるかもしれません。対話における同調は、お互いの信頼関係を深め、建設的な解決策につながります。
態度と姿勢を意識する
「態度と姿勢を意識すること」も重要です。適切な態度と姿勢を取ることで、話し手に尊重の念と関心を示し、信頼関係を築くことができるからです。
例えば、前のめりの姿勢で話し手に向かい合い、適度な視線を保つことで、集中して話を聞いていることが伝わります。また、うなずきや相づちを交えながら、リラックスした身振りで臨めば、話し手も安心して自分の気持ちを表現してくれるでしょう。
一方、無視するような無表情な態度や、攻撃的な姿勢を取ってしまえば、話し手を緊張させてしまい、かえって良い傾聴ができなくなってしまいます。
そのため、オープンで前のめりの姿勢、適度な視線、小まめな反応、リラックスした身振りなど、態度と姿勢に気を配ることが、話し手との信頼関係を築き、より良い傾聴をすることができるようになります。言葉以外の非言語的要素にも意識を向けることが、傾聴力の向上に欠かせません。
傾聴力のためには様々ンことに気を付ける必要がありますが、今どきの若手社員に接するときはさらに特別な意識が必要です。
●若手社員の考えがわからない
●若手社員の育成方法がわからない
●ベテラン社員と若手社員の関係構築がうまくいっていない
などにお悩みの方は必見の若手社員の育成方法を基礎から学ぶことができる無料マニュアル!
>>「これ1つでOK!イマドキマネージャーのメンバー育成マニュアル」はこちらからご確認いただけます!
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 傾聴における「レベル1:内的傾聴」の状態とは、具体的にどのような会話を指しますか?
A: 相手の話を聞いていても「昔の私と同じだな」など、自分の経験や価値観に焦点が当たっている状態です。相手は「聞いてもらっている感」を得られず注意が必要です。
Q2. 傾聴の3つの種類のうち、「反映的傾聴」とはどのような手法ですか?
A: 聞き手が話し手の発言内容や感情を、自分なりの言葉で解釈し言い換えながら確認する方法です。相互理解を深め、誤解を防ぐ利点があります。
Q3. 傾聴力を高めるために、会話の「理想的な割合」はありますか?
A: 自分の発言を3分の1程度に抑え、相手の発言が3分の2以上を占めるようにすることが推奨されます。これにより、相手の言葉に集中しやすくなります。
Q4. 「ミラーリング」を意識することが、傾聴力を高める上でなぜ重要になるのですか?
A: 相手の言葉遣いやボディーランゲージを意識的に真似ることで、心理的な同調(共感)が図られます。話し手は安心感を覚え、本音を打ち明けやすくなります。
Q5. 傾聴力を高める「ペーシング」とは、どのようなテクニックですか?
A: 話し手のペースやリズム(話し方やスピード)に同調して対応することです。相手に理解され受け入れられていると感じてもらい、本音を引き出すためです。
まとめ
本記事では、傾聴の3つのレベル・種類、傾聴力を高めるポイントを紹介しました。
傾聴力を高めることで、顧客、チームや部下に対して今以上に信頼関係を築くことができるようになり、効率化・成果に繋げられます。
傾聴力を高めて、1on1や面談、商談でぜひ実践してみてください。
効果的な1on1を実施するなら「Co:TEAM(コチーム)」

- 1on1のスケジュールを何度も設定する
- 毎回1on1のアジェンダを決めるのに時間がかかってしまう
- 1on1の記録の管理が面倒くさい
- 従業員がどんな1on1を実施しているのか把握できない
- 1on1で話した内容をチャット形式で簡単に記録・管理・保存できる!
- 1on1で話すことに困らないアジェンダテンプレート機能!
- 1on1の対話を深める質問を提案するAIアシスト機能!
- 1on1の実施率・アジェンダの使用率がわかる分析機能!
- 従業員の特徴に応じたコミュニケーションを促進するソーシャルスタイル診断機能!
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。