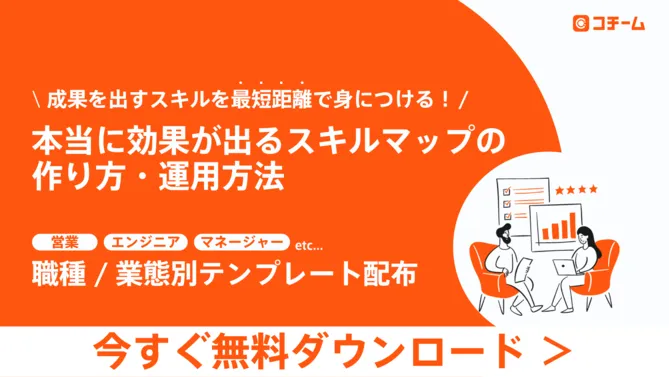スキルマップは、従業員のスキルを可視化し、人事配置・評価・育成に活用できるツールとして注目されています。特に、トヨタ生産方式に基づく多能工育成には欠かせません。
スキルマップを活用すれば、従業員の強みを把握し、最適な業務配置やスキルアップ計画を立てられます。この記事では、スキルマップの作成方法と活用法をわかりやすく紹介します。
≫無料で「本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法」をダウンロードする
▼ この記事の内容
- トヨタの目的: 多能工(マルチスキル人材)の育成による生産性向上と柔軟な体制構築です。
- 導入メリット: 習熟度の可視化により、適材適所の人材配置と公平な評価を実現します。
- 具体的項目: 「カイゼン」「なぜなぜ分析」「7つのムダ」など、TPS独自の視点を評価軸に設定します。
- 運用の要: 作成して終わりではなく、1on1ミーティングでの定期的な振り返りが定着の鍵です。
目次
スキルマップとは?
スキルマップは、従業員のスキルとそのレベルを記載した一覧表で、従業員一人ひとりのスキルと習熟度を具体的に把握できます。これにより、「仕事を遂行する上で必要なスキルがあるか」や「適性があるか」などを可視化することが可能です。海外では「スキルマトリックス(Skills Matrix)」と呼ばれ、また企業によっては、能力マップや力量表などとも呼ばれる事例があります。
>>無料で『本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法』をダウンロードする(職種 / 業種別のテンプレート公開中)
トヨタがスキルマップを導入した目的
トヨタがスキルマップを導入した目的は、主に効率的な人材育成と多能工の育成を実現するためです。トヨタは、生産ラインで複数の作業をこなすことができる「多能工」を育成することで、柔軟で効率的な生産体制を構築しています。
スキルマップを活用することで、従業員個人のスキルと習熟度を可視化し、適切な人材配置やスキルアップの支援が行いやすくなります。これにより、個々の従業員が持つスキルを最大限に活用できるだけでなく、業務の遅延や不具合を減らし、生産性の向上にも寄与しています。
また、トヨタではスキルマップを使って従業員の成長を促進し、業務の継続性を高めるとともに、未来のリーダーや管理職候補の育成にも役立てています。
スキルマップを運用するメリット
スキルマップという制度を運用するメリットとして、以下の4つが挙げられます。
- 従業員の育成が促進される
- 従業員のスキルが可視化される
- 効率的な人材配置や採用に効果的
- 従業員のモチベーションアップにつながる
それぞれについて、詳しく説明します。
従業員の育成が促進される
まず、1つ目は「従業員の育成が促進される」です。
スキルマップを活用すると、従業員一人ひとりのスキルや習熟度が数値などの面から明確になります。これにより、どのスキルが不足しているか、または強化が必要かがわかるため、個別に最適な研修や教育プランを立てやすくなります。
さらに、従業員は自分の成長の進捗を実感しやすく、スキルアップに向けた意欲が高まります。自分の強みや改善点がはっきりすることで、具体的な目標を設定しやすく、モチベーションも維持されます。このように、スキルマップを活用することで、計画的かつ効率的な人材育成が進み、従業員のスキルが向上する環境が整います。
従業員のスキルが可視化される
2つ目は、「従業員のスキルが可視化される」です。
スキルマップを使うことで、各従業員が持っているスキルやその習熟度を一目で確認できるようになります。これにより、どのスキルが強みで、どのスキルにさらに成長の余地があるのかが明確になります。
可視化されたスキル情報は、従業員本人だけでなく、管理者や人事部門にも役立ちます。適切な業務配置や、必要なスキルを補うための研修計画を立てる際に非常に便利です。
また、従業員自身も自分のスキルの現状を把握しやすく、自己成長に向けて積極的に取り組むことができます。このように、スキルの可視化によって、従業員の育成や業務の最適化が進みます。
効率的な人材配置や採用に効果的
3つ目は、「効率的な人材配置や採用に効果的」です。
少子高齢化や労働人口の減少により、優れた人材を確保するのが難しくなっています。そんな中で、既存の従業員への教育を強化し、スキル習得を促進することが重要になっています。
スキルマップを使うことで、従業員一人ひとりのスキルと習熟度のデータが一覧で確認でき、不足しているスキルや強化すべきポイントが明確になります。これにより、どの部署にどのようなスキルを持つ人材が不足しているのかが明確になり、人事異動の判断材料として利用することができます。
また、今の求職者が会社に対して重視していることは「成長」です。そのため、スキルマップによる育成体制が充実していることをアピールすることで採用活動にも好影響を与えることも期待できます。
従業員のモチベーションアップにつながる
4つ目は、「従業員のモチベーションアップにつながる」です。
スキルマップを使うことで、評価基準が明確になり、従業員のスキルに対して公平で適切な評価ができます。これにより、従業員のモチベーションが高まり、仕事への意識も向上します。また、スキルに合った部署に配属されることで、仕事のミスマッチがなくなり、離職率の低下やエンゲージメントの向上が期待できます。
スキルマップの作成手順
スキルマップの作り方についての手順について解説していきます。具体的には、以下の5つの手順を踏むとよいでしょう。
1.スキルマップの目的とターゲットを決定する
2.対象となる業務フローを明確にする
3.業務に必要なスキルを洗い出す
4.スキルマップの評価項目と評価基準を設定する
5.スキルマップを作成・運用する
STEP1:スキルマップの目的とターゲットを決定する
スキルマップの目的とターゲットを明確にすることは、効果的な活用に不可欠です。目的を明確にすることで、スキルマップが解決すべき課題が明らかになり、必要な項目や評価基準が決まります。ターゲットを定めることで、対象となる従業員や部署に必要なスキルが具体的になり、実用的なツールとして機能します。これにより、スキルマップが人材育成や業務改善に効果的に活用できるようになります。
STEP2:対象となる業務フローを明確にする
次に、対象となる業務フローを明確にしていきます。
ターゲットの職種がどのような業務フローを実施しているのかを整理することで、一般的に必要となるスキル項目が見えてきます。
例えば、製造業であれば「資材の調達・管理」「生産計画の立案」「加工・組立」「品質検査」「出荷・納品」などのフローが考えられます。それぞれの工程において、どのようなスキルが求められるのかを洗い出していきます。
STEP3:業務に必要なスキルを洗い出す
対象の業務フローが決まったら、次に必要なスキルを洗い出して設定します。
業務に必要なスキルには、現場で働いている従業員にしかわからない部分があるかもしれません。そのため、項目を洗い出す際には、上司だけでなく現場の従業員の意見も取り入れることが大切です。
項目をいくつかピックアップした後は、それが実際の業務とズレていないかを確認しましょう。内容をチェックしたら、重要な業務から必要なスキルを考え、どのスキルが優先されるべきかを決めます。また、実際にあまり使わないスキルをどの程度含めるかも、この段階で検討しておくと良いです。
STEP4:スキルマップの評価項目と評価基準を設定する
洗い出された項目に対して、スキルマップに採用するスキル項目と評価基準を設定します。
スキルマップに設定されるスキル項目は、目的によって異なります。客観的な評価が難しいスキルについては、誰にでも評価できる明確な基準を設定することが必要です。また、スキル項目が抽象的すぎても具体的すぎても評価が難しくなるため、バランスの取れた内容とすることが重要です。
評価基準に関しては、誰にでもわかるように明確に設定することが求められます。たとえば、5段階評価で達成レベルを表す場合、次のように基準を決めておくと良いでしょう。
レベル1:未経験
レベル2:担当になったばかり
レベル3:教えてもらえればできる
レベル4:1人でできる
レベル5:人に指導できる
目的や項目によっては、「できる・できない」の2択にする、評価段階を増やすなど、評価基準を適切に設定することが重要です。これにより、スキルマップを使った評価がより客観的で一貫性のあるものとなり、スキルの達成度合いを明確に示すことができます。
STEP5:スキルマップを作成・運用する
これまで整理した情報を基に、スキルマップをシート化し、正式に作成していきましょう。まずは一部署やチーム単位で試験的に運用することをおすすめします。
試験導入後は、実際に使用した従業員からフィードバックを収集し、定期的に見直しを行いながら、自社に最適なスキルマップへと改良していきましょう。 さらに、スムーズな運用を実現するために、現場向けの簡単な運用マニュアルを作成しておくと効果的です。
【成果を出すスキルを最短距離で身につけるスキルマップの作り方!】
・スキルマップを導入しようと考えているけど、効果が本当に出るのかわからない
・スキルマップを導入しているけど、なかなか効果が出ない・形骸化している
とお悩みではありませんか?
実は、スキルマップを効果的に運用するためには抑えるべきポイントがあります!人材育成で100社以上支援実績がある弊社のノウハウを盛り込んだ、ココでしか読めない情報が満載の無料スキルマップ解説資料!
>>『本当に効果が出るスキルマップの作り方・運用方法』はコチラから無料ダウンロード!(職種 / 業種別のテンプレート公開中)
トヨタ生産方式を参考にしたスキルマップの具体例
製造現場において、高い生産性と品質を維持するためには、従業員一人ひとりのスキルを可視化し、適切に育成していくことが重要です。特に、無駄を徹底的に排除し、効率的な生産を実現するトヨタ生産方式(TPS)では、「ジャストインタイム」や「自働化」などの考え方に基づいたスキルが求められます。
そんなトヨタグループの強みの源泉とも言える「トヨタ生産方式」を参考に、実際にトヨタ生産方式が現場で実行できるようにスキルマップを作成してみました。スキルマップの具体例を紹介し、どのようなスキルが現場で必要とされるのか、またそれをどのように評価・向上させていくのかを解説します。
カイゼン:現場の作業効率を良くする
トヨタにおけるカイゼンとは、「人、物、設備」に着目して改善を行い、組織全体で継続的な改善を維持することです。
例えば、「人」に関するカイゼンでは、作業手順書を作成し、作業内容や順序、機械の配置などを明記します。これにより、ムダな動きやばらつきが見える化され、改善策が明確になります。カイゼンを重ねて標準化することで、省力化や業務効率化、品質向上が実現します。
これらを身につけるスキルマップの具体例を以下に示します。
レベル1 :カイゼンの概念を理解していない
レベル2 :カイゼンの基本的な考え方を説明できる
レベル3 :カイゼンの手法を使い、小さな改善を実践できる
レベル4 :チーム内でカイゼン活動を推進できる
レベル5 :組織全体でカイゼン文化を定着させられる
これらの項目を習得することで、トヨタ生産方式に基づくカイゼン活動が実践できるようになり、効率的かつ効果的な生産システムの構築に貢献できるようになります。
また、カイゼンにて何を行うのかを解説します。
カイゼンで大切になるのは3Mの削減、5S活動の促進とボトムアップ式での現場主体です。
①3Mの削減
3Mとはムリ・ムダ・ムラの3つのMのことを指します。
ムリ:能力以上で負担が大きいこと
ムダ:付加価値を生まない作業
ムラ:仕事の品質が一定ではないこと
この3つは作業効率低下の原因になります。カイゼン活動を通じた3Mの削減は業務負担の削減、スピードアップ、コスト削減や品質の安定に大きくつながります。
②5S活動の促進
5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・躾の5つのSのことです。
整理:必要なものと不要なものに分けて、不要なものを処分する
整頓:必要なものを誰でもすぐ取り出せるようにする
清掃:汚れのない綺麗な状態を維持する
清潔:上記3Sを標準化し、維持できている状態
躾(しつけ):3Sが習慣化し、全員がしっかりルールを守っている状態
5S活動の定着はコスト削減やよりスムーズな作業に繋がります。その結果、製品やサービスの質が高まり、お客様の満足度を上げることが可能になります。
5S活動は「安全」「効率的」「快適」な職場づくりに大きな役割を果たしています。
③ボトムアップ式で現場主体
業務改善は大きく分けて「トップダウン」と「ボトムアップ」の2つに分けられます。
トップダウン:経営陣が業務改善に取り組み、定めた対策を社員に落とし込む
ボトムアップ:現場主体で取り組む業務改善
トヨタ生産方式では、ボトムアップでの問題解決が中心です。経営陣の指示ではなく、現場の社員で知恵を出し合いカイゼン活動を実施していきます。指示待ちから主体的な状態に変革するというのが特徴です。このような現場主体の方式は社員のモチベーションや当事者意識の向上にも繋がります。
なぜなぜ分析
なぜなぜ分析とは、明らかになったムダや課題に対し「なぜ」を繰り返すことで真因にたどり着く、いわゆる真因分析というものです。このなぜなぜ分析の力を身につけるためのスキルマップ項目の例を以下に示します。
レベル1 :なぜなぜ分析を知らない
レベル2 :なぜなぜ分析の基本的な概念を理解しているが、実施に不安がある
レベル3 :簡単な問題に対してなぜなぜ分析を実施し、根本原因を特定できる
レベル4 :複雑な問題に対しても、効果的に分析を行い、根本原因を見つけることができる
レベル5 :チームや他の部署に対してなぜなぜ分析を指導し、組織全体の問題解決力を向上させる
これらの項目をスキルマップに組み込むことで、「なぜなぜ分析」のスキルを段階的に習得し、実践で活用できるようになります。また、具体的な評価基準を設けることで、従業員の成長を明確に測定でき、組織全体で効率的な改善活動を推進することができます。
また、トヨタ生産方式では問題が発生した場合このなぜなぜ分析を5回繰り返します。
その理由は5回繰り返せば大体の原因を突き止めることができるからです。
製造業でのなぜなぜ分析の例を以下に示します。
問題:製造ラインで生産された金属製品にキズがついている
なぜなぜ分析:
1,なぜキズがついたのか?
→製造ラインで搬送中に製品同士がぶつかっている
2,なぜ製品同士がぶつかるのか?
→搬送用のコンベアのスピードが速く、製品の位置がずれている
3,なぜコンベアのスピードが速いのか?
→生産効率を上げるために、設定速度を上げている
4,なぜ設定速度を上げたのか?
→過去に生産目標を達成できなかったため、速度を上げることでカバーしようとした
5,なぜ生産目標を達成できなかったのか?
→作業員の手作業が多く、処理時間がかかっていた
対策案
・コンベアの速度を適正に調整し、製品の衝突を防ぐ
・製品がぶつからないよう仕切りを設置する
・手作業の工程を見直し、自動化できる部分を増やす
・作業効率を改善するためのトレーニングを行う
このようになぜなぜ分析を行うことで、真因特定が容易となり、適切な対策を導き出すことができます。
問題の見える化
「問題の見える化」とは、現場で発生している問題を誰もが即座に認識できる状態にして迅速な対応と改善を可能にする仕組みのことです。
これについてのスキルマップ項目は以下を参考にしてみてください。
レベル1 :見える化の重要性を理解している
レベル2: 基本的な問題管理ができている
レベル3: 問題発生時に適切な方法で対応できる
レベル4: 現場の問題点を分析してより効果的な見える化の手法を提案できる
レベル5 :全体を見る視点で見える化の仕組みを設計し、定着させられる
このように、問題の見える化というスキルを身につけると現場での迅速な対応と継続的な改善を促進することができるようになります!
それでは、トヨタ生産方式に倣った見える化を実践するための5つのステップを以下に示します。
ステップ1:改善後の目指す姿勢を定義
ステップ2:目指す姿を実現する行動の明確化
ステップ3:行動の適切性を知るための「見るべきもの」を決める
ステップ4:「見るべきもの」が日常的に「見える」工夫をする
ステップ5:見える化を実践するツールを用意する
特に見える化には誰でもすぐに確認できるようなシステムの構築が必要です。情報認知の偏りをなくすためにもツールの使用をおすすめします!
7つのムダどり
「7つのムダ」とは、トヨタ生産方式(TPS)において排除すべき非付加価値作業を指します。ムダを取り除くことで、生産性向上・コスト削減・品質向上を実現します。それぞれの例と対策もあります。
1 :つくりすぎのムダ(過剰生産)
対策→適正在庫の管理
各工程の1日あたりの生産量と、完成品1つにかかる時間「タクトタイム」を算出し、それを基に適切な生産計画を立てたり、完成品の保管場所を一箇所に定めたり棚卸しの定期実施を行なったりしましょう。必要なときに必要なだけつくることを軸にすることに注意してください。
生産管理システムの活用も有効な手段です。
2 :手待ちのムダ(待機時間)
対策→段取り改善・自動化
手待ちのムダの原因は作業の偏りと状況に適していない人員配置です。工程間の作業量の差がありすぎると従業員間の軋轢を生む原因にもなります。
そのため、工程ごとの適切な生産計画を立てることや後述する一個流し生産の適用、そして製造機器の定期メンテナンスなどを導入しましょう。
3 :運搬のムダ(不要な移動)
対策→工場レイアウトの最適化
工場レイアウトの最適化には、動線を配慮した各工程の作業場の配置設定やつくりすぎによる停滞を防ぐための在庫管理が大切になります。
入荷から出荷まで、いかにスムーズな作業の流れを作るかがポイントです。
4: 加工のムダ(不要な作業)
対策→適正な設備の選定
なぜこの加工が必要なのか、より効果的な技術を採用できないかといった定期的な作業工程に洗い出しと見直しが加工のムダを削るカギになります。
5:在庫のムダ(過剰在庫)
対策→生産計画の適正化
生産計画に基づいた在庫管理の徹底や小ロットの発注に対してひとつずつ後工程に回す「一個流し生産」を採用することで在庫のムダを削ることができます。
6:動作のムダ(不要な動き)
対策→動線の最適化
作業スペースのレイアウトや作業標準の見直し、作業標準の掲示や工具の定位置を定めるなど動線の最適化に努めましょう。
7:不良のムダ(品質不良・手直し)
対策→品質管理の強化
不良品の多くは人的ミスが原因であるため、作業標準を理解させる動画の使用や社内セミナーの開催、生産ラインに検査装置を導入するというような自動化も検討してみてください。
スキルマップの項目は以下を参考にしてみてください。
レベル1 :7つのムダの種類と影響を理解している
レベル2 :現場のムダを発見し、報告できる
レベル3 :ムダ取りの基本的な手法を実践できる
レベル4 :複数のムダを組み合わせて削減し、改善を推進できる
レベル5: 生産ライン全体のムダを分析し、仕組みとして定着させられる
7つのムダを取り除くことは、単なるコスト削減ではなく、よりスムーズで無駄のない生産活動を実現するための基本です。
スキルマップを効果的に運用するコツ
ここからは、スキルマップ作成後の効果的な運用について、特別に弊社のノウハウを解放して以下の3つの重要なコツを押さえてもらいます。
- 社内説明会を開催する
- 1on1ミーティングと掛け合わせる
- 定期的に見直しを行う
それでは、それぞれのコツについて詳しく説明していきましょう。
社内説明会を開催する
作成したスキルマップは社内説明会などで全社的にシェアする必要性があります。スキルマップを上層部だけに公開するなど透明性のない運用は、従業員からの信頼度低下にもつながる可能性があります。
もし不明点があった場合は、新たなルールを策定してマニュアルを作成するなど、全従業員が納得できる運用を目指すことが肝心です。
1on1ミーティングでスキルマップを運用する
現場の管理職やメンバーがスキルマップを効果的に活用するためには、「1on1ミーティング」が非常に相性が良い方法です。 1on1ミーティングは、メンバーの成長をサポートし、振り返りを行う場としての役割を持っています。
このミーティングでは、上司と部下が意識的に「どのスキルを獲得するか」を決め、日常業務で実践した内容を振り返ります。 具体的には、以下のような流れで進めます。
設定したスキルが業務の中でどのように活用されたかを確認
↓
実践してみて難しかった点や課題を整理
↓
上司からフィードバックを受け、行動改善のヒントを得る
このように、スキルマップと1on1ミーティングを組み合わせることで、着実にスキルを習得し、実践力を高めることができます。
弊社では、この手法を「スキルマネジメント」と呼び、まさに「究極のOJT(On the Job Training)」と考えています。スキルマップを作成するだけでなく、1on1を通じて実際にスキルを育成し、成長を促すことが重要です。
【即戦力採用<速戦力育成】
新入社員・若手社員を1~3年で高速成長させるには、1on1とスキルマネジメントの掛け合わせがおすすめ!
スキルシートの作成から実際の運用までを解説した資料!
>>『「人」ではなく「スキル」をマネジメントする1on1』はコチラから無料ダウンロード!
定期的に見直しを行う
スキルマップは作成して終わりではありません。ビジネスを取り巻く環境は常に変化しており、業務内容や企業ビジョンの変化、社会情勢の影響によって、必要なスキルも変化していきます。そのため、スキルマップは定期的な見直しと更新が必要です。
過去に作成したスキルマップを使い続けていると、現状にそぐわない内容になる恐れがあります。必要に応じてスキル項目を追加・修正し、テンプレート自体の変更が必要な場合もあります。また、スキルマップの運用で問題が発生した際は、速やかに問題点を修正し、運用を改善しましょう。
ただし、頻繁な変更は従業員に混乱を与える可能性もあるため、見直し時期をあらかじめ定め、適切なタイミングでアップデートを行うことが重要です。定期的なブラッシュアップを行い、常に最新の状態を保つよう心がけましょう。
効果的なスキル管理・スキルマップ運用なら「コチーム」!

- 会社ごとのオリジナルスキルマップを独自学習させたAIを用いて作成!
- 1on1機能とスキルマップ機能の連携で、スキルの習得を促進!
- スキルの獲得状況を一元管理!
- 1on1の省力化機能で現場管理職の負担を最小限に抑えて運用可能!
よくあるご質問(FAQ)
Q1. トヨタがスキルマップを重視する理由は何ですか?
A: 目的は「多能工の育成」です。 1人が複数業務をこなせる体制を作ることで、欠員時の対応や生産変動への柔軟性を高め、組織全体のムリ・ムダ・ムラを排除するために導入されています。
Q2. トヨタ流スキルマップにはどのような項目がありますか?
A: 通常の業務手順に加え、「カイゼン」「なぜなぜ分析」「7つのムダ取り」といった問題解決スキルが含まれます。単に作業ができるだけでなく、現場で改善活動を主導できるかを評価基準とします。
Q3. 「7つのムダ」とは具体的に何を指しますか?
A: 「つくりすぎ、手待ち、運搬、加工、在庫、動作、不良」の7つです。これらを現場で発見し、排除できる能力をスキル項目として設定することで、コスト削減と品質向上を自律的に行える人材を育てます。
Q4. 現場で形骸化させないための運用方法は?
A: 「1on1ミーティング」との併用が最も効果的です。上司と部下が定期的にスキル獲得状況を振り返り、日々の業務での実践結果をフィードバックし合うことで、スキルマップを生きたツールとして活用できます。
Q5. どのように評価基準(レベル)を設定すべきですか?
A: 「知らない」から「指導できる」までの5段階設定が一般的です。特にトヨタ式では、単に作業ができる(レベル3)だけでなく、他者に教えられる・改善できる(レベル4〜5)状態を重視して設定します。
まとめ
トヨタが導入した生産方式からスキルマップの例を掲載しましたがいかがでしたか?
スキルマップを活用することで、従業員のスキル向上だけでなく、組織の成長・売上の向上にもつながります。 企業全体でスキル向上を目指し、変化の激しい時代の中でも競争力を高めていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。スキルマップの作成・運用を検討されている方、またはお悩みの方は、ぜひ弊社サービスの『コチーム』をご活用ください。スキルマネジメントを成功させるための強力な支援ツールとして、お役に立てるはずです。 ご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
>>【マネージャーの負荷削減と組織の生産性向上を実現】3分でわかる「コチーム」がわかる資料3点セットを無料でダウンロードする
お役立ち情報
-
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
-
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
-
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。