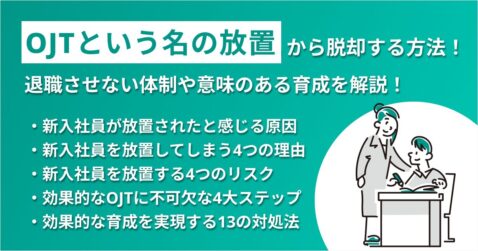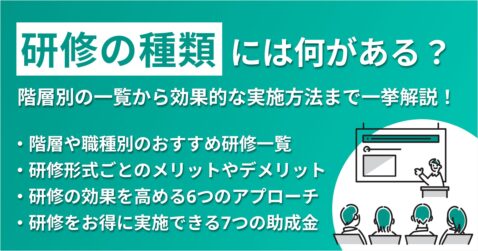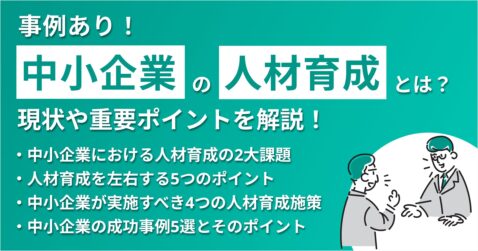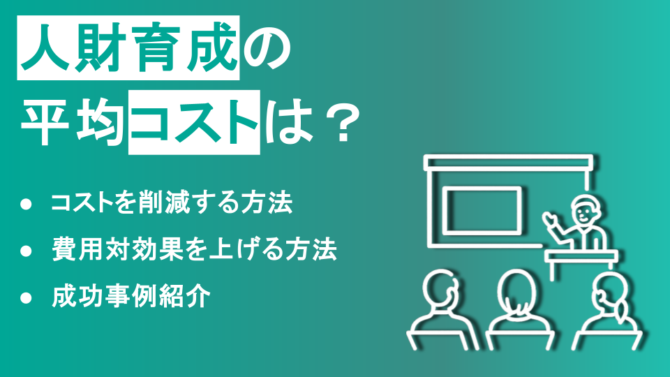
人材育成は企業の成長を支える重要なものだからこそ、どのくらいのコストをかけるかお悩みかもしれません。「研修は充実させたいけれど、費用は増やすことができない…」という方もいるでしょう。
本記事では研修内容ごとの一般的なコストから、費用を削減して費用対効果を上げる方法まで、詳しく解説します。人材育成に取り組んでいる人事担当者や経営者の皆さま、ぜひ最後までお読みください。
本当に効果が出る管理職・マネジメント研修をお探しの方へ
マネジメント研修を導入したいけど、比較しても正直「どれが自社にマッチしているのかがわからない…」とお悩みではありませんか?
「研修の違いが正直よくわからない」
「研修で現場にインパクトを与えるほどの効果が出るのか不安」
「管理職やマネージャーが研修に前向きでない」
こんなお悩みを抱えられている方は、コチームの「マネジメント研修」がおすすめです!
超実践的な研修内容で、研修後からすぐに使えるマネジメントのやり方「How」をお伝えし、本当に効果が出る研修です。
まずは、研修紹介資料からご覧になってみてください。期間限定で特典資料を配布中!
目次
1年で人材育成にかけられているコストの平均は?
人材育成にかかるコストを検討する際は、まずは平均的な費用を把握することが必要です。ここでは、調査で明らかになった現状をご紹介します。
・社員一人当たりの平均教育研修費は3〜4万円
・一人当たり50万円以上のコストをかける企業も
社員一人当たりの平均教育研修費は3〜4万円
日本の従業員1人あたりの教育研修費は平均して3〜4万円程度とされます。仕事内容や企業規模によってばらつきはあるものの、全体としてはおおよそこの範囲に収まる傾向です。
産労総合研究所が実施した「2024年度 教育研修費用の実態調査」(第48回)によれば、2024年度における従業員1人あたりの年間教育研修費用の平均は34,606円でした。前年比で2,194円増加し、コロナ禍以前の水準に近づいています。さらに、今後1~3年の間に教育研修費用総額が増加する見込みの企業は約6割に上るようです。
このように、平均3~4万円という金額はコロナ禍以降の回復基調を反映しており、企業が人材育成に再び力を入れていることがうかがえます。
【参考】産労総合研究所.2024年度 教育研修費用の実態調査
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/kyoiku/kyoikukenshu/pr2410.html(2025.8.5閲覧)
一人当たり50万円以上のコストをかける企業も
企業において、教育研修費用とは単なるコストではなく、将来への投資として捉えるべき重要な支出です。人材育成は従業員のスキルや意欲を高め、企業の成長力や競争力を向上させます。
こうした背景から、平均をはるかに上回る費用を投資する企業も存在します。東洋経済新報社が『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』2025年度版をもとに作成したデータによれば、ANAホールディングス、三井物産、伊藤忠商事の3社は、従業員一人当たりに年間50万円以上の教育研修費用をかけているようです。専門人材の育成やリカレント教育(学び直し)、グローバル人材の育成、eラーニングなどに力を入れていると考察されます。
しかしながら、教育費用を際限なく増やすことはできません。したがって、目的や費用対効果を明確にし、自社に合った適切な制度設計と費用配分をしていくことが、企業の持続的成長を左右するカギとなります。
【参考】東洋経済新報社.社員教育・研修にお金をたっぷり使うトップ100社
https://toyokeizai.net/articles/-/860281?page=2(2025.8.5閲覧)
人材育成にコストを本当にかけるべきか
先述のように人材育成はビジネスの成長を支える重要な要素ですが、費用かけるほど効果が得られるとは限りません。
近年は、研修や教育にかかる費用が増加傾向にある一方、若年層を中心に転職志向が広がっています。総務省統計局の2023年度調査では、転職希望者の割合が15.3%と過去最高になっており、人材を育成しても早期に離職されるケースが少なくありません。
一方で、教育費を安易に削減すれば社員が成長機会を得られずにモチベーションを失い、離職率が上がる可能性があります。そうなると、採用コストが増加してしまうでしょう。育成コストと採用コストは相互に関係しており、どちらかに偏りすぎるのは得策ではありません。
教育の質を保ちつつ持続可能な人材育成を行うためには、どの費用を維持し、どの費用を見直すべきかを見極めることが大切です。
下記のポイントを見ていきましょう。
・研修の質に関わるコストはかけた方が良い
・研修の質に直接の関係がないコストは下げるのがおすすめ
【参考】総務省統計局労働人口統計室.直近の転職者及び転職等希望者の動向について
https://www.stat.go.jp/info/kenkyu/roudou/r5/pdf/21siryou4.pdf?utm_source=chatgpt.com(2025.8.5閲覧)
研修の質に関わるコストはかけた方が良い
まずは、維持すべき費用を見ていきましょう。カットしてはいけないのが、研修そのものにかかるコストです。期待していた効果が得られなければ、研修をする意味がなくなってしまいます。
例えば、外部講師に研修を依頼する場合を考えてみます。研修の質は講師に大きく左右されるため、コスト重視で講師を選んだ結果、内容が社員のニーズに合わないものになってしまうかもしれません。反対に、多少費用がかかっても目的に合った講師に依頼すれば、定着率が上がり業績も向上します。
したがって、研修の質に関わるコストを削減するのは最終手段にするべきです。
研修の質に直接の関係がないコストは下げるのがおすすめ
一方で、研修の質に直接関係しない費用は削減すると良いでしょう。例えば、会場費や交通費、宿泊費が挙げられます。eラーニングやオンライン研修を利用すれば、これらをほぼゼロに抑えることも可能です。また、研修特化型のホテルを用いれば、宿泊費や会場費をまとめることができます。
ただし、交通費削減のために長時間のバス移動を強いるなどの方法は避けるべきです。社員の負担となり、研修への集中力が下がるかもしれません。社員の負担を考慮しながらも、研修の質に関わらないコストを削減することで、持続可能な人材育成が可能になります。
人材育成の費用対効果の測り方
ここまで人材育成のコストを見てきましたが、その費用対効果はどのように測ればよいのでしょうか。ここで活用できるのが、投資したコストから得られた効果・利益を表す指標となる「ROI(Return on Investment)」です。以下の計算式で算出されます。
ROI(%)= 利益 ÷ 投資資本 ×100
この式の結果が100%を超えれば投資成功、下回った場合は投資失敗です。
例えば、営業職社員10人に80万円の費用をかけて営業スキル向上研修を行い、一人ひとりの月間売上が5万円増加したとします。
この状態が6か月続いた場合、利益増加分は下記の通りです。
利益増加分 = 5万円 × 6か月 ×10人 = 300万円
これをROIに当てはめてみましょう。
ROI(%) = 300万円(利益) ÷ 80万円(投資) × 100 = 375%
この結果から、費用対効果は高く、研修への投資は成功したと判断されます。
ただし、人材育成における費用対効果は測りにくいのも現状です。離職率の低下やイノベーション創出、モチベーションアップによる業務効率向上などの成果は、短期間で生まれるものではないからです。
長期的視点で活用する指標だという前提を踏まえて役立てましょう。
育成方法別の費用の目安
続いては、育成方法別の費用の目安をご紹介します。なお、各項目の金額に加えて、研修参加者自身の人件費がかかることを忘れないようにしてください。普段は通常業務にあてている時間に研修を受ける場合は、その分の機会損失も生じます。
今回取り扱う育成方法は下記の通りです。
・社内講師による研修
・社外研修
・eラーニング
・スクール通学
・公開研修
・OJT(On the Job Training)
社内講師による研修
スキルを持っている社内の人材が講師を担う場合、コストを抑えて研修が実施できます。
費用は、講師分の人件費のほか、資料の印刷費、会議室等を借りる場合は会場費などです。具体的な金額は講師が必要とする準備時間に左右されます。なお、講師は通常業務を持っているため、本来の業務に影響が出て生産性が下がるのが注意点です。
他の研修に比べてコストが低いのが社内講師による研修ですが、プロフェッショナルを講師とする場合に比べて効果は低くなりがちです。十分な費用対効果が出るかを検討した上で実施する必要があります。
社外研修
社外研修とは、外部の企業や専門機関が提供する研修プログラムを利用して社員を育成する方法です。費用次第で、自社の課題に即してカスタマイズされた研修を受けることもできます。
一般的に、1日あたりの研修費用は20万〜70万円程度が相場です。ただし、有名講師や専門性の高いプログラムになると100万円を超えることもあります。
また、外部講師には大きく分けて、個人事業の講師と研修会社などに所属する講師の2種類があります。個人講師に依頼する場合の費用は10万〜15万円程度と比較的安価ですが、質やサポート体制に不安があることもあるため、実績を確認する必要性があるでしょう。一方、研修会社に所属する講師の費用は20~70万円と高めですが、カリキュラムが充実している傾向にあり、安心感があります。会社によっては研修以外のサービスや品質保証の制度があるのもメリットです。
自社内で研修を実施できる会場がない場合はレンタルスペースの利用料、遠方から講師を呼ぶ場合は宿泊費や交通費がかかりますが、リモートで実施する場合は費用を削減できます。
eラーニング
eラーニングは、パソコン・タブレット・スマートフォンなどの端末を活用し、オンラインで受講できる研修スタイルです。受講後のフォローや管理体制を整えることで、学習効果を高めることができます。
費用の相場は1人あたり約1万円からが一般的ですが、導入形態や機能、受講人数によって大きく変動するのが特徴です。
たとえば、自社サーバーにシステムを設置する「オンプレミス型」と、インターネット経由で利用する「クラウド型」では、導入・運用コストに差が出ます。オンプレミス型は初期費用が100~数百万円かかるほか、年に数回、数万円~10万円程度のメンテナンス費がかかります。クラウド型は初期費用が数万円~50万円程度で、固定額か利用人数に応じた従属課金制の月額利用料がかかります。学習管理機能(LMS)や進捗レポート機能等のオプション条件によっても、費用は変動するでしょう。
また、配信するコンテンツの制作費用も、自社で作成するか、外部に委託するかによって変化します。
スクール通学
スクール通学とは、社員が外部の教育機関や専門スクールに通って学ぶ研修形態のことです。期間は様々ですが数か月~1年程のものが多く、一定のカリキュラムに沿って進行します。
費用は通う機関やコースによって異なりますが、一人当たり数万円~数十万円が目安です。さらに、交通費が発生するほか、通学時間も労働時間として換算される場合は時間的コストが高くなります。
費用対効果を上げるためには、受講前に期待する成果を共有し、研修後には職場での共有・実践を徹底することが必要でしょう。
公開研修
公開研修は、研修会社などがあらかじめ用意した会場で実施される集合型の研修で、さまざまな企業や団体の受講者が参加します。異業種の参加者がいる環境で学ぶため、業種を超えた人脈づくりや新しい視点を得られる場としても価値があります。ただし、一般的な内容にとどまる傾向があるため、本当に自社課題にマッチした研修かを踏まえて参加を決めましょう。
費用は1人あたり2万円〜3万円程度が目安です。1日完結型のものから、数週間〜数ヶ月にわたる長期コースまで幅広く設定されており、期間が長くなるほど高くなります。
OJT(On the Job Training)
OJTは実務を通してスキルや知識を獲得する育成方法です。多くの場合、一人の新人・若手社員を一人の先輩・上司が担当し、直接指導を行います。
一見するとコストがかからないように見えますが、指導者の人件費や教材・マニュアルの作成費は発生します。属人化によって効果にバラツキが生まれやすいのも特徴です。指導体制や評価の仕組みを整えることが、費用対効果を上げるコツです。
人材育成費用の項目例
ここまでは、育成方法別の費用の目安を見てきました。以下では、多くの研修方法に共通して存在する費用項目を整理していきます。
・研修費用・教材費用
・会場費用・備品費用
・宿泊・飲食・移動の費用
研修費用・教材費用
研修・教材費用はあらゆる研修において必要とされますが、その種類によって金額は多種多様です。冒頭で述べた通り、研修の質に関わるこれらの費用はできるだけ確保することが望ましく、むやみなコスト削減をしないようにしましょう。
研修方法別にかかる研修費用・教材費用の内訳イメージは下記の通りです。
社内の講師による研修・OJT…講師や指導者の人件費、教材の印刷費等
外部講師による研修…謝礼、場合により別途教材費
eラーニング…利用するツールの導入費用、継続的な利用料、配信コンテンツの制作費
スクール通学・公開研修…受講費、場合により別途教材費
会場費用・備品費用
対面の集合研修において外部会場を利用する場合には会場の使用料が発生しますが、料金はスペースの広さや設備の充実度、立地などによって異なります。そのため、参加者の人数や研修の形式に応じた、過不足のない会場選びが大切です。
加えて、研修に必要な備品や設備の費用も見落とせません。パソコンやプロジェクター、スクリーン、マイク、スピーカーなどが該当します。外部会場に常設されている場合もありますが、利用には追加料金が発生するケースもありますので、事前の確認・問い合わせが必要です。
備品が会場に備わっておらず、自社でも保有していない場合は、レンタルまたは購入によって対応する必要があります。特にハイブリッド型研修(対面+オンライン)を行う場合は、音響や配信設備の準備に注意しましょう。
費用は、会場と備品を合わせて、10~20人ほどの小規模研修であれば2~5万円程度、50人以上の中規模・大規模研修であれば5~20万円程度が一般的です。
宿泊・飲食・移動の費用
講師が遠方から研修に来る場合には、交通費や宿泊費、飲食代、さらには駐車場代など、さまざまな移動関連費用が発生します。特に1日研修や長時間にわたるセッションの場合、講師と受講者の昼食代も必要になるケースが多く、忘れずに予算計画に含めておきましょう。
また、社員が外部の研修や公開講座、教育プログラムに参加する場合は、参加人数分の交通費が発生します。研修地が遠方であれば宿泊費も必要になるでしょう。このような周辺コストも含めて、研修にかかる総費用を見積もることがポイントです。
人材育成コスト削減のための6つの方法
これまで、研修の費用について概説してきました。続いては、人材育成のコストを削減におすすめの6つの方法をご紹介します。
1.内容や回数、対象者の見直し
2.eラーニングやリモート研修などITシステムの導入
3.外部講師から社内の講師への変更
4.研修の長期プログラム化
5.相見積もりの実施
6.助成金の活用
1.内容や回数、対象者の見直し
人材育成のコスト削減をする上で、内容・回数・対象者の定期的な確認は欠かせません。無駄な研修を続けるとコストの浪費になってしまいます。
以下に、それぞれの見直し例をご紹介します。
内容の見直し:
新入社員向けのマナー研修を、現場での実践力を重視した課題解決型研修に刷新。顧客課題のヒアリングから提案書作成までを体験することで、マナーに留まらない応用力や協働力を身に付けられるようになる。
回数の見直し:
毎月行っていた全営業社員向けの研修を、四半期ごとに「テーマ別」「対象者別」に分けたローテーション型研修に変更。研修への集中度や意欲を高めるとともに、業務への負担を軽減することができる。
対象者の見直し:
全社員必須だったマネジメント研修を、管理職やリーダー候補に限定。対象者を絞って抑えたコストを外部機関へのアウトソーシング費用に回し、内容をより高度かつ実践的にすることが可能になる。
このように、内容・回数・方法・対象者を見直して、非効率的な研修の是正に取り組みましょう。
2.eラーニングやリモート研修などITシステムの導入
コロナ禍の社会で活用の幅が広がったITシステムは、コスト削減をする上で非常に有効です。対面で行っていた研修をeラーニングやリモート研修に切り替えることで、会場費や教材の印刷費、講師の交通費・宿泊費などを削減することができます。また、eラーニングであれば一度作成した教材を繰り返し利用できるところもメリットです。制作費用はもちろん、準備にかかる時間や手間が削減できます。
例えば、サービス業チェーン店でITシステムを導入した場合、下記のような成果が得られるでしょう。
導入前:本社での集合研修が中心で、遠方の従業員には交通費・宿泊費を支給していた。
導入後:オンライン研修とeラーニングの導入により交通費・宿泊費が不要になる。マニュアル化した内容を配信することで研修内容が均一になり、サービスの質も向上した。
一方で、集中度に個人差が出る、コミュニケーションが不足するなどのデメリットも存在します。コスト削減により効果も下がっていないかどうか注意しながら、ITシステムを導入しましょう。
3.外部講師から社内の講師への変更
社内に専門スキルや知見を持つ社員がいる場合は、社内講師による研修へ切り替えるもの一手です。諸経費の削減をしながら、自社の人材育成課題に適した研修を構築することができます。社内にノウハウを蓄積できるのも副次的なメリットです。
例えば、外部講師から社内の講師へ変更した場合、下記のような成果が見込めます。
変更前:リーダー層に、外部講師による年4回のマネジメント研修を実施し、年間で100万円以上のコストがかかっていた。
変更後:管理職経験者の中から社内講師を選抜。選抜された社員は現場課題に即した研修を作成した。コストは資料準備費、会場管理費、軽微な謝礼のみで、40万円まで削減できた。
この例の場合は、コスト削減だけではなく現場に即した研修を実現していますが、研修のクオリティが下がる場合も存在します。社内講師への変更は、あくまで研修の質を維持・向上できる場合に留めることが大切です。
4.研修の長期プログラム化
必要な研修を一度に実施せず、長期的な研修計画を立てることも、費用削減につながります。研修の段階的に実施は学びの消化不良を防ぎ、学習効果を高める上でも有効です。
例えば、毎年は新入社員を採用しない中小企業であれば、下記のような施策が可能です。
課題:新入社員向け研修と中堅社員向けスキルアップ研修を同年度に行おうとしたが、予算が不足している
施策:初年度は新入社員研修、2年目は中堅社員向けの応用研修を実施する
一方で、研修の長期プログラム化のデメリットは、採用状況や経営方針の変更によって計画と実施のずれが生じやすいことです。長期プログラム化は気軽に決めるのではなく、経営戦略に基づき戦略的に設計しましょう。
5.相見積もりの実施
社員研修を外部に委託する際は、必ず複数の研修事業者から相見積もりを取り、内容や費用を比較検討することが大切です。事業者ごとに提供される内容や価格、ノウハウの質には差があり、1社の提案だけで決めてしまうと、自社に合わない研修を高い費用で導入してしまうリスクがあります。
なお、著名な講師や企業に属している講師ほど研修の質が安定する傾向はありますが、必ずしもフリーランスの講師の質が低いわけではありません。幅広い事業者に見積もりを依頼し、実績を踏まえて総合的に判断しましょう。
相見積もりの一般的なプロセスは下記の通りです。
①研修の目的・要件を明確にする
②複数の研修事業者をリストアップし、見積もり依頼書を作成・送付する
③見積もり・提案を受取り、内容・費用を比較検討する
④必要に応じて交渉やトライアルを行い、契約を締結する
6.助成金の活用
コストを削減するのではなく、国や自治体が提供する助成金を利用して費用負担を軽減するという選択肢もあります。利用を検討する際は事前に管轄の労働局やハローワークなどに確認し、該当するかどうかを確認しましょう。
代表的な社員研修向け助成金制度は、厚生労働省による「人材開発支援助成金」です。社員の能力向上を目的に研修を行う際に受給することができます。
用意されているコースは以下の7つです。
・人材育成支援コース
・教育訓練休暇付与コース
・人への投資促進コース
・事業展開等リスキング支援コース
・建設労働者認定訓練コース
・建設労働者技能実習コース
・障害者職業能力開発コース
受給要件などの最新の情報は、下記の厚生労働省ウェブサイトからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
さらに、「人材開発支援助成金」以外にも、地方自治体によっては地域独自の助成金制度があります。
例えば、中小企業に対する支援としては、東京都の「スキルアップ支援事業」や、岡山県倉敷市の『人「財」育成支援補助金』などがあるようです。
専門のコンサルタントや労働局の窓口に相談しながら、助成金を積極的に活用していきましょう。
人材育成の費用対効果を上げるための6つの方法
ここまで人材育成のコストを削減する方法をご紹介してきましたが、ここからは、費用対効果を上げるための6つの方法をお伝えします。短期的にはコスト削減につながらないものであっても、研修1回あたりの効果上昇により研修回数が減少したり、業績が向上したりすることで、長期的に見て研修コストの負担が低下するでしょう。
1.人材育成内容のマニュアル化
2.外部への研修委託
3.受講者による目標設定と振り返り
4.効果検証と改善
5.スキルマップなどのスキルマネジメントツールの活用
6.インセンティブの確保
1.人材育成内容のマニュアル化
研修内容のマニュアル化は、人材育成の費用対効果を高める上で重要です。
マニュアルがない状態では、準備に無駄な時間や労力が発生したり、研修の進行や内容が属人化して質にばらつきが出たりします。一方で、標準化されたマニュアルがあれば、誰が担当しても効率的に準備し、均一な研修を提供することができます。例えば、OJTの指導者に向けたマニュアルを用意すれば、指導者の負担が軽減するとともに教育の質が安定化するでしょう。
このように、研修のマニュアル化は研修の質と効率を上げて費用対効果を高める、有効な施策と言えます。
2.外部への研修委託
専門的な研修ノウハウがない社内人材が講師をしている場合は、研修を外部に委託することで費用対効果の高い研修が実現できます。講師費用はかかりますが、研修の企画設計や運営準備にかかる社内リソースを削減できるため、負担や人件費を抑えることにもつながるでしょう。
例えば、自社で行っていた新入社員研修を外部講師に切り替えて教育の質が向上した場合、次のような効果が見込まれます。
・現場での即戦力化が進んで残業が減り、人件費が減少する
・人事部の業務負担も軽減され、採用活動や人事制度設計にリソースを回すことができるようになる
この場合、初期費用は増加するものの、結果的に売上に対する人材育成コストが減少します。
このように、外部研修の活用は単なる「費用の追加」ではなく、効果と効率を高め、長期的なコスト削減にもつながる投資なのです。自社のニーズに合致する研修内容と提供者を選定することで、費用対効果の高い研修を実施しましょう。
3.受講者による目標設定と振り返り
研修の効果を高めるためには、目標設定や振り返りが不可欠です。ただ研修を受けさせるだけでは、学んだ内容が現場で活かされず、コストに見合った成果が得られないリスクがあります。しかし、目標設定と振り返りを取り入れることで、業務への定着率が上がるのです。
例えば、研修前に「事前目標設定」、研修直後に「学んだことを活かすアクションプランの提出」、1か月後に「振り返り1on1」をする場合、社員には「学んだ内容を活かして、自分で立てた目標を達成しなければ」という意識が働くでしょう。
このように、研修を「目標・振り返り・評価」と連動させることでスキルが定着し、研修の費用対効果が向上します。
4.効果検証と改善
研修の費用対効果を高める上では、効果検証と改善も欠かせません。参加者の満足度や理解度、行動変容、業務への活用状況などを多角的に振り返りましょう。
この検証を通じて、「費用に見合うだけの学びが得られたか」「成果に乏しい原因は何だったのか」「今後の研修にどんな改善が必要か」といった具体的な見直しが可能になります。
なお、新入社員向け研修と管理職向け研修では、育成のねらいや内容、求められる成果が違うため、かかる費用にも差が出ます。よって、効果を単に同じ基準で比べるのは適切ではありません。大切なのは、目的に見合った適切な投資になっているかという視点です。
効果検証と継続的な改善を繰り返すことで、無駄な研修への投資を防ぎ、本当に価値ある研修を行っていきましょう。
5.スキルマップなどのスキルマネジメントツールの活用
スキルマップとは、業務で必要なスキルを洗い出し、各従業員がどのスキルをどの程度習熟しているか(スキルレベル)を一覧表として可視化したものです。
スキルマップを活用することで、従業員全体に不足しているスキルが明らかになり、より効果的な研修プログラムを設計することができます。eラーニングを活用すれば、一人ひとりのスキルに合わせてカスタマイズした研修を行うことも可能です。
さらに、個々の従業員のスキルに合わせて人材配置をすることで、担当業務に対する従業員のスキルレベルが上がり、より高度な内容に特化した研修をできるようになります。
このように、スキルマップに代表されるスキルマネジメントツールを活用することで、より効果的な研修が実施でき、費用対効果も上がるのです。
 「コチーム」は、「スキルマネジメント(1on1×スキルマップ)」を運用できる国内唯一のツールです!スキルマネジメントを効果的に管理・運用するための各種機能を搭載しております。
「コチーム」は、「スキルマネジメント(1on1×スキルマップ)」を運用できる国内唯一のツールです!スキルマネジメントを効果的に管理・運用するための各種機能を搭載しております。

- 会社ごとのオリジナルスキルマップを独自学習させたAIを用いて作成!
- 1on1機能とスキルマップ機能の連携で、スキルの習得を促進!
- スキルの獲得状況を一元管理!
- 1on1の省力化機能で現場管理職の負担を最小限に抑えて運用可能!
6.インセンティブの確保
インセンティブを適切に確保することも、研修効果を高める上で非常に重要です。従業員のモチベーションを持続させられるためです。
例えば、研修の評価達成率に応じて社員表彰や報奨金、人事評価を設定すれば、受講者の意欲向上につながります。先述の「目標達成と振り返り」の手法と合わせて、研修実施後の目標達成を評価するのも有効です。
こうしたインセンティブの確保で研修の定着率や実務への応用度が高まり、研修の効果の最大化につながるでしょう。
人材育成コスト削減の成功事例3選
最後に、人材育成費用の削減に成功した3つの事例をご紹介します。現在の社会の動向を理由に、ここで紹介する事例はすべてITシステムの導入事例となっていますが、人材育成のコスト削減・費用対効果向上の方法は他にも存在します。必ずしもITシステム導入が必要なわけではない点に留意してください。
・大林組
・東京ガス
・デンソー
大林組
建設現場では、各現場特有の現状・ルール・安全事項を伝える「新規入場者教育」が必須です。大林組は2020年よりこの研修に、資料動画作成システムツールを導入することでコストを削減しました。
動画は現場に応じたものである必要があるため使い回しがききませんが、資料動画作成システムツールでは容易に作成することができます。この活用により、担当者がいなくても研修に対応できるようになり、効率化が進みました。
新規入場者教育に係る時間が削減され、年間で1万6000時間以上のコスト削減につながったとされています。
東京ガス
東京ガスでは、従業員と多数の協力企業を含めて、約8万人規模で独自の研修管理システムを長年使用していましたが、20年の運用で機能がブラックボックス化していました。eラーニング需要にも対応しきれず、研修運営に大きな負担が生じていたようです。
その中で、2024年に学習管理システム(LMS)を導入し、8万人以上の研修データを一元管理へ移行した結果、研修申込や履歴管理、eラーニング、試験の運用をオンラインで完結させることが可能になりました。さらに、eラーニング教材を外部委託から内製化することで、外注コストが減少したそうです。
運営体制が効率化され、技能やノウハウの可視化・伝達が強化されたことで、組織全体の人材育成力が高まり、結果的に費用対効果も向上したと言えます。
デンソー
デンソーでは、自動車部品の品質を左右する最終工程として人の目による検品作業を重要視しています。ところがこの検品業務には、主に期間従業員が従業しており短期間で人員が入れ替わるため、毎回ゼロから教育を施す必要があります。これが同社にとって大きな課題となっていました。
これに対してデンソーは、熟練者の目の動きを可視化して、検査対象を見る順番や中視点の移動を分析できるアイトラッキングシステムを導入。このデータを活かし、「どのタイミングで・どの部品を・どう見るか」といった作業のポイントを押さえて指導します。これにより、指導時間の半減と検品制度の向上に成功しました。
研修にかかる人件費の削減に成功した事例です。
まとめ
本記事では、人材育成にかかる一般的費用から、その費用対効果を上げる方法まで、網羅的に解説していきました。「コスト削減のための6つの方法」そして「費用対効果を上げるための6つの方法」をセットで用いて、より持続可能な人材育成を行いましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。弊社では、1on1とスキルマップの活用で「速戦力育成」を可能にするスキルマネジメントツール『コチーム』を展開しております。少しでもご興味がありましたら、ぜひ無料資料をダウンロードし、導入をご検討ください。
お役立ち情報
-
 全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。
全170P超の目標マネジメントパーフェクトガイド近年増えている目標マネジメントへの不安を解消するあらゆる手法やマインドなど目標管理の全てが詰まっている資料になっています。 -
 【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。
【170P超のマネージャー研修資料を大公開!】マネジメントと1on1って何ですか?「これさえ実践すれば間違いないという具体的なHOW」に焦点をあてて、マネジメントや1on1を実践できる内容となっています。 -
 【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。
【全260スライド超】メンバーの成長・マネジメントを最適化させるプロが実践する1on1パーフェクトガイド組織開発・1on1 ・評価の設計運用で 100 社以上の企業に伴走してきた弊社の知見をもとに作成したガイド資料になります。